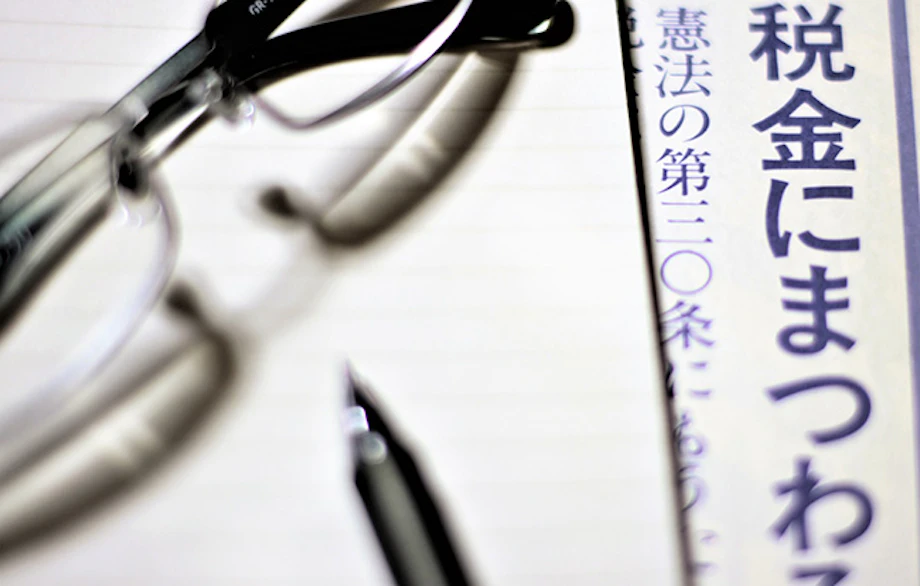個人から個人に対して財産を渡す場合には、贈与税が発生する可能性があります。生前に子どもや孫、夫や妻にご自身の財産を渡したいときに、できるだけ贈与税がかからないようにしたいと考える方もいるのではないでしょうか。
この記事では、贈与税がかからない方法について解説します。注意点についても理解することで、トラブルを予防し、スムーズに財産を引き継ぐことができるでしょう。
<この記事の要点>
・1年間の贈与額が基礎控除額110万円以下であれば、贈与税はかからない
・「配偶者控除の特例」の制度は贈与額2,000万円までが非課税となる
・死亡から直近3年以内の贈与は相続税の課税対象になるため、注意が必要
こんな人におすすめ
贈与税を抑えたい人
親族に財産を相続したい人
贈与税がかからない方法には何がある?
贈与税を納めるのは、財産をもらった側となります。子どもや孫、夫や妻の税負担をできるだけ軽減するためには、贈与税が発生しないケースについて理解することが大切です。ここでは、基礎知識として、贈与税の基礎控除額や非課税枠などについて紹介します。
贈与税の基礎控除額内での贈与
前提として、贈与があった場合に、財産をもらった側は「暦年課税」か「相続時精算課税制度」を選択します。
「暦年課税」とは、1月1日から12月31日の間で基礎控除110万円を超えた場合にのみ、贈与税が課せられる仕組みのことです。そのため、例えば年間で贈与された金額が80万円であれば、贈与税は発生しません。
相続時精算課税制度の利用
贈与税では、書類を税務署に提出することで「相続時精算課税制度」を選択できます。「相続時精算課税制度」とは、原則60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子どもや孫に贈与する際に使える制度です。2,500万円までの贈与であれば非課税となります。
しかし、暦年課税とは併用できないことが注意点です。一度、相続時精算課税制度を選択すると暦年課税には戻れません。
さらに、相続が発生した場合には贈与時の時価で相続財産に加算されるため、最終的な納税額をあらかじめ予測しておくことが大切です。
生活費や教育費としての受け渡し
生活費や教育費、結婚資金などは、社会生活を送る上で必要だと考えられています。そのため、贈与税が課せられるのは適切ではないというのが一般的な見解です。社会通念上相当と認められる範囲内であれば、原則として贈与税は発生しません。
さらに、祝儀金や弔慰金、お見舞金なども高額でなければ、贈与税は課せられないと考えてよいでしょう。
贈与税がかからないように利用できる特例
贈与税には、一定の要件を満たすことで利用できる、贈与税の非課税枠があります。それぞれの特例で要件があるため、しっかりと理解することが大切です。ここでは、特例の要件や非課税枠などについて紹介します。
配偶者控除の特例
「配偶者控除の特例」とは、居住用の不動産またはその取得資金を夫婦間で贈与する際に使える制度です。「婚姻期間が20年以上ある」「贈与のあった年の翌年3月15日までに実際に住み始める」といった要件を満たす必要があります。
非課税枠は2,000万円です。暦年課税の110万円と併用することで、最大2,110万円までが非課税となります。
住宅取得資金等の特例
「住宅取得資金等の特例」とは、父母や祖父母といった直系尊属から子や孫に対して、マイホーム資金などを贈与する場合に使える制度です。
「贈与を受ける方が18歳以上である」「贈与を受ける方の贈与のあった年の合計所得金額が2,000万円以下である」といった、多数の要件があります。
非課税枠は、省エネなどの要件を満たす住宅の場合には1,000万円です。それ以外の住宅であれば、500万円となります。
結婚・子育て資金の特例
父母や祖父母という直系尊属から、18歳以上50歳未満の方が結婚・子育て資金を受け取った場合には「結婚・子育て資金の特例」を活用できます。
妊婦健診や医療費、保育料という費用の場合、非課税枠が1,000万円あります。挙式費用や新居の家賃といった費用であれば300万円となります。贈与をもらう方は、金融機関で結婚・子育て資金口座を開設することが必要です。
教育資金の特例
「教育資金の特例」とは、父母や祖父母などの直系尊属が30歳未満の方に対して、教育資金を贈与する際に使える特例です。
非課税枠は、入学金や授業料、修学旅行費などであれば、1,500万円となります。塾の費用や定期券代などの場合には、500万円です。利用時には、金融機関で教育資金口座の開設手続きをします。
特定障害者の特例
贈与をもらう方が、特定障害者に該当する場合には「特定障害者の特例」を活用できます。信託銀行を通して、生活費や医療費などが特定障害者の方に定期的に交付される仕組みです。
非課税枠は、特別障害者(身体障害者手帳1級・2級の方など)であれば6,000万円となり、特別障害者以外の方であれば3,000万円となります。
現金の手渡しは贈与税がかからない方法になる?
生前贈与のために、現金で財産を手渡しするのはおすすめしません。税務署による贈与税調査や相続税調査は、定期的に行われています。被相続人や相続人の銀行口座の取引履歴などが調査の対象となります。
申告漏れがあった場合には、無申告加算税や延滞税が課せられる可能性があるため、期限を守って税務署に申告しましょう。
贈与税がかからないように対策する際の注意点
贈与税の発生を防ぐためには「生前贈与加算」の仕組みを理解したり、贈与のある度に贈与契約書を作成することが大切です。ここでは、贈与税に関する注意点について紹介します。
死亡から直近3年以内の贈与は相続税の課税対象になる
贈与税には、亡くなる3年以内に贈与があった場合には相続税の課税対象になる「生前贈与加算」の仕組みがあります。基礎控除110万円以下の贈与であっても、3年以内に亡くなった場合には相続財産に加算されるため、注意が必要です。
ただし「配偶者の特例」や「住宅取得資金等の特例」「結婚・子育て資金の特例」「教育資金の特例」での贈与は、生前贈与加算の対象外となります。
税務署に否認される可能性がある
生前贈与をする際には「贈与契約書」を作成しておくことが大切です。贈与契約書を作成することで、贈与の証明が確実にでき、税務署から否認されるリスクが低くなります。
贈与者(財産を渡す側)と受贈者(財産をもらう側)の氏名や住所、贈与する財産の金額や契約締結日などを記載し、贈与者と受贈者の両方が贈与を了承していることを示しましょう。
定期贈与のみなされる可能性がある
110万円以下の基礎控除を活用して、毎年家族に財産を渡すことを考えている方もいると思います。
税務署から定期贈与とされた場合、毎年1月1日から12月31日の間の贈与額が110万円以下であっても、全ての贈与の合計額で贈与税が計算される可能性があります。暦年贈与を効果的に使うためには、贈与のあるごとに贈与契約書を作成することをおすすめします。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
贈与税の110万円の基礎控除や配偶者控除といった制度を活用することで、家族に贈与税の負担をかけず、財産を渡すことができる可能性があります。各種特例の要件や非課税枠は異なるため、事前に確認して効果的に活用しましょう。
「小さなお葬式」では、皆さまの葬儀に関する疑問や不安を取り除くお手伝いをします。葬儀に関する準備は、できるだけ早めに始めることが重要です。24時間365日、専門スタッフが対応します。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


忌引き休暇は、実は労働基準法で定められた休暇ではありません。ホゥ。