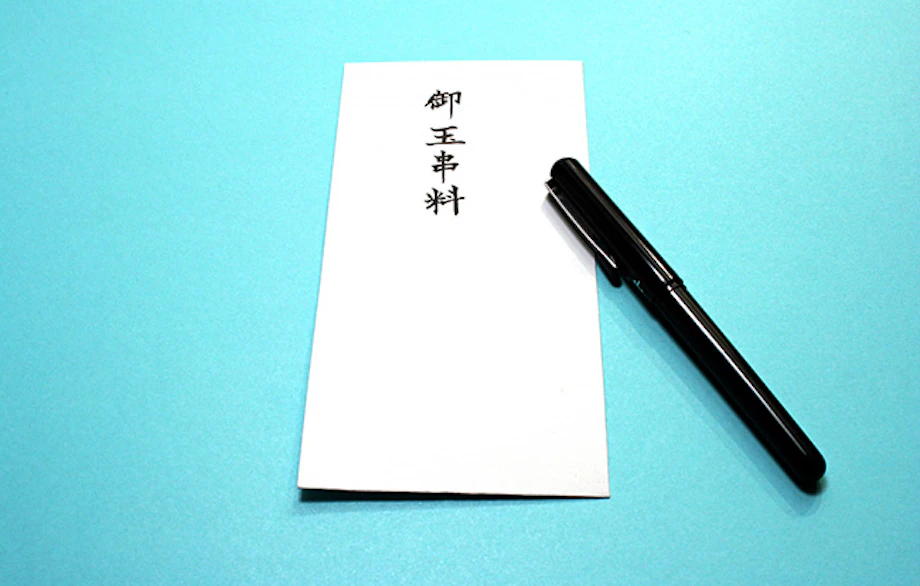法要やご祈祷で神社やお寺に納めるお金には、さまざまな呼び方があります。その1つが「玉串料(たまぐしりょう)」で、慶事から忌事まで、幅広い場面で使用できます。玉串料は封筒に入れて納めるのが一般的です。
この記事では、玉串料を入れる封筒の選び方や書き方、また玉串料全般に関するマナーといった基本的な情報を紹介します。神事や仏事の前の確認の際に、ぜひご活用ください。
<この記事の要点>
・忌事用の玉串料を包む封筒は、不祝儀袋を用いるのが一般的
・忌事の封筒の表書きは、「玉串料」「御玉串料」「御霊前」などと書くのがマナー
・忌事の玉串料は新札の使用を控えるのがマナー
こんな人におすすめ
玉串料を包む封筒の選び方を知りたい人
玉串料全般に関する
玉串料とは
玉串料の「玉串」とは、榊に紙垂(しで)のついたものを指します。玉串は、ご祈祷の際に神様にお供えするものですが、自身で用意して持参するのが難しいこともあるでしょう。そこで代わりにお金を納めることが増え、お供えのお金を「玉串料」と呼ぶようになりました。
まずは、玉串料が求められる場面や、玉串料と初穂料の違いについて説明します。
玉串料を用意するのはどんなとき?
玉串料は、慶事と忌事のどちらでも用意する場合があります。お寺や神社では、さまざまなご祈祷や法要が実施されます。
玉串料を用意するのは次のような場面です。
| 行事名 | 内容 |
| お宮参り | 生後1カ月のお祝いと報告 |
| 七五三 | 3歳・5歳・7歳のお祝いと今後の健やかな成長を祈る |
| 地鎮祭 | 工事の無事を祈り、土地の神様にご祈祷する |
| 神事 | 神棚の魂入れや破魔矢の処分などの神事 |
| 葬儀 | 人が亡くなった際に行うお通夜や葬儀 |
| 各種法要 | 葬儀後の節目に行う法要 |
初穂料との違いは?
玉串料と似た意味を持つ「初穂料(はつほりょう)」は、間違いやすい言葉なので注意が必要です。「初穂」はその年の初物のお米を指し、収穫の感謝を込め、神様に奉納していました。お米だけでなく、野菜や魚介類など地域の特産品がある場合には初物がお供えされていました。
しかし、時期や地域によっては収穫物が用意できない場合もあります。そこで、収穫物(初穂)の代わりにお金をお供えするようになり、これを「初穂料」と呼ぶようになりました。
慶事、忌事のどちらにも対応可能な玉串料とは異なり、初穂料は「神様への感謝」を伝える慶事にのみ用いられます。初穂料という言葉が使用できる場面の例は、以下の通りです。
・安産祈願
・お宮参り
・七五三
・厄除け
・神前式(結婚式)
・地鎮祭や新車購入時のご祈祷 など
忌事用の玉串料を包む封筒の選び方
慶事と忌事のどちらにも使用できる「玉串料」ですが、用途によってお金を包む封筒の種類は分ける必要があります。葬儀や法要などの忌事の際の玉串料は、どのような封筒に入れるとよいのでしょうか。
選び方のポイントは、「封筒の種類」と「水引」の大きく2点に分けられます。
忌事用の玉串料を包む袋を選ぶ際の注意点
通夜や葬儀、法要といった忌事では、「不祝儀袋」といわれる封筒を用いるのが一般的です。不祝儀袋は宗教や宗派、地域などにより仕様がやや異なりますが、お祝い事に用いられる紅白の封筒とは違い、黒やグレーで文字や装飾がされています。
袋の表に蓮やユリの花、十字架が印字されているものは仏教やキリスト教の封筒にあたるため、神道の玉串料には不向きです。また、1万円以上包む場合は、水引は印刷ではなく実物を用いるなど、包む金額によっても封筒を変える必要があります。
水引の色、結び方
水引の種類は複数あります。地域や包む金額などをもとに適したものを選択しましょう。封筒に水引が印刷されたものは5千円くらいまでで、高額の場合は本物の水引がついた封筒を選ぶと、封筒と中身のバランスが見合います。
また、水引の結び方は「結び切り」と「蝶結び」の2種類です。何度あってもうれしい慶事には「蝶結び」を用いますが、忌事は不幸が重ならないよう「結び切り」を選ぶようにします。忌事に用いる水引の種類は、以下の通りです。
| 水引の色 | 使用場面 |
| 黒白(または青白) | 5千円以下の玉串料に使用。水引が印刷されていることも多い。 |
| 黄白(または黄銀) | 1万円~5万円の玉串料に使用。関西地方以西で用いられることが多い。 |
| 双銀(または双白) | 5万円以上の玉串料に使用。封筒の大きさにも注意。 |
慶事用の玉串料を包む封筒の選び方
忌事と弔事では、封筒や水引の種類が明確に異なります。忌事は誰かが亡くなるなど、明るくないことに用いるため、主に黒や白、銀を用いる場合が多い傾向です。
しかし、慶事の場合は紅白が主になり、水引の結び方も忌事とは違うので注意しましょう。
慶事用の玉串料を包む袋を選ぶ際の注意点
慶事用の封筒は、紅白の水引が印刷、または実物がついているものを選びます。封筒の右上に折りのしなどが印刷されているのも、慶事用封筒の特徴です。
封筒を選ぶ際に注意するポイントは以下の通りです。
・金額や宗教、地域によって封筒の大きさや水引の種類が異なる
・慶事の内容で水引が変わることもある
・中袋があるものとないものがある
水引の色、結び方
慶事の玉串料の水引は、「紅白蝶結び」が基本です。ただし、婚礼の場合には「結婚が繰り返される=この婚礼がうまくいかない」という意味にならないよう、紅白結び切りの水引を使用します。
紅白のほか、慶事用の水引には金銀や赤金のものもありますが、玉串料として使用するなら、紅白のものを選びましょう。
お祓いの際の玉串料の場合
厄払いや子どものご祈祷など、さまざまなお祓いの場合も、紅白蝶結びの封筒を使用します。「お祓い」というとマイナスなイメージがあるかもしれませんが、お宮参りや七五三などのご祈祷は、お祝いの意味が強い傾向があります。
また、厄除けも「厄を祓ってよい方向に行く」というプラスの意味で捉えられ、慶事と同様の扱いを受けます。水引の色は「葬儀や法要は白黒、その他は紅白」と覚えておくと、わかりやすいでしょう。
玉串料を包む封筒の書き方見本
玉串料を神社やお寺に納めるときには、封筒の表書きや中袋への記入が必要です。中袋の有無によっても、書き方は異なります。
また、「玉串料」以外にも、お供えするお金には複数の名称があるので、覚えておくとよいでしょう。
葬儀の場合の表書きの書き方
忌事の封筒の表書きは、「玉串料」のほか、「御玉串料」「御霊前」「御榊料」「御神前」といった書き方があります。宗派などにより異なりますので、玉串料を用意する前に確認しておくとよいでしょう。
封筒の水引より上部分の真ん中に、「玉串料」といったの文言を書き、水引より下の部分に、贈り主の名前を書きます。以前は「涙で墨がにじむ、薄くなる」という意味から、薄墨で書くのが一般的でしたが、最近では普通の墨や筆ペン、油性ペンなどで表書きをする方も少なくありません。
忌事以外の場合の表書きの書き方
お宮参りや七五三のご祈祷、厄払いや地鎮祭といった、忌事以外で納める玉串料にも、「初穂料」「御神饌料」「御礼」など、玉串料以外の呼び名があります。これを水引の上中央に、下段中央に名前を記入しましょう。
忌事の場合は贈り主の名前でしたが、子どものご祈祷の場合は、封筒に子どものフルネームを記載しましょう。
中袋の書き方
ご祝儀袋・不祝儀袋ともに、表書きをした包みの中にお金を入れる中袋があることが一般的です。中袋には「いくら入っているのか」「誰が贈ったか」という大きく2点を記載します。
金額は表の中央部分に、特別な漢数字で書くのが一般的です。住所と氏名は裏面の左下に記入しましょう。
中袋がない場合の書き方
水引が印刷してあるタイプの封筒は中袋がありません。水引が実物の場合も、中袋のない封筒は存在します。中袋がない場合には、お金を入れて表書きをした封筒の左下に、住所と金額を記入しましょう。
もし、余裕があれば和紙や白い封筒を用意して、中袋の変わりにするのも1つの方法です。
連名の場合の書き方
複数人で玉串料を出す場合も、3名までは1人の場合と書き方は同様です。下段中央に、フルネームで名前を書きましょう。4名以上の場合は、代表者の名前のみ中央に記載します。他の方の名前は割愛して、左下に「他一同」と記載しましょう。
玉串料に関するマナー
玉串料を納める際は、封筒の種類や書き方など、注意したい点がいくつかあります。表書きのように目に入りやすい部分はもちろんのこと、お札の入れ方といった細かな部分にも気を配り、マナー違反にならないようにしましょう。
中に入れるお札のマナー
お札には新札と、ある程度使用感のある折り目のついたお札の大きく2種類があります。「慶事には新札」というのが一般的な考えですが、「お宮参りや七五三など、慶事の際の玉串料は必ずしも新札でなければならない」ということはありません。
あまりにもボロボロでなければ、多少折り目がついているものを入れても問題ないでしょう。しかし、おめでたいことに対して神様に捧げるものなので、できるだけ新札を用意することをおすすめします。
一方、忌事の玉串料は新札の使用は控えましょう。新札しか手元にない場合は、一度折り目をつけてから入れるようにしましょう。
お札の入れ方
封筒にお札を入れるときには、お札の向きにも注意が必要です。表裏、上下の決まりを確認しましょう。
・慶事、忌事どちらも全てのお札の裏表、上下をそろえる
・どちらも肖像画が表に来るように入れる
・慶事では肖像画が上向きになるように入れる
※封筒から出したときに肖像画がすぐに見えるようにする
・忌事では肖像画が下向きになるように入れる
※封筒から出したときに肖像画が最後に見えるようにする
書く際に使う筆記具のマナー
封筒に「玉串料」などの文字を書く際の筆記具は、筆や筆ペンが一般的です。忌事は薄墨で書かれていましたが、最近は慶事と同様の濃さのものを用いる方が増えています。また、日頃から筆や筆ペンを使い慣れていない方は、油性ペンで書いてもマナー違反にはなりません。
ただし、ボールペンのように文字が細くなるものは、見た目のバランスが悪いので避けた方がよいでしょう。
玉串料の金額相場
一般的な玉串料の金額相場は以下の通りです。あくまでも目安なので、神社やご祈祷の内容によっても玉串料は異なると考えておきましょう。具体的なご祈祷の種類や神社が決まったら、事前に金額を確認することも忘れてはいけません。
| 行事名 | 金額 |
| 安産祈願 | 5千円~1万円 |
| お宮参り | 5千円~1万円 |
| 七五三 | 5千円~1万円 |
| 地鎮祭 | 3万円 |
| 結婚式 | 5万円~10万円 |
| 厄払い | 5千円~1万円 |
| 葬儀 | 30万円~40万円 |
| 法要 | 3万円~5万円 |
旧字体の漢数字見本
玉串料の金額を記載する場合は「旧字体」を用います。日常的に使用する「一」「二」などの漢数字は線を簡単に書き足すことができ、入っている金額と異なる恐れがあるからです。
中袋に書く漢字は以下を参考にしてください。
| 数字 | 漢字 |
| 1 | 壱 |
| 3 | 参 |
| 5 | 伍 |
| 7 | 七・漆 |
| 10 | 拾 |
| 100 | 百 |
| 1,000 | 阡、仟 |
| 10,000 | 萬 |
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
慶事、忌事の際に神様に納める玉串料は、御祈祷料や初穂料、御礼、御霊前など、用途によってさまざまな名称が存在します。水引の種類やお札の入れ方についても、マナーを守って正しく納められるようにしましょう。
神道では、葬儀でも玉串料を用意します。葬儀で玉串料を渡すタイミングや正しい渡し方、事前に必要な準備などがわからないという場合にも、24時間365日対応の小さなお葬式へぜひご相談ください。
事前準備以外にも、お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



直葬とは、通夜式や告別式などの式をはぶき、火葬のみを行う葬儀のことです。ホゥ。