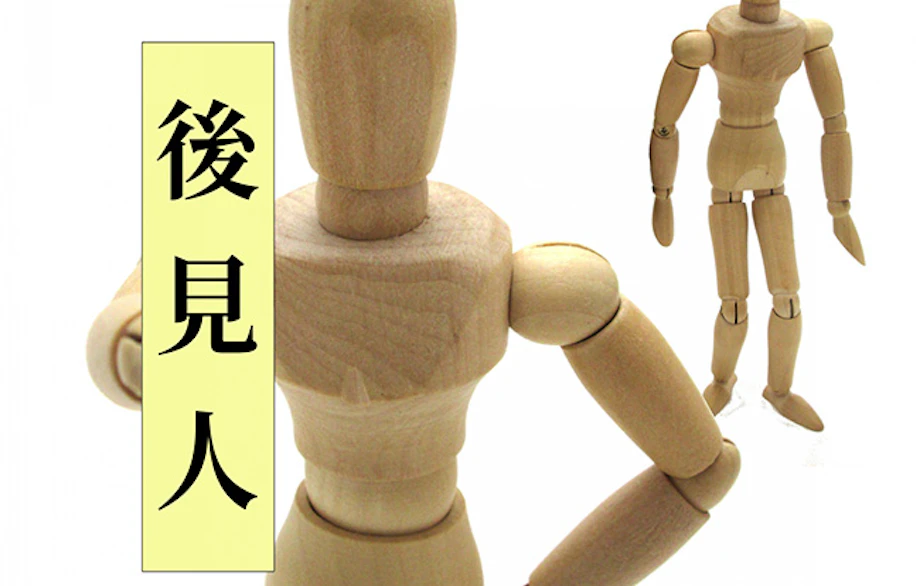成年後見制度は、認知症や知的障害などで判断能力が低下した方の代わりに、後見人が財産管理や法的手続きを行える制度です。生前の相続対策としても有効ですが、どのようなケースで必要なのか、きちんと知っておきましょう。
この記事では、後見人が必要な相続手続きとは何か、成年後見制度の特徴も含めて解説します。
<この記事の要点>
・遺言書がある場合や不動産の法定相続手続きでは後見人を立てる必要はない
・成年後見人になると、裁判所の許可がなくても相続放棄ができる
・成年後見人の対象になるのは配偶者や子供などの親族で、家庭裁判所の選任によって決まる
こんな人におすすめ
生前の相続対策のひとつである成年後見制度を知りたい人
成年後見制度を利用する流れを知りたい人
成年後見制度になれる人の適用条件を知りたい人
相続手続きで後見人が必要となる場合
相続が発生した際に、遺言書を残していない場合は、相続人同士で遺産分割協議を行うのが一般的です。しかし、相続人の中に認知症や知的障害などによって判断能力が低下した方がいる場合は、成年後見人を立てる必要があります。
後見人が本人に代わり遺産分割協議に参加することで、得られる法定相続分をきちんと受け取ることができます。
相続人が認知症でも後見人が必要ない場合
相続人が認知症であっても、遺言書がある場合や不動産の法定相続手続きでは後見人を立てる必要はないでしょう。ここからは遺言書がある場合と不動産を法定相続する場合について紹介します。
遺言書がある場合
被相続人が生前に遺言書を作成し、相続に関して明示していれば、後見人を立てる必要はないでしょう。遺言書があれば、基本的にその遺言書の指示通りに遺産相続が行われます。そうなると遺産分割協議を行う必要がないため、後見人の出番もありません。
不動産を法定相続する場合
土地や建物といった不動産の法定相続手続きは、相続人の誰か1人が行えばよく、成年後見人がいなくてもできます。そのため認知症や知的障害の方が関与する必要はなく、成年後見人を立てる必要はありません。
とはいえ、株式や預貯金といった金融資産においては、相続人全員の署名・捺印が必要となるため、成年後見人が必要となるでしょう。
後見人による相続放棄はできるのか
成年後見人になると、本人に代わって法的手続きを行えるため、裁判所の許可を得ずとも相続放棄が可能です。しかし、本人の利益を害する相続放棄が発覚した場合、後に責任追及される恐れがあります。
成年後見人になると、年に1回、家庭裁判所に定期報告をする必要があります。その際に相続放棄したことについても報告する義務があり、不適格な判断だとみなされると、解任される可能性が出てくるでしょう。
成年後見制度とはどんな制度?
まず、成年後見制度とはどのような制度なのでしょうか。相続対策として、この制度の特徴についてきちんと知っておくことが大切です。ここでは、成年後見制度の特徴について解説します。
成年後見制度の特徴
成年後見制度とは、認知症や知的障害などによって判断能力が低下した方を保護する制度です。被後見人にとって難しい意思決定や契約手続き、財産管理などを後見人が代わりに行えます。
成年後見制度を利用すれば、被後見人が不利な契約を行ったり、詐欺被害に遭ったりすることを防止できるのがメリットです。
法定後見制度と任意後見制度とは?
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分類されます。法定後見制度は本人がすでに判断能力が低下している際に利用する制度で、家庭裁判所が後見人を選任します。
任意後見制度は、今後判断能力が低下したときのために備える制度で、被後見人自らが後見人を指名します。
| 【制度】 | 【判断能力】 | 【選任・指名者】 |
| 法定後見制度 | 本人がすでに低下している | 家庭裁判所 |
| 任意後見制度 | 今後低下したとき | 被後見人本人 |
成年後見人には誰がなるのか
成年後見人は誰でもなれるわけではありません。親族をはじめ、弁護士や司法書士といった専門職が選任されるのが一般的です。ここでは、成年後見人の対象者やどのような基準で選ばれるのか解説します。
成年後見人の対象者は?
成年後見人の対象となるのは、配偶者や子供、兄弟姉妹といった親族です。また第三者である弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家も成年後見人になれます。
しかし、未成年者や破産者、本人に対して裁判を起こしたことがある方などは成年後見人にはなれません。
家庭裁判所の選任で決まる
成年後見人は家庭裁判所が選任するのが一般的です。成年後見人になるために必要な資格は特になく、被後見人にとって利益になる方が選ばれます。成年後見人は1人の場合もありますが、場合によっては複数人選任されることもあります。
成年後見制度の注意点
成年後見制度はメリットばかりのように思いますが、注意すべき点もいくつかあります。それは、費用が発生することです。
成年後見制度を利用した場合、手続きに関する手数料や、後見人への報酬が発生します。弁護士や司法書士といった専門家に依頼すれば、毎月数万円はかかるでしょう。また後見人へ財産管理を委ねることで、横領される可能性もあるかもしれません。
成年後見制度を利用する流れ
成年後見制度を利用するにあたって、さまざまな手続きが発生します。時間もかかるうえに煩雑であるため、どのような流れで進むのか知っておくとよいでしょう。ここでは、成年後見制度を利用する流れを紹介します。
1.申立をする
まずは裁判所へ申立てができる方と、後見人の候補を決め、家庭裁判所に申立てをします。申立てができる方は、本人や配偶者、4親等内の親族、市区町村長です。また申立てには、申立書や財産目録、親族の同意書などの書類を用意する必要があります。
2.家庭裁判所の審理をする
続いて、家庭裁判所の審理が始まります。裁判所側が申立書類を確認した後、申立人や後見人候補者との面接を行い、被後見人や被後見人を取り巻く状況を確認します。
必要に応じて本人と面接を行うこともありますが、本人が外出困難な場合は、家庭裁判所の担当者が直接訪問するケースもあります。親族の意向を照会する形で、家庭裁判所の審理を行います。
3.成年後見開始の審判や選任をする
成年後見開始の審判を行い、後見人の適任者を選任します。必要に応じて、成年後見人を監督する「成年後見監督人」が選任されるケースもあるでしょう。後見人の報酬が決まり、選任者に審判の内容を記した審判書が送付されます。
4.審判が確定する
審判書が到着して2週間経過すれば、後見の開始となります。後見人の住所や氏名、権限などが法務局に登記されます。審判の内容に不服がある場合は、審判書到着後の2週間以内であれば、申立人や利害関係人は不服の申立てをすることも可能です。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
成年後見制度は、認知症や知的障害などによって判断能力が低下した際に、後見人に意思決定や財産管理を任せられる制度です。生前の相続対策としても有効であるため、万が一に備えて利用を検討するのもよいでしょう。
しかし、後見人への報酬が発生したり、横領のリスクがあったりと、注意すべき点もあります。この記事で紹介したポイントをしっかりと押さえておきましょう。
小さなお葬式では、24時間365日、通話料無料でご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。
事前準備以外にもお亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


告別式とは、故人と最後のお別れをする社会的な式典のことです。ホゥ。