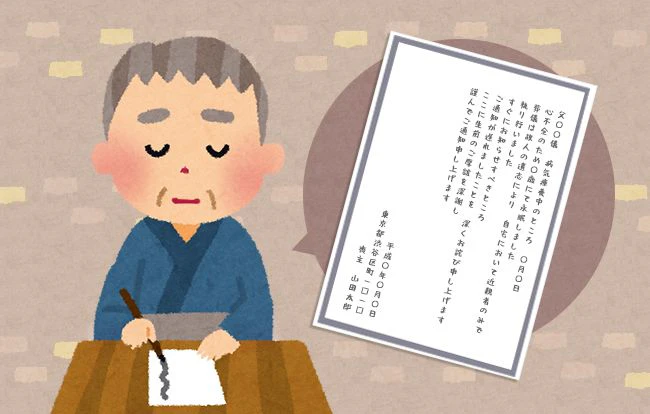葬祭扶助制度とは、生活保護を受けているなど経済的に困窮している人に対し、葬儀の費用を自治体が支給するものです。遺族が生活保護を受けていて葬儀費用をまかなえない、あるいは生活保護受給者だった人の葬儀を遺族以外の人が手配するなどの場合に利用することができます。
この記事では、葬祭扶助制度の概要、利用条件、支給金額の目安と可能な葬儀の内容、および申請方法についてご紹介します。
<この記事の要点>
・生活保護受給者や遺族が対象で、最低限の葬儀費用を自治体が支給する制度
・遺族の資金で葬儀が行えない場合や扶養義務者がいないなどの条件が必要
・申請は市町村の役所や福祉事務所でかならず葬儀の前に行う
こんな人におすすめ
葬祭扶助を受けられる条件を知りたい方
葬祭扶助で可能な葬儀を知りたい方
家族や親族が生活保護を受けている方
葬祭扶助とは
葬祭扶助とは、生活保護を受けているなど経済的に困窮している人に対し、葬儀費用を自治体が支給するものです。生活保護法の第18条に定められています。遺族も経済的に困窮していて葬儀の費用をまかなえない、あるいは遺族以外の人が葬儀を手配するなどの場合に利用することができます。
葬祭扶助で支給される金額は、最低限の葬儀を行うことができるだけの費用です。僧侶の読経などは基本的に行われず、直葬(ちょくそう)と呼ばれる火葬だけのお別れになるのが一般的です。
葬祭扶助の申請は、葬儀の前に、市町村の役所あるいは福祉事務所で行います。委任状など必要な書類が揃っていれば、葬儀社が代行して行うこともできます。また支給される葬儀費用は自治体から葬儀社に直接支払われる仕組みになっています。
<生活保護受給者の方へ>
小さなお葬式では、生活保護受給者の方が葬祭扶助が適用された場合に限り、自己負担0円で必要最小限のお葬式(直葬)を行うことが可能です。
詳しくはこちらをご確認ください。お電話(0120-215-618)でもサポートいたします。
葬祭扶助を受けられる条件
葬祭扶助は、故人が生活保護を受けていたなど経済的に困窮していて、葬儀のための資産を残していないことが前提です。そのうえで、以下の2つの条件のいずれかに当てはまる場合に利用することができます。
自分が該当するかどうか不安なときは、福祉担当のケースワーカーに相談をおすすめします。
条件1 遺族が生活保護を受けるなど困窮している
故人の遺族が葬儀を執り行う場合には、遺族も生活保護を受けるなど経済的に困窮していて、葬儀費用を負担できないことが条件です。故人が生活保護を受けていても、葬儀費用をまかなえるだけの収入や資産が遺族にある場合には、葬祭扶助を受けることはできません。
条件2 扶養義務者がおらず遺族以外の人が葬儀を手配する
故人に扶養義務者がいない場合には、家主や民生委員などが葬儀を手配することとなります。その場合にも、葬祭扶助を受けることができます。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
支給される金額の目安と可能な葬儀の内容
葬祭扶助によって支給される金額の目安および可能な葬儀の内容を見ていきましょう。
葬祭扶助によって支給される金額の目安
葬祭扶助によって支給される基準額は、次のようになります。
| 大人 | 子供 |
| 206,000円以内 | 164,800円以内 |
※ただし、自治体により異なる場合があります。
可能な葬儀の内容
生活保護法第18条において、葬祭扶助は次の範囲内で行うとされています。
1. 検案
2. 死体の運搬
3. 火葬または埋葬
4. 納骨その他葬祭のために必要なもの
そのために、葬祭扶助で支給される内容は、具体的には次のようなものとなります。
・寝台車
・ドライアイス
・枕飾り一式
・安置施設使用料
・棺
・仏衣一式
・棺用布団
・霊柩車
・火葬料金
・骨壷・骨箱
・お別れ用の花束
・自宅飾り一式
・白木位牌
僧侶の読経などは原則として含まれません。
葬祭扶助で可能な葬儀の流れ
葬祭扶助が行われる内容が以上のようなものであることから、葬祭扶助を受けて行う葬儀は通夜や告別式などは行わず、「直葬」と呼ばれる次のような流れで執り行われるのが一般的です。
1. 故人が亡くなった場所から安置施設まで寝台車で移動する
2. 火葬の日まで故人を安置する
3. 故人を棺に納棺し、火葬場へ霊柩車で移動する
4. 火葬し、骨壷に遺骨を納める
なお、葬祭扶助制度の詳細については、次の記事で確認することができます。
葬祭扶助の申請方法
葬祭扶助を申請するための方法を見ていきましょう。葬祭扶助は事前に申請しなければ受けることができません。
申請者は喪主あるいは葬儀社が代行
葬祭扶助の申請は原則として喪主が行います。ただし、喪主の委任状や印鑑などがあれば、葬儀社が代行することもできます。
申請先は市町村の役所か福祉事務所
葬祭扶助の申請先は、市町村の役所あるいは福祉事務所です。住民票がある自治体が申請者と故人とで異なる場合は、原則として申請者の住民票がある自治体で申請します。
かならず葬儀前に申請する
葬祭扶助の申請は、かならず葬儀の前に行います。葬儀後の申請は、受付がされません。
<生活保護受給者の方へ>
小さなお葬式では、生活保護受給者の方が葬祭扶助が適用された場合に限り、自己負担0円で必要最小限のお葬式(直葬)を行うことが可能です。
詳しくはこちらをご確認ください。お電話(0120-215-618)でもサポートいたします。
葬祭扶助の注意点
葬祭扶助を利用する際は下記に注意しましょう。
・申請は必ず葬儀をする前に行う
・直葬以外の葬儀はできない
・僧侶の読経や戒名授与はできない
・お墓や法要の費用は含まれない
・自己資金を足すことはできない
ここからは1つずつ解説します。
申請は必ず葬儀をする前に行う
葬祭扶助の申請は必ず葬儀前に行わなければいけません。生活保護法が適用されるのは、経済的に困窮する方であることが前提あり、香典などで手元にまとまったお金があると支払能力があるとみなされてしまいます。
直葬以外の葬儀はできない
葬祭扶助では一般的な葬儀は認められていません。また、支給された扶助費では一般的な葬儀が金額には届きません。
僧侶の読経や戒名授与はできない
一般的な葬儀が認められていない以上、祭壇を飾ってお坊さんに読経をしていただくことはできません。葬祭扶助制度が適用される場合は戒名をつけてもらうためのお布施の支払いも難しい状態だと考えらえます。お布施が支払えなければ、戒名をつけてもらうこともできません。
お墓や法要の費用は含まれない
葬祭扶助で支給される扶助費は直葬にかかる金額のみとなっています。故人が大人の場合、20万6,000円以内、12歳未満の子どもの場合は16万4,800円以内が目安です。
自己資金を足すことはできない
基本的に葬祭扶助は、あくまでも葬儀費用がまかなえない人に対しての救済措置として位置付けられており、葬儀費用を補う制度ではありません。そのため、自己資金を追加して華美な葬儀を行うことはできません。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ
まとめ
葬儀に関するご準備は事前に行うことが大切です。いざという時困らないように、葬儀全般に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
葬祭扶助の申請が遅れたらどうなる?
申請扶助が受理されなかったらどうなる?

自身が亡くなったときのために、エンディングノートを書いておくのもおすすめです。ホゥ。