相続とは、被相続人が所有していた不動産や預貯金などを引き継ぐことです。相続をするためには、手続きを行わなくてはなりません。しかし親が亡くなってしまった際、相続に関する手続きは何をしたらいいのかわからない方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、相続時に行う必要がある手続きについてご紹介します。内容を参考にすれば期限を考慮しつつ、相続時の手続きをきちんと遂行することができます。少しでも相続で悩む可能性がある方は、ぜひ参考にしてください。
法律では、生前に遺言書を作成することで家族以外に財産を引き継ぐことも可能です。遺産相続ができるかどうかは、遺言書の有無や効力によって左右します。また、相続には負の財産を相続することも含まれます。
事前に対処する方法を知っておけば、トラブルを回避できます。自分の身を守るためにも、この記事を読んで「相続」について押さえておきましょう。葬儀全体の流れについては別のページで詳しくまとめています。葬儀がまだの場合は、ぜひ参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・親が亡くなった場合、まずやるべき相続手続きは3つある
・「相続放棄」や「所得税の準確定申告」は期限が短いため、早めに手続きを始めるとよい
・遺産相続人が決まったら、遺産分割協議と凍結されている故人の銀行口座の解除を行う
こんな人におすすめ
親が亡くなったときの相続手続きを網羅的に知りたい人
相続手続きの手順・優先度について知りたい人
相続以外の主な手続きも知りたい人
親が亡くなったらまずやるべき相続手続き
親が亡くなった場合、やるべき相続手続きが3つあります。それは、「相続人を調べる」、「相続財産を調べる」、「遺言書の検認をする」ことです。これらの手続きをしておかないと、あとで大きなトラブルが発生してしまいます。
なぜなら、生前に遺言書を作成することで家族以外にも財産を相続させることが可能だからです。トラブルになる前に、手続きをすることをおすすめします。
相続人を調べる
相続人は、民法で順位が定まっています。まず配偶者が常に相続人となり、つづいて第1順位は子(子が死亡している場合は孫)。第2順位は、父母(父母が両方とも死亡している場合は祖父母)。第3順位は、兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪)の順です。
相続人が誰になるかを確認する際は、故人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本をもとに調べます。取得方法は、直系家族が役所にて自身の謄本を取り、故人の戸籍謄本を取得する流れです。郵送で取り寄せることもできます。
相続財産を調べる
相続財産を正確に調べておかないと、あとになって把握していなかった相続財産が見つかり手続きをやり直すことがあります。あとから相続財産が発覚した場合は、税務調査を受けて相続税を追加徴収されるケースや、最悪の事態として延滞税や過少申告加算税などが課されることもあります。
遺産相続には、借金も含まれます。そのままにしておくと故人の借金を肩代わりすることにもなるため、早めの手続きが必要です。借金額が多い場合は、相続放棄を検討しましょう。
遺言書の検認をする
遺言書は書いてある内容を見てはならず、家庭裁判所に提出しなければいけません。この手続きは、遺言書の存在を明確にすること、偽造を防ぐことが目的です。具体的には、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造を防止します。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもとで開封をする決まりがあります。勝手に開封をすると罰則により処罰を受けるので注意しましょう。
<関連記事>
遺言書の書き方や無効になるケースと対処法
注意が必要!相続手続きで期限が短いもの
相続手続きには、期限が短いものがあります。1つは、負の財産が多いときに手続きをする場合の相続放棄です。もう1つは、準確定申告と呼ばれる故人の分の確定申告です。
見過ごしているとすぐに期限が過ぎてしまい、のちのち厄介なトラブルにつながります。どちらも相続人が行わなければならないため、早めの確認と手続きが重要です。
相続放棄
相続放棄の期限は、相続開始を知ってから3か月以内です。手続きは、自分で行うことができます。手に負えない場合は、弁護士に依頼することも可能です。どのような場合に、相続放棄したほうが良いのかご説明します。
故人が残した借金を自分で返済していく選択もできます。しかし現実的には、相続によって大きな損害を被ることを回避するために相続放棄をしたほうが良いでしょう。プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)を見比べた結果、相続放棄をするなら期限に間に合うように手続きをしましょう。
所得税の準確定申告
準確定申告は故人の分の確定申告で、申告時期は相続を認知してから4か月以内です。この申告は相続人が行う必要があります。また全相続人が行う必要があるため、確定申告付表を用いて全相続人が連署する決まりです。
準確定申告の対象は、被相続人の1月1日から亡くなった日までの所得を含みます。被相続人が3月15日までに亡くなった場合は、その前年の確定申告が行われていなければ前年分の申告も準確定申告として手続きが必要です。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
遺産相続人が決まったあとの手続き
遺産相続人が決まったあとにやるべきことは、遺産分割協議と凍結されている故人の銀行口座の解除です。遺産分割協議とは、遺産の分け方を決める話し合いを指します。凍結解除の手続きをする必要があるのは、被相続人が死亡したことが銀行に伝わると故人名義の銀行口座が凍結されるからです。
遺産相続人が決まったあとの遺産分割協議と、凍結されている故人の銀行口座の解除について確認しておきましょう。
遺産分割協議をして遺産を分ける
相続人全員が遺言の内容に反対する場合は、相続人の間で協議を行い相続人全員が納得のいく遺産分割を追求することが可能です。遺産を相談して分けることに決まった場合は、遺産分割協議を行います。
相続人が1人でも欠けた場合は、その協議結果は無効です。分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。相続人に未成年者がいる場合は、その代理人の参加が必須です。協議を終えたあとは遺産分割協議書を作成しておきましょう。
故人の銀行の手続きを行う
被相続人の口座を凍結する理由は、銀行口座に残っている預貯金は相続財産であり相続税の課税対象となるからです。相続人の一人が現金を引き出して持ち逃げをしてしまうリスクなどを回避するためでもあります。
口座の凍結を解除するためには、書類の提出が必要です。書類は、遺産分割の方法によって異なります。遺言書の内容通りに分割する場合は遺言書、遺産分割協議によって分割する場合は遺産分割協議書です。また、銀行による違いもありますので事前に各銀行へ確認しておきましょう。
生命保険を受け取る
故人が生命保険に加入していた場合は、契約上の保険金受取人が死亡保険金を受け取ります。故人が加入していた生命保険があるか否かを確認して、生命保険に加入していればすみやかに手続きをしましょう。保険金を請求できる期限は、死亡から3年以内です。
死亡保険金は、遺産相続で分け合う対象にはなりません。保険金をもらう手続きには、ほかの相続人の同意は不要です。まずは、保険契約者または保険金受取人から生命保険会社に連絡を入れましょう。
不動産や自動車などを相続する場合は名義を変更する
不動産を相続する場合の名義変更に必要な書類は、基本的に必要となる書類がいくつかあります。
・相続登記を行う対象不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
・被相続人の最後の戸籍(除籍)謄本(死亡の記載があるもの)
・被相続人の住民票(徐票)
・不動産を取得する者の戸籍謄本
・不動産を取得する者の住民票【自身で記載し作成する書類】
・登記申請書
・相続関係説明図
・固定資産評価証明書
・委任状(代理人が申請する場合)
法定相続分どおりに相続登記を行う場合の追加資料は、以下の2つです。
・被相続人の出生までさかのぼる除籍謄本・改正原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本(不動産を取得しない者のものも含む)
遺産分割協議のとおりに相続登記を行う場合の追加資料は、以下の4つのものが該当します。
・被相続人の出生までさかのぼる除籍謄本・改正原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本(不動産を取得しない者のものも含む)
・相続人全員の印鑑証明書【自身で用意する書類】
・遺産分割協議書(原本)
親が亡くなったあとに自動車を相続する場合の名義変更は、以下の手順で行います。
1. 自動車の名義人を確認する。
2. 自動車の相続人を決める。
3. 遺産分割協議書を作成する。
4. 名義変更に必要な書類を準備する。
5. 運輸支局で名義変更手続きを行う。
お金以外の自動車などの遺産相続には名義変更が必要であり、手続きも別になるので注意しましょう。
相続税の申告は全員ではない
相続税の申告は必ずしも全員が対象になるのではなく、金額によっては必要な人、そうでない人が出てきます。トラブルを防ぐために、遺産の金額を正確に把握・確認する必要があります。
また、相続税の申告は10か月以内に行う必要があります。相続税の基礎控除(3,000万円+600万円に法定相続人数をかけます)を超える際は、相続税を申告しましょう。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
相続発生から手続き期限が長いもの
相続をすることになってから手続きの期限まで長く、優先順位を考えると急がなくてもよいものがいくつかあります。長いからといって先送りにしてしまうと期限を迎えてしまったり、正当な遺産が確保されなかったりする場合もあるでしょう。
把握をした上で徐々に取り組んでいく必要があります。言葉を見ただけでは想像しづらい手続きが多いため、以下より項目にわけてご説明します。
遺留分減殺請求
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)は、遺言が「特定の人物に多くの財産を譲る」旨が記載してあったときに有効です。たとえば愛人に全財産を相続すると書かれていた場合、最低限の取り分を遺留分として確保できます。
相続人が遺産を相続し、残された人の生活を保障する意味もあるため、相続人の範囲や順位が定められているのです。権利として最低限の遺産を確保することは妥当な観点であり、該当する場合は手続きを行います。
葬祭費・埋葬料などの申請
葬祭費とは、亡くなった方が国民健康保険の被保険者だった場合や扶養の家族に適用します。葬式にかかる費用の一部が支給され、支給額は1万円~7万円と市区町村によって異なります。
埋葬料は国民健康保険以外の被保険者、つまり会社員の方が亡くなった際に該当します。こちらも葬式にかかる費用の一部支給があり、5万円です。申請期限は亡くなった翌日から2年以内で、埋葬料は死亡日の翌日より支給され、葬儀費は葬儀の日からと違いがあります。受け取りは生計をともにしていた家族、埋葬を行った方が対象です。
<関連記事>
埋葬料とは?申請方法や支給対象、注意点を解説
高額療養費の申請
高額療養費は、医療費が高額になった場合に上限が設定されており、負担が最小限に抑えられる制度です。病気やケガで医療費がかかりすぎてしまった場合など、上限がなければ多額の医療費を支払わなければなりません。
このような事態を防ぐ制度となり、保険適用の3割負担のうち超過分を払い戻しされます。自己負担の上限額は年齢と所得で決定し、見合った額になる計算です。申請は2年以内に行うように期限が設けられています。
死亡一時金の受給
年金を受け取る前に亡くなった場合、要件を満たすことで遺族が死亡一時金を受給できます。亡くなった方が保険料を納めている実績があり、前月まで国民年金第1号被保険者として36か月以上の納付実績が必要です。
免除期間があれば加味するため、相談すると良いでしょう。支給の対象となる遺族は生計をともにする家族が該当します。
1. 配偶者
2. 子
3. 父母
4. 孫
5. 祖父母
6. 兄弟姉妹
優先順位は上から順になっており、順位の高い遺族へ支給が行われます。
遺族年金の受給
一家を養っていた方が亡くなった際に、家族は遺族年金を受け取ることが可能です。この遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。それぞれの違いをご説明します。
遺族基礎年金は個人事業主や自営業だった場合に該当し、遺族厚生年金は会社員やサラリーマンが該当します。受給する条件としては遺族基礎年金が国民年金に加入していれば該当し、滞納があると支給がされないこともあります。遺族基礎年金は、残された家族が亡くなった方により生計を維持されていた場合に該当します。
<関連記事>
遺族年金は受け取れる?受給条件や知っておきたいこと
親が亡くなったらやる相続以外の主な手続き
相続は手続きが多く、期限もあるため手続きのし忘れがないように注意が必要です。それぞれ把握をしていないと突然対応をせまられる場合があり、慌ててしまうでしょう。事前に備えておくことでスムーズな対応ができます。以下より必要な手続きをまとめたので、ぜひ参考にしてください。
死亡診断書をもらい死亡届を提出
亡くなった方が病気などで医師の確認が行われた場合、死亡診断書が発行されます。事故の場合は死体検案書です。死亡診断書は死亡届と1枚の用紙になっており、受け取ったあとに必要事項を右側に記載します。
手続きをする際に多く使う書類となるため、なるべく早い段階(当日や次の日)で受け取っておきましょう。また、提出をすると手元には残らないため、複数枚もらうかコピーをしておくことをおすすめします。提出を行うと火葬許可証が発行されます。
健康保険などの資格喪失届の提出
健康保険、介護保険は亡くなった次の日より無効です。そのため、死亡が確認されたら14日以内に資格喪失届を役所へ提出・保険証の返却を行わなければなりません。自治体によっては自動的に資格喪失手続きとなる場合もありますが、保険証の返却は必須です。
詳しくは窓口にて案内がありますが、世帯主が亡くなった場合に扶養されていた方は健康保険証を返却して新しく健康保険へ加入する必要があります。会社員などの場合、ほとんど会社のほうで手続きを行うことが多いです。
年金の受給停止手続きを行う
年金を受給していた場合、亡くなった方の受給停止を申し出なくてはなりません。届け出がないまま受給をしてしまうと、不正受給として扱われます。具体的な手順は、年金相談窓口や年金機構に年金受給者死亡届を提出します。
受給停止の手続き期限は国民年金と厚生年金でそれぞれ違い、国民年金の場合は亡くなってから14日以内です。厚生年金の場合は亡くなってから10日以内のため、葬式が終わったらできるだけすみやかに手続きをしましょう。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
遺品の整理・お部屋の片づけが必要な方へ
小さなお葬式では、故人様のお荷物の整理、お部屋の片づけや掃除などを行う「遺品整理」サービスをご用意しています。お見積りは完全無料!料金にご納得いただけた場合のみのご依頼なので安心です。また、急いで片づけなければいけない、見積りや作業に立ち合えない、予算に余裕が無いなどのご相談も可能です。まずは以下からお問い合わせください。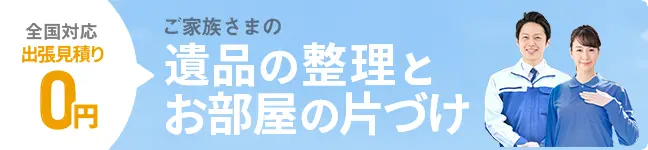
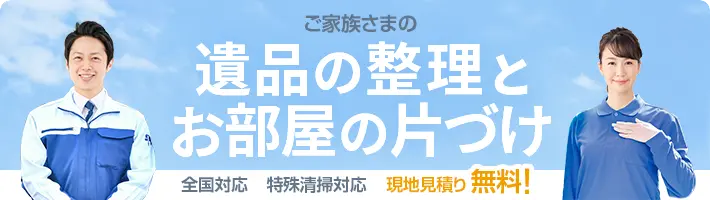
<関連記事>
死亡後の年金に関する手続きについて|もしもの時に役立つ知識
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
親が亡くなった場合の相続に関する手続きは複雑です。期限は短いものから長いものまであり、把握するには備えておかないと難しい場合があります。できるだけ期限が早いものから手続きを行いましょう。
相続の前に葬儀社を決めることになりますが、小さなお葬式ではお客様サポートダイヤルを設けています。葬式だけではなくそれらに関わる不安な部分を解消できるよう、サポートします。不安なことなどがあれば、相談だけでも小さなお葬式へご連絡ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
法定相続人って誰のこと?
相続放棄をしないと親の借金も肩代わりするの?
医療費の未払いがあるときは相続人が払うの?
亡くなった親のクレジットカードを使ってもいいの?
亡くなった親の銀行口座凍結のタイミングはいつ?
借家も相続の対象?
湯灌は故人の体を洗って清める儀式のことです。ホゥ。



























