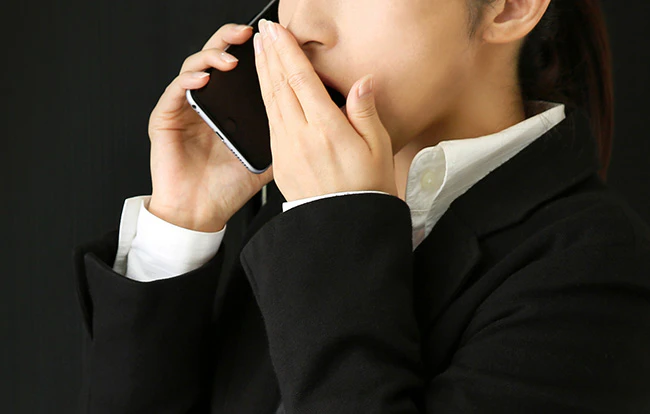危篤と重篤は、似た状況で使われることがある言葉です。どちらも医療の現場で聞くもので、患者が危険な状態にあることを指す言葉として用いられています。漠然と意味は把握していても、詳しい違いは分からないという方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、危篤と重篤の意味についてご紹介します。家族が危篤状態になった際にやるべきことも解説しますので、あわせて確認していきましょう。葬儀全体の流れについてあわせてご確認することもおすすめです。
<この記事の要点>
・危篤とは回復の見込みが薄い状態を指し、重篤とは命の危険があり予断を許さない状態を指す
・家族が危篤であると連絡を受けた場合は、臨終に立ち会えるよう至急病院へ向かう
・家族が危篤になった場合は親族や知人、職場に連絡する
こんな人におすすめ
危篤と重篤の意味の違いが知りたい人
家族が危篤になったときの対応方法が知りたい人
家族が危篤になったときの連絡方法が知りたい人
危篤とは?
危篤とはどのような状態のことなのか、まずはしっかりと理解しておきましょう。また、危篤とよく似た言葉に「重篤」があります。それぞれの意味の違いについても説明するので、参考にしてください。
危篤とはどういった状況?命はあとどれくらいなのか
死が目前に迫り、回復する見込みが薄い状態が危篤です。医師が患者の極端な脈拍の低下や呼吸微弱などから複合的に判断し、回復が困難とみなされた場合に危篤が宣告されます。
危篤になった場合でも、逝去するまでの時間は人によってさまざまです。宣告から数時間以内に逝去する場合もありますが、数日間にわたって小康状態(しょうこうじょうたい)を保つこともあります。亡くなるまでの時間は医師にもわからないため、危篤の連絡を受けたら可能な限り早く駆けつけることが大切です。
また、危篤と判断されてもまれに回復することもあります。危篤になったとしても、確実に亡くなるとは限らないことも覚えておきましょう。
危篤と重篤は意味が異なる?
重篤も命に危険が及ぶ状態を示す言葉ですが、危篤は死が想定される意味合いが含まれることに対し、重篤は主に症状の度合いを示す言葉です。しかし、どちらの言葉も命に関わる状態に変わりはありません。重篤はすぐに亡くなることはなくても、このままでは死に至ることを示しています。
重篤は危篤よりも医学用語として使用されることが多く、一般的には用いられない言葉です。危篤をはじめとして似た意味合いの言葉もあるため、多くの場合は「命を脅かす非常に重い病状」といった意味で使用されています。
一般的な解釈として重篤は、「危篤ほどではないが、命の危険がある予断を許さない状態」と考えるとわかりやすいでしょう。
家族が危篤となった際にすべきこととは?
家族が危篤になったと連絡を受けた際は、気が動転してしまって何をすればよいのか、わからなくなってしまうかもしれません。そのため、何をすべきかあらかじめ知っておくと安心です。
大至急病院へ行って危篤状態の本人に声掛け
危篤の連絡を受けた場合にまずしなければならないのは、病院に駆けつけることです。危篤状態と判断された人はいつ亡くなってもおかしくないため、ゆっくりしていると最期の瞬間に立ち会えない可能性があります。
回復する見込みが薄いという状況を理解して、臨終に立ち会えるように大至急病院へ行きましょう。可能であれば、数日間、泊まることになってもよいように準備をして行きます。
病室へ着いたら、危篤となった本人に声をかけましょう。感謝の言葉を伝えたり、本人との思い出を語ったりするのが通例です。ほかには、手を握ったり髪を整えてあげたりしながら、看取りのときを迎えます。
反応がなくても声は聞こえていることもあるため、言葉選びには気をつけましょう。「死ぬ」「助からない」といったネガティブな言葉を使うことは控えて、亡くなった後の話もしないようにするのがマナーです。
慌てないで!危篤になったときの心構え
家族が危篤となったとの連絡を受けた場合、まずは落ち着くことが大切です。大きく深呼吸して、気持ちを鎮めましょう。
病院へ向かうときに焦ると交通事故を起こしてしまう危険性があります。気を落ち着かせて、安全運転を心がけましょう。
また、つらいことではありますが、家族を看取る心構えを持たなければなりません。いつ亡くなってもおかしくないのだという事実をしっかりと受け止めましょう。
<関連記事>
危篤状態の本人にかける言葉とは?家族にかける言葉も紹介
小さなお葬式で葬儀場をさがす
危篤の際に連絡すべき相手とは?
家族が危篤になった際に、自分が病院に駆けつけるほかに関係者への連絡も必要です。気持ちが動揺している状態でも確実に伝えなければならないため、誰に連絡すべきなのかをあらかじめ把握しておきましょう。
親族や知人等への連絡
危篤の連絡を受け取ったら、まずは親しい親族や知人へ連絡します。同居している家族をはじめとして、親・子ども・兄弟・孫といった関係が近い親族へ知らせます。一般的には、三親等以内の親交が深い親族に連絡をすることが多いようです。
親族以外でも、関わりが深い人には連絡をする場合もあるので、関係性を考慮して臨機応変に判断する必要があります。多くの場合、プライベートでの親交がなければ、仕事関係者に声はかけません。危篤時は特に親しい人たちが最期の瞬間を看取るための時間ということを念頭に置いて判断するようにしましょう。
職場への連絡
危篤状態は数日に渡ることもあるため、立ち合いが泊まり込みになることも珍しくありません。長期間仕事を休むと人員不足などで業務にも影響が出る場合もあるので、早い段階で連絡を入れることが大切です。数日に渡って仕事を休む場合は、定期的に連絡を取りながらその都度状況を伝えて相談するようにしましょう。
職場に連絡する際は、直属の上司へ口頭で伝えるのが基本です。直接口頭で伝えられない場合は、電話でコミュニケーションを取りながら連絡するようにしましょう。メールはいつ読まれるのかわからないため、補助的な使い方に留めるのが賢明です。
牧師や僧侶への連絡
キリスト教では、危篤の人が存命のうちに臨終の儀を執り行います。臨終の儀では神父や牧師が祈りをささげるため、親族たちと同じタイミングで連絡をしましょう。神父や牧師も病室へ迎え入れます。カトリックでは神父、プロテスタントでは牧師を呼ぶので間違えないようにしましょう。
カトリックで臨終の儀を行う場合は、「病者の塗油(とゆ)の秘跡」を行うためのロウソクや聖水、タオルなども必要です。プロテスタントでは、信者へパンとワインを与える「聖餐式」を執り行います。
仏教の場合も、亡くなる前から僧侶に話を通しておくと、その後がスムーズになる場合があります。
<関連記事>
危篤状態は何日続くのか?身内が危篤になった際の対応法
危篤時の電話連絡の際に伝えるべき内容とは?
危篤を知らせる電話連絡は急を要するので、深夜帯や早朝であっても電話して問題ありません。その際は、「夜分遅くに申し訳ありません」「朝早くに恐れ入ります」といったひと言を添えると丁寧です。
危篤を伝える際は、自分と危篤の人の名前、危篤者との続柄から伝えます。危篤者の状態や医師から伝えられた残された時間も告げて、存命のうちに病院へ来てもらうようにお願いしましょう。
ほかには、病院に関する情報も伝えることを忘れないようにします。病院名・住所・電話番号・病室なども正確に伝達することが重要です。自分の電話番号も知らせて、何かあったらすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。
<関連記事>
危篤の読み方や使い方!危篤と言われたらどうするべき?
小さなお葬式で葬儀場をさがす
危篤の連絡方法と文例
危篤を知らせる際の連絡方法には、次のようなものがあります。
| 優先度 | 連絡方法 | 特徴 |
| 1. | 電話 | 迅速に連絡できる |
| 2. | メール | 伝えたい情報を文字によって確実に届けられる |
| 3. | SNSのダイレクトメッセージ | SNSでつながっている人にしか連絡ができない。不特定多数に情報が伝わらないように注意が必要 |
メールやSNSを確認するタイミングは受信した本人次第です。すぐに確認してもらえることもありますが、気づかれなければいつまでも読まれないこともあります。特に深夜や早朝に送った場合は眠っていて気づかれないことが多いので、電話が通じなかった際の補助として用いるようにしましょう。危篤メールの一例としては、以下のような内容を記します。
朝早くに恐れ入ります。
私は(危篤者の名前)の息子の(送信者の名前)と申します。
先ほど、父の容態が急変して危篤状態になったと病院から連絡がありました。
もって(医師から知られた余命)前後とのことです。
つきましては、存命の内にひと目お会いしていただけませんでしょうか。
父が入院している病院は(病院名)です。
住所:○○県○○市XXX-X ○○病棟XXX号室
(病院名)の面会時間はX時~XX時までとなっていますが、緊急につき、時間外窓口からお入りいただけます。
このメールをお読みいただけましたら、下記の私の携帯電話までお知らせいただけると助かります。
携帯電話番号:XXX-XXX~
冒頭の挨拶や病状を示す言い回しなどは、ご自身の状況に適した文章を当てはめて作成してください。
<関連記事>
危篤のメールをもらった時の返信方法&危篤を伝えるメールの送り方まとめ
危篤状態から亡くなってしまったときに必要な対応
家族が危篤になり亡くなった場合には、何をしなければならないのでしょうか。そのようなことは考えたくないと思う人がいるかもしれませんが、あらかじめ把握しておかなければ、いざというときに動けないものです。ここからは、もし亡くなった場合の対応について解説します。
葬儀の準備
家族が亡くなった場合、まず葬儀社に連絡をしなければなりません。すでに決めているところがあればスムーズですが、決めていなかった場合には葬儀社を選び、葬儀を依頼しましょう。連絡を受けた葬儀社は、遺体を自宅や葬儀場などの安置場所に搬送します。
葬儀の内容について葬儀会社と打ち合わせをした上で通夜や葬儀が執り行われますが、本人が元気なうちに、あらかじめ葬儀内容についても話し合っていた場合は、希望を伝えましょう。
死亡の連絡
故人が亡くなったことを、看取れなかった家族や友人といった、すぐに知らせたい関係者に連絡しましょう。また、通夜や葬儀の日程と会場が決まり次第、葬儀に参列してもらいたい人たちに連絡します。職場関係、学生時代の友人については、代表者に連絡をして広めてもらいましょう。
一方で、菩提寺の僧侶、あるいは神主、神父、牧師といった宗教関係者にも連絡をしなければなりません。最後に、故人の近所の人や町内会の人に連絡をしましょう。
自宅で亡くなった場合は?
病院ではなく自宅で療養中などに亡くなる場合もあります。自宅で亡くなった場合には、すぐにかかりつけの病院に連絡をしましょう。医師が臨終に立ち会っていなかった場合でも、24時間以内に診察・治療を受けていれば「死亡診断書」を発行してもらえます。
もし、かかりつけの病院がない場合には救急車ではなく、警察に連絡しなければなりません。事情聴取、現場検証の後に「死体検案書」が発行されるでしょう。
<関連記事>
危篤の意味とは?危篤時に行うべきことと葬儀までの流れ
小さなお葬式で葬儀場をさがす
葬儀をする際の注意点
亡くなった時点で、葬儀会社が決まっているか、決まっていないかでその後の進行が大きく変わります。病院と提携している葬儀会社に依頼もできますが、費用は高額になる傾向があるでしょう。
葬儀会社が決まっていないなら、複数の会社から見積もりを取ることをおすすめしますが、亡くなってからの短期間では難しいかもしれません。
できれば、事前に葬儀会社を検討するのがおすすめです。また、本人が元気なうちに、内容や費用については話し合っておくと、希望通りの葬儀を執り行えます。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
死が目前に迫り、回復する見込みが薄い状態が危篤です。危篤と重篤は症状の程度に差があります。どちらも命に関わる危険な状態ですが、危篤のほうがより深刻な死に直面した状態です。
危篤の連絡が入ると、親族への連絡や職場への休暇連絡といったことを行う必要があります。気持ちに余裕がない中でしなければならないため、メモを取っておくとよいでしょう。
また、亡くなってから葬儀の準備を始めると慌ただしくなり、十分な準備時間が確保できない場合が多く見られます。そのため、近年では、危篤を知らされた段階で葬儀の準備を始める方も珍しくなくなりました。小さなお葬式でも、生前での葬儀のご相談を承っています。ぜひお気軽にお問い合わせください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
病院へ向かう時に必要な持ち物は?
危篤状態から回復することもある?
重篤と重体は意味が違う?
重篤と重症は意味が違う?
臨終となった後の流れとは?
訃報の連絡はどの範囲まで行う?

湯灌は故人の体を洗って清める儀式のことです。ホゥ。