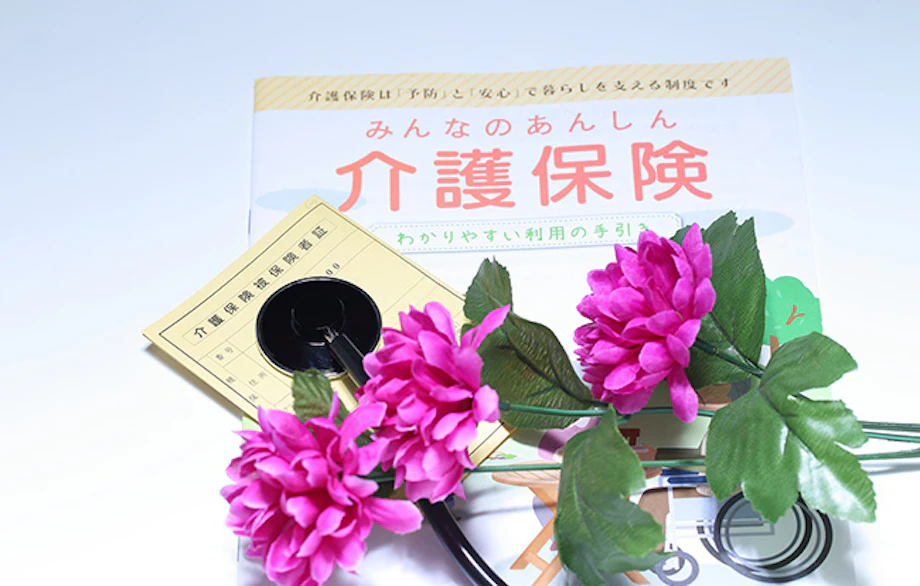「介護保険制度について詳しく知りたい」そうお悩みの方も多いのではないでしょうか。介護保険はご自身やご両親の方が介護になったときに生活の負担を軽くできます。ただし、介護保険は制度がどんどん改正されており、どんな制度なのかわからない人も多いでしょう。
ここでは介護保険制度の仕組みや保険料、サービス内容やよく聞かれる質問について基本的な知識を網羅してお伝えします。この記事を読めば、介護保険の手続きや保険料についてわかり、介護保険が必要になった場合に慌てずに対処できます。家族信託のサービスについても紹介しているので、参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・介護保険制度とは介護が必要な方に費用の一部を給付してくれる制度
・介護保険料の支払いは40歳から始まり、前年度の所得によって保険料が決まる
・介護保険サービスは大きく「在宅型」「施設型」「その他サービス」の3種類に分けられる
こんな人におすすめ
介護保険制度とはなにか知りたい方
介護保険制度にまつわるお金の基礎知識を知りたい方
介護保険で受けられるサービスについて知りたい方
介護保険制度とは
介護保険は国民が必ず加入している保険制度であり、介護が必要な方に対して自己負担1割~3割の間で様々なサービスを受けられる制度です。ここでは介護保険制度とはどんな制度なのか、その内容や対象年齢について詳しく解説します。
介護費用を給付するための保険制度
介護保険制度は何らかの病気により、介護が必要な方に対して、その費用を一部給付してくれる保険のことです。この保険は、税金と保険料で賄われており、一定年齢以上になった方は保険料を負担する義務が発生します。
一人ひとりに必要な介護サービスが選べる
介護保険で受けられるサービスは一人ひとり自分に必要な介護サービスを自分で選択できることが特徴です。一見すると当たり前に見えますが、実はそうではありません。
以前、介護は自治体が主体となって行われており、家族や利用者の意向が汲まれることはあまりありませんでした。その結果実際のニーズとかみ合わない対処になることも多かったようです。介護保険制度は定期的に改正されており、今後徐々に利用者のニーズに合わせて改善するのではないでしょうか。
現在介護サービスは、社会化が進んでおり、企業が介護事業へ参入することも増えました。これは競争原理を働かせることによって、サービスの質を向上させられることを目的にしています。
介護サービスの対象年齢
介護サービスの対象になるのは主に65歳以上で介護保険の支払いを行なっている方です。この方を第1被保険者と言います。第1被保険者が要介護認定を受けると、無条件でサービスの対象となります。
40歳~64歳の人は第2被保険者と呼ばれ、第2被保険者はほとんどの場合、この介護保険の支払いを受ける対象にはなりません。しかし、一部の条件を満たしている場合、介護保険の対象になります。
それが老化に起因する「特定疾病」によって介護認定を受けた場合です。特定疾病になるものとしては末期ガン、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症などの病気がこの特定疾病に該当します。
制度が始まった背景
介護保険制度ができた背景は女性の社会進出が進んだこと、社会保障費が増えたこと、施設介護から、家族介護に移行したことによる、女性の負担の増大がその背景にあります。
1960年代ごろの日本であれば、高齢者の割合もそれほど多くなく、介護負担もそこまでではなかったのですが、高齢社会が進んでいる昨今、医療費や介護にかかる費用が非常に高額になってきました。
このような状態を改善するために2000年4月から介護保険制度は整備されました。
介護保険制度の改正の経緯
介護保険制度は定期的に改正が行われており、時代に合わせて変化しています。ここでは改正される仕組みや今後の動向、これまでの改正の事例について見ていきましょう。
3年ごとに見直しがある
介護保険は3年ごとに定期的に見直される仕組みになっています。高齢化社会は日本でかなりのスピードで進んでおり、細やかな制度改正が求められています。そのため、今後も定期的に制度が変わっていくでしょう。
そのため、介護保険の支払いが始まったばかりという40代くらいの方であっても、今後の制度改正で関わりがでてくる可能性もあるため、少しずつ関心を持つようにするのをおすすめします。
これまでに行われた改正の例
介護保険制度は3年ごとに改正が行われており、徐々に変化しています。中でも新しいものとしては2018年の改正によって、介護サービスの自己負担額が1割~2割だったのが、1割~3割に引き上げられたことです。これは高齢化が進行することで、徐々に費用負担が増大したことが原因でしょう。
また介護職員の待遇改善や、介護事業者の不正防止などの取り組みを行い、介護の仕事環境を整える取り組みも行なっています。福祉用具レンタル価格の上限設定を行うことで、福祉用具のレンタルサービスが不当に高くなることがないようにしたのもその一つです。
「介護医療院」や「共生型サービス」が新しくできているのも、介護保険制度の改正の影響であり、時代のニーズに合わせて変化が加えられています。
今後の予測
今後の介護保険制度の予測として介護保険サービスは徐々に縮小されていくと考えられています。なぜなら高齢化によって財政はどんどん圧迫されており、その結果、介護保険のサービスの維持が難しくなっているからです。介護保険サービスの自己負担が最大3割になったこともその影響だと考えられます。
それ以外にも介護保険制度の改正で、自己負担額が徐々に増えている傾向にあり、サービスの適用範囲が狭まり、利用者への負担は今後徐々に増大していくと考えられるでしょう。
介護保険制度にまつわるお金の基礎知識
介護保険制度は2000年に新しくできた制度で、まだまだ馴染みがない人も多いかと思います。特に重要なのがお金の話です。ここでは介護保険に関わるお金の基礎知識をお伝えします。
介護保険料の支払いは40歳から
介護保険料の支払いは40歳から始まります。40歳から保険料の支払い義務が発生し、40歳から死亡するまで永続的に支払わなければいけません。本人の意思で加入するかどうか選べず、必ず加入することになります。
また介護保険料は民間のものにも加入することができ、それは任意で加入できます。将来的な介護を考えるのであれば、今のうちに加入を検討するのもおすすめです。
介護保険料の算定方法
介護保険料の算定方法は第1号被保険者の場合と、第2号被保険者の場合で計算方法が大きく変わります。それに加えて第2号被保険者の場合は国民健康保険に加入しているかどうかでも、計算が変わります。
一般的には前年度の所得が多ければ多いほど、保険料率の掛け率が上がり、高額になっていく仕組みです。保険料率は市区町村ごとに定められているもので、基準額や保険料率はお住いの地域ごとに変わるため、正確には問い合わせて確認してください。
介護保険サービスの自己負担額
介護保険サービスを受けたときの自己負担額は全体費用の1割~3割です。負担額の割合は利用者の所得額に応じて決められており、収入が多くなるほど負担額の割合が大きくなっていきます。
利用者の要介護の度合いによって上限額が定められており、その上限額を超えた利用金額は全額自己負担になります。ただし、1世帯1ヶ月あたりの利用者負担額が所得区分によって定められた上限額を超えた場合、利用者負担軽減を受けられます。
介護保険サービスの支給限度額
介護保険サービスは支給限度額があり、限度額を超えた支払いは自分で支払う必要があります。これは要介護度の度合いによって上限額が異なり、介護の必要性が高い方ほど限度額が高くなることが特徴です。
一般的には程度が軽い「要支援1」で月額約50,000円、程度が一番重い「要介護5」の場合は月額360,000円が限度額です。ただし、これは市区町村によっても異なるため、上限は確認しておく方がよいでしょう。
要介護認定を受けるには
介護保険を利用する場合、要介護認定を受ける必要があります。しかし、この要介護認定の手続きをどうやって進めるのか、いまひとつよくわからない人も多いのではないでしょうか。ここでは要介護認定を受けるための手続きのやり方について詳しく解説します。
1.自治体に申請する
要介護認定を受けるためには、まず自治体に申請する必要があります。市区町村の介護保険窓口で申請してください。なお、自分で申請することが難しい場合は、介護施設などに代行してもらえる場合もあるため、相談してみるとよいでしょう。
2.認定調査員によるチェック
この申し込みが行われると、まず認定調査員によるチェックが行われます。認定調査員が自宅を訪問し、申込対象者の心身の状態や毎日どのように生活しているのか調査し、「認定調査票」を作成します。
認定調査票をもとにコンピューターで自動判定する一次判定が行われます。この判定で問題なければ次に、「要介護認定審査会」にて二次判定が行われます。この二次判定では一次判定の結果と、「主治医の意見書」などの書類を参考に介護、医療、保険分野の専門家によって要介護の程度を決めます。
3.認定結果の判明
介護認定の結果に合わせて、認定結果の通知が行われます。認定結果は約1ヶ月後に出ることが一般的です。ここでは審査に通ったかどうかだけではなく、「要介護度」も通知されます。要介護度は以下のように分けられています。
・支援の必要がない「自立」
・一部の動作で手助けが必要な「要支援1~2」
・一部または生活全般の介護が必要な「要介護1~5」
大まかですが、数字が大きければ大きいほど、介護や支援の必要性が高く、介護保険の対象になるサービスの範囲が広がります。
介護保険で受けられるサービス
介護保険で受けられるサービスは大まかに「在宅型」「施設型」「その他サービス」の3種類に分けられます。ここではそれぞれのサービスの内容や特徴について詳しく解説します。
在宅型
在宅型とは、利用者が自宅にいながら、介護を受けられるサービスです。介護福祉士や訪問介護員が自宅で、日常生活で様々な手助けを行う訪問介護、デイサービスなど介護施設にてサービスを受ける通所介護、看護師や保健師が利用者の自宅で医療行為を行う訪問看護などがあります。
それ以外にも、短期間施設を利用し、介護を受けるショートステイ、ケアハウスなど特定施設への入居なども、この在宅型です。一部施設を利用していますが、いずれも短期入所の場合になります。
施設型
施設型とは、施設などで受ける介護サービスのことです。在宅型と一部似通っていますが、在宅型と異なり、要介護認定を受けていないと、利用できません。施設型の場合はそれぞれの施設に入院しながら介護サービスを受けることになります。
「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」や「介護老人保健施設老人保健施設」「介護療養型医療施設」などが代表的です。ただし、「介護療養型医療施設」は長期入院が増えて、財政状況を圧迫していることが問題となっており、2018年の法改正で廃止が決まりました。
その他のサービス
その他のサービスとしてあげられるのは、地域密着型のサービスや福祉器具のレンタルサービス、移動式浴槽にて、高齢者の自宅にお風呂を提供する訪問入浴サービスなどがあげられます。
2018年の介護保険制度の改正から、地域包括ケアシステムを推進させるということを重要視しています。地域包括ケアシステムとは、介護に必要なサービスを30分以内で受けられるよう介護のサービスの充実を測ることです。
サービスの内容は多様化が進んでおり、今後は介護ロボットの導入や情報通信技術の導入なども進んでいくでしょう。
家族信託という選択肢もある
ご自身やご両親の方に介護が必要になったときの心配ごととして、介護保険制度の他に、認知症のことがあるのではないでしょうか。認知症になると、法的に意思能力がないものとされる可能性があり、本人名義の不動産の売却や、銀行口座からの出金が凍結によってできなくなることがあります。唯一の対処法である「成年後見制度」も、費用や財政管理の面で戸惑う方が多いようです。
そこで今注目されているのが、大切な財産を信頼できるご家族に託す「家族信託」です。認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することができます。
ファミトラの「家族信託」は家族信託に必要な手続きを、弁護士や司法書士など多様な専門家がサポートし、誰でも簡単に・早く・安く組成できるサービスです。資産管理にお困りの方は、お気軽にお問合せください。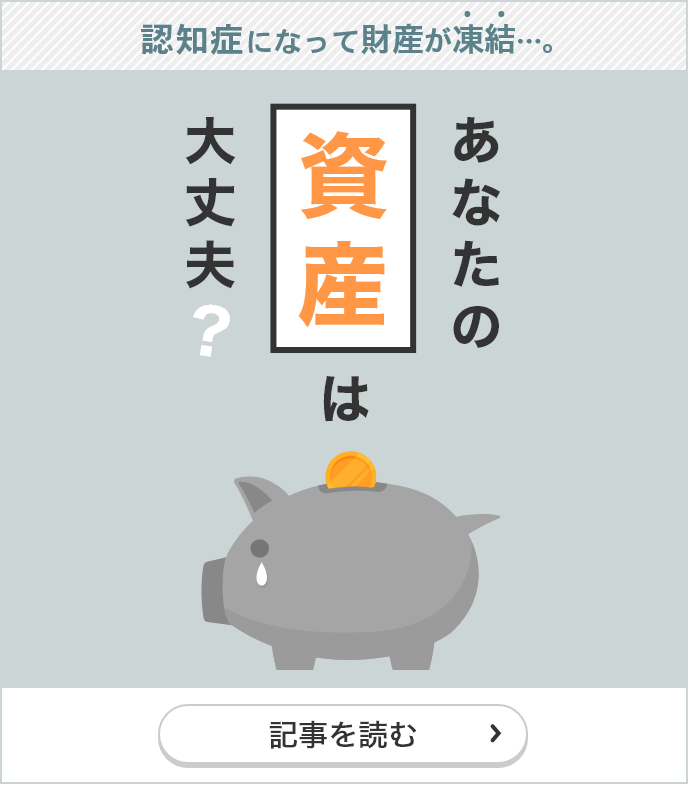
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
この記事では介護保険制度の仕組みや負担額、利用方法や申請の手続き、よく聞かれる質問などについて開設しました。介護保険制度は3年に一度内容の見直しが行われており、今後利用者のニーズや財政事情に合わせて制度はどんどん改正されるため、少しずつ理解を深めていくのがおすすめです。
介護についてその内容を知っておくことも大切ですが、高齢になってから考えるべきことの一つが自分の死後のことについてです。小さなお葬式では、いわゆる「終活」に備えて、情報を定期的に発信しています。
葬儀などにわからないことがある場合もぜひご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
収入が少ない場合、介護保険料を減免できる?
介護保険料を滞納するとどうなるの?
介護保険料は控除の対象になる?
健康状態が変わったらどうすればいい?
ケアマネージャーってどんな人?
地域包括支援センターとは?
御霊前は「亡くなった方の霊魂の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。