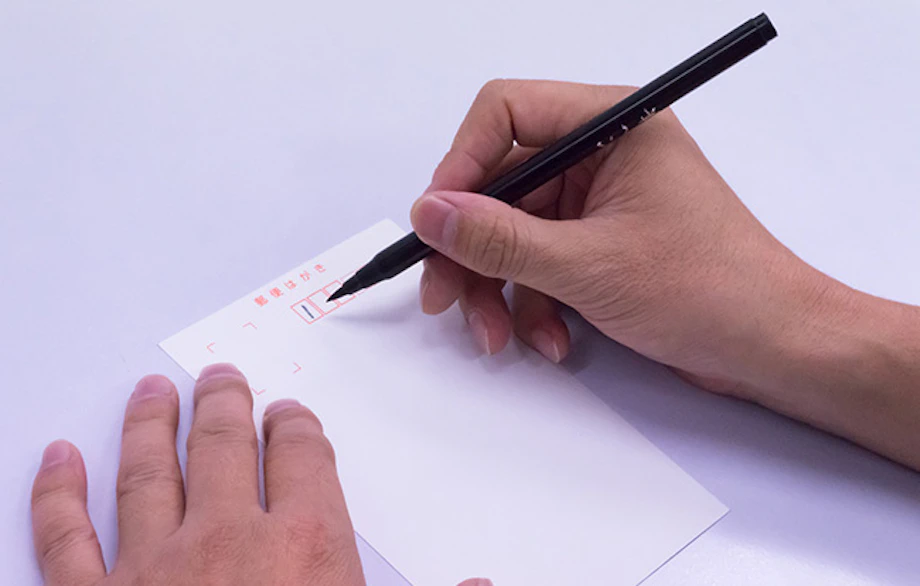故人が生前お世話になった人たちには、訃報をいち早く知らせたいものです。葬儀に参列してもらいたい人に日時を知らせることはもちろん、家族葬を行うなら、式を終えたあとに速やかに葬儀を執り行ったことを報告する必要があるでしょう。
訃報を伝える方法のひとつに、ハガキを郵送して故人が亡くなったことを知らせる「死亡通知状」があります。今回は死亡通知状を出すタイミングや、内容を記入する際の具体的な文例について紹介します。
<この記事の要点>
・死亡通知状とは、故人の氏名や年齢、葬儀の日取りなどを記載し生前の感謝を伝えるための手紙
・葬儀に参列してほしい人には、故人が逝去した後すぐに訃報ハガキを送付する
・死亡通知状には故人の宗派を記載する
こんな人におすすめ
訃報をハガキで伝える目的が知りたい方
訃報を伝える「死亡通知状」の記載内容が知りたい方
訃報ハガキを送るタイミングと文例が知りたい方
訃報をハガキで伝える目的は?死亡通知状とは?
死亡通知状とは、故人の氏名や年齢、葬儀の日取りなどの情報や、故人が生前お世話になった人に訃報を伝えて生前お世話になったことへのお礼を伝えるための手紙です。また、葬儀後に送る場合は滞りなく葬儀を済ませたことを報告する役割もあります。
葬儀の前であれば社葬が行われる際に会社の取引先などに葬儀の詳細を連絡したり、葬儀を執り行った後なら故人の友人や遠方に住む関係者に葬儀を執り行ったことを知らせたりする目的で郵送します。
訃報を伝える!死亡通知状に記載するべき内容
死亡通知状に記載する内容は複数あり、故人についての情報や葬儀に関する連絡などを明記して、葬儀に足を運んでもらったお礼や亡くなったことを知らせるのが遅くなったことへのお詫びなどを書き添えます。
また、死亡通知状は次の順番に基づいて記載するというマナーがあります。書く順序を間違えないように注意しましょう。
喪主との間柄と故人の氏名
差出人との間柄を記入し、続いて故人の氏名を記します。間柄については、たとえば「母」や「父」などになるでしょう。名前は社葬の場合や訃報ハガキを差し出す人と故人の姓が違う場合はフルネームを記入しますが、家族が喪主となる場合は下の名前のみでも構いません。
また、氏名の直後には忘れずに「儀」と記入しましょう。儀とは「○○について」、「○○に関して」という意味があり、名前の後に書き添えると「母 ○○について」という意味を表現できます。
死亡日と年齢
亡くなった日付と故人の年齢を記述します。数字にあたる部分はすべて漢数字を使うようにしましょう。死亡日については正確な時間が分かっていれば時刻まで書いても構いませんが、月日のみや、「未明」と記しても問題ありません。
場合によっては死亡理由を記載することもありますが、必須ではないので、差し出す遺族の判断で良いでしょう。たとえば「かねてから入院していた」「病気療養中であった」などの書き方をすることもできます。
葬儀に関する情報
お通夜と告別式の月日と会場について明記します。時間は「午後○時~○時」、「午前○時~○時」などのように12時間制で表記することが多いです。式場の場所を記入する際は参列者が迷わずにたどり着けるように、施設の名前だけではなく「○○駅下車」などと注釈を付けると親切でしょう。
また、香典や供物などを辞退する場合はその旨を記載します。遺族の希望で辞退することもありますが、故人が生前に受け取らないよう望むこともあるため、遺族と故人の意思を勘案して決めると良いでしょう。
お詫びやお礼
葬儀を済ませたあとに死亡通知書を送る場合は、訃報の連絡が遅くなったことについてのお詫びや、葬儀に参列していただいたことへの感謝を伝えます。また、いつ式を執り行ったのか具体的な月日を記しておきましょう。
参列の案内を事前に送らなかった場合は、なぜ連絡を差し控えたのかについて理由を一筆記しておくことも大切です。「遠方よりお運びいただくのが忍びなかったため」「故人の希望で近親者のみのお別れとした」などの理由が考えられます。
喪主の氏名と住所
最後に、喪主もしくは差出人の氏名と住所を記入します。葬儀や故人の逝去に関して連絡を取る必要がある人のために、電話番号などの連絡先も忘れずに明記しましょう。
氏名の前には故人との続柄を記します。たとえば「長男」や「妻」などになるでしょう。差出人が喪主を兼ねている場合は「喪主」と書いても構いません。また、一行空けて「外 親戚一同」と記載するケースもあります。社葬の場合は、「代表取締役」と「喪主」などを併記することも考えられます。
訃報ハガキを送るタイミングと文例
身内に不幸があったときは、適切なタイミングで訃報ハガキを送付することが大切です。葬儀前に送る場合と葬儀後に送る場合に分かれますが、どちらもできる限り早く故人に縁のあった人に訃報を知らせるべきであるということには変わりありません。
ここでは訃報ハガキを送るタイミングと、実際に内容を記入する際の文例をご紹介します。
葬儀に参加してもらいたい場合は葬儀前に送る
葬儀に参列してほしい人には、故人が逝去した後すぐに訃報ハガキを送付します。ただし、身内や親しい友人には電話などで連絡することも多いです。また、居住地が遠方で郵送では通知が間に合わないと思われる場合にも、電話で直接伝えることが考えられるでしょう。
一方、社葬を行ったり会社の関係者に逝去の事実を知らせたりするケースでは、訃報ハガキを郵送することが多いです。葬儀に参列したかったのに叶わなかったという人を出さないためにも、訃報の連絡は迅速に行いましょう。
葬儀前に送る場合のおすすめ文例
母 ○○儀 病気療養中でございましたが
去る○○月○○日 ○○歳にて永眠致しました
ここに生前のご厚誼に感謝し ご通知申し上げます
なお葬儀告別式は仏式において 下記の通り執り行います
故 ○○ 儀 通夜・葬儀告別式
通夜式 令和○年○月○日 ○時から
葬儀告別式 令和○年○月○日 ○時から
場所 ○○斎場
住所 ○○県○○市○○区○○
電話番号 ○○○-○○○-○○○○
喪主 ○○○○
住所 ○○○○
電話番号 ○○○
問い合わせ先 ○○ 電話番号○○○-○○○-○○○○
身内のみで葬儀をする場合は葬儀後に送ることも多い
家族葬など、身内のみで葬儀を行う場合は死亡通知書を葬儀後に送付するケースも少なくありません。親戚や親しかった友人など、故人と縁が深い相手には事前に逝去したことを伝えておくのが親切ですが、仕事の関係者などには葬儀を済ませた後に知らせることが多いでしょう。
年末が近い時期に葬儀を行ったときは、喪中はがきと死亡通知を兼ねて差し出すこともあります。喪中のため新年の挨拶を控えることを伝える目的で送付するものなので、具体的な死因や経緯などは書かずに故人が逝去したことをシンプルに記載しましょう。
葬儀後に送る場合のおすすめ文例
母 ○○儀 かねてより病気療養中でございましたが
○○月○○日 ○○歳にて急逝致しました
葬儀を○○月○○日に近親者のみにて執り行いました
すぐにお知らせすべきところでございましたが
ご通知が遅れました事をお赦しください
ここに生前中賜りましたご厚誼に心より御礼申し上げます
夫 ○○儀 天寿を全ういたし 去る○○月○○日
○○歳にて永眠致しました
本来ならばすぐにお知らせすべきところでございましたが
深い哀しみのうちにご通知が遅れました事をお赦しください
なお葬儀は○○月○○日故人の意志により家族葬にて執り行いました
ここに生前中賜りましたご厚誼に心より御礼申し上げます
訃報をハガキで伝える際の注意点
訃報ハガキで故人の逝去を知らせる場合は、時間が許す限り少しでも早く郵送するのが親切です。また、葬儀までの間隔が短いときは電話や新聞広告で連絡することも検討しましょう。
他にも、宗派の記載や使用を控えるべき言葉など、気をつけたいマナーがいくつかあります。ここでは、訃報をハガキで伝えるときの注意点を紹介します。
ハガキはできるだけ早く出す
葬儀の前に出す場合は、式の段取りが決まったら可能な限り早く郵送するように心がけましょう。葬儀への参加を希望する人にはなるべく足を運んでもらうためにも、葬儀の3日前には先方に届くように差し出すことが望ましいです。
葬儀を執り行った後に出す場合は初七日を迎える頃に出すのが一般的ですが、もし過ぎてしまったとしても、できる限り速やかに送ることが大切です。1日も早いタイミングで訃報を知らせるようにしましょう。
葬儀まで時間がない場合は電話などで連絡をする
遠方に住む人に死亡通知状で訃報を知らせる場合、葬儀までの期間が短いとハガキが到着する前に葬儀の日を迎えてしまうおそれがあります。そのため、時間に余裕がなく急いでいる場合は電話や電報などで訃報を知らせると良いでしょう。
交友範囲が広く、大人数に対して急ぎ訃報を知らせなければならないときは、新聞広告を利用するという方法もあります。葬儀の日程も掲載できるので、急な訃報でも広範囲に必要な情報を周知することができます。
宗派を記載する
どの宗派の形式で葬儀を行うか事前に分かっていれば、葬儀の参列者がマナーなどを下調べして準備をすることができます。所持品や装いをスムーズに決めるための先方に対しての心遣いでもあるので、宗派は必ず記載しましょう。
日本では仏式が主流となっていますが、神式やキリスト教式など、葬儀の執り行い方はさまざまです。また、無宗教という場合もあるので、参列者が迷わないようにどのスタイルで葬儀を行うのか案内することが大切です。
訃報ハガキで使ってはいけない言葉
「逝去」は尊敬語にあたり、他人が亡くなったときに使用するため、身内が亡くなったことを連絡するための死亡通知書に使うことはできません。代わりに「死去しました」「永眠いたしました」「生涯を閉じました」などがよく記載されます。
誤って「逝去」を身内の他界の際に使わないように注意しましょう。ただし、「急逝」は「急に死去すること」を意味しており尊敬語には該当しないため、身内の不幸に対して使うことができます。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
死亡通知状は、葬儀の前や後にかかわらず、適切なタイミングでなるべく早く差し出すことが大切です。過不足なく必要事項を記入し、故人が亡くなったことをいち早く知らせるようにしましょう。
葬儀に関するご準備は事前に行うことが大切です。いざという時困らないように、葬儀全般に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



遺言書には、誰の遺言かを明確にするために署名が必要です。ホゥ。