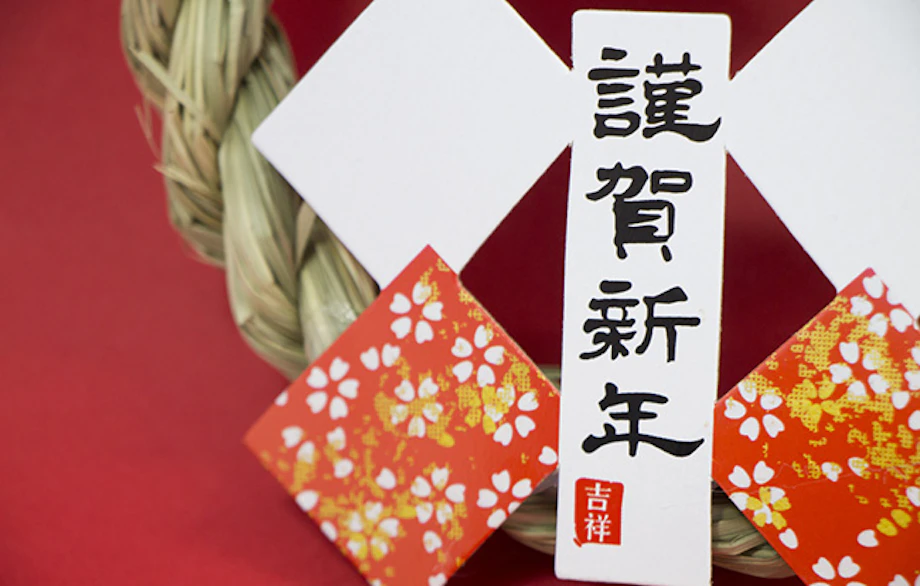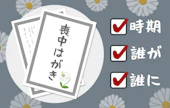冠婚葬祭に関わるしきたりやマナーは大切です。こういった場面での立ち居振る舞いが、人としての評価に繋がることもあるでしょう。しかし同時に葬儀など特別なときにしか関わることのないマナーも見られます。
この喪中のはじまりは明治時代にまでさかのぼります。古くからの由緒ある習慣と言える、この喪中の間は好まれない行動も出てきます。具体的にどんな行動がどこまで許されているのかを完璧に理解している人は少ないのではないでしょうか。喪中期間に新年を迎えたときの、気になる挨拶マナーをご紹介します。
<この記事の要点>
・喪中の場合、「おめでとう」という言葉では避けた方がよい
・喪中期間中に年賀状が届いた場合は寒中見舞いで返事を出すのがマナー
・SNSやメールの場合も「おめでとう」という言葉は控えた方がよい
こんな人におすすめ
今年身内が亡くなった方
喪中の際に使える新年の挨拶を知りたい方
喪中の方への挨拶についてお悩みの方
喪中に明けましておめでとうは控えた方がいいのか?
喪中という単語を聞いたことがある人でも、何故できたのか、また、どんな行動が慎むべきとされているのかを正確に知っている人は多くありません。今まで知らなかったことを整理し後々の対人関係でお互いに嫌な思いをしないためにも、喪中のマナーを今一度確認しておきましょう。
まずおさえておきたいこととして、喪中に「おめでとう」という新年の挨拶は、どんなときでも避けた方がいいのかということです。喪中にその挨拶を控える理由や背景を理解しておきましょう。
なぜ喪中に新年の挨拶を控えるのか
なぜ喪中のときは新年の挨拶を控えるべきなのか、あまり普段の日常生活で知ることはないかもしれません。まず喪中の意味を簡潔に知っておくのがベストです。喪中という言葉は喪に服していることから名付けられた言葉です。
愛する家族や尊敬できる師、一家の大黒柱など自分にとって大切な人々が亡くなったとき、それを悲しむ気持ちからできたのが喪と呼ばれる期間です。この期間は祝いごとへの参加を避けるべきだと言われています。亡くなった人にそっと寄り添う期間といえるでしょう。
「おめでとう」は避けた言い方にする
喪中の場合、新年を迎える前に喪中はがきを出します。周りにいる人にも自分が喪中であることを分かってもらうために、喪中はがきを事前に出しておきます。
様々なものを慎む期間であるため、数々の制限もあります。新年に関していえば、年賀状を出したり、正月飾りを用意したり、おせちを楽しむことも慎むべきという考えが一般的です。年賀状をもらっても、「あけましておめでとうございます」などの文言は避けるのが慣習です。
「今年もよろしくお願いします」などおめでとうという言葉を用いない、別の言葉を用いた返事が適しています。「昨年はお世話になりました」など相手に対する感謝の気持ちを伝えるのも1つの方法です。
仕事関係の人への挨拶
喪中を理由に新年の挨拶を控えるのは、日本の慣習です。しかし、仕事の人間関係はプライベートとは違い扱いが難しいものです。取引先との関係にも関わってくる上、相手が外国人だったりした場合は、喪中の文化を知らない可能性も高いです。
あくまでも仕事に携わる一個人として挨拶するのであって、そこに個人のプライベートな事情は挟まれません。「あけましておめでとうございます」というフレーズを使うのも問題ありません。
一方で、取引先などと違い職場など頻繁に顔を会わせる人の場合は異なります。喪中期間は同僚や上司には、必ずしもお祝いの言葉を送る必要はありません。
理由として、職場にいる人は喪中はがきを送るべき相手だと認識されているためです。事前に喪中はがきを送り、相手に喪中期間であることを知ってもらうのが理想でしょう。
喪中の期間
次に喪中の期間について説明します。喪中については何となくイメージできても、どのくらいの長さ喪に服すのが適切か分からないこともあるでしょう。喪中期間は亡くなった人との続柄によって決まります。以下の表を参照してください。
| 故人との続柄 | 喪中期間 |
| 配偶者 | 13ヶ月 |
| 父母 | 13ヶ月 |
| 子供 | 3ヶ月~12ヶ月 |
| 兄弟姉妹 | 3ヶ月~6ヶ月 |
| 祖父母 | 3ヶ月~6ヶ月 |
それぞれの欄をチェックしてみると、第1親等が一番長いことが分かります。喪中となる期間は最長で13ヶ月です。表を見て分かる通り、親等が近い続柄であればあるほど喪中の期間も長くなります。
父母や配偶者と比べ、兄弟姉妹や祖父母の場合は期間も短くなります。同居をしていない場合、祖父母であっても喪に服さないというケースもあります。また、表に取り上げられていない続柄でも、喪に服してはいけないということはありません。
喪中の新年の挨拶〜年賀状〜
次に喪中期間の年賀状についてまとめました。携帯電話やSNSなどの普及によってやりとりされる年賀状の数は減りましたが、いまだに送られる機会があるものです。
新年の挨拶も年賀状も限られた機会ですが、しっかりと喪中のマナーを知っておきましょう。年賀状は日本の文化に深く根付いている慣習であるがゆえに、喪中でも気にするべきポイントがいくつかあります。
喪中に年賀状は出さない
喪中の新年の挨拶、年賀状についてはまず初めに知っておくべき大枠があります。それは「喪中に年賀状は出さない」ということです。今まであまり年賀状を出してこなかった人、もしくは若い世代で喪中を経験していない人もいるでしょう。
喪に服す礼儀や言動は亡くなった人を悼んで行われるものです。年賀状自体が本来おめでたいものであるため、喪中に年賀状を出すことは控えるのが一般的です。年賀状が送られてきた場合、受け取ることに特に問題はありません。
返信には「寒中見舞い」を出す
後述する喪中はがきを出した場合、喪中であることを知っている人々から年賀状をもらう機会は少なくなるでしょう。しかし、それでも「喪中であることを相手が知らなかった」などの理由で年賀状が送られてくることはあります。こういったときの最適な対処法についてご紹介します。
喪中に年賀状を貰った場合、そのまま無視するのはおすすめできません。喪中とは言え年賀状を貰っているわけですし、相手は喪中であることに気付いていない可能性もあります。喪中はがきを出していない相手であればなおさらでしょう。
年賀状が届いたときは寒中見舞いで返事を出すのが喪中の正しいマナーです。寒中見舞いと聞くと暑中見舞いのように、時節に則した挨拶のように思われるかもしれません。確かに季節の挨拶としても寒中見舞いは使われますが、喪中に使われる挨拶状としての役割も持っています。
寒中見舞いに使うはがきは胡蝶蘭デザインの官製はがきか、寒中見舞いを想定したデザインのものを使うのが理想です。干支や新年を意識したデザインなど、おめでたい雰囲気のものは控えた方がよいとされています。
喪中であることを知らせる喪中はがきを送っていない相手から送られてきたときは、はがきを出していないことに対するお詫びの文章を追加しておくことも大切です。
事前に「喪中はがき」を出す
新年を迎える前に、喪中はがきを出すことも喪に服す際のマナーの一つです。喪中はがきはその名の通り、自分が喪中であることを事前に相手に知らせることが目的のはがきです。これによって迎える新年の挨拶を控えることを事前に周囲の人に知らせておくことができます。
喪中はがきは弔辞に関係するお知らせが趣旨となるものです。派手なデザインのはがきや年賀欠礼以外のプライベートな世間話などを差し挟むことは避けましょう。はがきのデザインなどは寒中見舞いと同じく、胡蝶蘭柄のもので問題ありません。
通常はもらった年賀状のうち、故人に宛てられたものも寒中見舞いでお返しします。
また、喪中はがきに関する注意点として喪中期間は更新される場合があります。例として子供が亡くなった後の喪中期間中に父親が亡くなった場合、父親が亡くなってからの13ヶ月が喪中期間となります。
喪中の新年の挨拶〜SNS・メール〜
対面しての新年の挨拶や年賀状の扱いについてはこれまでまとめてきた通りです。知らない人でも想像しやすく、祭事への参加は控えるなどマナーに則った内容と言えるでしょう。
喪中期間中に迎える新年のSNSやメールについて見てみましょう。フランクな関係や新しいツールになるほど、喪中であることを意識するのは難しくなってくるかもしれませんが、ここにも喪中のマナーが存在します。
喪中をSNSで知らせる人が増えている
近年は喪中であることをSNSやメールで伝える人も増えています。SNSやメールで送ることには数々のメリットがあるためです。
相手の住所を知らなくても伝えることができますし、SNSの種類によっては、既読機能によってきちんと届いたかを確認することもできます。投稿してから相手に届くまでのスピードもはがきに比べて早いのが特徴です。
喪中の成り立ちを考えると仕事でも喪中の姿勢を貫くべきだと思ってしまうかもしれません。しかし仕事とプライベートは別で、取引先やビジネスでのやりとりが必要な相手には新年のおめでたい挨拶を控える必要はありません。
SNSやメールでもおめでとうは控える
SNSやメールに喪中はがきの役割を持たせている人は増えています。ここからも分かるように、SNSやメールの場合でも基本的な注意事項は年賀状や対面での挨拶と同じです。
すなわち「おめでとう」という単語は控える、新年を祝うものには参加しないのがSNSやメールでもマナーとなります。これらはスタンプ機能や絵文字機能にも同じことが言えるでしょう。伝える方法は変わっても、対面や年賀状と同じく喪中期間中のマナーはSNSなどのオンライン上でも変わりません。
返信はしてもOK
次にLINEなどのSNSやメールで新年を祝うメッセージを受け取ったときについてです。SNSの発達によって、直接会わずとも新年を迎えたときにすぐにメッセージを交換できるようになりました。
友達同士や離れて住んでいる家族ともすぐに繋がることができます。親しい人との間や大勢であればあるほど役に立つSNSやメールでは、「あけおめメール」のような新年を祝うメッセージももらうことになるでしょう。
SNSでも自分から新年を祝うメッセージを発信するのは控えるべきですが、貰う分には年賀状と同じく特に問題はありません。それに対して返事をするのも別段咎められることではありません。
このケースでも気をつけるべきポイントは年賀状のときと同じです。祝う言葉を直接使わず、「昨年はお世話になりました。今年もよろしくお願いします」などの言葉を選ぶことが勧められています。
喪中の人へは気遣った挨拶を
これまでは自分が喪中を迎えたときについてのまとめでしたが、ここからは相手が喪中であるケースについての情報をまとめました。自分が喪中期間を迎えるときは事前に調べることもできますが、会話の中でふと相手が喪中であることを知ることもあるでしょう。
知らないうちに喪中の相手を困らせてしまうような行動を取ってしまわないよう、ここでしっかりと喪中のマナーを確認しておきましょう。
知っているなら行事への誘いは避ける
相手が喪中である場合、新年の挨拶やおめでたい行事へのお誘いは避けるのが最適です。喪中であるならば何かお祝いごとに誘っても相手は結局断ることになってしまいます。喪中であることを理由に来られないことがあらかじめ分かっているのであれば声をかける必要はありません。
「儀礼的でも誘った方がいいのでは」と考えてしまうこともありますが、喪中の相手に声をかけないことは失礼にはあたりません。
「喪中につき新年のご挨拶をご遠慮申し上げます」の文面など喪中はがきによって事前に知ることもあるでしょう。どの場合も相手が喪中であることを知っているのであれば通常の挨拶は避けましょう。
海外にも喪中はあるの?
仕事での取引先や同僚など、外国人と付き合いを持つことも昔に比べて増えています。親密ではなくてもメッセージのやりとりをする間柄ということもあるでしょう。海外には喪中のような文化はあるのでしょうか。
喪中かどうかは国にはあまりよらず、宗教によって決まることが多いです。イスラム教を例にとってみると女性の場合は4ヶ月と10日、男性は3日間です。ヒンドゥー教なら13日、またキリスト教の場合は喪中のような慣習はそもそも存在しません。
西洋の宗教では「死=神様の元に戻ること」と定義していることがよくあります。死ぬことが必ずしも悲しい、悪いことではないという考えが関係していると言われています。
相手への配慮を忘れずに
自分が喪中のときにどういった行動をするべきか知っていれば、相手が喪中のときにも戸惑うことなくスムーズに対処することができるでしょう。海外にも日本の喪中期間と似たような慣習があることも分かりました。
ここで重要なのが相手への配慮を忘れないことです。喪中期間は相手にとって心の整理や死後の手続きなどするべきことが多い時期でもあります。相手が喪中であることを何らかのきっかけで知ったのなら、失礼にあたらないようなマナーを心がけたいものです。
これは日本だけでなく、海外の人相手でも同じことが言えます。何となくOKだろうと思っていたことでも、相手の宗教によってはタブーかもしれません。特に喪中は人の生死に深く関わる期間ですから、配慮に欠ける行動はお互いに慎みたいものです。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
新年の挨拶は喜ばしいものですが、喪中は挨拶方法や対処法も異なります。喪中期間のマナーをしっかり守り、自分と相手双方が気持ちのよい新年を迎えたいものです。
事前に喪中はがきを出して新年の挨拶を控える趣旨を伝える、相手が喪中なら挨拶は控えるなど新年の挨拶の前段階で喪中であることを伝える、伝えられることもあるでしょう。古くからある礼式や慣習には難しいものもあります。お困りのことがあれば小さなお葬式へご相談ください。
喪中に関する疑問以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。


不祝儀袋は、包む金額に合わせて選ぶと丁寧です。ホゥ。