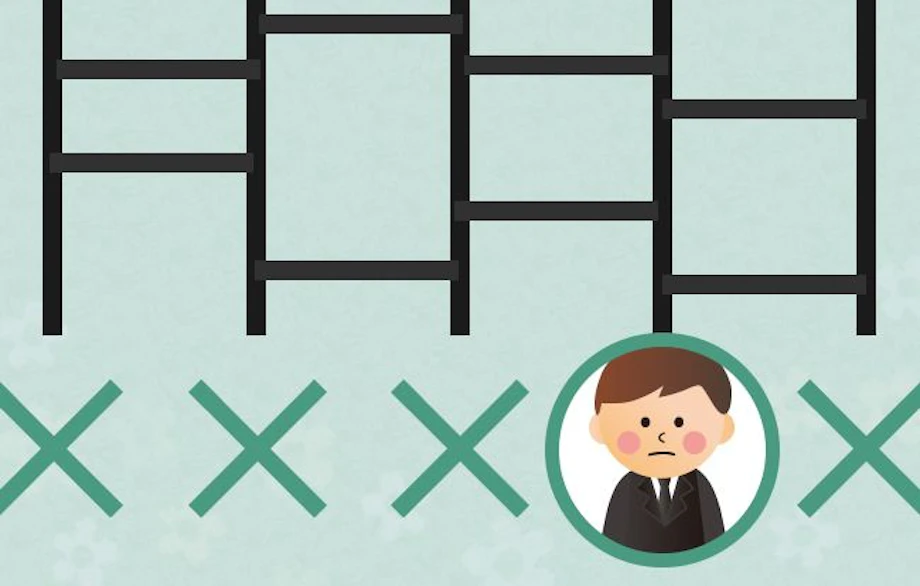葬儀の手配をすすめるには、まずは喪主(もしゅ)となる方を決めます。喪主は、葬儀内容の取りまとめ、会葬者やご僧侶への対応など、重要な役割を担います。
この記事では、喪主の決め方と役割についてご紹介します。葬儀全体の流れについても、あわせて理解を深めておきましょう。
<この記事の要点>
・喪主を決める基準は4つあり、故人の遺言があればそれに従い、なければ配偶者が務める
・配偶者がいない場合は血縁者が優先され、次いで知人や友人が喪主になることもある
・喪主は役所での手続きや葬儀の準備など様々な業務を担い、参列者への対応も行う
こんな人におすすめ
喪主の決め方について知りたい人
喪主の役割について知りたい人
直近に葬儀を控えている人
喪主の決め方
喪主を選ぶ時、どんな要素を元に決めればよいのか悩むこともあるでしょう。ここでは、優先度の高い順に4つの基準をご紹介します。
1.故人の遺言により決める
喪主を選ぶ時、もっとも影響力を持つのは故人の遺言です。遺言で喪主の指定がある場合は、それに従って喪主を決めます。遺言で喪主の指定がない場合は、以下の2~4を基準に決めるとよいでしょう。
2.配偶者が喪主を務める
遺言で喪主の指定がない場合は、故人の配偶者が喪主を務めるのが一般的です。古くは家督を継ぐという意味で、故人の後継者が喪主を務めていましたが、現在はその意識が弱くなっていることや、家族構成などから、故人の配偶者が喪主を務めることが多くなっています。
3.血縁関係から選ぶ
配偶者が高齢であったり、病気であったりと、喪主を務めることが困難な場合もあります。その時は血縁関係の深い方が優先されます。配偶者を除き、親族の続柄(つづきがら)を血縁関係の深い順に並べると次のようになります。
| 優先順位 | 続柄 |
| 1 | 長男 |
| 2 | 次男以降直系の男子 |
| 3 | 長女 |
| 4 | 長女以降直系の女子 |
| 5 | 故人の両親 |
| 6 | 故人の兄弟姉妹 |
4.知人や友人が喪主を務める
故人に配偶者や血縁者がいない場合は、知人や友人、または入所していた介護施設の代表者などが喪主を務めることもあります。この場合は、「友人代表」や「世話人代表」と呼ぶのが一般的です。
喪主を1人に決められない場合
喪主を1人と限定する必要はありません。 法律では、祭祀継承者(家を祀る行事を受け継ぐ人)は1人と定められていますが、喪主は複数人でも問題ありません。
喪主の役割
喪主は、葬儀の様々なことを決定する役割があります。その中でも知っておきたい3つのことをお伝えします。
1.役所対応(死亡手続き)
役所での対応は主に死亡手続きです。喪主に選ばれた場合は、役所で以下の手続きをしましょう。
・死亡診断書の受け取り
・死亡届の提出
・火葬許可証の受け取り
2.葬儀の監督(葬儀準備)
役所での死亡手続きが終わると、次は葬儀の準備を始める必要があります。準備は以下の流れで進めるとよいでしょう。
①訃報連絡
②葬儀社の決定
③葬儀全体の最終決定
④寺院への連絡
①訃報連絡
訃報の連絡相手が多い場合は、親戚、故人の勤務先、遺族の勤務先、近隣といったように分類してから連絡をするとスムーズに進めることができるでしょう。連絡する内容は、故人の氏名・死亡日時・通夜や葬儀の日時と式場・喪主の氏名です。また、通夜や葬儀に参列を希望する人への案内状も別途作成して送りましょう。
②葬儀社の決定
喪主が中心となって依頼する葬儀社を決定します。亡くなった病院や施設に紹介された葬儀社に依頼することもできますが、その場合、葬儀費用が高額になってしまうことが多いでしょう。なるべく複数社を比較して、検討することをおすすめします。
③葬儀全体の最終決定
喪主は葬儀に関する最終決定権を持ちます。葬儀の形式や日時、費用に関することを関係者と相談して決定します。
④寺院への連絡
寺院への連絡では、お付き合いのある菩提寺に連絡をとり、日程の調整をします。菩提寺がない場合には、葬儀日程に合わせてご僧侶にお勤めいただく「寺院手配」サービスもありますので、下記の参考ページをご覧ください。
参考:小さなお葬式の「寺院手配」
3.参列者対応(葬儀当日~葬儀後)
葬儀当日~葬儀後の喪主の役割は、挨拶や弔問などの参列者対応が中心です。
①喪主挨拶
通夜式や葬儀・告別式中では、喪主として挨拶をします。挨拶が必要な主な場面はこちらです。
・ご僧侶が到着した時・お布施を渡す時
・会葬者に対して受付をする時
・出棺時
・精進落としの席での開式・閉式時
②弔問を受ける
通夜や葬儀で弔問客を迎えたら、誰にでも同じ態度で挨拶する必要があります。弔問客からお悔やみの言葉をいただいたときは丁寧にお礼を述べましょう。ただし、喪主は実務に携わらず、受付や接待は親族と話し合い、役割分担を決めておきましょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
喪主は葬儀を行う上で大事な役割を担っています。喪主を決めるにあたっては故人の遺言や血縁関係などによって決めることが一般的です。喪主はお葬式全体を取り仕切り、様々な場面であいさつを行うこととなります。
葬儀をスムーズに行うためには、他の遺族や葬儀社、世話係の方にサポートしてもらいながら、故人との最期のお別れを悔いのないものにしましょう。
葬儀に関するご準備は事前に行うことが大切です。いざという時困らないように、葬儀全般に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
喪主はどうやって決めればいいの?
遺言がない場合の喪主の決め方は?
喪主にはどんな役割があるの?

葬儀の挨拶では、不幸を連想させてしまう忌み言葉と重ね言葉には気をつけましょう。ホゥ。