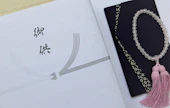お葬式後も故人を供養するためにさまざまな法要が執り行われます。三回忌は、亡くなってから2年後の命日で、三回忌法要はこの日に合わせて執り行う年忌法要のひとつです。
三回忌法要の案内をいただいたとき、どのように対処すべきか、何を持参するべきか分からない方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、三回忌の供物の必要有無や、三回忌に参列する際のマナーなどを解説します。法事に用意する供物とは何か、どのような物を持参すべきかが分かる内容です。
<この記事の要点>
・三回忌の供物の金額は3,000円~5,000円が目安で、ろうそくや線香などが一般的
・法要中止の連絡があった場合は、供物を宅配便で送る
・法要に招かれた場合はできる限り参列し、欠席の場合は法要前日までに供物を贈る
こんな人におすすめ
三回忌とは何か知りたい方
三回忌の供物にお悩みの方
三回忌のマナーを知りたい方
三回忌とは?
法要には中陰法要と年忌法要があり、三回忌は年忌法要です。ここでは、三回忌とは何かをご紹介します。三回忌法要に集まる前に意味合いを知って、故人を供養する意義を見つめ直してみましょう。
三回忌に法要を営むのは何のため?
三回忌とは、年忌法要のひとつであり、故人が亡くなってから満2年で行う法要のことで、一周忌の次の法要です。
三回忌などの年忌法要は中国の儒教の「十王信仰」基づくものと言われています。これは冥界の10人の王から裁きを受けるという言い伝えが追善供養を行う理由となり、年忌法要へとつながりました。
故人が善い道へ進めるように祈念するために、裁きを受けるタイミングで法要を行うと言われています。
三回忌の数え方
「亡くなってから3年後」と三回忌の時期を解釈している方もいますが、正しくは「亡くなってから2年後」です。亡くなった日を1回目の忌日と数えるので、翌翌年の忌日を三回忌と呼びます。
遺族は1年後に一周忌法要を、2年後に三回忌法要を営むのが一般的です。つまり、亡くなってすぐの年は2年連続で法要を営むことになります。
施主は誰が行う?
三回忌に限らず、法要は葬儀のときに喪主を務めた方が施主になることが多いようです。しかし、喪主を務めた方が亡くなっていたり務められない理由があったりする場合はその配偶者やきょうだい、子どもが代わって施主を務めることもあります。その場合は、きちんと話し合って決めましょう。
供物は必要?
三回忌は、身内や親族以外にも故人と親しかった方が集まることが一般的です。法事に招かれた際、香典とともに供物を用意するべきなのか悩む方を多いのではないでしょうか。
どのような立場での参列であっても、法事には供物を用意していくのが本来のマナーです。香典とは別に用意する場合と供物のみ用意する場合とあります。
ただし、供物に対する考え方も地域によって変わってきますので、あらかじめその地域の親類や知人に確認をしておくとよいでしょう。
三回忌の供物は何がよい?
三回忌の供物の金額目安は3,000円~5,000円と言われています。供物には、適した品物とそうでない品物があることにも注意が必要です。ここでは、供物の注意点について解説します。
定番の供物は?
よく選ばれるのはろうそくです。ろうそくは仏様の知恵を表現し、ろうそくの光を受けることで仏様の知恵を授かるという仏教の考えがあります。
また、ろうそくは季節を選ばず、消耗品であることからも人気です。供物としては側面に絵付けされている絵ろうそくなどを選ぶとよいでしょう。
次に線香が挙げられます。諸説ありますが線香をあげる理由のひとつに「故人の食事」という意味があるようです。「人は死後にお線香の香りを食べる」という説を食香といいます。
また、お線香の香煙があの世への道案内と言われており、四十九日までは線香の火を絶やしていけないと言われるほど法要に必ず必要なものです。お線香は供物として贈ると遺族からも喜ばれます。
花を贈る方も多くいます。花には故人を思う気持ちが込められており、故人の好きな花を贈ることで故人との思い出を表現できるでしょう。また、花言葉をはじめ、花にはいろいろな意味が込められていますので、法要の際に供物として贈る方が多いようです。
他にも故人が好きだったものを贈る方も多くいます。故人が好きだったものは、故人をしのぶことにつながるため、供物に最適です。しかし、いくら故人が好きだったとはいえ供物としてふさわしくないものも中にはありますので業者や施主に確認してから用意するとよいでしょう。
避けたほうがよいもの
供物は「消えもの」を選ぶのが主流のようです。消えものとは消費したらなくなってしまうもので、食べ物や飲み物などが該当します。残るものは「悪い縁を後に引きずる」という昔からの考え方から生まれた風習です。
食べ物でも、肉や魚は仏教では禁忌とされている殺生を連想してしまうという観点から、供物には選ばないようにしましょう。また、香辛料といった香りや辛みが強いものもNGです。
花を選ぶ際にもバラなどトゲがある花や毒をもっている花は避けましょう。花を選ぶ際は花屋に故人の好きな花を説明し、供物としてふさわしい花を選ぶとよいでしょう。
三回忌法要はなくても供物を用意する?
最近はコロナ禍の影響や、やむを得ない理由から、三回忌法要を執り行わなかったり、遺族のみで済ませたりするケースが増加傾向です。
本来参列したであろう関係の場合、三回忌にすることがあるか、供物はどうするか悩むかもしれません。ここでは法要を設けない場合の供物の対処法について解説します。
中止などの連絡が来たら……
三回忌法要を実施するであろう時期の前に、中止の案内状が届くこともあるでしょう。そうした場合は、受け取った後、三回忌の前までに何らかの供物を用意して届けます。
しかし、不要不急の外出の自粛が呼び掛けられる中、遺族側では訪問を受け入れづらい状況かもしれません。そのような場合には供物を送るとよいでしょう。
香典とともに送るのはNG
供物の配送を手配するとき、香典も一緒には送れません。金銭を宅配便などで送る行為は法律で禁止されているためです。
供物も香典も送る場合には供物は宅配便で、香典は現金書留で送るようにしましょう。また、配送手配の際には何日で着くかを確認し、目安の日数を遺族に伝えておくと安心です。
注意したい三回忌のマナーとは
三回忌は一周忌や四十九日に比べると、そこまで堅苦しく行う必要はないのかもしれません。しかし、社会人ならば最低限のマナーは守りたいところです。
マナーが守れないと本人だけでなく遺族や故人にも恥ずかしい思いをさせてしまいます。適切な対応や服装に関するマナーを事前に確認しておきましょう。
案内状が来たら早めに返信する
三回忌に限らず、法要に招かれた場合はできる限り参列しましょう。案内状が来たら速やかに返信をします。遺族側には参列者の人数把握や、会食の予約準備などがあるため、早めに返信する配慮が必要です。
また、やむを得ず欠席しなければならない場合は、まずは電話で一報を入れて、法要の前日までに供物料や供物を贈りましょう。
服装
三回忌は準喪服か略喪服を着用することが一般的です。案内状に「平服」でと記載してある場合があります。その場合でも、一度施主に確認をとっておくとよいでしょう。また、どの場合でも派手な装飾品はNGです。
挨拶と供物の渡すタイミングは?
会場には30分前には到着しておきましょう。到着したら、まずは遺族へ挨拶するのが丁寧です。挨拶では「ありがとう」の言葉を使いません。遺族はこの日は忙しいので、挨拶は簡単に済ませ、一言添えて供物を遺族へ渡します。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
三回忌の法要に参列するとなったら供物を用意します。その際には、故人を想いながら供物を選んでみてはいかがでしょうか。その他、定番のろうそくや線香、縁起が良いとされる盛籠(もりかご)なども喜ばれます。
人によって故人との関係性は違いますので、供物選びに迷いが生じることもあるかもしれません。また、マナーや常識についての悩みも発生しがちです。
「小さなお葬式」では、三回忌法要についてのご相談を承っております。24時間365日、法事や法要に詳しい専門スタッフが待機しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
法事・法要以外にも、葬儀全般に関する疑問がある場合には、ぜひ「小さなお葬式」へお問い合わせください。専門知識を持つスタッフが、お悩みに寄り添い丁寧にアドバイスいたします。


御霊前は「亡くなった方の霊魂の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。