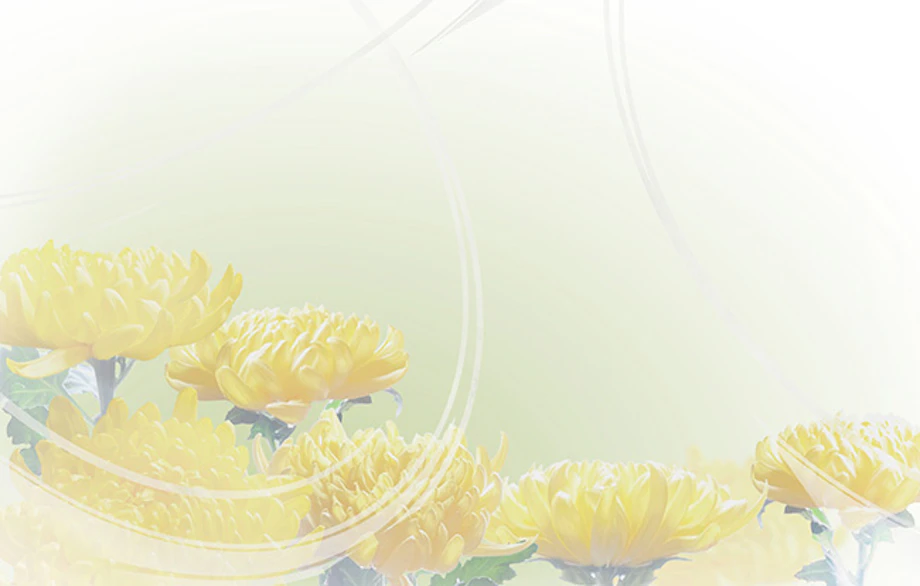葬儀を終えてから一周忌までは時間が短く、悲しみも癒えていないため、法要の準備に手間取ることもあるでしょう。しかし、一周忌には親族以外にも多くの方が参列する可能性があるため、できるだけ早めに案内状を送ることが大切です。
こちらの記事では、一周忌の案内状を送る際に押さえておきたいポイントをご紹介します。時間がなく慌ただしい中、案内状を作るために役立つ内容です。
<この記事の要点>
・一周忌の案内状は、法要の一ヶ月前に送るのが一般的
・案内状には、故人との関係性、法要の日時や場所、会食の案内などを明記する
・案内状には返信用はがきを同封し、弔事用の切手を貼って送る
こんな人におすすめ
一周忌で案内状を送る必要がある人
案内状の作成に不慣れな人
案内状をマナーを守って作成したい人
一周忌の案内状はいつ準備する?
一周忌法要は最初の年忌法要であり、親族だけではなく故人が親しくしていた友人や知人を招くのが一般的です。そのため、葬儀と同じく比較的大きな規模の法要となるでしょう。参列者の人数が分からなければ、法要の会場や会食の予定が立てられません。
葬儀から1年間は、初七日・四十九日など多くの法要に追われることもあり、「気がついたらもうすぐ一周忌法要だった」と慌てる方も多いでしょう。一周忌の案内状は、法要の一ヶ月前に送るのが通例です。日程に余裕を持ち、一ヶ月半前には用意を始めましょう。手配を先にしておくと、案内状を早く送れるため、参列する側も予定を押さえやすくなります。
一周忌の案内状に書く内容
トラブルなく法要に参列していただくためにも、案内状の内容は非常に大切です。案内状はわかりやすく明確に書くように心がけましょう。次は、案内状に書く内容やポイントを紹介します。
差出人と故人の関係性
案内状には、誰の一周忌法要かを分かるように記載しましょう。また、差出人と故人との関係を明記するとより親切です。「亡き父 〇〇(氏名)の一周忌」のように書けば、故人の名前と関係性を一度に説明できます。また、一周忌以外でも同じような書き方をするため、何回目の法要かも書きましょう。
頭語・結語をつける
一周忌法要の案内状は、頭語から書き始めます。頭語とは、手紙の冒頭に書く挨拶のようなものです。丁寧さに応じていくつかの種類があるため、文体や好みによって使い分けましょう。法要の案内状には、「謹啓」や「拝啓」といった頭語がよく使われます。頭語に呼応して、文末は「敬具」「敬白」といった結語で結びましょう。
時候の挨拶を入れる
頭語に続けて、季節を表す「時候の挨拶」を入れます。ただし、法事における時候の挨拶では「慶ぶ」や「喜ぶ」といったおめでたい表現はタブーのため避けましょう。
一例としては次のフレーズがあります。
・謹啓 錦秋の候 皆様にはお健やかにお過ごしのことと存じます
・拝啓 薫風のみぎり 皆様におきましてはお変わりなくお過ごしのことと存じます
季節や月によってふさわしい時候の挨拶は異なります。一周忌の案内を送る時期に合わせて慎重に言葉を選びましょう。
法要の日時と場所
参列する方が困らないように、法要の会場や日時についてもわかりやすく記載します。特に、遠方から参列される方は会場の場所がわからないケースも少なくありません。住所を正しく記載したり、近隣の地図を添えたりするとより丁寧でしょう。
また、高齢の方は小さな字だと見づらく、日時を間違うこともあります。会場や日時は重要な情報のため、できるだけ大きく読みやすいフォントを選びましょう。
会食の案内
一周忌法要の後には、会食をするのが通例です。しかし、最近では時勢などの理由から会食を省くケースもあるため、会食の有無も明記しましょう。会食場所と法要会場が異なる場合はその旨を記載し、会食場所へのルートも案内します。
返信のお願いと宛先
一周忌法要の案内状は、施主が差出人となります。不明な点がある場合は問い合わせできるように、施主の連絡先が分かるようにしましょう。また、法要会場や会食の準備のため、案内だけではなく出欠の確認をする必要があります。「いつまでに返事がほしい」など期日についても記載が必要です。
案内状の封筒や切手について
案内状を書いたら、送付するための封筒や切手を用意します。一周忌などの法要では、どのような封筒や切手を選べばいいか迷う方も少なくありません。ここからは、法要の案内状に使う封筒や切手の選び方やマナーを見ていきましょう。
白無地の封筒を使う
一周忌の案内状は、封筒の中に法要や会食の出欠を確認するための返信用はがきを入れて送るのが一般的です。返信用はがきには切手を貼り、そのまま投函できる状態にします。封筒は白無地のものを使いますが、二重封筒には「不幸が重なる」というイメージがあるため、仏事では避けましょう。
往復はがきを使う
案内状は封筒で送るのが通例ですが、最近では封書を簡略化して、往復はがきを利用する方も増えています。往復はがきタイプの案内状は、郵便局などでも購入可能であり、マナー違反にはなりません。しかし、地域差や家庭による決まりなどもあるため、心配な方は周囲に相談するとよいでしょう。
切手の種類
一周忌の案内状には、弔事用の切手を使いましょう。郵便局で購入できるのは、白地に紫色の小花が描かれたデザインの「弔事用63円普通切手」です。現在、封書用(82円)の弔事用切手は販売されていません。案内状を封書で送る際には、キャラクターものや華やかな切手は避け、落ち着いたデザインの普通切手または記念切手を選びましょう。
パソコンで作ってもOK
一周忌の案内状は多くの人に送付するため、手書きではなくパソコンで作成しても問題ありません。一度テンプレートを作っておけば、今後の年忌法要でも役に立つでしょう。また、法要会場や印刷会社にも依頼できます。作成を他者にまかせる場合は、日時や会場などの内容が間違っていないかを、印刷前にチェックしましょう。
案内状を送る上でのマナー
一周忌法要の案内状を送る際には、気をつけたいマナーがいくつかあります。受け取った方が不快な思いをしないためにも、マナーを守って案内状を作成しましょう。ここからは、一周忌法要における案内状の一般的なマナーを紹介します。
忌み言葉に気をつける
法事での挨拶同様、文面における忌み言葉にも注意が必要です。「度々」「色々」といった同じことを繰り返す「重ね言葉」は、不幸が連続することをイメージさせるため使いません。また、「四」や「九」など縁起が悪いとされる「忌み数」も避けます。
薄墨の筆記用具は使わない
仏事の案内状といえば、薄墨をイメージする方も少なくはありません。しかし、四十九日以降は薄墨を使いません。そのため、一周忌法要の案内状には濃墨を使いましょう。
行頭を揃え句読点は使わない
一周忌を含めた法事の案内状には、句読点を使わないというマナーがあります。句読点を入れるべきところは、空白にしましょう。また、通常の文章では、最初の行の先頭は1字下げて書き始めますが、弔事の場合は行頭を揃える(1字空けない)のが特徴です。
身内だけで一周忌を行う場合の案内状
遺族および参列者の負担を軽減するために、身内だけで一周忌を執り行うケースもあります。その場合は、誰が参列して誰が参列しなかったといったトラブルにならないように、親族とよく相談した上で法要を行うことが大切です。一周忌を身内のみで行う際には、参列しない親戚や知人に対して、その旨をお知らせする案内状かまたは挨拶文を送りましょう。
案内状が必要ないケースもある
親族だけでなく、故人の友人や知人を招き大きな規模で一周忌をする場合は、案内状の作成が必要です。しかし、近しい方のみで法要をする場合、案内状を作成しない方もいます。
身内の場合、電話やメールで連絡しても問題ありません。特に電話の時は、日時や場所を復唱してもらい、聞き間違いがないかを確認します。また、メールは相手が読んだかどうかわからないため、連絡した旨を後ほど電話で伝えるとよいでしょう。
一周忌の案内状が届いた際の返信方法
続いては、一周忌の案内状を受け取った側の一般的なマナーについて紹介します。一周忌は遺族にとって、まだ深い悲しみの中で行われる法要となります。
相手が不快な思いをしないように、丁寧な返信を心がけましょう。また、参列者からの返信をもとに会食や返礼品の準備をするため、施主が困らないようできるだけ速やかに返信するのがマナーです。
出席する場合の返信方法
一周忌に参列する場合は、出席の意思表示をします。返信はがきに「御出席」と書かれている場合、「御」を二重線で消した上で「出席」を囲みましょう。
また、「出席」の文字の下に「いたします」と一言追加することでより丁寧な返信となります。「御欠席」の文字を二重線で消すことも忘れてはいけません。
そのほか、返信用はがきに書かれた「御住所」や「御芳名」の「御」も二重線で消します。最後に、表面に書かれた「○○(施主名)行」の「行」を二重線で消し「様」と記入しましょう。
欠席する場合の返信方法
一周忌法要をやむなく欠席する際も、丁寧に返信することを心がけます。記入方法に関しては出席する際のマナーと変わりません。できれば、はがきの空いたスペースに次のような一文を添えましょう。
このたびはご連絡をいただきありがとうございます 本来ならば会場で皆様と一緒に〇〇様のご冥福をお祈りさせていただきたかったのですが 都合がつかず欠席いたします 大変申し訳ございません
万が一、一文を添えられなかった場合には、返信用はがきだけではなくお詫び状を送ることをおすすめします。
一周忌を欠席する際のお詫び状について
詫び状を送る際には、返信用はがきとは別に手紙を用意するとよいでしょう。体調が理由で欠席する際も、具体的な病名は伏せるのが一般的です。直接的ではない言葉で、体調不良で出席できない旨を伝えましょう。
仕事で参加できない場合はどうしても休めない仕事であることに加えて、遺族を気遣う文章を添えます。また、香典を合わせて送る場合は、現金書留を利用するとよいでしょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
一周忌は施主や参列者にとって大切な弔いの時間です。案内状が漏れなく必要な方に届くように、慎重に準備しましょう。また、受け取った返信もきちんと管理して出欠席の間違いがないようにチェックします。返信する側も、遺族に供養の気持ちが伝わるような配慮をすることが大切です。
小さなお葬式では、一周忌における案内状のご相談も承っております。葬儀を終え一周忌の準備を控えている方や、案内状の作成に不安がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。


四十九日法要は、故人が亡くなってから48日目に執り行います。ホゥ。