形式にとらわれない無宗教葬儀は自由度が高く、故人や親族の希望を取り入れやすいのが特徴です。あらかじめ決められた葬儀の流れがないゆえに、どのような流れや内容にすればよいのかと悩んでいる方もいるのではないでしょうか。葬儀の執り行われ方や内容を知っておけば、喪主を務めるときや参列するときに戸惑うこともありません。
そこでこの記事では、無宗教葬儀の流れや内容についてご紹介します。また、無宗教葬儀には葬儀費用の相場がありません。そのため、費用はどのくらいかかるのかについてもこの機会に確認しておきましょう。
<この記事の要点>
・無宗教葬儀は、宗教的な儀式にとらわれず、故人や遺族の希望に沿った自由な形式で行われます
・無宗教葬儀では、僧侶による読経や、故人が好きだった音楽を生演奏することもできます
・無宗教葬儀を希望する場合は、親族・菩提寺の了承を得ることが大切です
こんな人におすすめ
無宗教葬儀をお考えの方
自由度の高い葬儀に興味がある方
無宗教葬を行う際の注意点を知りたい方
無宗教葬はどのような葬儀?
無宗教葬とは一体どのような葬儀なのか、一般葬などとはどこが違うのか、気になっている方もいるでしょう。ここでは無宗教葬の概要に触れながらご紹介します。あまり聞きなじみのない形式の葬儀かもしれませんが、実際に利用している方はどの程度いるのかについても紹介するので、そちらを参考に具体的な利用の検討を進めることもおすすめです。
宗教儀式のない葬儀のこと
無宗教葬のもっとも大きな特徴は宗教的な儀式を行わないことであり、読経などのために僧侶を呼ばない点です。形式にとらわれることのない葬儀スタイルから「自由葬」と呼ばれることもあります。
設営や演出を含め、好みの内容にアレンジできるため故人を想起しやすく、「その人らしい」と感じられる葬儀を実現できます。たとえば、故人が好んで聞いていた音楽をかけたり、映像を流したりなど、通常の葬儀では行えないような演出を手掛けることも可能です。
特に葬儀の内容について故人の希望がある場合には、無宗教葬を選ぶことで希望に沿った葬儀を行いやすくなります。
近年認められつつある
少し特殊な印象が強い無宗教葬ですが、宗教的な儀式を行わない直葬を含めて考えると、首都圏を中心に利用者が微増しています。全日本冠婚葬祭互助協会のアンケートによると、お葬式の形式について「無宗教」と答えた方は、1970年代まで1.2%でしたが、2011年以降は2.2%に増えました。
日本人の葬儀への考え方は変化しており、無宗教葬も認められつつあります。そのような時代背景により、無宗教葬を選びやすくなっているといえるでしょう。
戒名やお経はどうするのか?
一般的な仏式の葬儀では、故人に戒名をつけてもらったりお経を読んでもらったりしますが、無宗教葬の場合はどうなるのでしょうか。
無宗教葬を行う上で戒名は必要ありません。ただし、お寺に納骨する際は戒名がないと受け入れてもらえない場合があるので、菩提寺がある場合は相談してみましょう。
無宗教葬は自由な形式で行えるので、お経を読んでもらっても問題ありません。読経の希望がある方は、葬儀社に依頼できるかどうか相談することをおすすめします。
無宗教葬のメリット・デメリット
無宗教葬は、宗教上の決まりにとらわれることなく、自由に執り行えるのが魅力です。一方で無宗教葬にはデメリットもあるので、よく理解しておきましょう。ここからは、無宗教葬のメリット・デメリットを紹介します。
無宗教葬のメリット
無宗教葬のメリットとして、以下の3点が挙げられます。
・宗教者へのお礼が不要
葬儀に僧侶を招く必要がないので、お布施などのお礼が必要ありません。また、戒名にかかるお金も必要ないので、経済的負担がない点がメリットです。
・葬儀の内容を自由に決められる
宗教に縛られずに、故人の意思や遺族の希望を最大限に生かした葬儀が行えます。
・信仰する宗教を問わない
家族間で宗教が異なる場合には、無宗教葬にすることで家族全員が参列できます。宗教上の理由により、他宗教・他宗派の葬儀に参列できない方でも、無宗教葬であれば参列できるでしょう。
無宗教葬のデメリット
無宗教葬にはデメリットもあるので、事前に把握しておきましょう。以下の3点がデメリットとして挙げられます。
・親族・友人から理解を得られないことがある
伝統的な葬儀にこだわりがある方や無宗教葬に違和感を持つ方から、理解を得られず反対される可能性があります。故人や家族の意向を丁寧に説明しておく必要があるでしょう。
・準備が大変になる
通常の葬儀であれば、ある程度形式が決まっています。そのため、葬儀社に依頼すれば葬儀の内容を決めてもらえます。無宗教葬の場合は、自分で内容を決めてしっかりと準備をしなければなりません。
・菩提寺とトラブルになることがある
菩提寺がある方が無宗教葬を執り行う場合は、納骨や法要を拒否されてしまうことがあります。
無宗教葬儀の流れ(一例)
無宗教葬儀は、特定の宗教に則った葬儀とは異なり決まった流れがありません。昔からの形式や慣習にとらわれないため、故人や親族の考えを反映しやすいといえます。
一方で、故人や親族の強い希望がない場合は、葬儀の流れや段取りを決めるのに時間がかかるケースが多くみられます。ここからは、無宗教葬儀の流れの一例を順番にご紹介します。
参列者入場
葬儀に参列する方(遺族、親族、友人、知人)が葬儀会場に入場し、決められた席に座ります。大規模な葬儀を執り行う場合は、入場したあとにどこに座ればよいか迷う参列者もいるかもしれません。スケジュールどおりに進めるためには、葬儀会場の入り口付近で参列者の席を確認・案内する係を設けるとよいでしょう。
このときに、故人のお気に入りだった曲を流したり、バンドによる生演奏で参列者を迎えたりする場合もあります。
開式の言葉
参列者が入場し着席が済んだことを確認して、司会者から開式の言葉が告げられます。このときの内容は、開式の言葉とあわせて、故人の人生を偲ぶようなメッセージや無宗教の葬儀を選択した理由などを伝えるとよいでしょう。このあとの進行を考えて、ほどよい長さにまとめるのがポイントです。
参列者が葬儀の際に読んでもらいたいメッセージなどがある場合は、開式前に司会者や親族の方へ渡しておくようにしましょう。
黙祷
無宗教の葬儀では仏式のように僧侶がお経を読むことはありません。初めて無宗教の葬儀に参列した方は、このような葬儀の流れに多少の戸惑いを感じることもあるようです。
無宗教の葬儀では、お経を読まない代わりに参列者全員で故人に対して黙祷を捧げます。在りし日の故人の姿を思い浮かべながら黙祷するようにしましょう。目をつぶって少し頭を下げ、故人を偲ぶ時を過ごします。
献奏
献奏(けんそう)では、故人が好きだった曲や思い出の曲をかけます。ほかにも、楽器やバンドによる生演奏をすることもあるようです。葬儀業者を利用する場合は、生演奏が可能かどうか確認しておきましょう。
生演奏以外でも、スライドショーを作成してナレーションを入れたりビデオを上映したりすることもあります。思い出の曲をかけるときは、誰からの依頼であるかということや、曲にまつわるエピソードも紹介するとよいでしょう。
お別れの言葉
お別れの言葉では、参列者が故人に別れの挨拶をします。挨拶をする人数は、一人、複数人、あるいは参加者全員という場合もあります。お別れの言葉は、仏教やキリスト教の葬儀でいう弔辞にあたり、参列者が故人との思い出や故人への気持ちを自由に伝えます。思いをつづった手紙を読み上げるケースもあります。
献花
無宗教の葬儀では仏式でいう焼香はなく、献花を行います。献花は故人を弔う意味を持つものです。菊やカーネーションなどが用いられることが一般的ですが、故人の好きだった花が選ばれることもあります。
喪主、遺族、親族、参列者の順番で花を供えます。その時に故人が好きだった曲をBGMとしてかけても問題ありません。生前の姿に近い状態を保てるようにエンバーミングがされている場合は、お顔を見ながらの献花も可能です。
閉式の言葉
閉式の言葉は、喪主から参列者に対しての挨拶です。葬儀への参列に対するお礼と、生前のお付き合いへの感謝の気持ちを表します。その後、閉式の言葉が告げられ、棺を会場から運び出す「出棺」に移ります。
出棺を行わない場合もあります。また、別室で食事をしながら故人を偲ぶ席が設けられることもあるようです。会食には参列者や、葬儀に協力してくれた方へのお礼の意味も込められています。
<関連記事>
出棺・火葬の流れと参列する際のマナー
無宗教の葬儀の内容例
無宗教葬は、宗教の概念や思想にとらわれず、自由な形式で執り行います。一般的な葬儀のように、僧侶などの宗教者を主体としないため、葬儀の段取りはある程度自分たちで決めることになります。
無宗教で自由な葬儀をしたい場合は、葬儀の内容や遺影写真など、前もって決めておくとよいでしょう。エンディングノートがあれば、ノートに書かれていることに従って葬儀を行うこともできます。
僧侶に読経をしてもらう
無宗教葬は自由葬でもあります。まったく宗教色を出さずに葬儀を執り行うこともできますが、一部分のみに宗教儀式を行うことも可能です。僧侶と連絡を取り、無宗教葬であることを告げたうえで受諾してもらうことができれば、火葬の際などに読経を依頼することもできます。
無宗教葬には縛りがなく、どのようなスタイルでも執り行える点がメリットです。近年の葬儀のあり方について理解を示す僧侶も少なくありません。斬新な演出をベースにしながらも、従来のお葬式らしさを出すこともできるので、年代を問わずに選択肢にあげられるスタイルといえるでしょう。
故人が好きだった音楽を生演奏・合唱
無宗教の葬儀では、故人が好きだった音楽を生演奏したり合唱したりすることが珍しくありません。故人を温かく見送るにはおすすめです。
参列者の中に楽器を演奏できる方がいれば問題ありませんが、そうでない場合は生演奏を依頼したり、楽器や機材の手配が必要です。合唱の場合は歌詞カードを準備しておきましょう。
スライドや動画を見ながら故人の思い出を語る
思い出の写真や画像をまとめたスライドや動画を見ながら故人の思い出を語るのもよいでしょう。参列者が故人とのエピソードを語る機会にもなります。遺族や親族が知らなかった故人の一面を知る大切な時間になるでしょう。
スライドや動画を作るのが得意な方が身近にいない場合は、業者に依頼しましょう。
故人の趣味や、思い出の品の展示をする
故人が打ち込んでいた趣味があれば、それに関係した品々を展示するのもよいでしょう。ほかにも、思い出の品やそれにまつわる写真を展示すると、参列者同士で故人を偲ぶことができるでしょう。忘れていた故人との思い出もよみがえるかもしれません。
しかし、遺族や親族の中には故人が亡くなったばかりで気持ちを整理できていない方がいる場合もあります。その場合、故人の品を見るのを辛く感じることがあるかもしれません。あらかじめ遺族や親族の許可を得る心遣いも必要です。
無宗教葬には相場がない
無宗教葬の内容は自由に決められるものであり、人によって内容が大きく異なるため相場に言及することはできません。
予算に応じた葬儀が行える点も無宗教葬の魅力なので、葬儀社の葬儀プランを比較して、想いに沿った葬儀形式を選ぶとよいでしょう。

葬儀後のお骨の供養は?
無宗教で葬儀を行った場合、その後のお骨の供養はどのようにするとよいでしょうか。お骨の供養方法についてご紹介します。
永代供養
永代供養とは、永代供養墓がある寺院や霊園などが、ご遺族に代わって故人の遺骨を管理する供養方法です。宗旨・宗派を問わずお墓を建てる必要もないので、一般のお墓での供養に比べて費用を抑えることができます。また、お墓の管理を任せられるので、お墓の後継人がいないという方には最適です。
永代供養だけでなく、お墓・納骨堂・樹木葬など、納骨先探しをお手伝いするサービスがあります。
「OHAKO-おはこ-」の永代供養は、
・全国の霊園・寺院から納骨先をお選びいただけます。
・ご希望の宗旨・宗派をお選びいただけます。
・安置方法や個別安置期間がお選びいただけます。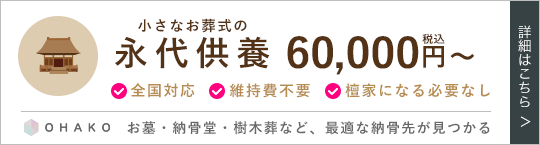
海洋散骨
海洋散骨とは、パウダー状にした遺骨を海に撒く供養方法です。自然に還す埋葬方法を希望する方が増えており、お墓に比べて維持費もかからず、宗教やしきたりにとらわれることがありません。
「OHAKO-おはこ-」の海洋散骨は、
・日本全国から散骨海域をお選びいただけます。
・ご家族に代わって散骨を行い、後日「散骨証明書」とアルバムをお届けします。
OHAKO-おはこ-の海洋散骨
また、納骨は四十九日法要の時期に行うのが一般的ですが、無宗教葬の場合は特に行う必要はありません。別の方法で行いたい場合は、追悼式や記念式という形をとることもできます。
宗教を問わない墓地を選ぶ
すべてのお寺には宗派が決まっているというイメージがありますが、宗教を問わないお寺の墓苑や霊園も各地にあります。無宗教葬を行った場合は、こういった宗派とは無関係な墓地を選んで納骨することをおすすめします。
その理由は、菩提寺が宗派を厳格に守るお寺だった場合、宗派の作法に則った葬儀をあげていない方の納骨を拒むことが多いためです。宗派を問わないタイプの墓地や霊園を選ぶことで、このようなトラブルは起こらなくなります。
公営の墓地にする
予算をなるべく抑えてお墓を購入したい場合は、公営の墓地を選択するとよいでしょう。公営の墓地には指定の宗教・宗派がありません。無宗教葬を行った方でも納骨できます。墓地によって設備の内容は異なるので、いくつかの候補を見比べてみましょう。
無宗教葬を行う際の注意点
費用を抑えられたり、故人の希望する葬儀が行えたりとメリットも多い無宗教葬ですが、知っておきたい注意点もあります。ここからは、無宗教葬の注意点を紹介します。
親族・菩提寺の了承を得る
ごく一般的な葬儀をイメージしている親族にとって、新しい形式の無宗教葬を受け入れることは難しい場合があります。親族の意向を考慮せずに無宗教葬を強行すると、トラブルのもとになります。
長く付き合いを続けてきた菩提寺がある場合も、無宗教葬を選ぶことで納骨できなくなる可能性もあります。このようなトラブルを避けるためには、親族や菩提寺と連絡を取り、無宗教葬を行いたいという希望を伝えましょう。
意図を理解してもらって、故人に関わるすべての人からの了承を得ることが大切です。
<関連記事>
直葬で納骨が断られる可能性がある!断られたときの対処法は?
やりたいこと・やりたくないことを決める
無宗教葬は決まった形式がないため、あっという間に終わってしまうケースもあります。故人がシンプルな内容を望んでいた場合を除き、思っていたとおりの進行ではなかった場合、後々まで悔いが残ってしまいかねません。
そのため、内容をしっかり計画して、やりたいこと・やりたくないことを細かく決めておきましょう。また、親族間だけで協議するのではなく、内容が決まったら、そのプランを葬儀社のスタッフ、会場のスタッフに伝えることも忘れないように注意しましょう。
無宗教葬に対応している葬儀社を選ぶ
無宗教葬は一般的に普及しているとはいえないため、葬儀を行った経験がない葬儀社もあることを理解しておきましょう。無宗教葬に慣れている葬儀社であれば、内容や進行について具体的な提案をしてもらえます。無宗教葬を滞りなく行うためには、葬儀社選びが重要です。
無宗教葬に参列する際のマナー
宗教上の縛りがないため、無宗教葬に参列する際のタブーは特にありません。ただし、一般的に守ったほうがよいとされるマナーがあるので、確認しておきましょう。
服装のマナー
無宗教葬に参列する際の服装には決まりがありませんが、略式の喪服を着用することが一般的です。男性は黒のスーツでワイシャツは白、靴、靴下、ネクタイ、ベルトは黒でそろえましょう。
女性は、黒のワンピースやアンサンブルで、靴やストッキングも黒のものを着用します。
香典のマナー
遺族が香典を辞退していない場合は、香典を準備しましょう。一般的な不祝儀袋に包み、「御霊前」や「御花料」という表書きにします。宗教とは関係のない表記にするのがマナーです。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
自由な形式で葬儀を行える無宗教葬は、首都圏を中心に認知度が増加傾向にある新しいスタイルの葬儀です。親族や菩提寺と連絡を取りながら、故人の意向を尊重できる、個性的な葬儀を選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。
小さなお葬式では「小さなお別れ葬」を用意しており、一般的な葬儀の平均費用に対して、比較的安価に葬儀が行えるプランをご紹介しています。できるだけ簡素な葬儀をご希望の方や、故人が宗教的な儀式を不要としているならば、ぜひともご利用をご検討ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



不祝儀袋は、包む金額に合わせて選ぶと丁寧です。ホゥ。




























