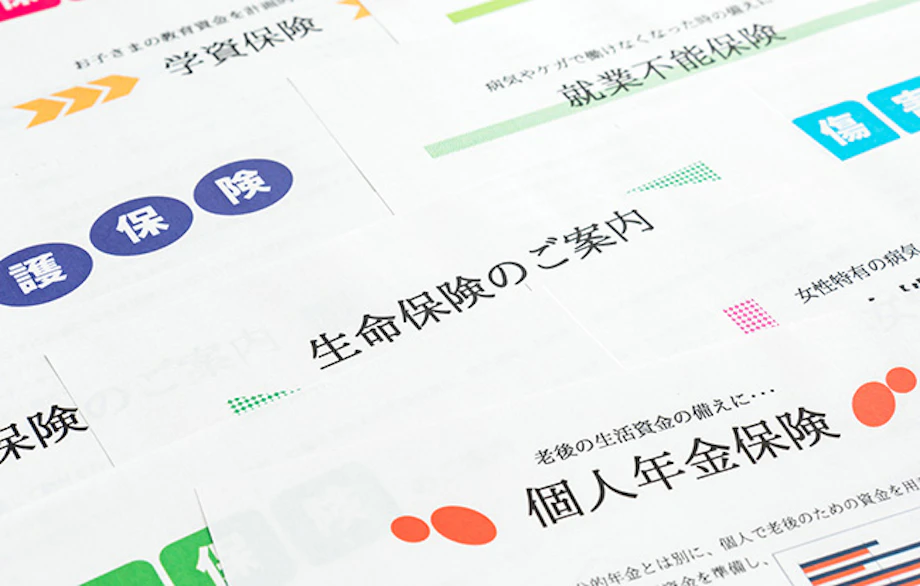個人年金保険の満期保険金や解約返戻金には税金がかかります。正しい税金を納めるためには確定申告が必要ですが、個人年金保険は契約者と年金受取人の関係によって税金の区分が変わるので注意しましょう。
また、受取形式を年金形式にするか、一括形式にするかによって所得金額に対する影響も変わります。それぞれの形式における所得金額の計算方法を理解し、どちらの形式で受け取る方が税制的に有利かどうかも考えて受取形式を選択するのがよいでしょう。
この記事では個人年金保険の税金の計算方法と納税の際の注意点について解説します。
<この記事の要点>
・個人年金保険を一括形式で受け取る場合、50万円以下の場合は課税されない
・個人年金保険の税金は総所得金額で税率が変動する総合課税によって決定する
・個人年金保険は、源泉徴収を受けた後に確定申告が必要
こんな人におすすめ
個人年金保険の税金について知りたい方
個人年金保険に関係する税金の計算方法を知りたい方
個人年金保険の税金に関する注意点を知りたい方
個人年金保険とは
個人年金保険は国民年金とは別に受給できる、民間の保険会社が提供する保険商品のことを指します。国民年金の支給額だけでは生活を安定させるのが難しい場合に、個人年金保険に加入することで生活費を補うことができます。
個人年金保険は国民年金とは異なり、保険会社が取り扱う商品です。種類もさまざま存在しているため、商品性にも違いがあります。個人年金を受け取れる期間が決まっており、支給期間中に死亡した場合は遺族が年金を受け取れる確定年金や、自身が死亡するまで年金が受け取れる終身年金など年金の受取期間に対する取り決めが異なります。
個人年金保険の保険金は年金形式で受け取るのではなく、満期時に保険料を一括で受け取る一時払いで受け取ることも可能です。個人年金保険には国民年金の老齢基礎年金と同様に税金がかかりますが、年金形式で受け取るか一括で受け取るかによって所得の区分が異なり、税金の計算方法まで変わります。
個人年金保険に加入するなら、税金の違いや計算方法について理解することで、自身に最も適した形式で年金を受け取れるようにしましょう。
個人年金保険の税金について
個人年金保険による年金収入は受け取り形式によって税金が異なります。年金形式と一時払いで変わる所得の区分について確認しましょう。
年金形式で受け取る場合は雑所得
個人年金保険を年金形式で受け取る場合は雑所得の対象です。雑所得は給与所得や事業所得などの9つの所得のどれにも分類されない所得のことであり、国民年金、印税・講演料、不動産所得や配当所得以外の投資の利益などが雑所得に該当します。
雑所得に該当する利益はさまざまあるため、個人年金保険の収入以外にも雑所得による収入があれば足し合わせた上で課税額を決定する仕組みです。
一時払いで受け取る場合は一時所得
個人年金保険を一時払いで一括受取をする場合は一時所得の対象になります。一時所得に該当する所得は営利や業務を目的とする利益を除いて、保険の一時金や損害保険の満期返戻金、懸賞や福引の景品、法人から贈与された金品、競馬や競輪の払戻金などが対象です。
一時払いは特別控除額が50万円に設定されているため、該当する所得が50万円以下の場合は課税されません。
契約者と年金受取人の関係によって税金が異なる
個人年金保険は契約者と年金受取人が同一であれば雑所得であっても一時所得であっても所得税の対象ですが、契約者と年金受取人が異なる場合は贈与税の対象です。
年金の受け取りが開始された時点で、契約者から年金受取人へ年金を受け取る権利が贈与されたと解釈されるので贈与税が発生します。さらに年金の支給額に対しても所得税が課される仕組みです。
仮に、契約者が配偶者の将来を考えて年金受取人を配偶者にして契約した場合は、贈与税と所得税の両方を支払う必要があります。結果的に自身が年金受取人になるか、配偶者が契約するほうが最終的に受け取れる額が増加するため、個人年金保険の加入する際には契約者と年金受取人の関係に注意が必要です。
個人年金保険における雑所得の計算方法
個人年金で受け取れる年金額の内訳は「基本年金+増額年金+増加年金」となっているので、すべての年金収入の合計を計算し、必要経費を差し引くことで求められます。
必要経費は個人年金保険の種類によって求め方が異なります。例えば、個人年金保険の年額の総収入が50万円であると仮定したとき、払込保険料の金額が1,000万円であるとします。
必要経費の計算に必要な支給期間は確定年金の場合は決まっていますが、終身年金の場合は所得税法82条の3で定められている年齢別の余命年数を参考に支給期間を求めます。
終身年金で見込み支給期間が23年の場合の必要経費と雑所得金額の計算は次のようになります。
必要経費:50万円(年金年額)×「1,000万(保険料払込総額)÷『50万円(年金年額)×23年(支給期間)』」=43万5,000円
雑所得金額:50万円(総収入金額)-43万5,000円(必要経費)=6万5,000円
参考:個人年金保険の年金を受け取って所得税がかかるときの計算方法は? 公共財団法人 生命保険文化センター
個人年金保険における一時所得の計算方法
雑所得を計算した例を基に一時払いで1150万円を受け取った場合の一時所得は次の通りです。
一時所得=1150万円(総収入金額)-1,000万(保険料払込総額)-50万円(特別控除額)=100万円
ただし、給与所得などの他の所得と合算し、税額を計算する際には一時所得金額の2分の1に相当する額で計算します。よって、50万円を他の所得と合算して税額を計算する仕組みです。
参考:No.1490 一時所得 国税庁
個人年金保険に関係する税金の計算方法
個人年金保険による所得金額が分かれば、具体的な税金の計算も可能になります。所得税と贈与税に関して計算方法を解説します。
総合課税による所得税の計算方法
所得税の課税方法は総所得金額で税率が変動する総合課税と税率が固定される分離課税に分かれますが、個人年金保険の税金は総合課税によって決定します。総合課税の税率を下記の表にまとめました。
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
総合課税は所得が増えるほど税率が上がる仕組みであるため、個人年金にかかる税率は年金受取人の課税所得額に依存します。実際には控除額もありますが、単純な税率のみを計算すると課税所得金額の計算は次の通りです。
課税所得金額が195万円以下:50万円×5%=2万5,000円
課税所得金額が4,000万円以上:50万円×45%=22万5,000円
個人年金以外の所得が大きいほど個人年金にかかる税率が高くなります。また、年金を一括で受け取ったことにより税率が上昇するリスクも大きいので、総合課税の仕組みの関係上、一時払いで受け取るほうが税金面で不利になることもあります。
参考:No.2260 所得税の税率 国税庁
贈与税の計算方法
贈与税は年金受取人に対して年金を受け取る権利を贈与した場合に、個人年金の受け取り額に対してかかります。個人年金の受け取り額が1,150万円の場合は贈与税の基礎控除である110万円を差し引いた1,040万円が課税対象です。
個人年金保険の受取人が配偶者や家族のケースでは贈与税の特例税率が適用されます。特例税率について下記の表にまとめました。
| 課税対象金額 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
1,040万円は1,500万円以下に該当するため、贈与税の計算は次の通りです。
贈与税:1,040万円×40%-190万円=226万円
贈与税を納めるのは年金の受け取りが始まった初年度のみになりますが、加入時に契約者と年金受取人の関係を適切なものにしなければ、予想外の税金が発生することになるので気をつけましょう。
参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁
個人年金保険の税金に関する注意点
個人年金保険の税金には誤解しやすい点が存在しており、確定申告の際に間違えると正しい税金額を納付できないことにつながります。個人年金保険の税金に関する注意点は3つあるので、勘違いのないように確認しましょう。
源泉徴収されていても確定申告が必要
保険料の負担者と年金の受取人が同一人の場合、所得税と復興所得税が源泉徴収されます。株式投資等の利益は源泉分離課税にでき、確定申告をしなくても税金の納付が完結するため確定申告の義務はありません。このことから、源泉徴収を受けているから確定申告の必要がないと勘違いする方もいるかもしれません。
しかし、個人年金の収入は雑所得として課税所得金額によって税率が変動する総合課税の対象であるため、源泉徴収された税金が正しい納付額にはなりません。個人年金保険の源泉徴収額は所得税と復興所得税を合わせた10.21%です。
個人年金保険においては、源泉徴収を受けた後に確定申告をおこない、改めて正しい税金を納付する必要があります。
参考:No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金 国税庁
受取人を変更した場合は課税関係が複雑になる
契約者と年金受取人の関係から自身の加入している個人年金保険が所得税と贈与税の両方が掛かると分かった場合は、途中から年金受取人を自身に変更することも可能です。ただし、年金受取人を変更した場合も贈与税を一部負担する必要があります。
・年金受取人が配偶者だったときの保険料に相当する保険金:贈与税の対象
・年金受取人を自身に変更した後の保険料に相当する保険金:贈与税はかからない
自身を年金受取人に変更した後の保険金には贈与税は課されない仕組みですが、年金受取人が配偶者だった時期に支払った保険料に相当する保険金に関しては贈与税が課される仕組みです。
契約者や受取人を変更すると課税関係が複雑になるので、確定申告をする際にも注意が必要です。加入時に契約者と年金受取人を同一にして契約するのが一番ですが、途中から変更する場合でも贈与税の負担を減らせるので、課税関係に気を付けながら変更をおこないましょう。
参考:契約者や受取人を途中で変更した場合の税金は? 公共財団法人生命保険文化センター
配偶者控除が受けられないことがある
自身が専業主婦(主夫)で配偶者が配偶者控除を受けている場合、個人年金によって所得が増加すると配偶者控除が受けられない可能性があります。配偶者控除を受けられる条件は自身の所得が48万円以下であることが条件であり、48万円~133万円の場合は配偶者特別控除となり所得が増えるほど控除額が減少する仕組みとなっています。
個人年金を含む年金を受け取る場合は、できる限り所得を減少させたほうが有利です。個人年金保険は一時払いよりも年金形式で受け取る方が所得を減少する効果が期待できます。自身が年金を受け取る際に配偶者が定年を迎えていないことが条件になりますが、自身と配偶者の年齢によっては意識しておいたほうがよいでしょう。
参考:専業主婦が満期保険金や年金を受け取ると、夫の配偶者控除はどうなるの? 公共財団法人 生命保険文化センター
外貨建て個人年金保険の税金
個人年金保険にはさまざまな種類の商品がありますが、保険金が外貨で支払われるタイプの保険もあります。為替差損が発生するリスクはありますが、円建て保険よりも運用収益を見込めることから保険料が安くなるメリットや、円建てよりも利率の高い保険も存在するので、外貨建て保険は円建て保険にはない魅力を持った商品となっています。
ただし、保険金を外貨で受け取った場合でも、日本に在住しているなら日本の税金がかかります。保険金の支払事由発生日の為替レートで換算した日本円の金額を用いて納税をおこなう仕組みです。基本的には保険会社から円換算した金額が通知されるので納税額を間違える心配はありません。
基本的な仕組みは円建ての個人年金保険と変わらないので、外貨建て個人年金保険で得た年金収入も円換算をした上で確定申告するようにしましょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
個人年金保険の税金は契約者と年金受取人の関係や、年金の受け取り形式によって変化するため、保険の加入時に最適な方法で契約して受け取ることが節税にもつながります。
個人年金保険を一時払いで受け取る場合は、保険金が総合課税の対象であることや、配偶者控除から外れることを考えると税金面で不利になるケースがあるので注意が必要です。
課税所得金額を計算し、税金の計算をした上でどのように契約するべきか考えたうえで個人年金保険に加入することが重要になります。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


忌引き休暇は、実は労働基準法で定められた休暇ではありません。ホゥ。