家族や親族が亡くなった後、故人が所有していた財産を相続することになります。「相続財産であるかどうか」が重要な判断基準ともいえますが、詳しいルールについては理解できていない方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、相続財産に関する具体的な情報を詳しく解説します。相続税がかかる範囲を把握しておくと、相続の手続きを進める際もスムーズに実行できるでしょう。後半では、相続放棄を希望する場合の規定もご紹介します。家族信託のサービスについても紹介しているので、参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・相続財産とは不動産やお金などの財産全般を指すが、借金などの負債も含まれる
・本来他人に移転できない権利や義務は、相続対象に含まれない
・相続財産のうち、金銭的な価値が明確であるものは課税対象となる
こんな人におすすめ
相続財産について知りたい方
課税対象となる相続財産について知りたい方
相続財産を調べる方法が知りたい方
相続財産とは
故人や生前所有していた不動産やお金など、相続の対象となる財産全般が「相続財産」です。物理的なもののほとんどが相続財産に該当しますが、含まれないものについても把握しておきましょう。相続人にとって、マイナスとなるような財産も相続の対象です。相続財産の基本的な考え方について、3つの項目に分けて詳しく解説します。
相続財産はプラスもマイナスも全てが基本
相続財産には、故人が所有権を持っていたものの多くが該当します。現金や車の他、株式のような投資関係も対象のひとつです。現金だけでなく、会員権のようなものも相続財産として扱われる規定を理解しておきましょう。
特に注意したいのは、借金などマイナスになるものも対象に含まれるという点です。故人が借金を多く抱えていた場合、相続人が債務を引き継ぐ結果になるケースもあります。金銭的なトラブルを避けるためには、相続決定前の入念な調査が重要です。
相続財産となるもの
現金から古美術品まで、さまざまなものが相続財産の対象に挙げられます。以下の項目を参考に、該当する範囲を認識しておきましょう。
・不動産(土地や建物)
・借地権
・預貯金や現金
・株式など投資関係の資産
・宝石・貴金属
・車
・金銭債務
特許権や営業権など、「無体財産権」と呼ばれる権利も相続財産です。上記の他にも複数の相続財産があるため、マイナスとなる債務も含めてしっかりチェックしておきましょう。
相続財産とならないもの
本来他人に移転できない権利や義務は、相続が発生した場合でも対象に含まれません。ものや書類を交わす契約が不可能であり、承継できない権利義務ともいえるでしょう。代表的には以下のような項目があります。
・雇用契約における使用者または被用者の地位
・年金受給者の地位
・親権者の地位
・扶養請求権者としての地位
・生活保護給付における受給権者の地位
例えば、故人が生前年金を受給していた場合、相続人が引き継いで受給できるわけではありません。相続財産の対象とは明確な違いがあるため、あらかじめ区別することが大切です。
相続財産を調べるには
故人の財産を具体的に知りたい方は、複数パターンの方法によって調査ができます。財産の内容によって調査方法が異なるため、対象に応じた手続きが必要です。専門家に依頼する可能性も踏まえた上で、調査にかかる費用の目安を把握しておきましょう。財産を2つの種類に分けたとき、実践可能な調査方法について解説します。
積極財産を調べる方法
不動産のように、特定の所有者に関わらず金銭価値を見込めるものが「積極財産」です。動産や預貯金も対象に含まれます。不動産の現状を調査する場合は、固定資産税関係の書類や名寄帳を確認しましょう。所有している場所や、不動産の形態などが明確化できます。
預貯金など銀行関係の財産を調べる際には、故人のキャッシュカードや通帳が有効です。ネットバンキングを利用している可能性があるため、銀行関係のメールがないか確認した方が良いでしょう。金融機関が確定した後は、直接問い合わせると情報を収集できます。
消極財産を調べる方法
故人が抱えていた債務など、金銭的にマイナスとなるものが「消極財産」です。借金に関する情報は、以下いずれかの機関に問い合わせると収集できます。
・CIC
・JICC(日本信用情報機構)
・KSC(個人信用情報センター)
債務の可能性がある方は、上記全ての機関で調査した方が良いでしょう。金融機関によって、記録先の機関も異なる可能性があるためです。窓口や郵送の他、Webサイトからも開示を申請できます。
調査にかかる費用相場
財産の調査は、相続人自ら行うことも可能です。ただし、金融機関や不動産など複数の観点から調査を進める手間がかかります。時間的・体力的な負担を考慮すると、弁護士または司法書士といった専門家に依頼した方が良いでしょう。依頼時は、専門家に対する報酬の他以下の費用が必要となります。
・戸籍などの請求費用
・登記情報の取得費用
・不動産関連の取引履歴取得費用
具体的にはさらに細分化されるケースもあるため、直接相談して内訳を提示してもらいましょう。全体での相場は、20万円~30万円の範囲です。
相続税は全てにかかるわけではない
相続財産が多数認められる場合でも、全てに相続税が課税されるわけではありません。相続財産と相続税の対象は別の規定が設けられているため、課税・非課税の違いを明確にしておきましょう。死亡保険金など、「みなし相続財産」と呼ばれる項目にも注意が必要です。相続税について押さえておきたいポイントを3つご紹介します。
相続税が課税となる財産
相続財産のうち、金銭的な価値が明確であるものは課税対象です。預貯金や現金以外に、不動産も相続税を支払う義務があります。代表的な対象は以下です。
・現金
・預貯金
・土地
・建物
・有価証券(株式など)
株式を所有している場合も、相続すると税金を納める義務が発生します。貸付金や特許権などの相続財産も、相続税を支払うルールです。項目が多いほど複雑に感じやすいため、相続財産とは別で区分すると考えやすくなるでしょう。
相続税が非課税となる財産
相続財産の中でも、宗教に深く関わるものや交易を目的とした寄贈は課税の対象外となっています。以下のように、非課税が認められる財産を把握しておきましょう。
・墓地や仏壇
・宗教など、公益を目的とした事業に寄贈・相続した財産
・相続財産のうち、公益を目的として寄付したもの
・個人経営の幼稚園で、事業に使われた財産(条件あり)
また、火葬や埋葬の費用が高額になった場合、相続税が減額されるケースもあります。あらかじめ定められた基礎控除に上乗せするかたちで差し引き、本来課税される金額よりも負担を軽減できる仕組みです。
みなし相続財産に注意
相続財産に該当しない場合でも、相続税が発生するものが「みなし相続財産」といわれています。通常、死亡による退職金や保険金は、相続人に直接支払われます。形式上は相続のかたちを反映していませんが、受け取り時には税金が発生する規定です。
保険金を受け取る可能性がある方は、控除額についても把握しておきましょう。500万円に法定相続人の数をかけた金額までは非課税となり、相続税が発生しません。1人の相続を想定した場合、500万円までの保険金は非課税で受け取れます。
相続放棄をするには
多額な債務などを理由に相続を避けたい場合は、「相続放棄」を希望できます。申請には相続発生から期限が設けられているため、予定通りに進められるよう規定を把握しておきましょう。安易に財産を使用すると、相続放棄自体が取り消される点にも注意が必要です。相続放棄の基本概要を踏まえた上で、重要なポイントをご紹介します。
相続放棄とは
相続を行うことで望ましくない結果が予測されるとき、選択できるのが「相続放棄」です。多くの場合、「故人の債務が多額で返済が難しい」といった理由が挙げられます。親族間でトラブルが発生するような状況であれば、相続問題を回避するための手段にも有効といえるでしょう。
相続放棄には、3か月の申請期限が設けられています。相続が発生した日ではなく、相続を予定している本人が事実を確認したタイミングが開始日です。協議や調査を含めると期限が過ぎる可能性もあるため、なるべく早急な手続きを意識しましょう。
相続放棄前に財産は調査するのが良い
多額の債務が明確な状況であっても、相続放棄を即決するのは賢明といえません。3か月の期限を把握した上で、財産の内容を細部まで調査してみましょう。プラスとなる積極財産を相続する場合、消極財産と相殺できる可能性も十分に考えられます。
焦って調査すると、本来相続できるものを見落とすかもしれません。調査内容に不安がある方は、弁護士など専門家に相談して徹底的に調べた方が良いでしょう。相続後に支払える金額であれば、相続した方が有益になることもあります。
相続放棄後に財産を使うと取り消される
財産放棄の手続きが完了した後は、相続予定であった財産の使用も認められません。債務を返済する義務がなくなると同時に、預金や不動産といった相続財産も使えなくなります。放棄後に使用すると手続き自体が取り消される可能性もあるため、財産の取り扱いには注意が必要です。
財産に関する規定上、相続の取捨選択ができない点も理解しておきましょう。希望のものだけ相続したり、消極財産のみ放棄したりといった手段は選べません。
家族信託という選択肢もある
相続財産について詳しく知りたい際に、認知症についても気になるという方は多いのではないでしょうか。認知症になると、法的に意思能力がないものとされる可能性があり、本人名義の不動産の売却や、銀行口座からの出金が凍結によってできなくなることがあります。唯一の対処法である「成年後見制度」も、費用や財政管理の面で戸惑う方が多いようです。
そこで今注目されているのが、大切な財産を信頼できるご家族に託す「家族信託」です。認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することができます。
ファミトラの「家族信託」は家族信託に必要な手続きを、弁護士や司法書士など多様な専門家がサポートし、誰でも簡単に・早く・安く組成できるサービスです。資産管理にお困りの方は、お気軽にお問合せください。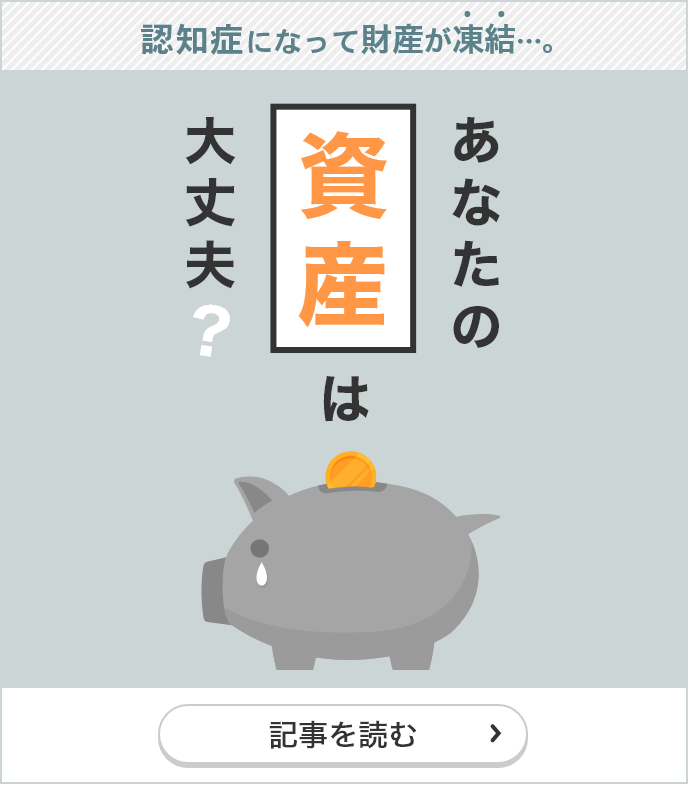
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
故人から相続が発生した際には、自分が受け取る財産の内容を明確にする必要があります。むやみに相続手続きを進めると、債務による金銭的負担を増幅させるリスクがあるためです。相続税も、今後の生活に影響する要素といえます。
万が一消極財産が多額であっても、積極財産によって負担を減らせるかもしれません。相続で得られる財産や出費を把握した上で、どのような手段が適切であるか見極めることが大切です。親族と相談しながら、より良い環境へ近づけていきましょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
相続財産とは?
何が相続財産を調べる方法は?
課税対象となるものと、ならないものの違いは?
みなし相続財産とは?
初盆(はつぼん)とは、亡くなった方の忌明け後、最初に迎えるお盆のことです。ホゥ。






























