家族の形は多様化しています。なかには、娘の夫を婿養子にしているという方もいるのではないでしょうか。しかし、婿養子についての相続ルールを誤解していたり見落としていたりする方も少なくありません。
そこでこの記事では、婿養子の相続権について詳しく解説します。家族信託のサービスについても紹介しているので、参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・婿とは妻側の名字を名乗っている男性全般、婿養子とは妻の両親と養子縁組をしている男性を指す
・婿養子は実子と同様に相続人となる
・娘が婿養子と離婚をした場合でも通常の養子として相続の権利は残る
こんな人におすすめ
婿養子と婿の違いについて知りたい方
婿養子に相続の権利はあるのかを知りたい方
婿養子の相続割合はどのくらいかを知りたい方
婿養子と婿の違いとは
はじめに、「婿養子」や「婿」の定義を確認しておきましょう。
まず「婿」とは法律で定義された言葉ではありませんが、一般的に婚姻にともない妻側の名字を名乗っている男性全般を指します。妻側の名字を名乗る男性の中でも、特に妻の両親と同居をしている男性を指す場合もあります。
一方で「婿養子」とは、妻側の名字を名乗っていることに加えて、妻の両親と養子縁組をしている男性のことです。
単に妻側の名字を名乗っていたり妻の両親と同居をしたりしているからといって、自動的に「婿養子」になるわけではありません。婿養子に該当するかどうかは養子縁組をしているかどうかが大きなポイントとなるので、この違いを確認してきましょう。
なお、国民的アニメに登場する「マスオさん」は妻側の名字を名乗っているわけではないため、正確には「婿」でも「婿養子」でもありません。
婿養子に相続の権利はある?
では、婿養子に相続の権利はあるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
婿養子も相続人になる
実は、婿養子も妻の両親の相続人です。
婿養子に限らず、養子である以上は実子と同様に相続人となるので、婿を養子にする際にはこの点も知ったうえで養子縁組をするとよいでしょう。
婿養子がいる場合に相続人になるのは誰?
婿養子がいる場合に、相続人となる人は誰なのかを整理しておきましょう。次の2つの例で解説します。
ほかに実子がいるケース
たとえば、妻、長女、長女の夫である婿養子と同居しており、ほかに既に婚姻をして別の世帯で暮らしている次女と三女もいるものとします。この場合の法定相続人は、次のとおりです。
・妻
・長女
・長女の夫(婿養子)
・次女
・三女
既に別で世帯を築いている次女や三女と同様に、婿養子も相続人となります。
ほかに実子がいないケース
では、ほかに実子がいない場合はどうなるのでしょうか。たとえば、妻は存命で子はもともと長女のみの一人っ子であったものの既に他界、亡くなった長女の夫である婿養子とは別居しているもののあえて養子縁組の解消はしていないものとします。長女と婿養子との間に子はいませんでした。なお、被相続人には兄弟姉妹や甥姪が計5名存在します。
この場合の法定相続人は、それぞれ次のとおりです。
・妻
・長女の夫(婿養子)
娘が亡くなったとしても、その夫である婿養子の養子縁組が自動的に解消されるわけではありません。仮に解消したいのであれば、別途手続きを踏む必要があります。そして、第一順位の相続人である子(婿養子)がいる以上は、相続人としての順位の劣る兄弟姉妹や甥姪は相続人とはなりません。
婿養子ではない婿は相続人ではない
婿養子は妻の両親の相続人である一方で、養子縁組をしていない単なる婿は相続人ではありません。たとえ妻側の名字を名乗り両親と長年同居をしていたとしても、養子縁組をしていない以上は相続権が発生することはないので、注意しましょう。
婿養子ではない婿に財産を渡したい場合には、次の方法などを検討する必要があります。
・遺言書
遺言書で財産を渡す相手に制限はありません。相続人ではない婿に対して財産を渡すことも可能です。
・生前贈与
生前贈与は、お互いの「あげます」「もらいます」との意思が合致すれば成立します。ただし、生前贈与にかかる税金は贈与税であり、贈与をした財産の額によっては高額な贈与税がかかる場合もあります。生前贈与は、事前に税金の試算をしてから行うようにしましょう。
婿養子の相続割合はどのくらい?
婿養子が相続人になるということは、遺産を分ける話し合いである遺産分割協議に、婿養子も参加するということです。
では、その遺産分割協議で主張ができる婿養子の相続分は、どのように定められているのでしょうか。ここでは、婿養子の法定相続分について確認しておきましょう。
婿養子の相続割合は実子と同じ
婿養子の法定相続分は、実子と同じです。
たとえば上で記載をした妻、長女、長女の夫である婿養子、次女、三女が法定相続人になるケースでは、それぞれの法定相続分は次のようになります。
妻:2分の1
長女:8分の1
長女の夫(婿養子):8分の1
次女:8分の1
三女:8分の1
婿養子と実子との相続分には何の差もありません。実子である次女や三女と婿養子の相続での権利は同じとなります。
なお、「夫婦」の単位で見れば長女夫婦は長女と婿養子とを合わせて財産の4分の1を相続することになるため、相続分がそれぞれ8分の1である次女や三女から見れば不公平に感じる場合もあるでしょう。
しかし、相続のルールは夫婦ではなく個人の単位で考えるため、夫婦単位でみれば、他より取り分が多いからと言って、法律上なんらかの調整がされるわけではありません。
代襲相続が起きているケース
上の例で長女がすでに亡くなっており、長女と婿養子との間に2名の子(被相続人の孫)がいる場合の相続分はどうなるのでしょうか。
この場合のそれぞれの法定相続分は、次のようになります。
妻:2分の1
長女の夫(婿養子):8分の1
長女の子である孫①:16分の1(長女が受け取るはずであった8分の1×2分の1)
長女の子である孫②:16分の1(長女が受け取るはずであった8分の1×2分の1)
次女:8分の1
三女:8分の1
この場合であっても、婿養子の相続分が特に増減するわけではありません。
婿養子に相続で財産を渡さないことはできるのか
ご家族の関係性や相続についての考え方などは、さまざまです。場合によっては、婿養子には財産を渡したくない場合もあるでしょう。
ここでは、婿養子に財産を渡さないことはできるのかどうか解説します。
婿養子に財産を相続させない遺言書の作成は可能
まず、婿養子に財産を渡さない内容の遺言書を作成すること自体は可能です。
たとえば、実子である長女(婿養子の妻)と婿養子の2名が相続人である場合に、長女に全財産を相続させる内容の遺言書を作るようなケースが考えられます。
婿養子には遺留分がある
婿養子に一切財産を遺さない内容の遺言書をつくることはできるものの、この場合には遺留分に注意が必要です。
遺留分とは
遺留分とは、子や配偶者など一定の相続人の保証されている、相続での最低限の取り分のことを指します。婿養子であっても相続の権利は実子と同じなので、遺留分の権利があります。
遺留分を侵害した内容の遺言書をつくること自体は可能ですが、相続が起きた後で、遺留分権利者から遺言で財産を多く受け取った人に対して遺留分侵害額請求がなされるかもしれません。
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額を金銭で支払ってくれとの請求のことです。この請求がされると、実際に侵害した遺留分に相当する分の金銭を支払わなければなりません。
特に財産の大半が自宅の不動産など金銭に変えることが難しいものである場合には、遺留分を支払うためのお金を確保することができず、困ってしまう場合もあるでしょう。
そのため、婿養子に財産を渡さない内容の遺言書をつくる際には、婿養子にも遺留分の権利があることを知ったうえで作成をすることが必要です。
とはいえ、例のように自分の妻である被相続人の長女が全財産を相続した場合には、婿養子固有の取り分がなかったとしても遺留分侵害額請求をするケースはそれほど多くはないでしょう。
ただし、たとえば離婚に向けての協議中であるなど長女と婿養子の間の夫婦関係が悪化している場合などにはしっかりと遺留分を請求される場合もありますので、注意が必要です。
娘が離婚をしたら自動的に婿養子の相続権はなくなるか
婿を養子にしているのは、自分たちの娘の夫であるからというのが最大の理由であるケースは少なくないでしょう。
では、娘が婿養子なっている夫と離婚をした場合には自動的に婿養子ではなくなり、相続の権利はなくなるのでしょうか。
離婚をしても相続権はなくならない
実は、娘が婿養子となっている夫と離婚をしたからといって、自動的に養親と養子の関係性までが解消されるわけではありません。つまり、娘が婿養子と離婚をしたとしても、それだけで妻の両親に対する婿養子の相続の権利がなくなるわけではないということです。
娘と離婚をした以上は「婿養子」の定義には該当しなくなるものの、通常の養子として相続の権利は残ります。
婿養子の相続権をなくすには離縁が必要
婿養子から相続の権利をなくすためには、別途婿養子と養子縁組を解消する手続きを経なければなりません。養子でなくなれば、相続人ではなくなるためです。なお、養子縁組を解消する手続きは、たとえば養親のみなど一方の意思だけで行えるものではない点にも注意しておきましょう。養子縁組を解消するためには、離婚と同じように、原則として双方の意思が必要です。
養子縁組を解消するためには、次の方法が考えられます。
協議離縁
当事者双方の話し合いで離縁をする方法です。離婚でいうところの「協議離婚」と同じようなものだと考えるとよいでしょう。
調停離縁
調停離縁とは、裁判所で調停委員の立ち会いのもと話し合って離縁をする方法です。調停はあくまでも話し合いの場であるため、裁判所や調停委員が決定を下すわけではありません。
参考:『離縁調停 裁判所』
裁判離縁
裁判離縁とは、裁判所が諸般の事情を考慮して離縁を決める方法をいいます。調停においても話し合いがまとまらない場合には、裁判所に離縁の訴えを提起するのが通常の流れです。
ただし、民法814条によれば、裁判所に離縁の訴え提起するための条件として次のいずれかの事情が必要とされています。
1.他の一方から悪意で遺棄されたとき
2.他の一方の生死が三年以上明らかでないとき
3.その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき
裁判を申し立てさえすれば必ず離縁が認められるわけではありません。養親側としては離縁をしたいにもかかわらず婿養子が離縁に応じない場合などには、弁護士へ相談されることをおすすめします。
死後離縁
離縁をするには、市区町村役場に養子離縁の届出をしなければなりません。ただし、養親又は養子が死亡している場合には、市区町村役場への届出の前に裁判所の許可を得る必要があります。その許可を得る手続きが「死後離縁」です。
亡くなった養親と離縁をしたい場合には養子が、亡くなった養子と離縁をしたい場合には養親が手続きをします。
死後離縁は、申し立てをしたからといって必ずしも許可されるものではありません。諸般の事情を考慮の上、裁判所が許可か不許可かを判断します。
なお、死後離縁が認められても相続の権利には影響がありません。たとえば、養親が亡くなってからすぐに婿養子が死後離縁の手続きをおこない許可されたとしても、婿養子がその亡くなった養親から相続を受ける権利は残ります。
死後に死後離縁が認められたとしても、相続が起きた時点(亡くなった時点)で相続人であることには変わりがないためです。
参考:『「死後離縁」の手続とは・・・ 名古屋家庭裁判所 』
他家の婿養子に入った子は実親の相続権もある?
ここまでは、婿養子が妻の両親である養親から受ける相続について解説してきました。最後に、婿養子と実の両親と相続関係について見ていきましょう。
他家の養子に入った婿養子は、もはや実の両親からの相続を受けることはできないのでしょうか。
他家の婿養子になっても実親からの相続権は失われない
実は婿養子などで他家の養子になったからといって、実の両親から相続を受ける権利が失われるわけではありません。他家の養子に入ったことにより、実の両親の子でなくなるわけではないためです。
つまり、婿養子は、実の父・実の母・妻の父(養親)・妻の母(養親)の4人の親から相続を受ける権利があります。
なお、養子であっても実の親が養育できないなどの事情で幼い頃に他家の養子となる「特別養子縁組」の場合には、養親のみが親となり実の親との親子関係は終了します。そのため、特別養子の場合には実の親から相続を受ける権利もありません。
家族信託という選択肢もある
婿養子の相続権について詳しく知りたい際に、認知症による口座の凍結などについても気になるという方は多いのではないでしょうか。認知症になると、法的に意思能力がないものとされる可能性があり、本人名義の不動産の売却や、銀行口座からの出金が凍結によってできなくなることがあります。唯一の対処法である「成年後見制度」も、費用や財政管理の面で戸惑う方が多いようです。
そこで今注目されているのが、大切な財産を信頼できるご家族に託す「家族信託」です。認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することができます。
ファミトラの「家族信託」は家族信託に必要な手続きを、弁護士や司法書士など多様な専門家がサポートし、誰でも簡単に・早く・安く組成できるサービスです。資産管理にお困りの方は、お気軽にお問合せください。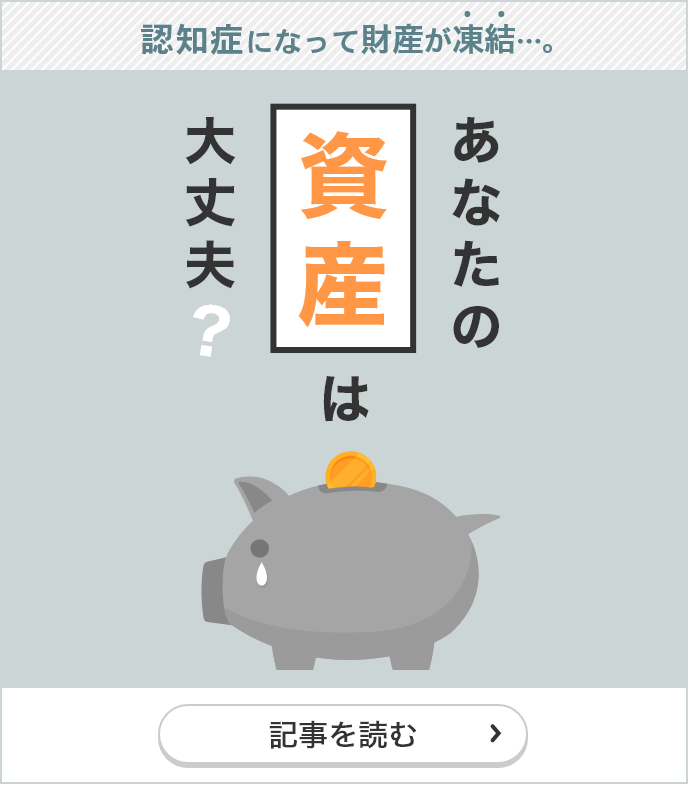
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
「婿養子」は、養親である妻の両親から財産を相続する権利を持ちます。
一方で、養子縁組をしていない単なる「婿」は相続人ではありません。この違いを知り、ご自身やご家族の相続関係を確認しておくとよいでしょう。
そのうえで、婿養子と実子とで相続で渡す金額に差をつけたい場合などには早くから専門家へ相談され、遺言書を作成するなどの対策をしておくことをおすすめします。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


故人が年金受給者の場合は、すぐに年金受給停止の手続きが必要になります。ホゥ。






























