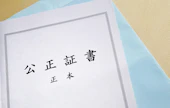最近では、さまざまな事情から事実婚の状態となっている人もめずらしくありません。では、事実婚の場合にパートナーが亡くなった場合、相続はどのようになるのでしょうか。
この記事では、事実婚の場合の相続ルールや、事実婚のパートナーに遺言で財産を渡す場合の注意点などについてくわしく解説します。
<この記事の要点>
・法律上の籍を入れていない事実婚のパートナーに相続権はない
・事実婚のパートナーに財産を渡したい場合、遺言書を作成しておく
・事実婚のパートナーに財産を渡す場合、相続人の遺留分に注意する
こんな人におすすめ
事実婚のパートナーに相続権はあるのかを知りたい方
事実婚のパートナーに相続で財産を渡す方法を知りたい方
事実婚のパートナーに財産を渡す際の注意点を知りたい方
事実婚のパートナーに相続権はあるのか
事実婚とは、法律上の婚姻届を提出しないまま夫婦として生活をしている状態を指します。事実婚を選択している理由はそのカップルごとにさまざまで、法律上なんらかの障壁があり入籍をしたくてもできないケースや、入籍自体にメリットを感じていないケースなど多種多様です。
はじめに、事実婚パートナーの相続権について確認しましょう。
事実婚のパートナーに相続の権利は一切ない
事実婚のパートナーは、相続人に該当しません。つまり、パートナーが亡くなったとしても、事実婚であれば原則として何も相続できないということです。
最近では、市区町村がパートナー証明などを発行しているケースや、遺族年金のように事実婚であっても法律上の配偶者と同様に受給できる公的制度も存在します。
しかし、相続において、法律上の籍を入れていない以上は、いくら長年同じ家で暮らし互いに生活を支え合ってきたとしても、相続のルールで言うところの「配偶者」には該当せず、相続人にもならないこととなっています。
事実婚のパートナーが特別縁故者となるケースはある
事実婚のパートナーは相続人ではありません。しかし、特別縁故者に該当する場合は多いでしょう。
特別縁故者とは、被相続人と特別の縁故のあった者のことです。家庭裁判所が特別縁故者に該当すると認めることで、遺産の一部が付与されます。
ただし、相続において特別縁故者が登場する場面は、非常に限られていますので、特別縁故者の制度があるからと言って何ら対策をしないのはおすすめできません。
特別縁故者が登場するのは相続人が誰もいない場合のみ
相続において特別縁故者が遺産の分与を受けられるのは、被相続人に法定相続人が1人もいない場合のみです。法定相続人が1人でもいれば、事実婚のパートナーが遺産の分与を受ける余地はありません。
なお、被相続人と長年会っていない場合や仲違いをしている場合、所在がわからない場合などであってもそれのみをもってただちに相続人から除外されるわけではありませんので、注意しましょう。
法定相続人となるのは、次の人です。
【配偶者相続人】
籍の入った配偶者のことです。仮に離婚協議中であっても相続人です。
【第一順位の相続人】
被相続人の子。子が被相続人の死亡以前に亡くなったことなどにより相続権を失った場合には、その子の子である被相続人の孫。子も孫も相続権を失っていれば、ひ孫。
【第二順位の相続人】
被相続人の親。親がいずれも被相続人の死亡以前に亡くなっていて祖父母のうち存命の人がいれば、その存命の祖父母。
【第三順位の相続人】
被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に亡くなったことなどにより相続権を失った場合には、その兄弟姉妹の子である被相続人の甥や姪。なお、甥や姪の子は相続人とはなりません。
第一順位の相続人が1人でもいれば、第二順位と第三順位の人は相続人とはなりません。同様に、第一順位の人がいなくても第二順位の人が1人でもいれば、第三順位の人は相続人ではありません。また、配偶者相続人は別枠扱いで、配偶者相続人と第一順位から第三順位の相続人がいれば、どちらも相続人となります。
これらに当てはまらない人は相続人とはなりません。例えば、叔父や叔母、いとこなどが相続人となることはないということです。
特別縁故者が遺産の分与を受けられる可能性があるのは、これらの法定相続人が誰もいない場合に限定されます。特別縁故者が登場するのはかなり限られた場面であることを知っておきましょう。
事実婚のパートナーに相続で財産を渡すには
事実婚のパートナーは相続人ではないため、何も対策をしなければ原則として財産を渡すことはできません。ここでは、事実婚のパートナーに財産を渡す方法を解説します。
なお、これらはどれか1つを選択すべきということではなく、組み合わせて活用することも可能です。
遺言書を作成する
1つ目の方法は、遺言書を作成することです。遺言書で財産を渡す相手には特に制限はなく、事実婚のパートナーなど相続人ではない人に財産を渡すことも可能です。
事実婚のパートナーに財産を渡す内容の遺言書を作成する際の注意点は、後ほど詳しく解説します。
生前贈与をする
もう1つの方法は、相続を待たずに生前に贈与することです。生前贈与はお互いに「あげます」「もらいます」の意思表示が合致すれば成立します。また、生前贈与ができる相手に制限もありません。
ただし、生前贈与は贈与税の対象となる点に注意が必要です。贈与税は一般的に相続税よりも高く、高価な財産を生前贈与した場合には驚くような額の贈与税がかかる可能性があります。
また、事実婚のパートナーの場合には、籍の入った配偶者とは異なり贈与税が安くなる「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」などの特例なども使用できません。
そのため、生前贈与をする際には事前に税理士などへ税額を確認してからおこなった方がよいでしょう。
生命保険を活用する
事実婚のパートナーに財産を渡す方法としては、生命保険の活用も検討できます。
ご自身を被保険者としてご自身が保険料を支払うことで生命保険に加入し、その生命保険契約の受取人を事実婚のパートナーとしておくことで、ご自身が亡くなった際にパートナーが保険金を受け取ることが可能です。
ただし、生命保険の受取人として指定ができる相手には一定の制限があることが一般的で、なかには事実婚のパートナーを受取人に指定ができない場合や、指定ができる場合であっても保険金額に上限を設けている場合もあります。そのため、契約する保険を選択する際には、事実婚のパートナーを受取人として指定できるかどうかに注意しましょう。
事実婚のパートナーに遺言で財産を渡す場合の注意点
事実婚のパートナーに遺言で財産を渡す場合には、次の点に注意しましょう。
「相続」ではなく「遺贈」になる
事実婚のパートナーに財産を渡す場合の遺言の書き方は、「相続させる」ではなく「遺贈する」です。
遺言書で財産を渡すための書き方には、主に「相続させる」と「遺贈する」の2つのパターンがありますが、このうち「相続」は、相続人に対してしか行うことができません。一方で、遺贈は誰に対してであっても行うことが可能です。
公正証書遺言で作成する
事実婚のパートナーに財産を渡す内容の遺言は、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言で作成しましょう。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人と2名の証人の立会いのもとで作成する遺言書です。費用や手間がかかりますが、無効となる可能性がかなり低く、より確実な遺言方法と言えます。
一方、自筆証書遺言とは、全文を遺言者が自筆する形式の遺言書です。自分ひとりで作成することができるため手軽であるうえ費用もかからない点がメリットであるものの無効になってしまったり書き方があいまいで手続きができなかったりといった問題が生じやすい点に不安が残ります。
事実婚のパートナーは、仮に遺言書が無効となってしまえば財産を一切受け取ることはできません。そのため、より確実である公正証書で作成しておくと安心です。
遺言執行者を定めておく
亡くなった後で遺言書の内容を実現する際に、遺贈の場合には次のいずれかの人の協力が必要です。
・相続人全員
・遺言執行者
遺言執行者がいなければ相続人全員の協力が必要となりますが、相続人の中に事実婚のパートナーへの遺贈を快く思っていないなどで非協力的な方がいた場合には、手続きが停滞してしまいます。また、そうでなくとも手続きのたびに相続人全員の協力が必要となれば、非常に煩雑となるでしょう。
そのため、事実婚のパートナーに財産を渡す内容の遺言書を作成する際には、その遺言書の中で遺言執行者を指定しておくとスムーズです。遺言執行者は専門家へ依頼することもできますが、事実婚のパートナー自身など財産を渡す相手を指定することもできます。
なお、遺言書に遺言執行者の指定がないものの相続人全員の協力を得ることが難しそうな場合には、相続が起きてから家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうことも可能です。
遺留分に注意する
事実婚のパートナーに財産の大半を渡す内容の遺言書を作成する際には、相続人の遺留分に注意しましょう。遺留分とは、配偶者相続人と第一順位の相続人、第二順位の相続人に保証されている相続での最低限の取り分のことです。
遺留分を侵害した内容の遺言書を作成することもできますし、遺留分を侵害したからといって遺言書が無効になるわけではありません。しかし、相続が起きてから遺留分を侵害された相続人から事実婚のパートナーに対して、遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。
遺留分侵害額請求とは、侵害した遺留分相当の金銭を支払って欲しい旨の請求です。この請求がなされると、侵害した遺留分相当の金銭を実際に支払わなければなりません。
仮に遺産の大半が自宅不動産など簡単に売却できないようなものである場合には、遺留分を支払う金銭が用意できず事実婚のパートナーが大変な思いをする可能性があります。
そのため、遺言書を作成する際には、まず遺留分のある相続人の有無を確認しておきましょう。遺留分のある相続人がいる場合には、その相続人に遺留分相当額は渡す内容で遺言書を作成したり、仮に遺留分侵害額請求をされた場合でも事実婚のパートナーが遺留分相当額を支払えるように資金を準備しておいたりといった対応が必要です。
相続税が高くなる
相続税には、一定の人以外が支払うべき相続税が2割増しになるルールがあります。2割増しにならない人は、次のとおりです。
・被相続人の一親等の血族
・代襲相続人となった被相続人の孫
・被相続人の配偶者
事実婚のパートナーはこれらに該当しないため、相続税の2割加算の対象となります。
なお、遺産総額が次の式で算定する相続税の基礎控除額以下であれば相続税自体がかからないため、2割加算がされることもありません。
相続税の基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数
参考:『No.4157 相続税額の2割加算 国税庁』
登録免許税が高くなる
遺産に不動産がある場合には、その不動産の名義を変えるに当たって登録免許税を支払わなければなりません。この登録免許税は財産を受け取る人が相続人か否かによって異なり、事実婚のパートナーなど相続人ではない人が不動産を受け取る場合には、登録免許税が高く設定されています。
相続や遺贈により不動産を名義変更する際の登録免許税は、次のとおりです。
・相続や相続人に対する遺贈:固定資産税評価額の1,000分の4
・相続人以外に対する遺贈:固定資産税評価額の1,000分の20
登録免許税の計算のベースとなる固定資産税課税評価額は、毎年4月から6月頃に不動産の所在する市区町村役場から送付される固定資産税の納付書に同封の不動産の一覧表で確認することが可能です。評価額が高額である場合には登録免許税も高くなる可能性があるため、一度試算をしてみるとよいでしょう。
参考:『No.7191 登録免許税の税額表 国税庁』
事実婚のパートナーがいる場合の3つの相続対策
事実婚のパートナーがいる場合には、次の3つの対策をセットで行っておくと安心です。
1.遺言書を作成する
1つは、先にもお伝えしたとおり、遺言書を作成しておくことです。遺言書がなければ、亡くなった後で内縁のパートナーに財産を渡すことはできません。そのため、ご自身の亡き後にパートナーの生活を守るためには、遺言書の作成は必須と言えるでしょう。
遺言書というと年配の方のみがつくるものであるというイメージを持っている方もいますが、内縁関係の場合には若いうちから作成しておくと安心です。
2.任意後見契約を締結する
任意後見契約とは、将来認知症などにより判断能力が衰えた場合に備え、信頼できる相手と結んでおく財産管理の契約です。
認知症になってしまえば、自分の銀行口座であってもお金を引き出すことが困難となります。また、入院や施設へ入所をする際の契約を代理するにも、事実婚のパートナーでは応じてもらえないケースも多いでしょう。こうした事態に備え、判断能力が衰えた場合の預金の引き出しや入院、入所の契約などを代わりに行ってもらうための契約を、あらかじめ結んでおくのが任意後見契約です。
戸籍謄本などで関係性が証明できない事実婚の場合は様々な手続きで不都合が生じることも少なくないため、任意後見契約は必須と言えるでしょう。
3.死後事務委任契約を締結する
死後事務委任契約とは、死後に生じる次のような事務を委任する契約のことです。
・家族・友人への連絡
・葬儀や埋葬の手続き
・役所や関係機関への届出
・生前の医療費や施設利用費など未払分の精算
・遺品整理
・各種サービスの解約
事実婚の場合には、死後事務委任契約も締結しておくと安心です。こちらも戸籍謄本などで関係性が証明できない事実婚の場合、亡くなった後に生じる事務の執り行いにあたって不都合が生じるためです。
参考:『死後事務について 第二東京弁護士会』
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
事実婚のパートナーは、たとえ籍の入った配偶者と同じように長年夫婦としての生活を送っていたとしても、残念ながら相続の権利は一切ありません。そのため、亡くなった後で内縁のパートナーに財産を渡すためには、遺言書の作成が必須と言えます。
また、いざという時の手続きをスムーズに進めるために、任意後見契約や死後事務委任契約も締結しておくと安心です。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


自身が亡くなったときのために、エンディングノートを書いておくのもおすすめです。ホゥ。