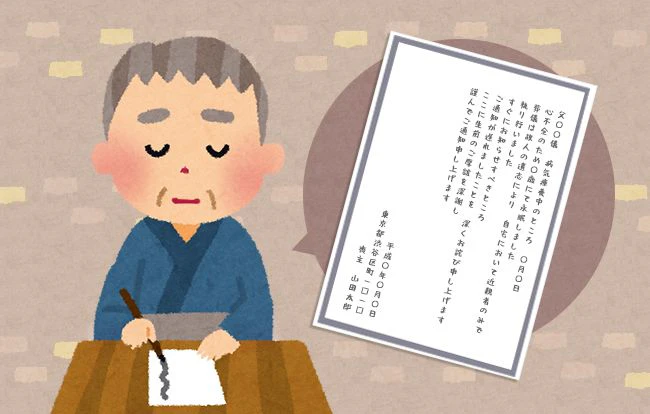故人が亡くなってからは速やかに死亡届を市役所へ届け出る必要があります。そこで、葬儀の準備の忙しさから、「葬儀社に死亡届を代わりに提出してもらうことはできるのだろうか」と考える方もいるのではないでしょうか。
この記事では、死亡届に記入する届出人は親戚以外の他人が代筆してもよいのか、死亡届の提出を他人がしてもよいのか、などについて解説します。
<この記事の要点>
・死亡届は故人の親族だけでなく、他人でも提出可能
・死亡届は、故人の本拠地か所在地、または死亡した地の市役所の戸籍係へ届け出る
・国内で亡くなった場合は、死亡を知った日から7日以内に死亡届を管轄の市役所に提出する
こんな人におすすめ
死亡届とは何かを知りたい方
死亡届の届出人はどの範囲までの人なのかを知りたい方
死亡届の書き方を知りたい方
死亡届とは
人が亡くなった際には、市役所へ「死亡診断書・死体検案書」と「死亡届」を一緒に届け出ましょう。故人の本拠地か所在地、または死亡した地の市役所の戸籍係へ届け出ます。死亡届を届け出ることで、住民票の登録が抹消され、戸籍上でも死亡した扱いになります。
死亡届を届け出ても、すぐに死亡の旨が戸籍に反映されるわけではありません。本拠地から遠い市役所に届け出ると、手続きに1週間ほどかかる場合もあります。
死亡届は基本的に、医師や警察医から作成される死亡診断書や、死体検案書という書類と一体化しています。書類の片側が死亡診断書・死体検案書で、反対側が死亡届です。
死亡届はどこでもらうのか
通常は死亡診断書・死体検案書の作成と同時に手元にくる死亡届ですが、ごくまれに死亡診断書・死体検案書のみ作成されることがあります。例えば、自宅や施設などで死亡し、医者が訪問してその場で死亡診断書を作成した場合です。
死亡診断書・死体検案書しか作成されなかった場合は、病院の受付や市役所・区役所で死亡届をもらうことができます。もしくは、インターネット上でダウンロードすることも可能です。
死亡診断書・死体検案書は医師が書き記すものなので、何も書き込んではいけません。届出人(遺族)が記入できるのは死亡届だけなので、注意しましょう。
死亡届はいつまでに出すのか
死亡届は、国内で亡くなった場合は、死亡を知った日から7日以内に管轄の市役所へ届け出ましょう。死亡を知った日を1日目と数えるので、例えば2月10日に死亡を知った場合は、2月16日までに届け出さなければいけません。
国外で死亡した場合は、提出期限が3ヵ月以内になります。なぜなら、死亡届と一緒に届け出る死亡診断書・死体検案書は、死亡した国で作成されたものが必要となるからです。さらに、和訳したものを届け出なければいけないため、手続きや作成に時間がかかります。
国内・国外の場合とも届け出の期限を過ぎると、5万円以下の罰金が発生するおそれがあるので注意しましょう。また、故人が亡くなってから24時間以内は、死亡診断書・死亡届は届け出ることができません。
<関連記事>
死亡届は誰がいつまでに提出する?手続きについてケース別に解説
死亡届はなぜ出す必要があるのか
死亡届を出さないと火葬・埋葬の許可が下りません。つまり、死亡届を管轄の市役所へ届け出ていないということは、正しく埋葬をしていないということです。
また、死亡届を届け出ずにいると、戸籍上はまだ生きていることになります。つまり、故人の年金を受け取ることになってしまうので、不正受給となり犯罪に当たります。死亡届を届け出ないということは、犯罪行為に繋がってしまうので注意しましょう。
死亡届と一体の死亡診断書・死体検案書とは
死亡診断書・死体検案書は、医師のみが発行・記入できる書類です。故人の死因や亡くなった時間、医師のサインなどが書き込まれています。
事件性がない場合に、病院などで医師が作成するのが死亡診断書です。一方で、事件性があると判断され、警察が介入したときは死体検案書が作成されます。
死亡診断書・死体検案書は名前が異なりますが、同じものです。医師が作成するか、警察医が作成するかの違いしかありません。そのため、表題は「死亡診断書(死体検案書)」となっているケースがほとんどです。
そして、この死亡診断書・死体検案書は、一般的に死亡届と一体となっています。死亡診断書・死体検案書のもう半分が死亡届です。死亡届は届出人(主に遺族)が必要事項を書き込みます。しかし、死亡診断書・死体検案書の方は医師以外が書き込んではいけません。
死亡診断書・死体検案書にあとから不備が見つかっても、遺族や市役所の方で勝手に訂正することは禁止されています。訂正は作成した医師のみしかできません。死亡診断書・死体検案書を医師から渡されたときは、まずは記入漏れや名前の間違い、主治医師のサイン漏れがないかなどを必ず確認しましょう。
<関連記事>
死亡診断書と検案書の違いは?コピー忘れは再発行できる?
小さなお葬式で葬儀場をさがす
死亡届の書き方
死亡届の書き方は、書式通りに記入していけば問題ありません。まず死亡届に「提出日」、そして故人の「氏名・生年月日(和暦)・死亡時刻と死亡場所・住所・世帯主の名前・本籍地」を書き込んでいきます。世帯の主な仕事・故人の職業(産業)の欄は、わかる場合だけで構いません。
死亡時刻は午後・午前で書きましょう。例えば、昼12時に亡くなった場合は午後0時、夜12時の場合は午前0時と表記します。昼13時は午後1時と書くようにしましょう。死亡診断書・死体検案書にならって書けば問題ありません。
「その他」の欄は基本的に書く必要はないので、空白で構いません。あとは、届出人の情報を書き込んでいきます。書き方がわからないときは、葬儀社スタッフや市役所に聞いて記入しましょう。間違えたときは二重線で消して、届出人の印鑑で訂正印を押します。
死亡届の届出人はどの範囲までの人?
届出人として死亡届に記入できるのは以下の人です。
・故人の配偶者
・故人の6親等内の親戚
・3親等内の姻族関係者
・家主(家屋管理人)・地主(土地管理人)など
・生前に財産管理を任されていた、後見人・保佐人・補助人など
後見人が届出人となる場合には「登記事項証明書」と「審判書謄本とその確定証明書」が必要です。
<関連記事>
死亡届の届出人になれる順位はある?手続き期限や提出先も解説
小さなお葬式で葬儀場をさがす
親族の届出人がいないケースはどうする?
集合住宅の大家や死亡した土地の地主といった親族以外でも届出人となり、死亡届に記入することができます。どうしても届出人が誰もいないケースは、病院長や老人ホームなどの施設長といった人物が届出人として死亡届を出すこともあるでしょう。
その際に気をつけておきたいのが、行政書士法に反するため、葬儀社は届出人として死亡届を書くことができないという点です。
死亡届は他人が出してもよいのか
死亡届の届出人は6親等内の親族や3親等内の姻族関係者などが基本でした。しかし、ここでいう「届出人」とは、市役所に死亡届を届ける人のことではありません。死亡届に記入する人を届出人と呼びます。
そのため、届出人が記入した死亡届を、他人である葬儀社スタッフが代行して市役所に届け出るのは問題ありません。葬儀社スタッフが代行して、死亡届と死亡診断書・死体検案書を市役所に届け出る際には、届出人の印鑑も預ける必要があります。その理由は、万が一死亡届に不備があって訂正しなくてはいけなくなった場合に、訂正印として必要だからです。よくある間違いが、死亡時刻の書き方なので記入する際は気をつけましょう。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
死亡診断書(死亡届)を再発行するには
死亡診断書・死体検案書と死亡届は、市役所に届け出ると二度と返却してもらえません。そのため、届け出る前に10枚ほどコピーしておく必要があります。しかし、うっかりコピーを忘れていたり、届け出る前に紛失してしまったりした場合は再発行できるのでしょうか。
担当医や警察医に依頼する
まず、死亡診断書・死体検案書は担当医や警察医に依頼すれば再発行してもらうことができます。しかし、再発行するためには書類がいくつか必要です。病院によって必要な書類が違う可能性があります。
主に必要となるのは「再発行する人の身分証明証」「戸籍謄本などの故人との関係が証明できる書類」などですが、再発行を申請する前に電話で確認するようにしましょう。
死亡届の記載事項証明書
また、遺族年金や郵便局の簡易保険の死亡保険金の手続きには、「死亡届の記載事項証明書」という、死亡届の写しが必要になります。こちらは死亡届のコピーではなく、記載事項証明書という書類を市役所で発行してもらわないといけません。しかし、気軽に発行できるものではなく、記載事項証明書を発行してもらうには上記の理由で必要だということを証明する必要があります。
死亡届の記載事項証明書のコピーは、銀行口座の手続きやその他保険、名義変更などさまざまな手続きに使用することができます。ただし、記載事項証明書を発行する権利がなければ、医師から死亡診断書を再発行してもらうしか方法はありません。
また、再発行には料金がかかります。金額は数千円であることがほとんどですが、病院によって異なるので、必要書類を確認する際に一緒に聞いておきましょう。
死亡届は会社や学校の忌引証明に使える?
会社や学校を忌引で休む際は、証明する書類が必要になることが一般的でしょう。証明書類として使えるのは、下記の書類のコピーです。
・死亡診断書・死体検案書
・死亡届
・火葬許可証
・埋葬許可証
・葬儀証明書
・会葬御礼
葬儀証明書は葬儀社で作成してもらえます。死亡診断書(死亡届)などのコピーを会社や学校へ提出するのは気が引けるという場合には、葬儀証明書を作成してもらうとよいでしょう。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
死亡届を記入する届出人は、6親等内の親族か3親等内の姻族関係者が基本でした。親族がいない場合は、大家や病院長が記入することもできます。また、葬儀社などの他人が届出人の代理として、届出人によって記入された死亡届を役所の戸籍係に届け出るのは問題ありません。
故人の死亡後の手続きなどは、ご不明な点が多く出てくることでしょう。小さなお葬式では、ご遺族に寄り添い、24時間365日いつでも専門スタッフが電話でお答えしております。小さな疑問でも遠慮なくご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



葬儀費用は「葬儀一式費用・飲食接待費用・宗教者手配費用」で構成されます。ホゥ。