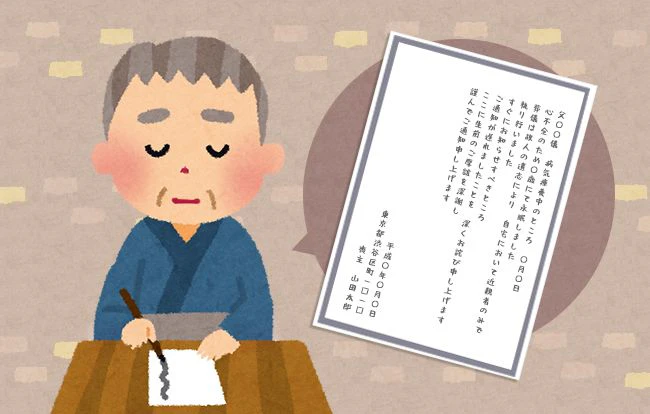ペットと共に暮らす人は、ペットのことをとても大切に扱っています。家族同然の付き合いをしていることも珍しくなく、それゆえに失ったときの悲しみは計り知れません。
この悲しみは短期間で癒されることもありますが、ペットロスと呼ばれる状態に陥ると長く続いてしまうことがあります。
ペットロスを瞬時に回復させる方法はなく、時間をかけてケアしていくしかありません。立ち直るためには本人の意思はもちろん、周囲の人の対応も重要になってくるため、この機会にペットロスについて覚えておきましょう。
<この記事の要点>
・ペットロスの症状には、感情が不安定になる・無気力・食欲不振・幻覚症状などがある
・回復には拒否・怒り・交渉・抑うつ・受容の5段階の悲嘆のプロセスを理解することが重要
・対処法としては、思い切り泣くことやペットへの手紙を書くことが推奨されている
こんな人におすすめ
高齢のペットがいる方
ペットを亡くされた方
ペットロスの症状やプロセスを知りたい方
ペットロスの症状
ペットロスに陥った場合、深い悲しみを受けた結果、日常生活に支障をきたしてしまいます。
例えば以下のような症状が現れるとされています。
・感情が不安定で突然泣いてしまう
・無気力やめまい
・食欲不振や過食
・幻覚症状や妄想をよくする
この他にも通常風邪と思われるような頭痛や発熱などの体調不良も、ペットロスによって起こる場合もあります。「うつ」や「自殺衝動」といった精神的な症状にまで発展すると、極めて危険な状態だといえます。
こうした症状から良い状態に戻していくためにも、まずは次項で紹介する悲嘆のプロセスを理解しましょう。
悲嘆のプロセス
ペットロスを感じてから回復するまでは、一定のプロセスがあるとされています。当事者や周囲の人がこのプロセスを理解しているか否かで、ペットロスからの立ち直りの早さは大きく変わります。
このプロセスにはいくつか説がありますが、ここではもっとも有名なエリザベス・キューブラー=ロスが提唱した「キューブラー=ロスモデル」をご紹介します。

1.拒否
プロセスの第1段階では、ペットが死んだという事実を受け入れないという拒否反応を起こします。あらゆる理由を自分の中で作り上げ、頑なに死を受け入れません。
↓
2.怒り
第2段階では、怒りを覚えます。この怒りの矛先は、他人であったり自分であったりと様々です。獣医の処置に対して怒りを覚えることもあれば、自分自身の管理不足に対して怒りを覚えることもあります。苦しみに対しての漠然とした怒りであるため、その都度対象が変わることもあります。
↓
3.交渉
第3段階では、人ではない何かにすがるようになります。いわゆる神頼みの状態です。「自身の命・寿命と引き換えにペットを生き返らせてほしい」といった願いが多く、そのため交渉と呼ばれています。
↓
4.抑うつ
第4段階は抑うつで、全てに対して無気力な状態になります。3段階目までの行動が無意味であったことも、抑うつ状態に拍車をかけます。抑うつ状態がひどくなると、うつ病の危険性もあります。
↓
5.受容
抑うつの状態を克服すると、最終段階である受容に至ります。受容の段階ではペットの死を正しく受け止めることができ、うつ状態から解放されます。これまで忘れていたポジティブな感情も徐々に思い出し、正常な生活ができるようになります。もちろん悲しみが全く消えるわけではありませんが、それも含めてひとつの思い出として昇華されます。
前述のように、キューブラー=ロスモデル以外にも様々な説があります。これらに共通しているのは、拒否反応から精神的な苦痛を経て回復へ向かうということです。最後には回復へと向かうことをわかっていれば、当人および周囲の人のペットロスでの負担は大きく軽減されます。
ペットロスの対処法
ペットロスへの対処法は、当人が行うべきこともあれば周囲の人が気をつけるべきこともあります。できる限り早く立ち直るためには、これらの対処法を実践しましょう。
当事者が実践すべきこと
思い切り泣く
子供の場合は悲しみによって涙を流すことも多いですが、大人になると簡単には泣けなくなります。特に成人男性の場合は我慢してしまう傾向が強いです。
しかし、素直に泣くことで気持ちをリセットできることもあるため、ペットロスの疑いがある場合は思い切り泣くことが大切です。
ペットへの手紙
ペットロスに陥った場合、自分が具体的に何に悲しんでいるのかがわからなくなることもあります。その原因を整理することで、気持ちも同時に整理することができます。
そのためにはペットへの手紙を書いてみるのがいいでしょう。論理的に整理ができない場合でも、手紙という形であれば自分の想いを吐き出すことができるため、自然と気持ちの整理がつきます。
周囲の人が気をつけるべきこと
言葉のかけ方
まず、他人と比較するような言葉はNGです。「ペットを飼っている人はみんな通る道」「私も悲しい」などが当てはまります。ペットを失った悲しみはその人だけのものであるため、たとえ同じ経験をした人がいても感情は唯一無二のものなのです。
「止まない雨はない」など、常套句での慰めも意味はないでしょう。よくあることだと言っているようなものなので、逆効果になります。
こういった言葉をかけるよりは、当人とペットとの思い出話をしたり、黙って話を聞いてあげたりするほうが効果的です。
悲しみを表現させることを促す
楽しいことに意識を向けさせるというのは、悲しみを忘れさせる常套手段です。しかし、ペットロスのように重度の悲しみを抱えている場合は、楽しみを感じることができず、逆に立ち直る邪魔になってしまうことも。
前項で泣くことを推奨したように、悲しみは素直に表現するほうが良い効果をもたらします。紛らわせるのではなく、表現することを促しましょう。
ペットロスの専門機関
ペットロスは時間をかけてケアすることで、十分に回復することができます。しかし、中には悲しみが深く、こじれてしまったためにうまく解消できないという場合もあります。そういった場合には、ペットロスの専門機関に相談してみるといいでしょう。
ペットロスの専門機関としては、日本ペットロス協会というものがあります。日本ペットロス協会では、ペットロスカウンセラーの育成を行ったり、ペットロスに関するセミナーを開催したりしています。その活動の一環で、ペットロス110番という電話相談を行っています。
ペットロスから立ち直れないという場合には、こういった相談を利用してみるのもいいでしょう。
焦らず協力して乗り越えよう
ペットを失う悲しみは大きく、当人にしかわからないものです。いつまでも悲しんでいるわけにはいかないものの、悲しみから立ち直れないこともあります。
ペットロスから回復するためには、当人だけでなく周囲の人の協力が必要不可欠なのです。決して焦らずプロセスを理解しながらサポートしましょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
葬儀に関するご準備は事前に行うことが大切です。いざという時困らないように、葬儀全般に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



お通夜とは、家族や友人たちが集まり、故人と最後の夜を過ごす儀式のことです。ホゥ。