仏教では命日を迎えるごとに法要を行い、故人の冥福をお祈りします。「一周忌」は文字通り死後1年が経った年の命日に行われる法要です。しかし、その後の法要では「三回忌」「七回忌」「十三回忌」と呼ばれ、「一回忌」「二回忌」という言葉を耳にしないことに気がつくのではないでしょうか。
そこでこの記事では、仏教に伝わる法要の習わしから年忌法要の数え方を解説します。年忌法要は亡くなってからの年数や供養までの目安になります。「一回忌」「二回忌」をきちんとカウントすることで、その後の法要も習わしどおりに進めることができるでしょう。
<この記事の要点>
・年忌法要とは、毎年巡ってくる命日に合わせて行う法要のこと
・年忌法要は亡くなった年から数え、1年目に一周忌、2年目に三回忌、と年数に応じて行う
・一回忌は亡くなった命日を意味し、二回忌は「一周忌」を指す
こんな人におすすめ
一回忌と一周忌の違いを知りたい方
なぜ二回忌がないのかを知りたい方
年忌法要の数え方を知りたい方
年忌法要とは?
年忌法要は、命日に故人のことを思って追悼する仏教ならではの儀式です。しかし、インドから中国へと仏教が広まった1500年前は、故人に対して特別な儀式はありませんでした。
その頃あたりから芽生えた忠誠心や親孝行のような道徳的な思想が仏教と混じることで、故人を追悼する年忌法要が誕生したといわれています。当時の年忌法要は現在とは異なり、亡くなってから49日で生まれ変わるという仏教の教えを元に、短期間で全ての法要が終えるように設定されていました。
しかし、奈良時代には1年以内、平安時代には3年程と徐々に期間が長くなり、鎌倉時代から室町時代には三十三回忌で永代供養して一連の法要を締めたとされています。このように毎年巡ってくる命日に合わせて行う法要のことを「年忌法要」と呼ぶようになりました。
年忌法要の数え方
年忌法要は、亡くなった年も数えることから数字に惑わされやすいのが特徴です。「○周忌」は何周年と同じように「亡くなってからの年数」を数えます。それに対して、「○回忌」は「法事の回数」を数えます。
年忌法要と回忌の関係は以下の表のとおりです。
| 回忌 | 年忌法要 | |
| 1年目の命日 | 二回忌 | 一周忌 |
| 2年目の命日 | 三回忌 | 二周忌 |
| 3年目の命日 | 四回忌 | 三周忌 |
| 4年目の命日 | 五回忌 | 四周忌 |
三十七回忌までは三と七を重ねた奇数年に行われます。一回忌を耳にしないのは、一回忌は亡くなった命日を指すとともに、葬儀を1回と数えるためです。
一回忌とは?
年忌法要の中で、「一回忌」と称される法要を耳にする機会はほとんどありません。理由は、一回忌は故人が亡くなった命日を意味し、亡くなった後の葬儀を1回目の法事とするためです。2回目の法要は1周年の経過を数えるため「一周忌」と呼び、混乱される方も少なくありません。年忌法要は、亡くなった年の葬儀も含まれることを覚えておきましょう。
二回忌とは?
一回忌と同じく「二回忌」も耳にする機会がほとんどありません。中には、亡くなった日から2年後に実施される法要を二回忌と勘違いする方もいるでしょう。2回目の法要は亡くなってから1年経ったということから「一周忌」といいます。忌日の数え方として「二回忌」ではありますが、年忌法要では「一周忌」にあたります。
一周忌の流れ
亡くなってから1年後に実施されるため「一回忌」と間違えられることの多い一周忌は、喪明けにもあたることから葬儀の次に大切な法事です。あらかじめ流れを理解しておくと、スムーズに進行することができるでしょう。ここからは、一周忌の流れについて解説します。
1. 出席者、僧侶の入場
出席者が全員着座し終わったら、僧侶が入場します。僧侶の席は仏壇の正面で、その真後ろに喪主が座り、故人との関係が深かった順番に座るのが通例です。喪主は、僧侶を席まで案内するとよいでしょう。
2.喪主の挨拶
出席者全員が着座したら、喪主が挨拶を行います。それほど長く話す必要はありません。出席いただいたことに対する感謝や、読経をしていただく僧侶に向かって感謝を述べるのが一般的です。
3.読経
喪主による挨拶が終わったら、僧侶が読経を始めます。手元に数珠を持ちながら静聴しましょう。
4.焼香
焼香を促されたら、喪主から順番に焼香をあげます。基本的には、故人との関係が深い順番で行いますが、多くの場合、席順になっているので迷うことはあまりないでしょう。
作法は地域や宗派によって異なります。不明点が生じた場合は直前の方の作法を真似すればよいでしょう。
5.法話
焼香をあげ終えると、僧侶による法話が実施されます。故人のためにお話しされるので静聴するのがマナーです。
6.僧侶の退場
法話が終わると、僧侶が退場します。まだお布施等を渡していないのであれば、このタイミングで渡すとよいでしょう。会食の場が設けられている場合は、僧侶は退場せずにそのまま会食の会場へと向かいます。
一周忌に向けて備えるもの
一周忌は、年忌法要の中でも特に重要とされているため、必然的に規模が大きくなることが一般的です。準備することが多くなるので、段取りよく進めていきましょう。ここからは一周忌に向けて準備するものについて解説します。
僧侶を手配する
僧侶の手配はできるだけ早めに行うことが重要です。僧侶も一年中予定が空いているわけではないので、直前になって手配すると予定が合わない可能性があります。会場の予約を確定する前に、僧侶の予定を確認してから進めるとタイミングよく進められます。
お寺とお付き合いのある方
菩提寺(ぼだいじ)とは、先祖代々のお墓のあるお寺のことです。菩提寺がある場合には、菩提寺に連絡をして、読経の依頼を行いましょう。
お寺とお付き合いが無い方
菩提寺が無い場合には、知人縁故からお寺を紹介してもらう方法や、葬儀の際にお世話になったお寺に相談する方法があります。
その他最近では、インターネット上でお坊さん手配サービスを利用される方も増えています。
自宅はもちろん、手配したお坊さんのお寺での法要も行えるので、菩提寺がない方には便利です。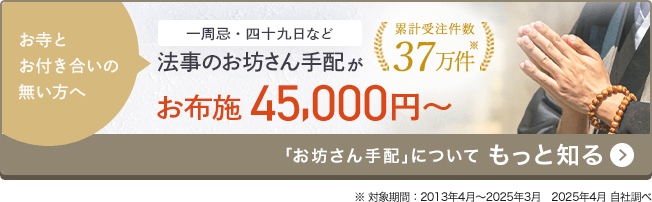
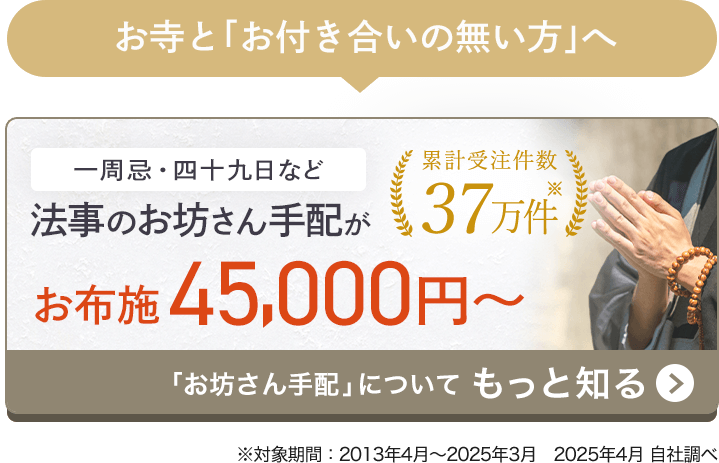
お寺の都合によっては希望日に添えない場合もあるため、1ヵ月~2週間前を目安に寺院手配の予約をすることをお勧めします。
招待する方に案内状を出す
招待する方を決めたら、すぐに案内状を出しましょう。身内だけで行うのであれば電話で伝えても問題ありませんが、身内以外の関係者も招待する場合は一斉に案内状を出すのがおすすめです。案内状は、伝え忘れがない上に出席者の数を正確に把握できるので、準備がしやすくなります。
飲食物の手配をする
法要の後に会食の場を設ける場合は、飲食物の手配を行います。故人を偲ぶ場なので、大量の料理を手配する必要はありません。しかし、人数が多くなるほど直前での手配は難しくなるので、人数や時間帯なども考慮して手配しましょう。
香典返しを準備する
出席者は香典を持参されるので、感謝の品物を用意します。お茶やお菓子といった消耗品、あるいはタオルや洗剤といった生活必需品を選ぶのが一般的です。
お布施を準備する
僧侶に読経していただくので、お布施を用意します。また、会場がお寺以外の場合は、交通費としてお車代、会食に参加されないのであればお食事代として御膳料を渡しましょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
年忌法要は、毎年の故人の命日に合わせて行われます。一回忌は亡くなった命日を指し、二回忌は「一周忌」を指します。葬儀を1回目の回忌法要と数えることで、2回目の回忌法要が「一周忌」にあたることが理解できるでしょう。数え方が理解できると、三回忌以降も忌日に故人を偲ぶ法事・法要をスムーズに行えます。
小さなお葬式では葬儀の手配だけでなく、法事・法要が初めての方でも安心していただけるよう葬儀の後もサポートいたします。不安に思っていることや疑問がありましたら、お気軽にお問合せください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


忌引き休暇は、実は労働基準法で定められた休暇ではありません。ホゥ。
































