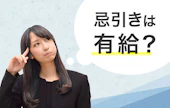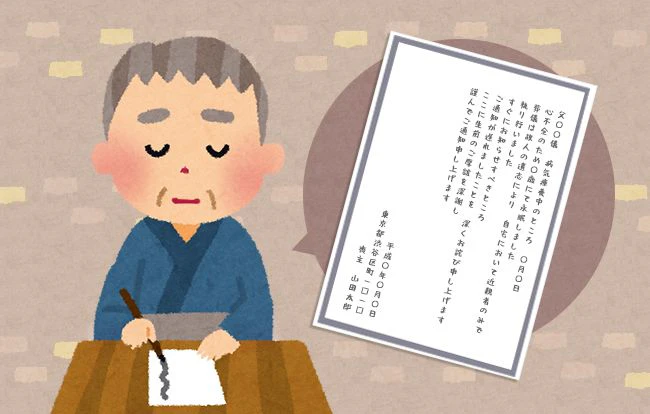「妻の出産予定日に合わせて、数日間仕事を休んで寄り添いたい」「急に身内に不幸があり、遠方の実家に帰らなければいけなくなった」という状況は誰にでも起こりうることです。このような場合は、休暇を取得する必要があるでしょう。
一口に「休暇」といっても、企業にはさまざまな種類の休暇があります。その中でも、お祝い事(慶事)やお悔やみ事(弔事)の際に取得できる休暇が「慶弔休暇(けいちょうきゅうか)」です。
この記事では、慶弔休暇の特徴について詳しく解説します。
<この記事の要点>
・慶弔休暇は慶事や弔事の際に取得できる休暇のことで、「法定外休暇」にあたる
・慶弔休暇が有給休暇となるかは就業規則による
・3親等以上の場合は慶弔休暇が認められないこともある
こんな人におすすめ
配偶者の出産のため休暇を取りたい方
身内に不幸があった方
「慶弔休暇」とは何か知りたい方
慶弔休暇とは?日数の目安は?
慶弔休暇とは、本人や身近な親族の慶事(結婚や出産などのお祝い事)や弔事(お悔やみ事)の際に取得できる休暇のことです。では、どのような場面が慶事と弔事に該当して、何日くらい取得することができるのでしょうか。
ここからは、慶弔休暇の規定や取得できる日数について解説します。
慶弔休暇は慶事や弔事で取得できる休暇
企業で働く方が取得できる休暇は2種類に分けられます。
1つ目は、「法定休暇」です。法律によって設定することが定められている休暇で、以下のような休暇が法定休暇にあてはまります。
・年次有給休暇
・産前産後休暇(産休)
・育児休暇(育休)
・介護休暇
・子の看護休暇
・生理休暇
・裁判員休暇 など
2つ目は、「法定外休暇」です。慶弔休暇も法定外休暇のひとつで、この休暇は企業が独自で定めています。法律で定められた休暇ではないので注意しましょう。
現在では多くの企業が慶弔休暇を社員に付与していますが、その内容は各企業の裁量に任せられています。そのため、結婚式や葬式に伴う休暇が「欠勤」扱いになっても違法にはなりません。
慶弔休暇が有給休暇となるかは会社次第
慶弔休暇を取得した日の賃金はどうなるのでしょうか。慶弔休暇は法定外休暇なので、慶弔休暇中の賃金の支払いに関する法的な規定はありません。そのため、慶弔休暇を有給とするか無給とするかは会社が独自に定めています。
多くの企業では、慶弔休暇は有給休暇として扱われることが一般的です。慶弔休暇取得時の賃金の支払いに関することは、企業の就業規則に記載があるので確認しておくとよいでしょう。
慶弔休暇日数の目安
慶事休暇は、内容によって取得できる日数が異なります。慶事の場合は、従業員本人か配偶者かによっても取得可能日数は変わるでしょう。弔事であれば、従業員本人との親等数によっても日数に違いがあります。ここでは、多くの企業が採用している慶弔休暇日数の目安を紹介します。
| 慶事休暇 | ||
| 休暇の種類 | 対象者 | 日数 |
| 結婚休暇 | 従業員本人が結婚する場合 | 5日 |
| 配偶者出産休暇 | 従業員の配偶者が出産する場合 | 2日 |
| 子供の結婚休暇 | 従業員の子が結婚する場合 | 2日 |
| 弔事休暇 | |
| 故人との関係 | 日数 |
| 0親等の配偶者が亡くなった場合 | 10日 |
| 1親等の父母・子供が亡くなった場合 | 7日 |
| 2親等の兄弟姉妹・祖父母・義理の父母・孫が亡くなった場合 | 3日 |
慶弔休暇の対象とはならないケース
慶弔休暇の対象とはならないケースもあるので、自身の勤務先の就業規則を確認しておきましょう。
慶弔が3親等以上の場合
おじ・おばや、曾祖父母は3親等の親族、いとこは4親等の親族にあたります。企業によっては、3親等以上の慶弔休暇を認めない場合もあります。
喪主の場合
葬式の当主のことを喪主といいます。配偶者が亡くなった場合は故人の妻や夫が喪主を務めるのが一般的ですが、配偶者以外が喪主を務めることもあるでしょう。
場合によっては、慶弔休暇の日数だけでは通夜や葬式など葬儀の全工程を終えられないかもしれません。その場合は、慶弔休暇の規定日数に加算して追加で休暇を取れるケースもあります。ただし、加算した日数分の賃金が有給になるか無給になるかは、各企業に委ねられています。
遠方の葬儀に参列する場合
遠方の葬儀に参列する場合は、往復の移動日数を含めると慶弔休暇の日数だけでは足りないことがあります。その際に、移動にかかる時間の分だけ慶弔休暇を増やしてくれる企業もありますが、超過した分は年次有給休暇で補う必要のある企業もあります。
慶弔休暇を取得する流れ
慶弔休暇を取得したい場合は、どのような手続きをすればよいのでしょうか。
ここからは、慶弔休暇を取得する流れについてご紹介します。
申請の流れは会社による
慶弔休暇の申請の流れは企業によって異なります。申請用紙の提出を求める企業もあれば、必要事項をメールに記載して送るという企業もあるでしょう。
結婚や出産などの慶事であれば、日程がきまっていたりある程度予測がついたりするため、事前に申請しておくことができます。一方で、弔事は予想が難しいでしょう。そのため、口頭やメールで親族が亡くなったことと休暇を取得したい旨を会社に伝えていれば、弔事による休暇の申請は事後でもよいとしている企業が多い傾向です。
証明書の提出を求められる場合もある
弔事の場合は、葬儀をおこなったこと証明する書類の提出を求められることもあります。通夜や葬式の際に渡される「会葬礼状」と呼ばれるお礼状の提出が義務づけられている企業も多いでしょう。会葬礼状がないような家族葬や小規模葬儀の場合は、死亡診断書のコピーなどが求められた事例もあります。
また、会社から弔電を送るために、故人の名前や葬儀の詳細について尋ねられるケースもあるでしょう。
慶弔休暇を申請する際のポイント
慶事と弔事は、いずれも本人にとって大きな出来事です。とはいえ、慶事や弔事をおこなっている間も会社は営業を続けています。慶弔休暇を取得する前に申請時の注意点やマナーを意識しておくと、休暇明けも良好な人間関係が築けるでしょう。
前もって就業規則を確認する
慶弔休暇について、勤務先の就業規則を確認しておきましょう。弔事の場合はいつ起こるかわからないので、入社時に把握しておくことが大切です。
【確認しておくポイント】
・慶弔休暇制度はあるのか
・慶弔休暇が取れる場合は、有給か無給か
・申請方法にきまりはあるのか
休む期間について伝える
慶弔休暇中は、ほかの従業員が自分の代わりに対応することになります。上司や同僚、取引先に対して、あらかじめ休む期間を伝えておけば業務への支障を抑えられるでしょう。
弔事の場合は、取引先にまで連絡はできないかもしれません。そのような場合でも仕事が滞りなく進むように、日頃から業務について同僚や上司と情報共有しておくと安心です。
休暇後はお礼を伝える
慶弔休暇取得後は、休んでいる間にフォローしてくれた同僚や上司にお礼を伝えるのがマナーです。自分の業務を代わりに担当してくれたり業務手順を変更したりしてくれているので、きちんと言葉にしてお礼を伝えましょう。
また、同僚や上司が慶弔休暇をとる立場になった際は、快く受け入れてあげることも大切です。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
慶弔休暇は法定外休暇ですが、多くの企業が設けている休暇制度です。休暇の内容は企業ごとに定めているので、取得できる日数や申請方法もそれぞれ異なります。
慶弔休暇中には、ほかの同僚や上司が自分の代わりに業務を担ってくれています。感謝の気持ちをもって、休暇後にはお礼の気持ちをしっかりと伝えることが大切です。
いざというときに焦ることのないように、ご自身の企業の慶弔休暇制度を改めて確認しておきましょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



年金制度には大きく分けて公的年金制度と私的年金制度の2種類があります。ホゥ。