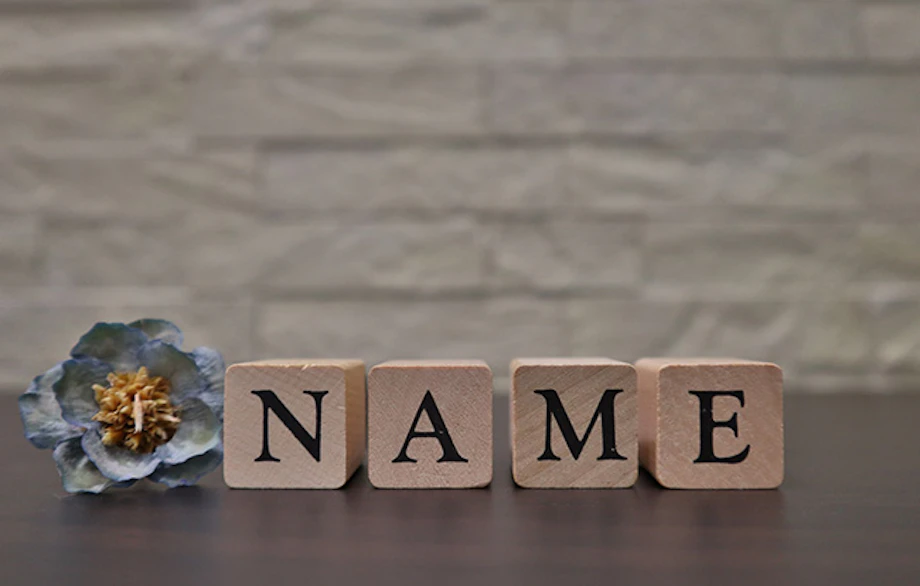知人や友人が亡くなった場合、お通夜や葬儀・告別式へ最後のお別れに行きたいと思うでしょう。とはいえ、遠方である、急なことで都合がつかないなど、足を運ぶことができないこともあります。このようなときにお悔やみの気持ちを伝える手段が、弔電です。
初めて弔電を送る際には、故人の敬称や弔電の内容など、わからないことも多いでしょう。この記事では、弔電のマナーや続柄別の例文などを紹介します。また、弔電を送る際に使用する故人の敬称も一覧で示しています。ぜひ参考にしてください。
<この記事の要点>
・弔電を送る際は喪主から見た故人との続柄で敬称を記載する
・弔電を送るときの宛名は、喪主の名前にするのが一般的
・弔電を送る際、縁起の悪い「忌み言葉」は使わない
こんな人におすすめ
弔電の書き方にお困りの方
弔電を送る際のマナーについて知りたい方
故人や遺族にお悔やみの気持ちをしっかりと伝えたい方
弔電で使う故人の敬称一覧
弔電では、生前とは異なる呼び方で故人を表します。一般的に、受取人には喪主を指定します。では、受取人との関係性によってどういった敬称になるのかを見てみましょう。
| 受取人から見た続柄 | 敬称 |
| 父 | ご尊父さま、お父上さま、お父さま |
| 母 | ご母堂さま、お母上さま、お母さま |
| 夫 | ご主人さま、旦那さま、ご夫君さま |
| 妻 | ご令室さま、ご令閨さま、奥さま、奥方さま |
| 祖父 | ご祖父さま、御祖父さま、祖父君 |
| 祖母 | ご祖母さま、御祖母さま、祖母君 |
| 兄 | ご令兄さま、兄上さま、お兄さま |
| 弟 | ご令弟さま、弟さま |
| 姉 | ご令姉さま、姉上さま、お姉さま |
| 妹 | ご令妹さま、妹さま |
| 息子 | ご令息さま、ご子息さま |
| 娘 | ご令嬢さま、ご息女さま、お嬢さま |
| 伯父(父母の兄) | 伯父上さま、伯父さま、ご令伯 |
| 伯母(父母の姉) | 伯母上さま、伯母さま、ご令伯 |
| 叔父(父母の弟) | 叔父さま、ご令淑 |
| 叔母(父母の妹) | 叔母さま、ご令淑 |
| 義父(配偶者の父) | お舅さま、お父上さま、お父さま |
| 義母(配偶者の母) | お姑さま、お母上さま、お母さま |
受取人の父母の敬称
故人が受取人のお父さま、お母さまの場合は、次のような敬称を用います。
・父:ご尊父(そんぷ)さま、お父上さま、お父さま
・母:ご母堂(ぼどう)さま、お母上さま、お母さま
馴染みのある「お父さま」「お母さま」を用いても問題ありませんが、最も丁寧なのは「ご尊父さま」「ご母堂さま」です。これらはビジネスシーンなど、かしこまった場面で使用することが多いものだといえます。
受け取られる相手との関係性、親密さによって、どの敬称を選ぶか検討しましょう。故人が夫や妻(配偶者)の親の場合は、以下の敬称を使用します。
・義父(配偶者の父):お舅(しゅうと)さま、お父上さま、お父さま
・義母(配偶者の母):お姑(しゅうとめ)さま、お母上さま、お母さま
受取人と故人の関係性を重視すると、「お舅さま」「お姑さま」が最適ですが、どこか他人行儀な印象もあるため、実父、実母と同様の敬称を用いてもかまいません。「ご尊父さま」「ご母堂さま」も使用できます。
受取人の祖父母の敬称
故人が受取人の祖父、祖母の場合に使用する敬称は、以下の通りです。
・祖父:ご祖父(そふ)さま、御祖父(おじい)さま、祖父君(おじぎみ)
・祖母:ご祖母(そぼ)さま、御祖母(おばあ)さま、祖母君(おばぎみ)
同じ「祖父」「祖母」と書いても、読み方が大きく異なります。どの敬称を選んでも大きな差異はありませんが、「ご祖父さま」「ご祖母さま」が主流となっています。
受取人の配偶者の敬称
故人が受取人の妻や夫といった配偶者の場合には、どういった敬称を用いるのでしょうか。
・夫:ご主人さま、旦那さま、ご夫君(くんふ)さま
・妻:ご令室(れいしつ)さま、ご令閨(れいけい)さま、奥さま、奥方さま
「ご夫君さま」「ご令室さま」「ご令閨さま」は日常的に使用しない敬称のため、より丁寧にしたい場合におすすめです。その他の敬称を使用しても失礼にはなりません。
受取人の子どもの敬称
故人が受取人の息子や娘(子ども)の場合には、次のような敬称を使いましょう。
・息子:ご令息(れいそく)さま、ご子息(しそく)さま
・娘 :ご令嬢(れいじょう)さま、ご息女(そくじょ)さま、お嬢さま
受取人の子どもの場合、まだ幼い、年齢が若いうちに亡くなってしまうケースもあります。敬称はもちろん、故人への最大限の気遣いを込めた弔電の内容にするなどの配慮も必要です。
その他の敬称
その他、受取人の兄弟姉妹やおじ・おばの敬称を紹介します。
兄弟の場合
・兄:ご令兄(れいけい)さま、兄上さま、お兄さま
・弟:ご令弟(れいてい)さま、弟さま
・姉:ご令姉(れいし)さま、姉上さま、お姉さま
・妹:ご令妹(れいまい)さま、妹さま
父母の兄・姉の場合
・伯父上(おじうえ)さま、伯父:伯父さま、ご令伯(れいはく)
・伯母上さま、伯母:伯母さま、ご令伯(れいはく)
父母の弟・妹の場合
・叔父:叔父さま、ご令淑(れいしゅく)
・叔母:叔母さま、ご令淑(れいしゅく)
兄弟姉妹、おじ・おばは「ご令~」という敬称が丁寧です。また、受取人自身の兄・姉、そして受取人の父母の兄・姉は目上であることから「~上さま」という敬称も使用できます。
おじ・おばについては父母の兄・姉か、弟・妹かによって敬称が異なるので、間違えないよう注意が必要です。
弔電を送る際のマナーは?
訃報を受け取ったら、お通夜や葬儀・告別式の前日までに弔電を送ります。連絡をいただくのが遅かった場合も、葬儀の開始時刻に間に合うよう、早めに手配をしましょう。
弔電を送る際には、宛名や文面に関して守りたい2つのマナーがあります。
宛名は喪主の氏名にする
弔電は故人へのお別れの言葉を記したものですが、故人宛てに発送してはいけません。宛名は喪主の氏名にします。喪主の氏名がわからない場合には、「故 ○○様」と故人の氏名を書き、「ご遺族様」と併記しましょう。
企業、団体などが葬儀を主催するような場合では、葬儀責任者や主催者の名前や部署を宛先にします。受取人にわかりやすいよう、差出人の氏名と故人との関係性を記しておくと親切でしょう。
故人との関係性で文面を変える
弔電は、故人へのお別れの言葉なので、故人との関係性によって内容を変えましょう。親しい友人や親族へ送る場合は、お悔やみの言葉はもちろん、故人との思い出や故人の人柄がわかる話を盛り込むと、生前の様子を遺族に知ってもらえます。
職場の上司や仕事関係の方には、個人的にではなく会社や所属部署などが連名で送ることも多い傾向です。この場合は個人的な感情を記すのではなく、簡潔にお悔やみの気持ちを伝える内容にすることをおすすめします。
弔電を送る際に避けたほうがよい言葉は?
弔電は故人へのお別れの言葉ですが、もちろん喪主をはじめとした遺族の方が読まれます。送る際にはマナーを守ることも大切です。故人と自身の関係によって内容を変える工夫だけでなく、弔電にふさわしくない言葉を使用しないことにも配慮しましょう。
忌み言葉
縁起の悪い言葉、不吉な感じのする言葉を「忌み言葉(いみことば)」といいます。弔電を読んだ遺族が不快に思ったり傷ついたりしないよう、忌み言葉を避けた文章にすることが大切です。
例えば、「重ね重ね」「ますます」「たびたび」などの重ね言葉は、不幸を繰り返すような印象になるため使用を避けます。ほかにも、「消える」「落ちる」「なくなる」「大変」「続く」「再び」など、ネガティブなイメージ、不幸が重なるようなイメージの言葉は使用しないようにしましょう。
同じ内容でも、言い回しをポジティブにするだけで、文面から受ける印象は大きく変わります。「生きていた頃に」よりも「お元気な頃は」「生前は」など、遠回しな表現を使うだけでも、遺族への配慮になるのではないでしょうか。
宗教や宗派に合わない言葉
忌み言葉を避け、故人との関係性によって内容を考えれば問題ない、と思われがちですが、弔電を送る際には宗教や宗派にも配慮する必要があります。日本人の多くは仏教を信仰していますが、キリスト教や神道をはじめ、そのほかの宗教を信仰されている方も少なくありません。
仏教では使用可能な言葉でも、他の宗教、宗派の方にとっては失礼になる場合もあるので注意しましょう。
例えば、よく耳にする「ご冥福をお祈りします」という挨拶の「冥福」には、死語の幸福を祈るという意味がありますが、これは仏教用語です。
キリスト教や神道などでは使用しないことはもちろん、同じ仏教でも「亡くなったらすぐに極楽浄土へ行ける」という考えの浄土真宗の方にも使用しません。
「成仏」「供養」など、日常的に使用している言葉も、仏教の言葉なので注意が必要です。弔電を送る際には、故人の宗教、宗派を確認してから送る言葉を考えることも忘れないようにしましょう。
受取人の続柄別!敬称を用いた弔電の文例
弔電を送る際、どういった内容にすればよいのかは大きく悩むところでしょう。故人への最後の言葉なので思い残すことのないよう、また遺族に失礼にならないような内容にすることが大切です。
弔電は故人との思い出などを盛り込むことも重要ですが、遺族や親族が目を通すことを踏まえて考えましょう。また、葬儀で読まれることも想定し、簡潔で公的な内容・文面を意識するとよいでしょう。
最後に、受取人の方と故人との続柄別に、弔電の文例を紹介します。
受取人の父母が故人である場合の文例
■ご尊父さまのご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げます。ご生前は未熟な私に多くのことを教えてくださいました。ご尊父さまからいただい言葉は、これからも私の背中を押し続けてくださると信じております。ご遺族の方々のご心痛をお察し申し上げますとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。
■突然の悲報に接し、驚きを隠せません。ご母堂さまがお元気な頃に過ごした時間は、かけがえのない宝物です。生前のお姿を偲びつつ、ご母堂さまが安らかにお眠りになられるよう、お祈りいたします。
受取人の祖父母が故人である場合の文例
■ご祖父さまのご逝去の報に接し、心から哀悼の意を捧げます。ご生前、共に過ごした時間は、これからも忘れません。悲しみにたえませんが、安らかな旅立ちでありますよう、お祈り申し上げます。
■ご祖母さまご逝去のお悲しみに対し、弔問かなわぬ非礼をお詫びいたします。いつまでもお元気でいてくださると思っておりましたので、残念でなりません。安らかにご永眠されますよう、心よりお祈りいたします。
受取人の配偶者が故人である場合の文例
■ご主人さまのご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げます。ご生前のご厚情に感謝するとともに、安らかにご永眠されますよう、心よりお祈り申し上げます。
■ご令室様の突然のご悲報に接し、お悲しみをお察し申し上げます。ご生前は、思い出となる時間を過ごさせていただき、ありがとうございました。心より哀悼の意を捧げますとともに、謹んでご冥福をお祈りいたします。
受取人の子どもが故人である場合の文例
■ご令息さまの突然の悲報に接し、ご家族の皆様のお悲しみ拝察申し上げます。お元気だった頃の無邪気な笑顔、かわいらしい笑い声が忘れられません。心より哀悼の意を表しますとともに、謹んでご冥福をお祈りいたします。
■ご令嬢さまの突然の訃報に、愕然といたしております。ご両親さまのお悲しみ、お察し申し上げます。在りし日の凜としたお姿を偲びつつ、心よりご冥福をお祈りいたします。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
弔電は故人と直接お別れができない場合に送る、最後の言葉です。直接お伝えできない気持ちを文面にするため、マナーを守った内容にすることはもちろん、遺族への心遣いも忘れてはいけません。
弔電での敬称は、受取人と故人の続柄で決まります。特に、伯父と叔父、伯母と叔母は間違えやすいので注意しましょう。
遺族や故人のさまざまなご要望を叶える葬儀プランをご提案する「小さなお葬式」では、24時間365日対応のお客様サポートダイヤルで、弔電に関するご相談も承っております。些細な疑問もお気軽にご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



葬儀の挨拶では、不幸を連想させてしまう忌み言葉と重ね言葉には気をつけましょう。ホゥ。