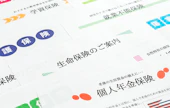年金は、老後の大きな収入源といえるでしょう。そのため「どのくらい税金が引かれる?」「手取りはいくらになる?」と、気がかりになるかもしれません。結論から述べると、年金の種類や所得によって異なります。
ここでは、年金に税金がかかるケース・かからないケース、税額の計算方法、所得控除、源泉徴収についてまとめました。疑問解消に、ぜひお役立てください。
<この記事の要点>
・公的年金は課税対象であり、受給額が一定額を超えると所得税や住民税が発生する
・年金が非課税となるのは受給額が基準以下の場合で、年齢や扶養状況によって異なる
・所得控除や税額控除を活用することで、課税対象額を軽減できる
こんな人におすすめ
年金の種類を1から知りたい人
どういうときに年金に税金がかかるか知りたい人
自分で税金の計算ができるようになりたい人
年金の種類をおさらいしよう
年金は主に、公的・企業・私的の3種類あるのが特徴です。自営業者か会社員か、扶養されている配偶者なのかによって加入先が異なります。ここでは、自身の加入先を再確認しておくとよいでしょう。
公的年金とは
国が管理している年金で、「国民年金」と「厚生年金」の2種類に分類できます。国民年金は、原則20歳以上60歳未満で日本国内に住んでいる方が対象です。一般的に自営業や農業を営む方、無職、学生は国民年金、会社員や公務員は厚生年金に加入します。ただし会社員や公務員の扶養に入っている配偶者は、国民年金の対象です。
国民年金は「老齢基礎年金」、厚生年金は「老齢厚生年金」を受け取ると覚えておきましょう。
企業年金とは
企業年金は、一部の会社が福利厚生として設けている任意加入の制度です。大きく2種類に分類でき、規約に基づき加入期間や給付額を決める「確定給付企業年金」と、従業員自らが拠出された掛け金を運用する「確定拠出年金」があります。
個人年金とは
個人で加入し、積み立てや運用をするのが個人年金です。制度としては補完的な役割があり、将来受け取る額を増やしたい方が加入します。
個人による拠出や運用の一例として、iDeCo(個人型確定拠出年金)が挙げられます。また生命保険会社の提供するサービスを利用している方もいるでしょう。
年金に税金がかかるケース・かからないケース
年金をすでに受け取っている方や、これから受給する方は、課税されるかどうか気になるでしょう。下記では、課税されるケース・されないケースを表にまとめました。税金がかかるかどうかは年金の種類によって決まります。
| 【課税される年金】 | 老齢年金(基礎、厚生) ※所得税・復興特別所得税・住民税などが課せられる |
| 【課税されない年金】 | 遺族年金、障害年金 |
上記のほかにも、所得によって課税されないケースもあります。
| 【年金以外の所得】 | 【年金収入】 |
| 1,000万円以下 | 65歳未満:60万円以下 65歳以上:110万円以下 |
| 1,000万円超2,000万円以下 | 65歳未満:50万円以下 65歳以上:100万円以下 |
| 2,000万円超 | 65歳未満:40万円以下 65歳以上:90万円以下 |
※令和2年分以後の要件です。平成17年分~令和元年分までについては、旧要件を確認してください。
(参考:『国税庁』https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm)
年金にかかる税金の計算方法
年金の税金は基本的に毎年徴収されるため、どのくらい手元に入るのか気になるでしょう。ここでは、税額の計算方法について解説します。公的・企業・個人年金のなかで、加入状況に応じて税額の求め方を確認しましょう。
公的・企業・iDeCoの場合
どのくらい税金がかかるのか調べるには、「雑所得⁻所得控除」の金額を速算表でチェックします。下記では、雑所得の求め方と速算表を紹介します。1~3の手順で計算すると、税額がわかりやすいでしょう。
【1:雑所得の計算方法】
公的年金等の収入(×金額に応じた割合)-金額に応じた控除額
<65歳未満>
| 【収入金額】 | 【下記の割合を乗ずる】 | 【控除額】 |
| 130万円未満 | - | 60万円 |
| 130万円以上410万円未満 | 25% | 27万5,000円 |
| 410万円以上770万円未満 | 15% | 68万5,000円 |
| 770万円以上1,000万円未満 | 5% | 145万5,000円 |
| 1,000万円以上 | - | 195万5,000円 |
<65歳以上>
| 【収入金額】 | 【下記の割合を乗ずる】 | 【控除額】 |
| 330万円未満 | - | 110万円 |
| 330万円以上410万円未満 | 25% | 27万5,000円 |
| 410万円以上770万円未満 | 15% | 68万5,000円 |
| 770万円以上1,000万円未満 | 5% | 145万5,000円 |
| 1,000万円以上 | - | 195万5,000円 |
【2:所得控除について】
所得控除には、基礎控除や配偶者控除、医療費控除を含めて8項目あります。該当する項目の要件と控除額を確認し、雑所得から差し引きましょう。
【3:所得税の速算表】
| 【課税所得(雑所得 - 控除額)】 | 【税率】 | 【控除額】 |
| 195万円未満 | 5% | - |
| 195万円以上330万円未満 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円以上695万円未満 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円以上900万円未満 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円以上1,800万円未満 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円以上4,000万円未満 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
(参考:『国税庁』https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm)
(参考:『国税庁』https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)
保険会社の個人年金の場合
保険会社で個人年金に加入している場合、雑所得の求め方が異なります。
・雑所得:総収入額-必要経費
・必要経費:1年間の支払い総額×(総払込保険料÷年金受取額)×年数
ただし一括で受給するケースだと、雑所得ではなく「一時所得」の扱いになります。
その際の計算式は、「一時所得の金額=一括受取額-払込保険料総額-特別控除額(50万円)」です。
加えて、保険の加入者と受取者が異なると贈与税が課せられるため注意しましょう。
年金にかかる税金の源泉徴収|公的・企業・個人年金
支給額の一部は源泉徴収されるため、全額を受け取れるわけではありません。しかし所得税を仮計算して徴収しており、確定申告をすると還付金として戻ってくるケースもあります。ここでは、各種年金の源泉徴収について触れています。
公的年金の源泉徴収と計算式
公的年金を受け取るとき、仮計算された所得税が差し引かれます。源泉徴収額の計算式を確認しましょう。
【源泉徴収税額の計算式】
(公的年金等の支給額-社会保険料-控除額)×5.105%(所得税+復興特別所得税)
基礎控除を除く所得控除は、扶養親族等申告書を提出しなければ適用されません。提出しないと控除を受けられず、多めに天引きされる恐れもあるので注意しましょう。
(参考:『日本年金機構』https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/1228.html)
企業年金の源泉徴収と計算式
企業年金は支給額の大きさに関わらず、7.6575%の所得税が徴収されます。ただし給付型と拠出型によって、源泉徴収額が異なるため違いをみてみましょう。
【給付型:企業が管理・運用する】
源泉徴収税額=(年金支給額-年金支給額×25%)×{所得税率(10%)+復興特別所得税率(10%×0.021)}≒年金支給額×7.6575%
ただし給付型を引き継いだあと拠出金があった場合は、「年金額-加入者拠出金相当額」を算出した額から、上記で求めた源泉徴収額を差し引きます。詳しくは、企業年金連合会のホームページよりご確認ください。
【拠出型:加入者が運用する】
源泉徴収税額=(年金支給額-年金支給額×25%)×{所得税率(10%)+復興特別所得税率(10%×0.021)}≒年金支給額×7.6575%
(引用:『源泉徴収税額の計算式|企業年金連合会』https://www.pfa.or.jp/nenkin/nenkinkyufu/zeikin/index.html)
個人年金の源泉徴収と計算式
加入者自身が年金を受け取る場合、所得税が源泉徴収されます。計算式は、以下のとおりです。
【源泉徴収税額の計算式】
(年金支給額-年金額に対応する保険料相当額 )×10.21%(復興特別所得税含む)
※例外として雑所得が年間25万円未満の場合、源泉徴収されない
保険の加入者と受取人が異なるケースは、年金支給の初年度は非課税で、2年目以降に課税額が増えていく仕組みです。
(参考:『国税庁』https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1610.htm)
(参考:『国税庁』https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm)
年金にかかる税金は確定申告が必要?
年金を受給しているからといって、必ず確定申告をするとは限りません。申告の負担を減らすために、「不要」となるケースもあります。ここでは、「確定申告不要制度」と確定申告が必要なケースについて確認しましょう。
「確定申告不要制度」の対象者は不要
確定申告不要制度の対象者は、確定申告をする必要がありません。
【対象者】
・年金収入が400万円以下の方
(※所得税法第203条の7(源泉徴収等を要さない公的年金等)に当てはまるケースを除く)
・年金以外の所得(給与や不動産)が20万円以下
ただし確定申告をすると、払いすぎている分の還付を受けられます。課税分を計算し、払いすぎている可能性がある方は、確定申告をしましょう。
(参考:『国税庁』https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/b/01/1_06.htm)
確定申告が必要なケースあり(所得控除について)
所得控除の対象になる場合、確定申告が必要になるでしょう。厳密に言うと、税額を求める際の雑所得から所得控除を差し引いても残額がある方は確定申告が必要です。
【所得控除の種類】
・基礎控除:所得の合計が2,500万円以下
・寄付金控除:2,000円以上の寄付をした(※国・地方公共団体・公益団体等に対する特定寄付)
・医療費控除:医療費で年間10万円以上負担した
・生命保険料控除:生命保険や個人年金の保険料を納めた
・社会保険料控除:社会保険料(健康保険や介護保険)を納めた
・配偶者控除:生計を一にする配偶者の所得が48万円以下
・配偶者特別控除:生計を一にする配偶者の所得が48万円超え133万円以下
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
税金がかかるのは、老齢年金(基礎・厚生)を受給したときです。ただし配偶者控除や医療費控除といった所得控除が適用されると、課税所得は減るでしょう。控除の対象者は、確定申告をすることで、還付金が入る可能性があります。気になる方は、税額と源泉徴収額を計算し、シミュレーションするとよいでしょう。
「小さなお葬式」では、葬儀や法要のご相談を受け付けています。お客さまサポートダイヤルを設けているので、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


直葬とは、通夜式や告別式などの式をはぶき、火葬のみを行う葬儀のことです。ホゥ。