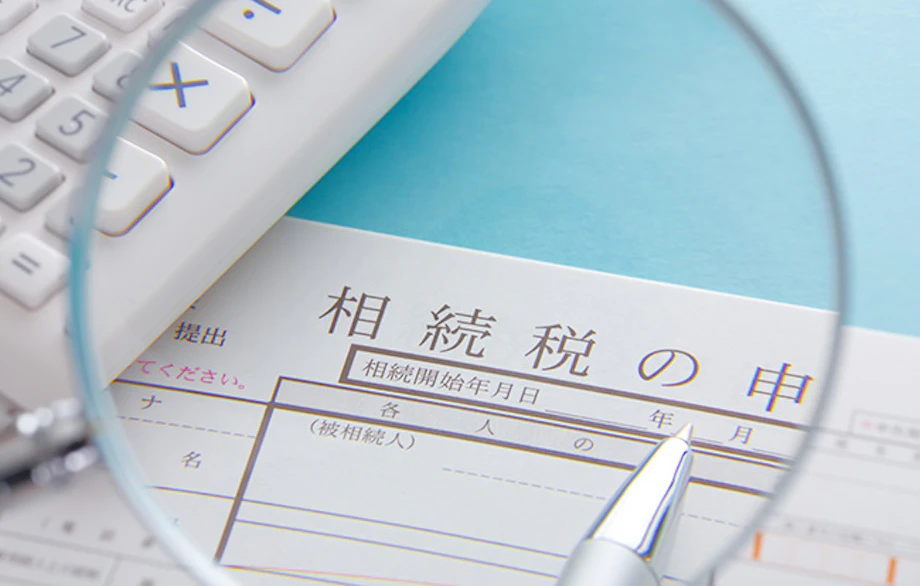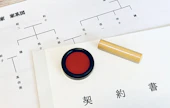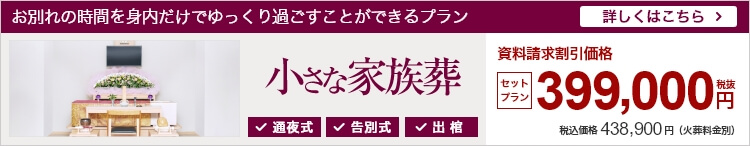「相続税の申告をするべきかわからない」という理由から、無申告を選んでしまう方がいるかもしれません。しかし無申告だと発覚すれば、遅延税や加算税が課せられることもあるでしょう。
ここでは相続税の申告が不要なのか、判断する方法を解説します。「申告前にチェックすること」の項目では、生命保険金・死亡退職手金の非課税枠にも触れているので、ぜひ確認してみてください。
<この記事の要点>
・相続財産の合計が基礎控除額以下の場合には、相続税申告が不要となる
・基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算できる
・生命保険金や死亡退職金には非課税枠があり「500万円×法定相続人の数」まで非課税となる
こんな人におすすめ
相続税申告をすべきか、判断基準がわからない人
控除や特例について知りたい人
相続税の申告は必要?不要?
相続税の申告は、不要なケースと必要なケースがあります。
【申告が不要な場合】
申告が不要になるのは、基礎控除額を下回るときと、税額控除により非課税となるときです。
【申告が必要な場合】
税額控除を受けても、申告が必要なケースもあります。「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」は、相続税の申告をしなければ控除されません。
相続税の申告が不要かも?計算して確かめよう
相続税の申告が不要かを判断するには、「課税対象額」と相続税の「基礎控除額」の2つを算出しなければなりません。課税対象額が基礎控除額を下回れば、申告は不要です。
それぞれの求め方は、下記を確認してみてください。
【課税対象額】
プラスの財産とマイナスの財産により、課税対象額が決まります。
・プラスの財産例:現金、預貯金、住宅や土地、保険金、株式や投資信託など
・マイナスの財産例:借金、未払いのローン、葬儀費用、保証人になっているものなど
【基礎控除額】
・3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数)
・法定相続人は、民法の定めにしたがって確認する
(相続人の優先順位として、1配偶者+子ども、2配偶者+被相続人の父母、3配偶者+被相続人の兄弟姉妹となる)
もし法定相続人が2人の場合は、「3,000万円+(600万円 × 2人)=4,200万円」となり、相続財産が4,200万円を下回れば申告不要と判断できます。
相続税の申告前にチェックすること
申告前にチェックしておきたいのが、「みなし相続財産」「相続時精算課税制度」「3年以内の贈与」です。申告漏れや計算ミスを防ぐために、それぞれの項目を確認してみましょう。
みなし相続財産(生命保険金・死亡退職手金)
みなし相続財産とは、本人の死亡により発生する「生命保険金」「死亡退職金」のことです。それぞれ非課税枠があるため、差し引いて税額がいくらになるのか確認しましょう。
【生命保険金(損害保険金含む)の非課税枠】
500万円 × 法定相続人の数
【死亡退職金の非課税枠】
500万円 × 法定相続人の数
(参考:『国税庁 相続税の課税対象になる死亡退職金』)
(参考:『国税庁 相続税の課税対象になる死亡保険金』)
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度を利用している場合、相続税の申告が必要になるかもしれません。こちらの制度は、2,500万円までの生前贈与は非課税になります。ただし相続時には、贈与した分も含めて、相続税が課せられます。つまり贈与した分+相続した分に相続税がかかる仕組みです。
相続時精算課税制度を利用して生前贈与した方は、贈与+相続の税額が基礎控除内になっているか確かめましょう。
(参考:『国税庁 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務』)
3年以内の贈与
税法では、死亡前3年以内の贈与に、相続税が課せられると定められています。例えば毎年100万円を亡くなる3年以内に贈与していた場合、100 × 3=300万円は相続財産になると覚えておきましょう。
相続財産+亡くなる前3年以内の贈与が基礎控除額を下回っていれば、申告は不要になります。
相続税の申告前に!控除や特例の種類
相続税には、税額を軽減する控除・特例制度が設けられています。控除の種類によっては申告不要ですが、金額に関わらず申告必要なケースもあるため要チェックです。ここでは申告不要と申告必要の2項目に分けて、控除や特例について説明しました。
申告不要な控除
申告不要な控除は、「未成年者」「障害者」を対象とした控除の2種類あります。
【未成年者の税額控除】
養育費や教育費を必要とするため、未成年者は税額控除が受けられます。控除額は「(18歳-相続発生時の年齢)×10万円」で計算しましょう。
【障害者の税額控除】
障害のある方にも、税額を軽減する措置があります。控除額は、一般障害者と特別障害者に分けるのが特徴です。
| 一般障害者 | (85歳-相続発生時の年齢)×10万円 |
| 特別障害者 | (85歳-相続発生時の年齢)×20万円 |
(参考:『国税庁 未成年者の税額控除』)
(参考:『国税庁 障害者の税額控除』)
申告必要な控除・特例
基礎控除額を下回る場合でも、申告すべき控除があります。相続税の申告なしでは控除を受けられないため、注意しましょう。申告を要するのは、下記の4つです。
【寄付金控除】
相続財産を寄付した場合、支出した金額は相続税が課せられません。ただし寄付する先は、国、地方公共団体、認定NPO法人、公益を目的とする法人が対象です。
(参考:『国税庁 相続財産を公益法人などに寄附したとき』)
【配偶者の税額の軽減】
配偶者から相続されるとき、配偶者の税額軽減を受けられます。下記の(1)もしくは(2)のうち、どちらか高い方を選択し、その分は非課税となる措置です。
(1) 法定相続分相当額
(2) 1億6,000万円
参考:『国税庁 配偶者の税額の軽減』)
【小規模宅地などの特例】
被相続人と生計を一にしていた家族は、自宅、店舗、事務所といった宅地に対して、税額が軽減されます。
軽減額は、以下をご覧ください。
・居住用、事業用:評価額の80%引き
・事業用として貸す土地:評価額の50%引き
(参考:『国税庁 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例』)
【農地の納税猶予の特例】
要件を満たす場合、農地の納税猶予の特例を受けられます。被相続人、相続人、農地それぞれに要件があり、詳しくは国税庁のホームページで確認可能です。
<要件の一例>
・被相続人:農業を営んでいた、または農地を貸していた人から相続した
・相続人:相続税の申告期限前に農業をスタートした方
・農地:相続税の申告までに遺産分割された農地
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
相続税の申告は、基礎控除額を基準に判断しましょう。ただし控除や特例制度もあるため、該当しそうな場合は「要件を満たしているか」「申告不要な控除か」「控除額を差し引いたうえで税額ゼロになるか」といった点に気を付けましょう。
小さなお葬式では、葬儀や法要のご案内をしています。ご遺族やご本人の意向に合わせて、小規模なお葬式も選択可能です。小さな疑問にも答えるフリーダイヤルを用意しておりますので、気になる方はいつでも気軽にお問合せください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


遺産相続が発生した場合、いかなる場合でも配偶者は相続人になります。ホゥ。