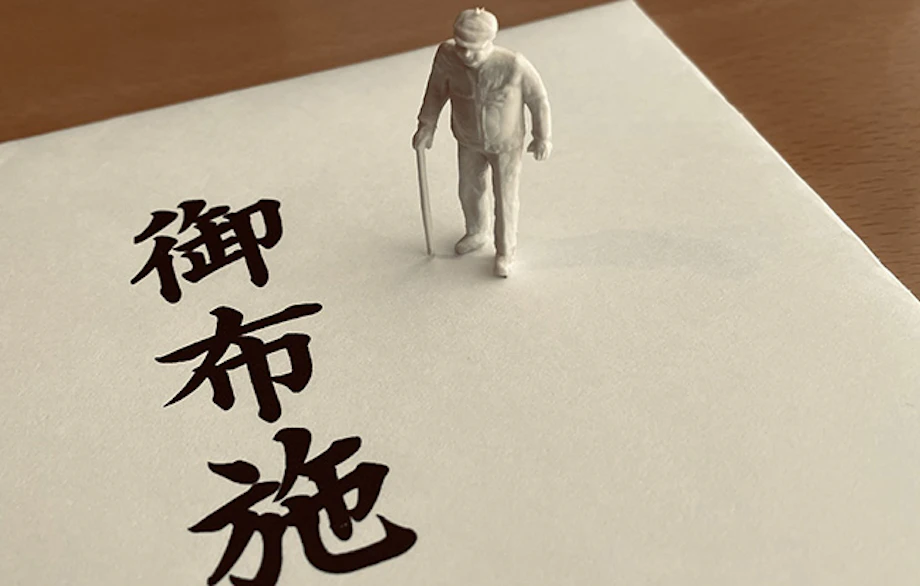お墓の維持や管理を寺院や霊園に任せるのが「永代供養」です。その場合に、お布施が必要な場面があるのか、疑問に思う人もいるかもしれません。この記事では、永代供養でお布施が必要な場面や、永代供養のお布施マナーなどについて解説します。
<この記事の要点>
・永代供養した後でも、年忌法要を執り行う場合はお布施を渡すことが一般的
・永代供養のお布施は白無地の封筒に入れ、表書きは「御布施」と書く
・永代供養における年忌法要のお布施は一周忌の場合、3万円~5万円程度が目安
こんな人におすすめ
永代供養を検討している人
永代供養のお布施の知識を身につけたい人
永代供養でもお布施が必要な場面がある
永代供養にしたらお布施は不要と考えている方がいるかもしれませんが、お布施が必要な場面はあります。まずは、どのような場面でお布施を用意する必要があるのかを解説します。
年忌法要のお布施は永代供養料に含まれていない
年季法要とは、故人の命日から1年目に「一周忌」、2年目に「三回忌」、6年目に「七回忌」、12年目に「十三回忌」などと、節目となる年に執り行われるものです。
年忌法要の際には、僧侶に読経をしてもらい、お布施を渡すことが一般的です。永代供養した後に年忌法要を執り行う場合のお布施については、契約時に支払う永代供養料には含まれていないので、その都度渡す必要があります。
納骨法要のお布施は契約内容しだい
永代供養においても、お墓に遺骨を納める際には「納骨法要」を執り行います。僧侶に読経をしてもらい、お布施を渡します。
ただし、永代供養の契約時に支払う永代供養料の中に納骨法要のお布施が含まれている場合と、含まれていない場合があるので注意が必要です。契約内容によりますので、事前に確認しておきましょう。
お布施の考え方
お布施とは、もとは仏教における僧侶の修行法の1つで、人に施しを与えるという意味を持っていました。現在のお布施の持つ意味とはどのようなものなのでしょうか。また、金額についてもどう考えたらよいのか解説します。
お布施の種類と意味
お布施とは、仏教における「六波羅蜜(ろくはらみつ)」という修行のうちの1つで、見返りを求めずに施しを与えることです。さらにお布施は、次の3種類があります。
・財施(ざいせ):金銭・食べ物・品物などを施すこと。
・法施(ほうせ):仏の教えを説いて聞かせること、読経すること。
・無畏施(むいせ):恐れや不安を取り除いて安らぎを与えること。
お布施は寺院のご本尊に捧げるもの
お布施は法要などで、僧侶に読経してもらったことに対するお礼として渡すものだと、考えている人が多いかもしれません。
しかし、本来は仏教の修行の1つとして、寺院のご本尊に、感謝の気持ちを持って捧げるものです。僧侶に手渡しますが、実際には僧侶を通じてご本尊に渡しているのです。
金額に明確な決まりはない
お布施は、僧侶に読経してもらったことに対する料金ではありません。あくまでも、お布施をする方の感謝の気持ちの表れとして、金銭を包んで渡すものです。
そのため、金額に明確な決まりはありません。一般的な目安はあるものの、自分が用意できる程度のものを用意すれば問題ありません。
永代供養のお布施を納める方法
永代供養のお布施を納める際には、ただお金を渡せばよいというものではありません。納める方法にはマナーがありますので、理解しておきましょう。封筒、表書き、お札、渡すタイミングなどについて解説します。
白封筒を使用する
永代供養のお布施を納める際にも、封筒で包んで渡すのが一般的です。封筒は、郵便番号の枠が書かれていない無地で白いものを選びましょう。
不祝儀袋はお布施では使いませんが、水引がついた封筒であれば黒白の水引のものにします。文具店やコンビニ、ネット通販などで購入することができます。
表書きの書き方
表書きには、封筒の中央上段に「お布施」や「御布施」と書きます。すでに表書きが印刷された市販の封筒を用いる場合には、そのままでかまいません。
封筒の中央下段には、代表者の氏名を書きましょう。「◯◯家」と姓を書く場合もあります。正式には、濃墨を使って毛筆で書きます。市販の筆ペンを使ってもよいでしょう。
裏面の書き方
封筒の裏面には、住所、氏名、金額を書きます。お寺の経理で必要になるため、金額もしっかりと記載しましょう。
金額の書き方はまず、「金」と書き、漢数字を旧字体で記します。例えば、一、二、三、十、万を、壱、弐、参、拾、萬と書きます。最後に「圓也」と書き入れましょう。
お札は新札でも構わない
香典としてお札を包む場合には、新札を使わないのがマナーです。不幸をあらかじめ準備していたと思われるかもしれないからです。
ただし、お布施は香典ではないため、お布施として封筒に入れるお札は新札でもかまいません。
お布施を渡すタイミング
法要の際にお布施を渡すタイミングは、読経や法話の後に渡すのが一般的です。ただし、お寺によっては支払い方法は銀行振込などと決まっている場合もあるので、事前に確認しておいたほうが確実です。供養方法によっては、複数回に分割して渡す必要がある場合もあります。
永代供養における年忌法要のお布施の相場
お布施はあくまでも気持ちを表すものなので、金額に決まりはありません。それでも、いくら包んだらよいのかわからない方もいるでしょう。永代供養における年忌法要のお布施の目安は、次のとおりです。
まず、一周忌の場合は、3万円~5万円程度です。三回忌以降は1万円~5万円程度が目安になります。
また、寺院ではなく自宅や葬儀場で法要を執り行う場合には、御車料と御膳料が必要です。目安はそれぞれ5,000円~1万円程度です。
永代供養にはどのくらい費用がかかる?
永代供養にかかる必要は永代供養墓の種類によって異なります。実際にどのくらいの費用がかかるのか目安を紹介します。また、費用の内訳や永代供養料の納め方についても解説します。
永代供養の種類別の費用目安
永代供養墓の種類ごとの永代供養にかかる費用の目安は以下のとおりです。
| 永代供養墓の種類 | 永代供養にかかる費用の目安 | 一般的な料金の目安 |
| 単独墓 | 30万~100万円程度 | 約40万円 |
| 集合墓 | 10万~30万円程度 | 約20万円 |
| 合祀墓 | 3万~10万円程度 | 約10万円 |
| 納骨堂(1人用) | 25万~100万円程度 | 約50万円 |
| 納骨堂(家族用) | 50万~200万円程度 | 約100万円 |
永代供養にかかる費用内訳
永代供養にかかる費用の内訳は次のとおりです。
| 永代供養料 | 遺骨の管理や供養のための費用です。遺骨を納める占有スペースの使用料も含まれています。 |
| お布施 | 納骨法要の際に僧侶に読経してもらう場合に必要となります。 |
| 刻字料 | 墓誌に故人の名前を彫刻してもらうための費用です。 |
| その他 | 墓石を建てる場合には墓石料が必要です。また、寺院、霊園によっては年間管理費などが必要な場合もあります。 |
永定供養料として支払う際に、どの項目がその中に含まれているのかを契約時に確認する必要があります。
永代供養料の納め方
永代供養料は白い無地の封筒に入れて、表書きに「永代供養料」と書きましょう。ただし浄土真宗の場合には、供養という考え方がないので「永代経懇志」と書きましょう。
封筒を直接手で渡すのはマナー違反です。封筒は袱紗(ふくさ)に包んで、切手盆に乗せ、封筒の表書きが相手に見えるような向きで僧侶に渡しましょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
永代供養でも、お布施が必要な場面があります。「年忌法要」の際にはその都度、お布施を渡します。永代供養における年忌法要のお布施の目安も合わせて確認しておくとよいでしょう。
永代供養でも、お墓に遺骨を納める際に「納骨法要」を執り行います。永代供養の契約時に支払う永代供養料の中には、納骨法要のお布施が含まれていない場合もあるので、事前に契約内容をよく確認することが必要です。永代供養のお布施についてよく理解した上で、永代供養をしてもらいましょう。
小さなお葬式では、葬儀に精通したコールスタッフが、24時間365日、通話無料でご連絡をお待ちしております。 永代供養やお布施について知りたい方や、葬儀についての疑問をお持ちの方は、ぜひ小さなお葬式へご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


お彼岸の時期は年に2回で、春分の日、秋分の日の頃だと覚えておくとよいでしょう。ホゥ。