初盆は「はつぼん」や「ういぼん」と呼ばれ、新盆(しんぼん・あらぼん・にいぼん)と同じ意味を持ちます。初盆の迎え方は、信仰している宗派によって異なります。この記事では、浄土真宗の初盆の迎え方を解説します。
初盆を迎える際に必要なものや祭壇の飾り方についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
<この記事の要点>
・浄土真宗の初盆では、「歓喜会(かんぎえ)」と呼ばれる法要が行われる
・浄土真宗の初盆では、切子灯籠・打敷・供笥・和ろうそく・線香などが必要
・僧侶に渡すお布施の目安は3万円~5万円程度
こんな人におすすめ
初盆とは何か知りたい方
浄土真宗の初盆について知りたい方
浄土真宗の初盆に必要なものを知りたい方
初盆とは
初盆とは、四十九日を過ぎて初めて迎えるお盆のことです。お盆の時期は地方によって異なり、7月に行う地域や8月に行う地域がありますが、一般的には8月13日~8月16日の4日間を指します。ただし、四十九日以前にお盆を迎えた場合は翌年が初盆となります。
初盆は、亡くなってから初めて故人の霊が自宅に帰ってくる日です。そのため、親族や親戚、友人など生前親しくしていた方達を招いて特に手厚く法要を営みます。
浄土真宗とは
浄土真宗は親鸞によって鎌倉時代中期に開かれました。現在は教義によって10の宗派があり、その中でも代表的なものは東本願寺を本山とする「真宗大谷派」と西本願寺を本山とする「本願寺派」です。
浄土真宗では「阿弥陀如来の力を信じ南無阿弥陀仏を唱えると、すべての人が極楽浄土へ行くことができる」と教えています。亡くなるとすぐに浄土に往生し、成仏すると考えられているため、「霊」という概念をもちません。そのため、葬儀や法要の内容がほかの宗派と異なります。
浄土真宗におけるお盆の解釈
一般的な仏教宗派では、お盆の時期になると先祖があの世から帰ってくると考えられています。そのために盆棚(精霊棚)や精霊馬の準備をしたり、迎え火を焚いたりするのが一般的です。
一方で浄土真宗では、故人は浄土で幸せな生活を送っていると捉えられています。つまり、お盆だからといって現世に帰って来ることはありません。浄土真宗にはお盆そのものの概念がないのが特徴です。

浄土真宗の初盆の準備
お盆という概念がない浄土真宗ですが、初盆の時期になると他の仏教宗派同様に法要を行います。ここからは、浄土真宗の初盆の迎え方や法要の手配について詳しく解説します。
僧侶への連絡は「初盆の1か月前」が目安
浄土真宗は初盆と同じ時期に「歓喜会(かんぎえ)」とよばれる法要を行います。歓喜会とは先祖に感謝する日で、僧侶を呼んで読経をしてもらうのが一般的です。法要の流れは、一般的なお盆の法要とほぼ変わりません。
読経を依頼する僧侶には、初盆の1か月前までに連絡をしましょう。お盆の時期は初盆にかかわらず法要が多く、僧侶も多忙になります。直前に連絡すると、すでにスケジュールが埋まっていて依頼できないこともあります。なるべく早めに手配を済ませておきましょう。
基本的には自分の先祖のお墓がある菩提寺(ぼだいじ)の僧侶に依頼しますが、菩提寺が分からない、遠方にあるなど事情がある場合は、仲介業者を通じて読経を行ってくれる僧侶を探すことができます。
法要に招きたい人にも早めの連絡を
お盆の時期であっても、仕事がある方や宿泊先の手配が必要になる遠方の方もいます。招待したい方には、早めに案内状を送付しましょう。初盆までに時間の余裕がある場合は、招待する方の都合がつく日程を確認したうえで、法要の日程を決定してもよいでしょう。
日程だけでなく、会場や会食を行うかどうかも伝えておきましょう。また、簡易法要を近親者のみで行う場合は、礼服着用の必要性も連絡します。
会食の手配をする
会食を行う場合は、一般的に法要を行う会場内や会場の近くで食事の場を設けます。僧侶にも必ず会食の参加可否を確認しておきましょう。
会食や会場を手配する際は、人数変更やキャンセルの期日も確認します。また、招待客に食物アレルギーがないか把握しておくことで、メニューをスムーズにきめることができるでしょう。
浄土真宗の初盆に必要なもの
浄土真宗の初盆に必要なものは、法要の形式によって異なります。ここからは、一般的に初盆で必要になるものを紹介します。簡易法要の場合は不要なものもあるので、準備物について迷った際は、法要を行う会場や招待する僧侶に問い合わせてみましょう。
祭壇の飾り
一般的な初盆準備とは異なり、浄土真宗では精霊棚を設けません。また、祭壇に送り⽕・迎え⽕、ナスやキュウリで作った精霊馬も不要です。浄土真宗の初盆に必要なものは以下のとおりです。
| 切子灯籠(きりことうろう) | 地域によって異なるが、浄土真宗の盆提灯は切子灯籠 |
| 打敷(うちしき) | 仏壇に敷く敷物で、浄土真宗は逆三角形の形 |
| 供笥(くげ) | 果物やお菓子は供笥と呼ばれる仏具に供える。地域によっては、その上にお菓子や果物を重ねる「お華束(おけそく)」を用意する |
| 和ろうそく | 先端が太いイカリ型の白いろうそく |
| 線香 | 浄土真宗では線香は寝かせた状態で焚く |
僧侶へのお布施
僧侶に渡すお布施は、3万円~5万円程度が一般的です。僧侶を自宅に招いて法要を行う場合は、加えて1万円程度をお車代として渡します。また、僧侶が会食を辞退された時は、御膳料として5,000円~1万円程度渡しましょう。
お布施袋は「御布施」「御経料」と黒墨で書かれた白無地の封筒を使用しましょう。お布施袋は手渡さずに、盆などに乗せて渡します。お布施・御膳料・お車代とそれぞれ封筒を分けて用意しておくのがマナーです。
参列者への返礼品
お供え物や香典をいただいた場合は、「返礼品」と呼ばれるお返しをします。一般的には、1,500円~3,000円程度のタオルや菓子折り、お茶などを用意しておきます。参列予定人数に加えて、予備として1,000円程度の返礼品を準備しておくと安心です。
いただいた香典が高額だった場合は、後日カタログギフトなどを郵送します。香典返しは「半返し(いただいた額の2分の1程度)」が主流とされていますが、気持ちを添える意味もあるため、必ずしも半返しにする必要はありません。感謝の気持ちを込めた返礼品を送るようにしましょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
浄土真宗の初盆では、「歓喜会(かんぎえ)」と呼ばれる法要が行われます。改めて先祖を偲び、命について考え感謝して過ごしましょう。
浄土真宗の初盆は一般的な初盆とやや異なるため、不安に感じることもあるかもしれません。一番大切なことは、阿弥陀如来様に感謝する気持ちです。この記事で解説したことを参考に、初盆の準備をしてみてください。
小さなお葬式では、葬儀に精通したコールスタッフが、24時間365日通話料無料でご連絡をお待ちしています。葬儀にかかわるお悩みだけでなく、初盆やお盆に関する疑問についてもお答えします。お困りの際は、ぜひ小さなお葬式にお問い合せください。


初七日とは故人の命日から7日目に行われる法要のことです。ホゥ。












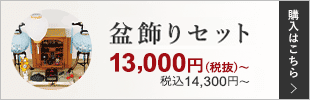
20190425094722_7101405897.jpg?fm=webp&h=108&w=170&fit=clip)





















