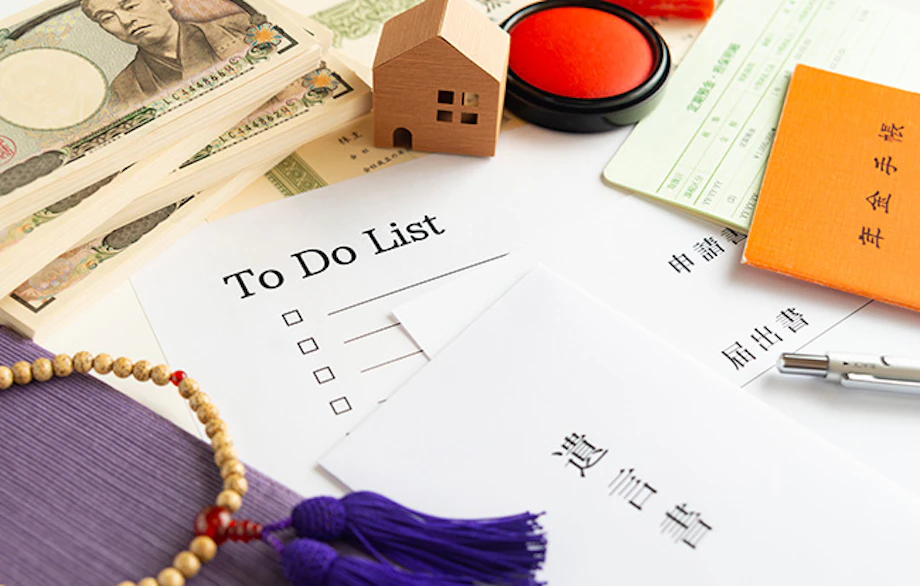家族が亡くなった際には、行わなければならない手続きがたくさんあります。気が動転していたり、深く悲しんでいたりしても、おろそかにするわけにはいきません。漏れのないように進めるためには、死亡手続きに関するチェックリストを活用するのがおすすめです。
そこでこの記事では、死亡当日から3年後までに必要な手続きについて、時系列順に紹介します。あらかじめ、全体の流れを理解しておけば、慌てずに済むでしょう。
<この記事の要点>
・死亡診断書の受け取りと親族への連絡、葬儀手配
・葬儀・告別式、出棺・火葬、初七日法要の実施
・葬儀後~3年以内に行うべき確認事項と公的機関へのさまざまな書類提出
こんな人におすすめ
大切な方が亡くなったら時何をしたらいいのかわからない方
死亡後の手続きについて知りたい方
死亡届等の手続きの流れを知りたい方
【死亡当日】死亡直後の手続き
家族が亡くなった当日には、まず医師から死亡診断書を受け取ります。その後、遺体を安置場所に移動させるために、葬儀社の手配も必要です。また、親族や職場への連絡や、菩提寺への連絡なども行います。死亡直後の手続きについて詳しく確認してみましょう。
死亡診断書の受け取り
病院などで家族が亡くなった際には、医師によって死亡が確認されます。その上で、医師に死亡診断書を作成してもらいましょう。自宅で亡くなった場合にも、死後診察を受けて、医師に死亡診断書を作成してもらいます。
また、事故など、生前に診療を受けていた傷病ではない理由で死亡するケースもあるでしょう。そのような場合には、死亡診断書ではなく死体検案書が発行されます。
<関連記事>
死亡診断書の発行料金は?発行方法や発行後の受け取り方を解説
親族や職場への連絡
故人が亡くなった事実を、近親者や職場の人達に連絡しましょう。思いついた人に連絡をするのではなく、連絡をする前に連絡先リストを作成すれば、確実に伝えられます。
伝える内容は、取り急ぎ、亡くなった事実のみで十分です。ただし、通夜・葬儀の日程や場所が決まっているのであれば、あわせて伝えましょう。
葬儀社の手配
遺体を搬送しなければならないため、葬儀社をすぐに手配する必要があります。ただし、葬儀内容について検討中ということであれば、搬送だけを依頼する葬儀社を手配することも可能です。
葬儀内容については、故人が葬儀についての希望を持っていたかを確認しておきましょう。エンディングノートなどに書き残している場合もあるため、確認した上で、葬儀形式を決め、葬儀社を選びます。葬儀社を選ぶポイントは、葬儀プラン、費用、選択可能なオプションなどです。
遺体の搬送
自宅で亡くなった場合には搬送の必要はありませんが、病院で亡くなった場合、遺体は一時的にしか安置してもらえないため搬送が必要です。自宅もしくは葬儀社の安置場に搬送してもらいましょう。
また、病院から搬送する際には、そのタイミングで退院手続きを行います。入院費の清算などができるように、費用を準備しておきましょう。
菩提寺への連絡
菩提寺がある場合には、故人が亡くなったことを連絡し、僧侶の都合を確認しましょう。その上で、葬儀社の担当者と打ち合わせを行います。
葬儀の日程、場所、内容などを決め、菩提寺にも葬儀を執り行うことをお願いしなければなりません。葬儀会場は、参列者数、アクセスなどを考慮して、規模や場所を決めましょう。
【2日目】葬儀前に必要な手続き・通夜
死亡の翌日にも、しなければならないことがあります。葬儀の日を迎える前に行うのは、死亡届や火葬許可申請書の提出、そして通夜です。具体的に説明していきますので、全体の流れを把握しましょう。
死亡届の提出
死亡届の提出について、以下の表にまとめました。
| 死亡届の入手方法 | 死亡届は死亡診断書に付属していることが一般的。自治体の戸籍係でも入手可能 |
| 死亡届の提出期限 | 亡くなったことがわかった日から7日以内 |
| 死亡届の提出先 | 故人の本籍地がある役所、本人が他界した地の役所、届け出をする人の居住地の役所のいずれか |
| 死亡届を提出する人 | 親族、または他界した人と同居していた人 |
| 死亡届提出の際の必要書類 | ・死亡診断書 ・死亡届 ・届け出た人の身分がわかるもの ・届け出た人の印鑑 |
死亡診断書と死亡届は原本を提出する必要がありますが、提出すると書類は返却されません。しかし、生命保険の請求などに死亡届を提出することになるため、提出前にコピーを取っておけば、後々慌てずに済みます。
<関連記事>
葬儀に必要な日数とは?2日間で行う場合の流れ
火葬許可申請書の提出
火葬の許可を得るには、火葬許可申請書を提出しなければいけません。火葬許可申請書の提出期限や提出先は以下の通りです。
| 火葬許可申請書の提出期限 | 厳密な決まりはないものの、許可が下りなければ火葬はできないため、死亡届と同様に速やかな提出が必要。 |
| 火葬許可申請書の提出先 | 死亡届と同じく役所の戸籍係に提出する。 死亡届を出した人が火葬許可申請書を出す必要がある。 |
通夜や葬儀を終えたら遺体を火葬して弔うことが一般的です。火葬は手続きなしでできるものではなく、許可が下り次第行えるようになっているため、確実に手続きをしましょう。
通夜
通夜は、葬儀の前日に執り行うのが一般的です。喪主を決め、葬儀社と打ち合わせをして進めましょう。遺族の役割は、通夜当日に参列者を出迎えること、遺族代表としての挨拶をすること、終了後に参列者を見送ることなどです。
通夜の後には「通夜振る舞い」と呼ばれる会食の席を設ける地域もあります。親族の意向、地域の慣習などによっても通夜の形態は異なることに注意が必要です。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
【3日目】葬儀・火葬
必ずしも亡くなってから3日目に限ったわけではなく、火葬場や参列者の都合などによっても変わりますが、通夜の翌日には、葬儀・告別式が執り行われます。その後、出棺、火葬、初七日法要と続く流れを紹介します。
葬儀・告別式
葬儀社と打ち合わせをした内容に沿って、葬儀・告別式を執り行います。葬儀社と事前に確認しておくべきことは次の通りです。
・喪主を誰が担うか
・受付担当などの役割分担
・席次
・葬儀・告別式当日の流れ
・会場・祭壇などの準備
・弔電の受け取り
葬儀・告別式も通夜と同様に、親族の意向、地域の慣習などによっても形態が異なります。
<関連記事>
お葬式にかかる時間はどれくらい?日程や流れを確認しよう
出棺・火葬
葬儀・告別式終了後は出棺し、同日に火葬を行うのが一般的です。献花などをして故人と最後のお別れをした後に、棺を霊柩車に乗せて、火葬場へ運びます。
喪主は火葬許可証を携帯して同乗し、他の親族は自家用車やタクシーなどで会場に移動します。火葬にかかる所要時間は1時間程度です。
火葬済み証明の受け取り
火葬の際に提出する「火葬許可証」は、火葬が終わると、火葬執行済みの印が押されて返却されます。この押印された火葬許可証は火葬済み証明となり、納骨の際に必要です。
一般的には、火葬後すぐに納骨せず、四十九日法要以後に納骨します。納骨までは、押印された火葬許可証を保管しておき、納骨の際に墓地などに提出しましょう。
初七日法要
本来、初七日法要は、亡くなった日を含めて7日目に執り行うものです。三途の川の渡り方が決まる日とされており、遺骨の前で僧侶が読経を行います。
ただし、最近では、葬儀後に再び遺族らが集まることは難しいため、葬儀当日の火葬後に、初七日法要を執り行うことが一般的です。法要後は「精進落とし」と呼ばれる会食を行います。
【5日目~7日目】葬儀後の手続き
葬儀を終えると一区切りにはなりますが、葬儀後にしなければならない手続きがいくつかあります。チェックリストを確認しながら進めていきましょう。葬儀社への支払い、納骨の準備、遺言書の確認の3点について解説します。
葬儀社への支払い
葬儀が終わったら、葬儀社から発行される請求書を確認し、支払いをします。終了後1週間程度で発行されるのが一般的ですが、葬儀社によっては葬儀当日に現金で支払うケースもあるでしょう。どのタイミングで支払う必要があるのか、事前に確認しておくと安心です。
葬儀代を支払うと、葬儀社から領収書が発行されます。葬祭費の申請手続きに必要であるため、保管しておきましょう。
納骨の準備
納骨はいつまでにしなければならないという決まりはありませんが、四十九日法要後に行うケースが一般的です。
実施時期や納骨方法などを親族で話し合って準備を進めていきましょう。納骨に招待する参列者が多い場合には案内状を作成します。また、納骨後には会食をするのが一般的です。
遺言書の確認
故人に相続対象となる遺産がある場合は、遺言書があるかどうかを確認しておきます。遺言書に遺産を相続できる人が書かれている場合は、遺言書通りに相続の手続きを行いましょう。遺産を相続した人は相続税の支払いが発生することも覚えておく必要があります。
遺言書がない場合は民法の規定に従います。どのような遺産があるか、相続人の対象になるのは誰かなどによって、相続手続きが複雑になることもあるでしょう。相続関係で問題が発生した場合は、弁護士に仲介してもらった上で話を進めていくことがおすすめです。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
【10日目】死亡日から10日以内に必要な手続き
亡くなった人が年金を受け取っていた場合は、年金事務所や年金相談センターで手続きをします。ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、原則手続きは必要ありません。
年金の受給資格があるのは存命の間のみです。死亡届が必要な場合は、他界後、受給資格が失われたことを申請するために、死亡日から10日以内に年金事務所などに届け出をしておく必要があります。
亡くなったことを申請せずにいるといつまでも亡くなった人に対して年金が支払われます。亡くなっていることが発覚したとき、亡くなった月の翌月分からの受給額を全額返金しなければならないので、後に大きな問題となるかもしれません。
【11日目~14日目】死亡日から14日以内に必要な手続き
死亡日から14日以内に必要な手続きは複数あるため、漏れがないように注意しておきましょう。公的な手続きばかりなので、ひとつずつ事前に確認しておくことが必要です。国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、世帯主に関わる手続きについて解説します。
国民健康保険資格喪失届の提出
日本では公的医療保険に加入することが義務付けられているため、加入者が亡くなった場合には、資格喪失届を提出する必要があります。
公的医療保険には企業に雇われている人が加入している健康保険、公務員が加入している共済組合、自営業者らが加入している国民健康保険などがあり種類によって届け出先が異なります。
健康保険の場合は勤務先へ、共済組合の場合は所属する自治体の共済組合へ、国民健康保険は市町村に届け出をします。届け出はそれぞれの医療保険で期限が異なるので注意しましょう。国民健康保険資格喪失届の提出期限は14日以内です。
後期高齢者医療保険資格喪失届の提出
故人が後期高齢者であった場合には、後期高齢者医療保険資格喪失届の提出が必要です。提出期限は、死亡日から14日以内と定められています。
提出先は、故人の住民票があった市区町村の役場です。後期高齢者医療資格喪失届に記入して提出する際には、後期高齢者医療被保険者証も返却しましょう。
介護保険資格喪失届の提出
健康保険と同様に、介護保険についても、介護保険資格喪失届を提出しなければなりません。故人の住民票があった市区町村の役場に、死亡日から14日以内に提出しましょう。提出する際には、介護保険被保険者証も忘れずに返却します。
なお、故人が要介護(要支援)認定を申請中であった場合には、申請の取り下げ手続きが必要となるケースがあることも覚えておきましょう。
世帯主の変更手続き
世帯主が逝去した場合、役所で世帯主の変更手続きが必要です。世帯がもともと成人の二人だけであればこの手続きは不要ですが、逝去した世帯主以外に15歳以上の人が二人以上いる世帯であれば世帯主を変更しなければなりません。
提出期限は世帯主が亡くなったことがわかった日から14日以内です。葬儀を終えて状況が落ち着いたら、新しい世帯主の身分証明書と印鑑を持って早めに役所に行きましょう。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
【1か月】死亡日から1か月以内に必要な手続き
緊急性は薄いものの、死亡日から1か月以内にしなければならない手続きもあります。時間がたつと手続きを行うことを忘れてしまいやすくなるため、気を付けましょう。
ここでは、雇用保険受給資格証の返還、銀行等金融機関の手続き、各種名義変更の手続きについて解説します。先送りにせず、順番に着手していきましょう。
雇用保険受給資格証の返還
故人が雇用保険を受給していた場合には、死亡日から1か月以内に、雇用保険受給資格証を返還しなければなりません。雇用保険を受給していたハローワークに返還しましょう。
返還の際には、雇用保険受給資格者証に加えて、故人の死亡の事実がわかる書類(死亡診断書や住民票など)が必要です。
銀行等金融機関の手続き
故人が銀行口座を所有している場合は、口座を持っている銀行に他界したことを連絡しておかなければなりません。銀行は口座所持者が他界したことがわかると、所持している口座を凍結します。
簡単にお金を引き出せなくすることによって、遺族間のトラブルを防止することにつながります。2019年7月に故人の銀行口座取り扱いに関わる民法の改正があり、一定額であれば預貯金が引き出せるよう変更されました。
逝去すると葬儀の準備などでお金が必要です。どのくらいの費用が必要になるのかを周りと相談して、その分を故人の口座から引き出すことを検討してもよいでしょう。
各種名義変更の手続き
故人が所有、契約していたものは、いずれも名義変更しておく必要があります。名義変更が必要なものとしては以下があります。
・土地・不動産
・自動車
・電話や公共料金
・クレジットカード
・パスポート
・運転免許証
・携帯電話やプロバイダー
故人が所有していたもの、契約していたものを一覧に書き出しておき、それぞれの名義変更を着実に行っていきましょう。
【3か月】死亡日から3か月以内に必要な手続き
相続人が相続放棄をする場合には、家庭裁判所に、相続放棄の申述をしなければなりません。申述期間は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内と定められています。
相続放棄の申述先は、故人の最後の住所地の家庭裁判所と定められています。必要な書類は、相続放棄の申述書に加えて、故人や申述人の戸籍謄本などです。
<関連記事>
形見とは何?該当するものや適さないもの、形見分けの注意点もご紹介
【4か月】死亡日から4か月以内に必要な手続き
本来であれば確定申告をするはずだった人が、年の途中で亡くなった場合、死亡した日までの所得金額・税額を相続人が計算して、所轄税務署に「準確定申告」をしなければなりません。申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
【1年】死亡日から1年以内に必要な手続き
遺留分の請求は、被相続人が死亡した事実と遺留分を侵害する遺言書や生前贈与を知ったときから1年以内にしなければなりません。
遺留分とは、一定範囲の相続人について、故人の財産から、法律上、最低限保障されている取り分のことです。
不平等な遺言や贈与などによって、遺留分に相当する財産を受け取れなかった相続人は、財産を遺贈された人や贈与を受けた人に対して、侵害額に相当する金銭を請求できます。この権利を遺留分侵害額請求権といいます。
【3年】死亡日から3年以内に必要な手続き
亡くなった人が生命保険に加入していた場合は、速やかに保険金の受け取り手続きを行います。この手続きは保険契約者か保険金受取人のどちらかしか行えませんので、保険金受取人に指定されている人が手続きを行いましょう。
死亡診断書、保険金請求書、契約者の住民票、受取人の戸籍抄本と印鑑、保険証券を用意し、加入している生命保険会社に連絡をします。保険会社の担当者がわかるのであれば、そちらに連絡をすることでスムーズに手続きができるでしょう。
ただし、生命保険の請求には、保険法で3年の時効が定められていることに注意が必要です。死亡してから3年が過ぎると、保険金の支払いを請求する権利が消滅してしまいます。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
よくある質問
死亡後の手続き、チェックリストに関して、よく寄せられる3つの質問を集めました。それぞれに対する回答を紹介しますので、参考にしてみてください。
Q1:死亡時の手続きの順番は?
死亡後から初七日法要までの期間に行う主な手続きの順番は次の通りです。
・死亡診断書の受け取り
・親族や職場への連絡
・葬儀社の手配
・遺体の搬送
・菩提寺への連絡
・死亡届の提出
・火葬許可申請書の提出
・通夜
・葬儀・告別式
・出棺・火葬
・火葬済み証明の受け取り
・初七日法要
葬儀が終わってからも、役所での手続きや各種名義変更手続きなど、さまざまな手続きが必要です。
Q2:親が死亡したときの手続きチェックリストはありますか?
親が死亡したときの手続きチェックリストは、Web上で公開されているため、好みに応じて活用しましょう。
また、小さなお葬式では「喪主が必ず読む本」を無料でプレゼントしています。この中にも、親が死亡したときの手続きが書かれていますので、ぜひ参考にしてみてください。

Q3:死亡後の手続きに必要な書類は?
死亡後の主な手続きにおける、必要書類を以下の表にまとめました。
| 主な手続き | 必要書類 |
| 死亡届の提出 | ・死亡届 ・死亡診断書 ・届け出た人の身分がわかるもの ・届け出人の印鑑 ※同時に火葬許可申請書も提出する |
| 健康保険の資格喪失手続き | ・資格喪失届 ・保険証 ・死亡を証明する書類(戸籍謄本など) ・届け出人の本人確認書類(マイナンバーカードなど) |
| 介護保険の資格喪失手続き | ・資格喪失届 ・介護保険被保険者証 など |
| 世帯主変更の手続き | ・世帯主変更届 ・窓口で申請する人の本人確認書類 ・国民健康保険の保険証(加入している場合のみ) |
| 死亡保険金の請求手続き | ・死亡保険金請求書など保険会社所定の書類 ・保険証券 ・死亡診断書のコピー ・被保険者の死亡記載のある住民票 ・保険金受取人の本人確認書類 など |
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
死亡後の手続きにはさまざまな種類のものがあります。チェックリストを活用すれば、いざというときにも漏れなく進められるでしょう。
死亡後の手続きのチェックリストに関する疑問などがある場合は、お気軽に小さなお葬式へお問い合わせください。専門知識を持つスタッフが、お悩みに寄り添い丁寧にアドバイスいたします。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



葬儀費用は相続税から控除することが可能です。ホゥ。