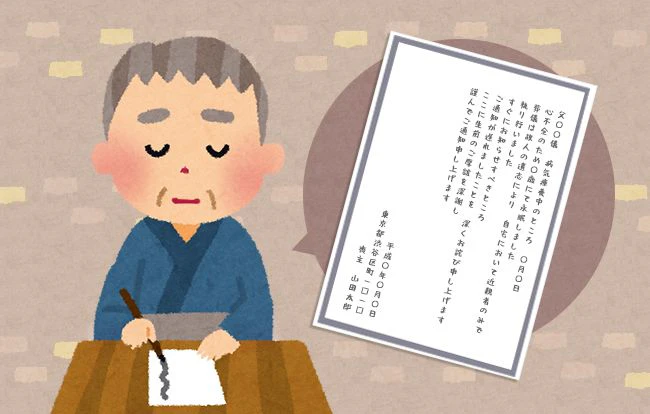親が死亡したら銀行口座が凍結されると聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。凍結されるタイミングや理由を知っておくと、戸惑うことなくスムーズに手続きができます。
亡くなった親の銀行口座を料金支払いの引き落とし口座として使っている場合は、準備が整ってから手続きするとよいでしょう。預貯金口座の引き継ぎも、遺言書の有無で手続き内容が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。この記事では、親の死亡後の銀行口座の凍結について解説します。
<この記事の要点>
・親名義の銀行口座は、銀行に死亡した旨を伝えることで初めて凍結される
・銀行口座の凍結前に、あらかじめお金を引き出しておくなどの対策が必要
・凍結された口座を引継ぐ方法は、遺言書の有無によって異なる
こんな人におすすめ
死亡後の銀行の手続きについて知りたい方
預貯金口座の引継ぎ方法を知りたい方
銀行口座の凍結前の確認事項を知りたい方
銀行に死亡の連絡をした段階で口座が凍結される
親の死亡後、親名義の銀行口座は親族が銀行に死亡した旨を伝えることで初めて凍結されます。銀行口座は、親が亡くなった後に勝手に凍結されるわけではありません。親の死亡後にどのような流れや理由で銀行口座が凍結されるのかを確認しましょう。
死亡後すぐに凍結されることはない
親が死亡した病院や死亡届を提出した役所から銀行に情報が漏れることはないため、銀行口座がすぐに凍結されることはありません。
銀行口座が凍結されるのは、親族が銀行に口座の名義人が死亡したことを連絡したときです。銀行に連絡を入れた方は、死亡した名義人との関係を銀行に確認されます。銀行の相続担当部署が口座の凍結を行います。
あまりないケースではありますが、会社の社長や著名人であれば、新聞のお悔やみ欄などメディアの報道により銀行口座の凍結が行われることもあります。ただし、凍結前に親族に連絡が入るため勝手に凍結されることはありません。
銀行口座が凍結される理由
銀行口座が凍結される理由は2つあります。1つ目は、死亡した日時での相続財産を確定させるためです。親が死亡した後の親名義の預貯金は、相続財産の対象となります。
2つ目は、死亡した親の預貯金を遺族が勝手に引き出すことを防ぐためです。相続財産のひとつである死亡した親の預貯金は、一時的に共有財産として管理されます。具体的に相続財産の分配の仕方が決まるまで、銀行口座はひとまず凍結されるのです。
キャッシュカードの暗証番号が分かれば、お金の引き出しは可能です。遺族の誰かが持ち去ってしまわないためにも、できるだけ早く銀行口座の凍結を行いましょう。銀行口座を凍結する背景には、「預貯金は名義人が亡くなってもその人のものである」という考え方があります。
銀行口座の凍結前に行う対策
死亡後の銀行口座の凍結に備えて、親が生前のうちに行える対策があります。親が死亡した場合、葬儀などにまとまった金額が必要になります。あらかじめ準備を進めておけば、資金面で困らなくて済むでしょう。ここからは、銀行口座の凍結前の準備について解説します。
お金を引き出す
事前にお金を引き出して現金化しておく方法です。親の死亡後であっても、相続人全員の合意があれば、銀行口座の凍結前にお金を引き出しても問題ありません。
後できちんと清算できるように、葬儀費用や介護費用などの領収書を保管しておきましょう。また、現金の保管にも注意が必要です。
生命保険に加入する
生命保険に加入すれば、死亡後に保険金を受け取って葬儀費用などに充てられます。領収書を保管しておくと相続時に清算できます。生命保険金は指定された受取人の財産となるため、相続人同士で話し合う必要もなくスムーズに受け取れるでしょう。
複数の口座を整理
故人が複数の銀行口座を持っていた場合は、それぞれが凍結されるため、凍結解除の手続きが煩雑になりがちです。
特に、海外に銀行口座や証券口座を開設している場合には、できるだけ生前のうちに解約し、口座の数を整理しておいたほうがよいでしょう。銀行口座が限られていれば、財産の確定や凍結解除もしやすくなります。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
死亡後に銀行口座をすぐに凍結したほうがよいケース・困るケース
親の死亡後に銀行口座をすぐに凍結したほうがよいかどうかは、状況によって異なります。財産を巡ってトラブルが起きそうな場合は、できるだけ早く凍結したほうがよいでしょう。
そうでない場合は、亡くなった親の銀行口座凍結後に困ることがないか十分に考えてから凍結しましょう。ここからは、銀行口座を凍結したほうがよいか状況別に解説します。凍結解除の手続き前に現金が必要になった場合に利用できる「仮払い制度」についても、あわせて紹介します。
銀行口座をすぐに凍結したほうがよいケース
死亡した親に多額の財産があり、財産争いが起きそうな場合はすぐに銀行口座を凍結しましょう。キャッシュカードや暗証番号を知っていれば、親族以外でも簡単にお金を引き出せます。相談することなくお金を引き出してしまいそうな方がいる場合は特に注意が必要です。
手続きや分配を決める前に相続財産の一部を誰かが引き出してしまうと、親族間で大きなトラブルにつながる恐れがあります。死亡した親の銀行口座にある財産は、手続きを行った上で正確な分配が決められます。親が残した財産が多いほど財産争いは起こりやすいため、早めの行動が重要です。
<関連記事>
故人の銀行口座の死亡手続きに必要なことは?必要書類や預金相続の手順を紹介
銀行口座を凍結すると困るケース
死亡した親の銀行口座で普段から家計のやりくりをしていた場合や、各種料金の引き落とし口座に設定していた場合は銀行口座を凍結してしまうと支払いが滞ってしまいます。口座が凍結されると、引き出しも引き落としもできないため、お金の管理も今までどおりにはいきません。
お金に困らないようにするためには、準備を終えてから銀行に親が死亡したことを伝えましょう。特に、各種料金の引き落とし口座はひとつずつ確認しながら口座設定の変更をする必要があります。
遺産分割前の仮払い制度も活用できる
遺産分割を行い、銀行口座の凍結を解除するまでには、ある程度の時間がかかります。葬儀費用や当面の生活費のために現金が必要になった場合、一定の金額であれば法定相続人が故人の預貯金を引き出せる制度が「仮払い制度」です。
ただし、この制度を利用した場合は、相続放棄ができなくなってしまう可能性がある点に注意が必要です。
凍結された口座の預貯金残高を引き継ぐ方法
死亡した親の遺言書があるかどうかで、凍結された口座の預貯金残高を引き継ぐ際に必要な書類は異なります。ここからは、遺言書がある場合とない場合それぞれについて、凍結された口座の預貯金残高を引き継ぐ流れを解説します。
遺言書がある場合
凍結された口座の預貯金残高を引き継ぐには、預金を払い戻す方法が一般的です。遺言書を用意して、金融機関の担当者を予約に残高証明書の発行を希望する旨を伝えると、手続きもスムーズです。
銀行に行くときは、残高証明書の請求に必要な書類をそろえて持参しましょう。必要なものは、以下のとおりです。
・通帳
・死亡記載のある戸籍謄本
・法定相続人が分かる戸籍謄本
・実印
・印鑑証明
この際、預金の払い戻しに必要な「相続手続き依頼書」を受け取りましょう。
相続手続きの記載事項を記入して書類提出をする際に必要なものは、以下のとおりです。
・遺言書および家庭裁判所の検認が済んでいることが確認できる書類
・死亡した方の戸籍謄本
・受遺者・遺言執行者の印鑑証明
・遺言執行者選任審判書
・受遺者・遺言執行者の実印
・通帳
・キャッシュカード
書類提出後は、2週間程度で代表相続人の口座に預金が振り込まれます。振り込まれた預金は、代表相続人がほかの相続人に分けるのが一般的です。
遺言書がない場合
遺言書がない場合も、預貯金残高の引き継ぎは預金の払い戻しが一般的です。口座を凍結したら、銀行の担当者を予約して残高証明書の請求を行います。必要な書類は、以下のとおりです。
・通帳
・死亡記載のある戸籍謄本
・法定相続人が分かる戸籍謄本
・実印
・印鑑証明
遺言書がある場合と同様に、「相続手続き依頼書」を受け取っておきましょう。
相続財産の確定と相続人の確定を行った後、財産の分配を協議して、結果を遺産分割協議書にまとめましょう。
相続手続き依頼書に必要事項を記入して、相続人全員の署名と実印を押し、相続依頼手続き依頼書とともに以下の書類も提出します。
・遺産分割協議書
・死亡した方の戸籍謄本
・法定相続人が分かる戸籍謄本
・通帳
・キャッシュカード
・相続人の実印
・印鑑証明
書類提出後、2週間程度で代表相続人の口座に預金が振り込まれます。振り込まれた預金は、代表相続人がほかの相続人に分けましょう。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
凍結後の手続きをしないほうがよいケースとは?
死亡した親の銀行口座が凍結された場合、すぐに凍結解除に向けて手続きを始めなければならないと考える方もいるかもしれません。しかし、手続きをせずそのままにしておいたほうがよいケースもあります。
相続放棄・限定承認
相続する財産は資産だけとは限りません。借金や未払いの税金などの負債があった場合は、マイナスの財産を相続することもあるでしょう。負債のほうが多い場合は、そのまま相続すると支払いが生じてしまうため、相続放棄もしくは限定承認のどちらかを選ぶのが一般的です。
相続放棄は、資産も負債もすべて相続しないことを指します。一方で、限定承認とは、資産の範囲でのみ負債を相続することです。
口座の残高が少ない
銀行口座の凍結解除には、書類の提出などの手間と時間がかかります。それでも銀行口座に資産が残っているのであれば問題ありませんが、残高が少ない場合には手間をかけずに放っておく方法もあります。まずは残高を調べ、凍結解除をするかどうかよく検討することが大切です。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
親が死亡した際、故人を偲ぶことも大切ですが、銀行口座の凍結や預貯金残高の引き継ぎなど、必要な手続きを行うことも重要です。
死亡した親の銀行口座の凍結は、各種料金の支払いやクレジットカードの引き落とし口座に設定されていないかを確認した上で行いましょう。確認しないまま凍結の手続きを行うと、引き落としができなかったり督促状が届いたりしてしまいます。
預貯金残高を引き継ぐ手続きの流れは、遺言書の有無によって異なります。それぞれのケースを確認してから、手続きをしましょう。
小さなお葬式では、葬儀関係のサービス以外にも相続のお手伝いもしています。セットプランや必要な内容のみサポートをする個別プランもあるため、慣れていない方にもおすすめです。不安や分からないことがある方は、小さなお葬式へご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
口座凍結後は公共料金などの引き落としはどうなるの?
役所が銀行に死亡を伝えることはある?
銀行に死亡の連絡をするとほかの銀行にも伝わるの?
連絡をしていないのに口座が凍結されたのはなぜ?
銀行に死亡の連絡をしないと法的に違法?
凍結された口座を解約せず放置するとどうなるの?

一日葬とは、通夜をはぶいた葬儀形式のことです。ホゥ。