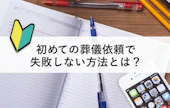これまで葬儀に出たことがある人でも、喪主の役割は分からないという方もいるのではないでしょうか。そこでこの記事では、喪主が行う事柄を具体的にご紹介します。喪主を決める方法や、喪主が遠方に住んでいる場合どうしたらいいかなど、喪主の全体像をつかめるでしょう。
<この記事の要点>
・喪主とは葬儀のすべてに責任をもつ主催者のこと
・喪主は葬儀プランを決定し、弔問客の対応などが求められる
・喪主は参列者からの香典を管理する必要がある
こんな人におすすめ
喪主を今後務める可能性のある方
喪主の意味と役割について知りたい方
喪主の決め方を知りたい方
喪主とは何か
まずは喪主の役割を大まかにご説明します。喪主がもつ2つの顔を理解することで心構えができるでしょう。
喪主と混同しやすい施主についても解説します。ひとつの葬儀に喪主と施主が両方存在するのはどのようなときでしょうか。具体的なケースもご紹介します。
喪主の役割
喪主には主に2つの大きな役割があります。遺族を代表することと、葬儀を主催することです。たとえば遺族の代表として行うことのひとつに、喪主の挨拶があります。見たり聞いたりしたことがある人も多いでしょう。葬儀に来てくれたことや、生前故人を助けてくれたことへの感謝を述べます。
また喪主は葬儀のすべてに責任をもつ主催者です。葬儀が最初から最後まで滞りなく進むように気を配り、トラブルが発生したら喪主の判断で解決します。
喪主と施主の違い
施主とは葬儀の費用を出す人です。一般的には喪主が施主を務めますが、喪主と施主が別でも葬儀の主催者や親族の代表が喪主であることは変わりません。施主はあくまでも金銭面を負担します。
ではどのようなケースで喪主と施主が別になるのでしょうか。一例としては喪主が故人の配偶者で高齢の場合です。子どもが葬儀の費用を負担し、施主になることがあります。ほかに、葬儀の費用を故人が勤めていた会社が負担する場合があり、そのときの施主は会社です。喪主が未成年で支払い能力がないときには、親族が施主になることもあるでしょう。
葬儀における喪主の役割
ここでは喪主が行なう具体的な内容を見ていきます。葬儀を主催するうえでどれも大切な役割ですから、準備から葬儀当日まで気をつけるポイントを押さえましょう。
喪主というと葬儀での役割と思われるかもしれませんが、葬儀後も対応することがあります。葬儀が終わると気持ちが緩んで忘れてしまうこともあるので、注意が必要です。
葬儀の手配
喪主の仕事は葬儀を準備するところから始まります。葬儀社に連絡して資料を集めたり、予算や参列者の人数に合わせて葬儀プランを考えたりするのも喪主です。
葬儀社が決まったら、日程から祭壇、葬儀の内容などをひとつひとつ相談して決めていきます。宗教や宗派によって異なる部分もあるので、慎重に確認していきましょう。
葬儀の日程や場所が決まったら、弔問客へ連絡します。葬儀に呼ぶのは、故人の親族や友人・知人、会社関係者などです。
弔問客の対応
葬儀当日は弔問客が到着した際に挨拶したり、葬儀前後の空いた時間に声をかけたりします。弔問客への対応に責任をもつのも喪主です。忙しい中、故人を弔う葬儀に足を運んでくれたことへのお礼などを伝えましょう。
飲み物や食事を提供する場合は、すべての人に行き渡っているか気を配ることも必要です。足りなければ、家族やスタッフに声をかけて対応をお願いします。
僧侶への対応
菩提寺など、お付き合いのあるお寺があれば連絡しましょう。あてがなければ、葬儀社が手配してくれることもあるので相談します。
式の長さや順序などで要望があれば、事前に相談しましょう。お布施の金額や支払い方法も忘れずに確認します。
葬儀当日は、僧侶が葬儀場へ着いたら挨拶し案内します。休憩できる場所があれば、待機所として使ってもらうといいでしょう。読経を行う僧侶ののどが乾かないように、飲み物を切らさない配慮も必要です。僧侶が帰る際は、感謝の挨拶をして見送ります。
金銭管理や葬儀後の対応
喪主が施主を兼ねる場合は葬儀費用を支払いますが、金銭の扱いはそれだけではありません。参列者からの香典も管理する必要があります。受付で受け取った香典を最後に取りまとめ、どのように使うかを決めるのは喪主です。葬儀費用に充てたり、ほかの法要の機会に使ったりもできます。
葬儀が終わったあとは、後片付けもしっかり確認します。葬儀をサポートしてくれた関係者へはお礼を伝えましょう。香典返しを葬儀後に送る場合は、漏れなく届くようにチェックします。
喪主になる人はだれか
ここまで喪主の役割を紹介してきましたが、誰が喪主になるのかはどのように決めるのでしょうか。喪主を決める方法は比較的自由です。家族でなくても喪主になれます。喪主の決め方にはどのような方法があるのか、いくつかのパターンをご紹介しましょう。
喪主の優先順位
喪主は故人との続柄で決めるのが一般的です。優先順位もある程度決まっていて、故人の配偶者が最も優先されます。故人に配偶者がいなければ長男、続いて次男というように移っていきます。以下が優先される順位です。
| 優先順位 | 続柄 |
| 1 | 配偶者 |
| 2 | 長男 |
| 3 | 次男以降の直系の男子 |
| 4 | 長女 |
| 5 | 次女以降の直系の女子 |
| 6 | 故人の両親 |
| 7 | 故人の兄弟姉妹 |
高齢や病気などの理由で優先順位の上位者が喪主を務めるのが難しい場合は、優先順位を必ず守る必要はありません。家族で相談し、全員が納得のいく喪主を決めましょう。
生前の故人をよく知る人が喪主代理となることもできる
故人に家族がいても、家族以外が喪主になることもあります。その人と故人が親しく、関係が深い場合です。
ただし、このケースには故人の親族や家族の理解と協力が必要です。費用は故人の家族が負担し、葬儀の内容もある程度家族の希望を反映したものにする必要があるでしょう。家族や親族以外が喪主を務めるには、親族を取りまとめられる人物であることも大切です。
喪主になる人は比較的自由に決められる
前述のとおり優先順位に基づいて喪主を決めるのが一般的ですが、守らなければいけないルールではありません。
喪主は比較的自由に選ぶことができます。たとえば、兄弟などが複数人で喪主を務めるケースです。この場合は葬儀の費用や手配などの負担を分担できるのがメリットといえるでしょう。
ときには血縁が重視されて女性が喪主を務めるケースもあります。関係者で話し合い、故人を見送る儀式の中心になるにふさわしい人を喪主に選ぶことが大切です。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
喪主は葬儀に関わるひとつひとつを決定し、滞りなく行われるよう気配りすることが必要です。たくさんのことに対応しなければいけないので突然喪主になると、戸惑うこともあるでしょう。生前からどんな葬儀を希望するのか、喪主は誰に務めてほしいのかなどを相談しておくと、いざというときにスムーズに進められます。
小さなお葬式では生前から葬儀のご相談を承っております。専門スタッフにお客様の疑問や不安をお聞かせください。通話無料のフリーダイヤルもご利用いただけます。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
血縁者がいない場合喪主はだれがやるの?
喪主の妻は何をしたらよい?
喪主はどのような服装で参列すべき?
喪主は香典や供花を出すべき?
喪主になる人が遠方に住んでいる場合どうしたらよい?
喪主と故人の宗教が異なる場合はどうしたらよい?

東京や一部の地域では7月、ほかの地域では8月にお盆を迎えることが多いようです。ホゥ。