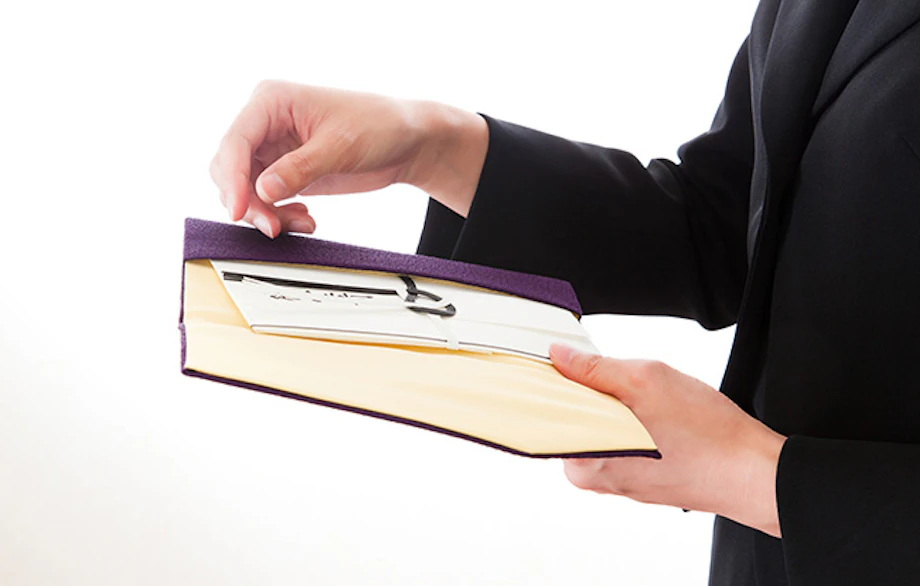創価学会は、大乗仏教の日蓮大聖人の仏法を信奉する宗教法人です。一般的な仏教の宗派とは異なり、創価学会は「友人葬」と呼ばれる独特な葬儀を行います。そのため、初めて友人葬に参加する場合、香典のマナーや作法などが分からないという方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、創価学会の葬儀である「友人葬」における香典のマナーを解説します。葬儀全般のマナーや作法についても解説するので、初めてでもスムーズな参列が可能です。ぜひチェックしてみてください。
<この記事の要点>
・創価学会の友人葬では香典は必要ないが用意しておくと安心
・香典袋の表書きは「御霊前」や「御香料」と書き、薄墨を使うのがマナー
・内袋の表面には金額、裏面には住所や氏名を書く
こんな人におすすめ
創価学会の葬儀(友人葬)の香典について知りたい方
創価学会の葬儀(友人葬)の香典の書き方・マナーを知りたい方
創価学会の友人葬で香典以外に気をつけるマナーを知りたい方
創価学会の葬儀(友人葬)は香典を持参しなくてよい
仏教の一般的な葬儀では香典が必要ですが、創価学会の友人葬の場合は、香典は必要ありません。創価学会員であれば普通の感覚かもしれませんが、会員ではない方であると「本当に香典は必要ないのか」と不安に感じることもあるでしょう。
基本的に香典は必要ありませんが、喪主の意向や地域性などによって香典を受け取るケースや完全に受け取らないケースがあります。念のため香典は用意しておき、どのような状況にも対応できるようにしておくと安心でしょう。
創価学会の葬儀(友人葬)の香典の仏式に則った書き方・マナー
創価学会は「友人葬」という独特な葬儀を行うため、「何か特別な書き方があるのでは」と感じる方もいるかもしれません。しかし、実際には「友人葬だから」と特別な書き方をする必要はないので安心しましょう。
香典袋や内袋は、通常の仏式に則って記載すればマナー違反とはなりません。こちらでは、香典袋や内袋の書き方、お札の入れ方について解説をします。
香典袋の表書き
友人葬における香典袋は、仏式に則って表書きを書くのが一般的です。表書きは、「御霊前」や「御香料」と書きましょう。香典袋の上部に表書き、下部には自分の氏名を記入します。
表書きを書く際は、薄墨の筆ペンや毛筆を使用しましょう。香典は、基本的に薄墨で書くのがマナーです。薄墨は「悲しみで力が入らず薄くなってしまった」「悲しみの涙によって墨が薄くなってしまった」という意味があることから、香典は薄墨で書くのがマナーとされています。
弔事用として薄墨の筆ペンが販売されているので、文具店などで探してみましょう。筆で書いたような字体の「弔事スタンプ」がありますが、使用してもマナー違反ではありません。しかし香典を受け取った遺族の価値観によっては、気にされる可能性もあります。そのためできればスタンプではなく、毛筆や筆ペンで書きましょう。
<関連記事>
香典袋の書き方は?宗教ごとの違いや渡す際のマナーなどを解説
香典の内袋の書き方
表書きだけではなく、内袋についてもしっかりと記入しなくてはいけないことがあります。内袋には自分の住所や氏名、金額を記入しましょう。内袋の表面には金額、裏面には住所や氏名を書きます。金額を書く際は、漢数字の大字を使う点がポイントです。たとえば、5,000円であれば「金五阡円」と記入します。
内袋は毛筆や筆ペンではなく、黒いペンで書いてもマナー違反ではありません。受け取った遺族が、何と書いてあるか分かりやすくすることが大切です。自分が書きやすいものを選んで書きましょう。
内袋に住所や氏名を書く欄がある場合は、その欄の中に記入をします。欄がない場合は、縦書きで書きましょう。
香典袋へのお札の入れ方
香典は、お札の入れ方にも注意をしなくてはいけません。まずは、お札の向きや表裏の確認をしましょう。人物が描かれているほうが表、描かれていないほうが裏です。上下は、お札を縦にしたときに左側に金額があるほうが上、右側の人物が描かれているほうが下として定義されています。
お札は内袋の表面に対して、お札が裏を向くように入れましょう。内袋がないタイプの香典袋の場合は、香典袋の表面に対してお札が裏を向くように入れます。上下は、人物が描かれているほうを上にするケースや、下にするケースがあるため、年長者などに確認をするとよいでしょう。
お札が裏を向くようにするのは、「顔を伏せる」という意味合いがあるとされています。お札が表を向いている場合、マナー違反となるので注意をしましょう。
創価学会の葬儀(友人葬)で香典を渡す場合は2,000円~3,000円が一般的
創価学会の友人葬で香典を渡す場合、金額の相場は2,000円~3,000円です。あまり高額な金額を包んだ場合、受け取った側が気にしてしまう可能性があるので、相場に合わせることをおすすめします。
一般的な仏教の葬儀の香典であると、友人や知人の葬儀は3,000円~1万円、親族の場合は1万円~10万円が相場です。一般的な仏教の葬儀の相場と比較すると、低い金額であることが分かるでしょう。
創価学会の葬儀(友人葬)で香典以外に気をつけておくべきマナー
創価学会の友人葬は、一般的な仏教の葬儀とは異なるマナーがあるので注意しましょう。香典以外で特に注意が必要なマナーは、「焼香」「供花」「服装」「数珠」の4つです。どのマナーも、守るのはそれほど難しくはないでしょう。事前に把握をしておけば、マナーを守ってスムーズに参列ができます。
友人葬での焼香のマナー
焼香は、自我偈が読まれているときに行います。司会者が焼香を案内してくれるので、指示にしたがって焼香をしましょう。
焼香の前には遺族へ一礼をしてから、祭壇へと進みます。焼香は、3回行うのがポイントです。右手の親指と人差し指、中指でお香をつまみ、目を閉じて額の高さまで上げます。そして、つまんだお香を静かに香炉の中へと落としましょう。これらの動作を3回行い、遺影に合掌礼拝をしてから、遺族へ一礼をして席に戻ります。
友人葬での供花のマナー
供花は、白い生花やシキミを用いるのが一般的です。少しであれば菊や洋花などを供花として使用してもよいとされてきました。最近では「白い生花」にとらわれず、色彩豊かな花で遺影や祭壇を飾り付けするケースもあります。
花を送りたい方は、遺族に確認をとってから送りましょう。遺族によっては、ほかの花は一切いれずにしきみだけとする方もいます。もし遺族の意向と異なる花が送られてきた場合、遺族が気にしてしまう恐れがあるので注意が必要です。
友人葬に参列するときの服装
服装においては、友人葬だからといって特別に規定されていることはありません。一般的な葬儀と同様に、男女ともに喪服を着用しましょう。
男性の場合の「フォーマルスーツ」「ネクタイ」「靴下」「靴」は、黒に統一します。女性も男性と同様に、黒のフォーマルウェアで構いません。ただし、スカート丈は普段よりも長めにするのがポイントです。「通夜」「葬儀」「告別式」ともに、同じ服装で参列ができます。
<関連記事>
告別式・葬儀での服装について
友人葬で使用される数珠
創価学会の友人葬では、会員は両手にかけられる長い数珠を使用します。創価学会の会員でなければ、普段使用している数珠を使用してもマナー違反ではありません。使い慣れた数珠を使用しましょう。
しかし「周りの多くの方が、長い数珠を使っていると気になる」という方もいるかもしれません。その場合は、友人葬に数珠自体を持参しないという方法もあります。不安な方は、数珠を持参せずに参列をしましょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
創価学会の友人葬は、基本的に香典の必要はありません。遺族の意向によって、香典を受け付けている場合と、受け付けていない場合があります。香典を渡す場合の相場は2,000円~3,000円であるため、念のため3,000円前後を包んで持参するのがおすすめです。
友人葬に参列する際は、マナーに則りスムーズに参列することが重要となります。初めて友人葬に参加する場合、作法やマナーなどが分からず、不安な思いをするかもしれません。不安があれば、葬儀のプロにご相談ください。
小さなお葬式では、葬儀に関する事前のご相談もお電話で24時間365日、承っております。葬儀の準備やマナーにお悩みがある方は、お気軽にご利用・ご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



自身が亡くなったときのために、エンディングノートを書いておくのもおすすめです。ホゥ。