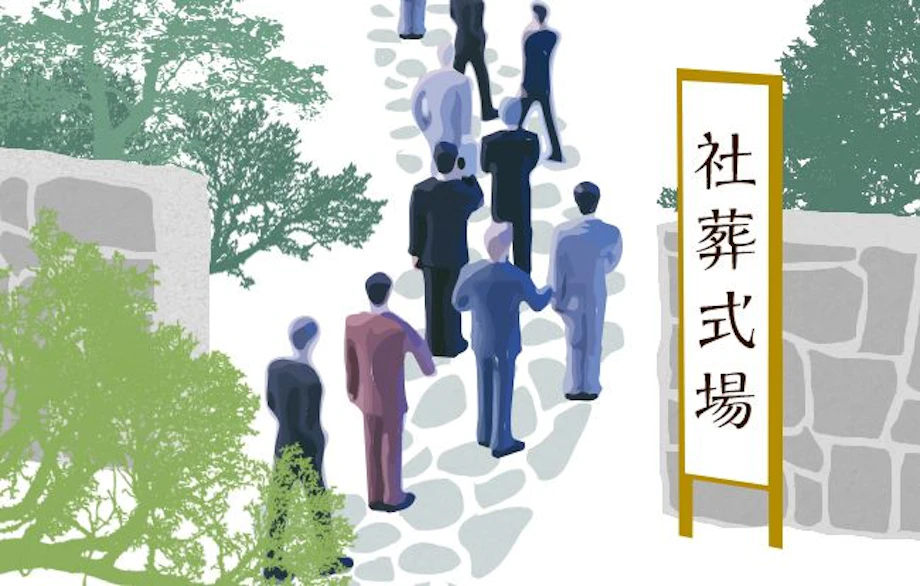会社の重役や、功績があった方が亡くなった場合、関係者を多数招いて社葬(しゃそう)を行うことがあります。一般的に、社葬は大規模に行い、「追悼式」の意味があります。また、準備するための期間が必要となるため、亡くなったすぐに、まずは遺族中心の密葬を行い、火葬をしてから2週間以降に社葬を行うことが多いようです。
この記事では、社葬のメリットや気を付けたいマナーについてご紹介します。
<この記事の要点>
・社葬は、費用の大部分を「福利厚生費」として計上できます
・社葬は故人の業績を振り返るとともに、これからの会社のあり方を示す機会になります
・事前に社葬の内容を協議し、ガイドラインや名簿を作成しておくことが大切です
こんな人におすすめ
社葬の流れを知りたい方
社葬のメリットを知りたい方
社葬の対象になる方をしたい方
社葬のメリット
1.遺族の負担を軽減できる
影響力のある方が亡くなると、多数の関係者に連絡を取らなければなりません。必然的に葬儀の規模も大きくなり、費用も高額になります。
そこで、葬儀を社葬として行うと、葬儀にかかる費用の大部分を「福利厚生費」として計上することができます。式場や棺、霊柩車に葬儀の案内状などが経費となります。規模の大小はありますが、社葬規模の葬儀費用はおよそ500万円から2,000万円といわれています。 遺族がすべて負担するのは大変ですが、社葬として企業が施主となることで、大規模な葬儀を執り行うことができるのです。墓石や位牌、戒名料、精進落としなどの飲食費等は含まれませんが、遺族にとっては大きな助けとなります。
2.会社のイメージアップ
会社の経営者が亡くなった場合は、社葬は後継者を披露する場となります。故人の業績を振り返るとともに、これからの会社のあり方を示す機会となります。さらに社葬は取引先、社員、株主など、会社に関係する人々を始め、一般の人々に対してイメージアップの場ともなり得ます。社葬をしっかり執り行うことにより、きちんとした会社だという印象を周囲に与えることができ、社員の結束力も高まるなど、企業にとって重要な行事になります。
社葬を執り行う場合に気をつけたいマナー
社葬には色々なメリットがありますが、裏を返せば「絶対に失敗できない」のが社葬だともいえます。
葬儀の際、社員たちがおしゃべりをしている。受付の対応、言葉遣いが悪い。そういったことで、会社に対するイメージは大きく下がってしまいます。また、遺族への連絡不足や配慮不足から、社葬後に不満が残ってしまうこともあります。故人と付き合いのあった企業や関係者をきっちり把握しておかなければなりません。
社葬について、社内であらかじめ協議をし、ガイドラインや名簿を作成しておくなど、しっかり事前準備をしておくことが大切です。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ
まとめ
社葬は故人を偲ぶ場であるとともに、社会に対して企業の組織力や広報的な意味合いを持ったりする場でもあります。社葬を行う場合は事前に準備を行い、社内で柔軟な連携を取って協力することが大切です。いざという時困らないように、葬儀全般に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618へお電話ください。



「お悔やみ申し上げます」は通夜や葬儀の定型句なので、宗派を気にせず使えます。ホゥ。