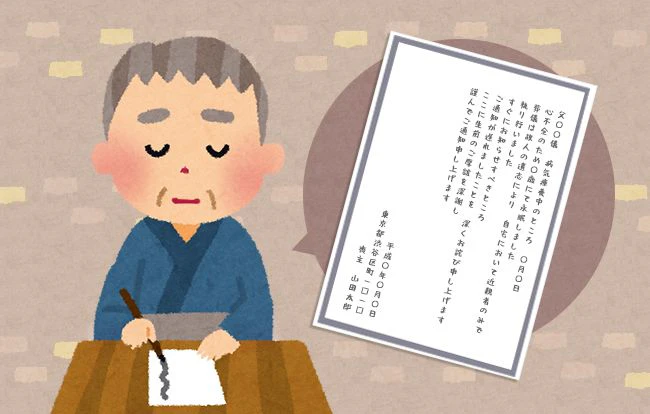家族が亡くなった際、周囲への訃報連絡はどのようにすればよいのでしょうか。身内の不幸を伝える際は、相手のことを考えて慎重になる必要があります
この記事では、訃報の伝え方や伝える内容についてわかりやすく解説します。文例も紹介しているので、万が一のときは参考にしてみてください。
また、ご不幸があった場合は「家族が亡くなったら|あなたが今すぐやらなければならないこと」の記事をご覧ください。葬儀全体の流れについてあわせてご確認することもおすすめです。
<この記事の要点>
・訃報連絡とは、亡くなった方の親族や友人などに対し、死の一報を知らせること
・訃報連絡は、電話でするのが一般的だが、手紙やメールなどを使う場合もある
・連絡内容は、故人との関係性、亡くなった日時、連絡先などを簡潔に伝える
こんな人におすすめ
訃報連絡の方法を知りたい方
訃報連絡で伝える内容を知りたい方
「訃報」と「葬儀案内」の違いを知りたい方
訃報とは?葬儀案内との違いは
人が亡くなったことを知らせる「訃報」は頻繁にあることではないので、聞いたことがあっても実際にどのような案内をすればよいか詳しく知らない方も多いでしょう。訃報と似たお知らせに葬儀の案内がありますが、本来は別物です。まずは、訃報と葬儀の案内の役割と違いを解説します。
訃報とは
「訃報(ふほう)」とは、誰かが亡くなったことを電話やメールなどで知らせることです。人が亡くなると、通夜や葬儀・告別式などが執り行われますが、訃報はあくまでも家族などが亡くなったという事実のみを取り急ぎ伝えるものです。
訃報は死亡確認後、なるべく早めに「故人の名前」「享年」「喪主の名前」「連絡先」などを伝えます。葬儀の日程が決まっていれば、訃報と同時に日時や場所を含めた詳細を伝えることもあるでしょう。
訃報と葬儀の案内の違い
訃報と葬儀の案内は異なるものですが、訃報連絡に葬儀の案内が含まれることは多くあります。葬儀の案内は日取りや式場が決まってから出すものなので、親族や親戚など近しい人以外は葬儀の案内で訃報に接することとなるでしょ
葬儀の案内では訃報と同じく「故人の名前」「享年」「喪主の名前」「連絡先」などに加え「亡くなった日」「通夜・葬儀の日程と場所」「宗派」など、通夜・葬儀参列に必要な情報も知らせます。身内だけで葬儀を行う場合は、その旨もきちんと伝えましょう。
訃報連絡は誰にする?
訃報と葬儀の案内は厳密には違うものですが、近年は2つを同時に連絡するケースも増えています。訃報連絡をする相手は、葬儀に来てほしい人です。
故人の親族をはじめ、友人や知人、勤務先、自治体や地域の方など生前お世話になった方に連絡します。葬儀の詳細が決まっておらず訃報のみ伝える場合は、急ぎ連絡したい方にだけ連絡するようにしましょう。
遺族は訃報連絡のほかに忌引きの手続きも必要です。連休を取る場合は引き継ぎをする必要もあるので、自身の勤務先にも早めに連絡しましょう。
訃報の連絡方法
親族や友人など近しい人が亡くなったときは、ショックや悲しみから関係者への連絡や葬儀の準備など、行動を起こせないこともあるかもしれません。
しかし、故人と生前深く関りのあった方には、なるべく早く訃報を届けることが大切です。いざというときに落ち着いて行動できるように、ここからは訃報の伝え方を紹介します。
参考動画:訃報の連絡の仕方【小さなお葬式 公式】 動画が見られない場合はこちら
基本の連絡手段は「電話」
訃報は迅速かつ確実に伝える必要があるため、電話が適しています。言い間違いや聞き間違いがないように伝えましょう。
連絡が必要な方のリストを事前に作成しておくと、慌てずに連絡できるのでおすすめです。「すぐに連絡する必要がある人」「通夜・葬儀の日程が決まってから連絡する人」と分けておくとスムーズです。
メールやSNS
友人や知人に伝える場合、メールやSNSなどを用いることもあります。しかし、これらの手段は訃報を知らせる正式な方法とはいえず、こうした連絡方法をよく思わない方もいるため注意が必要です。
特に、目上の方にメールで知らせる場合は十分配慮しましょう。人によってはメールを見ていないこともありますので、メールで通知をした後に電話でも伝えると確実です。
手紙・死亡広告
手紙は故人が亡くなったことを、大勢の方に知らせるのに有効な手段です。「死亡通知書」として、はがきや手紙などの書面で郵送します。詳しくは、死亡通知書についての記事をご覧ください。
また、広い交友関係を持っていた方や、社会的に立場が高かった方が亡くなった場合は「死亡広告」が利用されることもあります。死亡広告は不特定多数の方が訃報を知るのに有効な方法です。死亡広告についてはこちらの記事を参考にしてください。
訃報を連絡する順番
訃報連絡には以下の優先順位があります。
1. 家族など親族
2. 故人の友人・知人・会社関係者・学校関係者など
3. 遺族の関係者(上に同じ)
4. 町内会・近所の方
親族は、おおむね三親等辺りまでの範囲に知らせるようにします。その範囲外であっても、故人と縁が深ければ知らせたほうがよいでしょう。臨終に立ち会えなかった親族や故人と親しかった方には、相手の気持ちを考慮しできるだけ早く伝えることが大切です。
自宅で葬儀を行う場合など、町内会や近所の方の協力が必要な場合は早めに連絡します。
通夜や葬儀に参列していただきたい遠方の方には、移動時間を考慮して優先順位に関係なく迅速に訃報を伝えましょう。通夜や葬儀についても、速やかに決定・通知できるように、葬儀社・菩提寺などへの連絡も忘れないようにします。
訃報連絡で伝える内容
電話で訃報を伝える場合は、亡くなった事実を手短に伝えることが大切です。長電話は相手の迷惑になってしまうので、気をつけましょう。
まずは「知らせる」ということに集中して、葬儀の日程や場所などは詳細が決まってから改めて連絡しましょう。
伝える内容は大きく5つ
訃報連絡をする際に伝える内容は、以下の5点です。
・電話主と故人の関係性
・故人の氏名
・故人の死亡日時
・死因(簡潔に)
・緊急連絡先
通夜・葬儀の詳細も同時に通知する場合は、葬儀の日程や会場・形式・宗派・香典、供花についても伝えましょう。
訃報連絡が来た場合、故人との最後のお別れに駆けつけたいと思う方も少なくありません。家族葬で香典や供花を辞退する場合などは、その旨をきちんと伝えて失礼のないようにしましょう。
訃報連絡だけの場合
親族や故人と縁の深い知り合いなどには、亡くなった事実だけを早めに連絡します。葬儀については訃報とは別に改めて連絡しましょう。
離れたところから駆けつけてもらう場合は相手の移動時間を確認して、来てもらいたい場所(病院、安置先、自宅など)を指定します。
葬儀連絡なども含む場合
遠縁の親戚や親族以外の方などには、葬儀の詳細が決まったタイミングで訃報と通夜・葬儀の連絡を行います。伝える内容は、「誰がいつ亡くなったのか」「通夜・葬儀の日程と様式」「喪主の名前と間柄」です。
喪主の名前と間柄は忘れがちですが、弔電を送る際に必要なので必ず伝えましょう。会社関係者や地域関係者へは、代表者に訃報連絡をして必要な方に伝えてもらいます。
家族葬を行う場合は、その旨も必ず伝えましょう。知らせておかないと弔問客が訪れて、多くの方に迷惑をかけてしまいます。家族葬を執り行う際は、混乱を避けるために葬儀後にハガキで死亡通知書としてお知らせするのもひとつの方法です。
【シーン別】訃報連絡の文例
訃報で最低限伝えたい内容は「故人の名前」「訃報を伝えた人と故人の間柄」「緊急連絡先」です。故人との関係性や、通夜・葬儀を行うかどうかによって伝える内容は変わります。
身内が亡くなって間もないタイミングだと、気が動転してしまうこともあります。伝える内容をメモに整理しておくと、落ち着いて短時間で必要事項を伝えられるでしょう。ここからは、シーン別の訃報連絡の文例を紹介します。
電話での訃報連絡 | 親族の場合
「〇〇の長男の△△と申します。以前より入院していた父の〇〇が、〇月〇日の早朝に息を引き取りました。遺体は〇〇に安置しております。通夜は〇〇斎場で、明日〇月〇日〇時から行います。告別式は〇月〇日〇時です。宗派は〇〇式(宗教形式)で執り行う予定です。何かあれば私の携帯にご連絡ください。電話番号は090-××××-××××です。」
電話での訃報連絡 | 故人の友人の場合
「突然のお電話申し訳ありません。〇〇の長男の△△です。以前より入院していた父の〇〇が、〇月〇日の未明に死去しましたことをお知らせ申し上げます。生前は大変お世話になりましたこと、心から感謝申し上げます。」
葬儀を行う場合
「通夜は〇〇斎場で、明日〇月〇日〇時から行います。告別式は〇月〇日〇時からです。
喪主は私△△が務めます。宗派は〇〇式(宗教形式)で執り行う予定です。面会などご連絡いただく際には、私の携帯へお願いいたします。電話番号は090-××××-××××です。」
家族葬・密葬の場合
「葬儀は故人の生前の意思により家族だけで行いますので、葬儀へのご参列につきましては失礼ながらお断りさせていただきます。」
電話での訃報連絡 | 故人の会社の場合
「お世話になっております。営業部〇〇の息子の△△です。以前より入院していた父が、〇月〇日〇早朝に亡くなりました。通夜は〇〇斎場で、明日〇月〇日〇時から行います。告別式は〇月〇日〇時です。お手数をおかけいたしますが、関係者のみなさまにお伝えいただければと思います。
喪主は私△△が務めさせていただきます。何かございました際には、私の携帯にご連絡ください。電話番号は090-××××-××××です。」
メールでの訃報連絡文例
【訃報】○○死去のお知らせ
父〇〇がかねてより病気療養中のところ、令和〇年〇月〇日、〇歳にて永眠いたしました。ここに生前のご厚誼を深謝し、謹んで通知申し上げます。
尚、この度の葬儀に関しましては故人ならびに家族の意思によって、家族のみで行うことに致します。葬儀へのご参列、お供え、お花、ご香典は、失礼ながら辞退とさせていただきます。何卒よろしくお願い申し上げます。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ
まとめ
訃報には、故人が亡くなった事実を迅速かつ確実に親族や友人などに知らせる役割があります。遺族は悲しみのさなかでも、訃報連絡や葬儀など多くの手続きをする必要があります。万が一のときも慌てず行動できるように、事前準備をしておくことが大切です。
「小さなお葬式」ではご遺族の負担を軽減し、どなたにもご満足していただける葬儀プラン・サービスのご提供を目指しています。お客さまサポートダイヤルでは、24時間365日通話料無料で専門スタッフがサポート体制を整えています。葬儀に関する疑問や不安についてお気軽にご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



初盆(はつぼん)とは、亡くなった方の忌明け後、最初に迎えるお盆のことです。ホゥ。