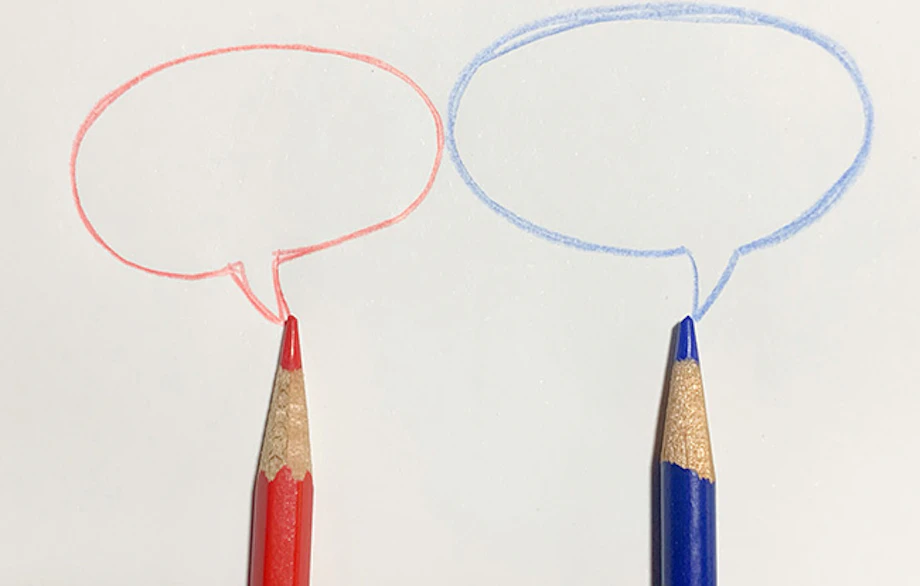葬儀の際や不幸があったときに、使用することが多い表現方法のひとつに「ご愁傷様」があります。普段日常的に使用する言葉ではないので、「ご愁傷様です」と言われたときに、的確な返答が分からず困ってしまった経験がある方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、「ご愁傷様です」という言葉の意味や、ベストな返事の仕方を紹介します。「ご愁傷様」以外の表現や、メールや英語での返答方法も解説しますので、参考にしてみてください。この記事を読めば、万が一の時にも社会人として的確な対応ができるようになるでしょう。
<この記事の要点>
・「ご愁傷様です」は、基本的にお悔やみの言葉として使うことがほとんどである
・「ご愁傷様です」と言われた場合の返事は、「恐れ入ります」や「痛み入ります」が一般的
・返事の仕方に決まりはないが、重ね言葉や忌み言葉は避けるのがマナー
こんな人におすすめ
身内にご不幸があった方
「ご愁傷様です」といわれたときの返答に困りそうな方
「ご愁傷様です」の意味は?
「ご愁傷様です」は、葬儀や法事のときに使うことが多く、「何となく悲しい言葉」として認識している方も多いでしょう。具体的にどういった意味があるかは、意外と知られていないかもしれません。
しかし、的確な返事ができるようになるためには、言葉の由来や意味をしっかりと把握しておく必要があります。
「ご愁傷様です」の言葉の由来
「ご愁傷様です」で使う「愁」の字は、「うれえる」「うれい」と読み「なげき悲しむ」「思い悩む」という意味です。また「傷」には、「きず」「けが」以外にも「心をいためる」「つらくおもう」といった意味があります。
この2つの由来から、「心をいためることを悲しく思う」ということを表現できる言葉であることが分かります。
また、そこに丁寧語である「ご」と「様です」を付けることで、自分自身ではなく特定の相手に捧げる心遣いの言葉になることを覚えておきましょう。
お悔やみの気持ちを伝える言葉
基本的には、お悔やみの言葉として使うことがほとんどです。知人の身内にご不幸があった場合やトラブルに見舞われた場合などに、「あなたが心を痛めていることを悲しく思います」「私もあなたと同じように悲しい」と伝えるために使用します。
弔事で使う場合は、悲しみに暮れるご遺族への心遣いとして「この度は、ご愁傷様でございます」と伝えるのが一般的です。
皮肉やからかいを込めた言葉
親しい関係の方に、相手への冷やかしとして皮肉を込めて「ご愁傷様です」と言うこともあります。本来は「嫌なことがあって気の毒」という気持ちを伝えるために使用しますが、この場合は「嫌なことがあった」の部分にフォーカスを当てているイメージです。
「本当に嫌な気分でしょう?」「ドンマイ」といった意味になりますが、本来の使用方法とは異なり、また配慮に欠けた言葉とも捉えられるので使う方は少ないでしょう。
「ご愁傷様です」を使うシチュエーションは?
「ご愁傷様です」は話し言葉なので、自分と相手との会話の中で使用するのが一般的です。そのため手紙や弔電など、文章として表すときには使いません。
「ご愁傷様です」を使うのはどのようなシチュエーションでしょうか。基本的には言葉の意味と同じく2通りですが、いくつかのシーンに分けて具体例を紹介します。
会葬時の挨拶
葬儀やお通夜に参列するときには、ご遺族に対し「この度はご愁傷様です」「突然のことで、ご愁傷様でございます」などと言葉をかけます。
参列者が「ご愁傷様です」と遺族に声をかける主なタイミングとしては、以下の通りです。
・受付のとき
・焼香のとき
・会食のとき
参列者が遺族の近くを通ったときにも、声をかけることがあります。参列者からの、「少しでもご遺族の心に寄り添いたい」という心遣いなので、タイミングは人によって場合によってさまざまです。
友達との会話
親しい間柄の友達に対して「ご愁傷様です」と言うこともあります。この場合は、からかいや皮肉を込めた意味になります。
友達に対して「ご愁傷様です」を使うタイミングの一例は、以下の通りです。
・友達に嫌なことや理不尽な出来事が起きた場合
・同僚に残業やトラブルが舞い込んできた場合
どのケースも「頑張ればなんとかなる」ときに使用するのが一般的です。相手が深く傷ついていたり、深刻な出来事が起きたりしたときは使用しません。
ビジネスシーン
「ご愁傷様です」の言葉は、親戚や友達だけでなく取引先の方や目上の方へといった、ビジネスシーンで使用することも可能です。以下は使用するタイミングの一例として確認しましょう。
・取引先の方の身内に不幸があったことを知ったとき
・同じ会社の上司の身内に不幸があったとき
・会社関係者の葬儀に参列したとき など
ただし、「ご愁傷様です」という言葉は話し言葉であるため、メールや手紙で使用しないように気を付ける必要があります。
「ご愁傷様です」と言われた場合のベストな返事の仕方
身内に不幸があり自分が遺族だった場合、参列者や知人から「ご愁傷様です」と言葉をかけられることがあるでしょう。
実は「ご愁傷様です」という言葉に対する、返事の仕方には明確な決まりはありません。ただし、一般的に行われる返事のパターンは、ある程度決まっています。
「ご愁傷様です」の言葉に対する、具体的な返事の仕方をいくつか実例にして紹介しますので、確認しましょう。
「恐れ入ります」と「痛み入ります」
広く使われる返事のひとつは、「恐れ入ります」です。似たような意味の言葉として「痛み入ります」も使用できます。
2つの言葉の意味は、「相手のご厚意に恐縮する」「心苦しいほどありがたく思う」といったような意味があり、どちらも「ご愁傷様です」と言われたときの無難な返事といえるでしょう。
「恐れ入ります」と一言伝えた後に、今の心境や家族の状況などを伝えると丁寧で、心遣いをくれた方へのお礼の心を伝えやすくなります。
「ありがとうございます」
「ありがとうございます」と返事をするときには、以下のように言葉を付け加えて使用します。
・ご丁寧に、ありがとうございます
・お心遣い、ありがとうございます など
気遣ってくれている気持ちに対しての感謝であることが、しっかりと伝わるよう配慮が必要です。
ただ単に「ありがとうございます」という言葉のみを使用すると、「不謹慎」「縁起が悪い」と感じる方もいます。この言葉を使用する際は、単体で使用しないように気を付けましょう。
「生前はお世話になりました」
「ご愁傷様です」の返事には、「生前はお世話になりました」という言葉も使用できます。生前故人が親しくしていた方に、感謝を伝えるための言葉です。
この言葉を伝えるときは、「恐れ入ります」など他の言葉と一緒に使用することで、より自然に気持ちを伝えることができます。以下の例文を参考にしましょう。
・恐れ入ります。生前は父がお世話になりました。
・お心遣い、ありがとうございます。生前は祖母がお世話になりました。
黙礼をする
大切な方が亡くなったときには、気持ちに整理が付かず、返す言葉が思いつかないこともあるでしょう。そのようなときには、何も言わずただ一礼するだけでも問題ありません。
相手のほうに体を向け、深くお辞儀をしましょう。「ご愁傷様です」と声をかけてくれたことに対する感謝の気持ちは、黙礼だけでもしっかりと伝わります。
重ね言葉は避けるのがマナー
返事の仕方に明確な決まりはありませんが、言葉の選び方で気を付けたいポイントはあります。
「重ね重ね」「くれぐれも」などの重ね言葉や、縁起の悪い言葉など忌み言葉は使用しないように気を付けましょう。不幸が続くことを連想させるため、弔事の場での使用は避けるのがマナーです。忌み言葉はさまざまありますので、一例を紹介します。
・わざわざ、いろいろ、ますます、日々、次々、最後に、浮かばれない、迷う、焦る、短い、相次ぐ、忙しい
ご愁傷様以外の使える言葉
弔事の際に使える言葉は、「ご愁傷様」だけではありません。似たような意味を持つ、別の言葉でお悔やみの気持ちを伝えることもあります。
遺族として法事に参列するときには、「ご愁傷様です」以外の言葉をかけられる可能性があることを事前に想定しておくとよいでしょう。ここでは、弔事で使用できる言葉をいくつか紹介します。
「お悔やみ申し上げます」
「お悔やみ申し上げます」という言葉は、「ご愁傷様です」をよりストレートに表現した言葉です。「故人が亡くなったことを悲しく思い、弔いの言葉を伝えます」という意味があります。
「ご愁傷様です」は、ご遺族への心遣いがメインでしたが、「お悔やみ申し上げます」の場合は、故人に対しても遺族に対しても悲しみの気持ちを伝える内容になっているのが特徴です。また、話し言葉ではないので、メールや手紙にも使用できます。
「ご冥福をお祈りします」
「ご冥福をお祈りします」もよく使います。「亡くなったあとの故人の幸福を祈ります」という意味で、遺族ではなく故人へ向けた言葉です。言葉の前に故人の名前を付け、「〇〇様の、ご冥福をお祈りいたします」と表現することもあります。
「冥福」は仏教でのみ使用する言葉で、キリスト教や神式の葬儀の際には使用しないのがマナーです。また、四十九日には故人が無事死後の世界に辿り着くと言われているため、それ以降の法要では使わないという特徴もあります。
「追悼の意を表します」
「追悼の意を表します」も、弔事のときに使用できる言葉です。「追悼」には、生前の故人を偲ぶことや、故人が亡くなったことを悲しむという意味があります。
そのため、「追悼の意を表します」とだけ伝えるのではなく、「お悔やみ申し上げます」や「ご愁傷様です」といった、遺族への心遣いを添えるのが一般的です。
また、直接的な面識のない方に対しても使用でき、災害や事件、事故などで亡くなった方に向けて使用することもあります。
その他の例文一覧
親しい間柄の方には、もう少しカジュアルな表現でお悔やみの気持ちを伝える場合もあります。一例は、以下のとおりです。
・大変でしたね
・突然のことで寂しくなります
・言葉が見つかりません
・本当に残念です
・お力を落とされませんように
「ご愁傷様です」や「お悔やみ申し上げます」といった言葉と一緒に使うと、より気持ちが伝わりやすくなります。また、いくら親しい間柄とはいえ目上の方には好まれない場合もありますので、注意が必要な表現方法とも言えるでしょう。
「ご愁傷様です」と同義の言葉を使用するべき特殊なケース
目上の方と話すときや、メールでやり取りするときなどは、使用する言葉に注意が必要です。また、ビジネスシーンでは英語を使う機会もあるかもしれません。
「ご愁傷様です」は、弔事に比較的良く使う言葉ではありますが、同じような意味を持つ別の言葉で伝えることが望ましいケースもあるため、詳しく確認しておきましょう。
メールのやりとりの場合
葬儀に参列できない場合には弔電や手紙を送るのが一般的ですが、まずはメールを送るという方も増えています。また、ビジネスシーンで、取引先の方の身内に不幸があったと耳にした場合にもメールでお悔やみを伝えることがあるでしょう。
メールでは話し言葉である「ご愁傷様です」は使わず、「お悔やみ申し上げます」と伝えるのがマナーです。以下の例文を参考にして、オリジナルの文章を作ってみましょう。
お悔やみ申し上げます
突然の訃報に接し驚きと悲しみに堪えません
仕事の都合により本日伺えないことを大変心苦しく思います
心よりご冥福をお祈り申し上げます
目上の方との会話の場合
会社の上司やご年配の親戚といった目上の方にお悔やみの言葉を伝えるときには、「です」ではなく「ございます」を使い、「この度はご愁傷様でございます」と伝えるとより丁寧な印象になります。
また、できるだけ簡潔に言葉をまとめるのも、目上の方への配慮となる重要なポイントです。
「この度は急なことで、ご愁傷様でございます。何かお手伝いできることがあれば、おっしゃってください」といったように簡潔にお悔やみの言葉を伝えましょう。
英語を使用する場合
知り合いが海外の方である場合には、英語でお悔やみの言葉を伝える機会もあるかもしれません。英語では、「I’m sorry(残念に思う)」や「Condolence(追悼)」「Sympathy(悔み)」といった表現を使用するとよいでしょう。例文は、以下の通りです。
・I’m sorry to hear about your loss.(お悔やみ申し上げます)
・Please accept my sincere deppest condolences.(追悼の意を表します)
・My sincerest sympathy are with you.(心中お察しします)
宗教による使い分け
神式葬儀やキリスト式葬儀に参列するときなどは、宗教によってお伝えする言葉が異なるので注意が必要です。
・仏式葬儀:ご冥福をお祈りします
・神式葬儀:御霊のご平安をお祈り申し上げます
・キリスト教式葬儀:安らかなお眠りでありますようお祈り申し上げます
特にキリスト教では、天国に召されるのは喜ばしいことと考えられています。「安らか」「お眠り」「旅立ち」など、宗教に関係なく使える言葉を使用するのがベストです。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
「ご愁傷様です」の言葉には、大切な方を亡くした遺族を思いやる気持ちが込められています。葬儀などで「ご愁傷様です」と声をかけられた場合には、「恐れ入ります」と返事をするとよいでしょう。
また、「ご愁傷様です」以外にもお悔やみの言葉は複数あります。宗教や状況により使用する言葉にも違いがあるので気を付けましょう。
お悔やみの言葉に対する返事の仕方以外にも、気になることやお困りのことがあれば、小さなお葬式にお気軽にご相談ください。小さなお葬式では24時間365日専門のスタッフがお客様をサポートいたします。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



全ての箇所を自筆する普通方式の遺言書を「自筆証書遺言書」と呼びます。ホゥ。