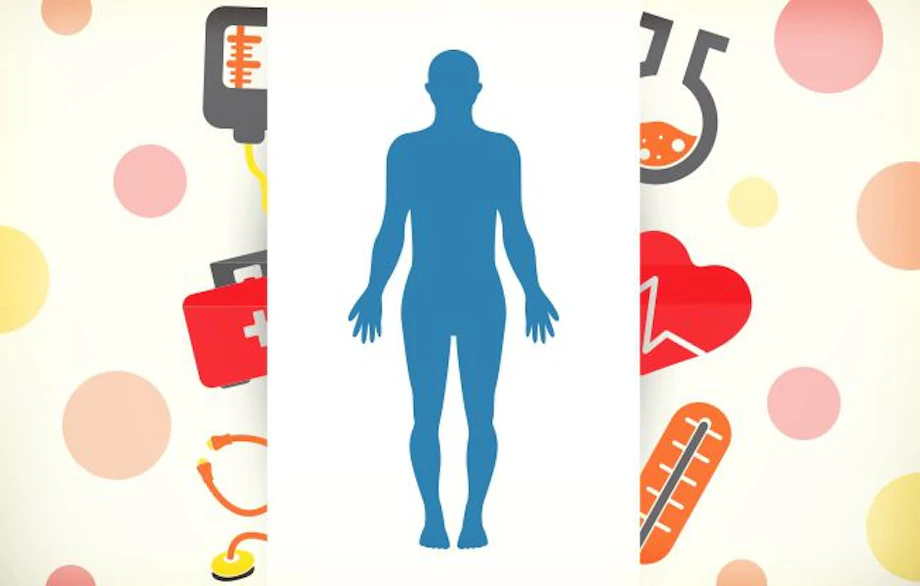献体(けんたい)とは、亡くなった方の遺体を、医学の研究・発展のために提供することです。献体者となるには、亡くなる前から管理する団体へ登録をしておく必要があります。
献体は医学に貢献でき、意義ある行為ではありますが、献体した遺体はどのように扱われ、葬儀や供養はどのようになるのでしょうか。
この記事では、献体について知っておきたいこと、登録の手順、献体前の葬儀について、実際に献体を登録した方やご家族の声をご紹介します。
<この記事の要点>
・献体は、亡くなった方の遺体を医学の研究・発展のために提供する行為
・献体者は亡くなる前から管理する団体に登録しておく必要がある
・献体は遺族の同意が必要で、遺骨の返還は1年から2年以上かかることもある
こんな人におすすめ
献体について知りたい方
献体登録をお考えの方
献体をした際の葬儀について知りたい方
医学の発展に必要な献体とは
献体は、死後に遺体を解剖教室などに提供し、医学の発展に活かすことです。提供された遺体は、医学生や医師の研修などに役立てられ、医学の発展や優秀な医師の育成に貢献します。
献体を行うためには、生前から大学や関連団体に登録しておく必要があります。さらに献体実施時には、遺族や関係者の同意が必要です。
献体が増えている理由
以前は献体を選ぶ方は少なく、大学が実習に必要とする遺体が集まらずに苦労している背景がありました。しかし、最近はその意義深さを訴える活動の効果もあってか、増加傾向をたどっています。これは単純に「亡くなった後に何か役に立てれば」と考える方が増えたとも考えられますが、そのほかにも理由があります。
火葬の費用を大学側が負担することから、家族の負担を減らせると考える方がいるのです。また、引き取り手のない遺骨に対してお墓を用意し、供養までしてくれる大学もあります。高齢化社会と呼ばれる現代では、身寄りのないお年寄りもたくさんいて、その背景からも献体を選択する方が増えているのです。
ただし、負担してくれる費用は、あくまでも大学までの遺体の運搬費用と、火葬の費用のみということに気を付けておかなければなりません。葬儀の費用も負担してくれるものと勘違いする方も多くなっています。
<関連記事>
日本の常識は世界の非常識!?日本の火葬率は世界No.1
小さなお葬式で葬儀場をさがす
献体をする場合の注意点
遺骨はすぐに返還されない
遺骨の返還はすぐには行われません。これには理由があります。
(1)解剖には準備期間が必要
防腐処理などを施すための期間だけで、半年ほど見ておく必要があります。
(2)実習期間が長い
実習は段階的に行われるため、解剖は長期間にわたります。
(3)すぐに解剖が行われない可能性がある
解剖はカリキュラムで管理されているため、年度中の実習に間に合わなければ来年度に持ち越されます。これには、献体として保管されている遺体の数も大きく関係します。
これらの理由から、遺骨の返還は早くて1年~2年、長ければ3年以上かかってしまうこともあります。そのため、献体として遺体を提供する前にお葬式を執り行い、お別れの時間をとることをおすすめします。
肉親の同意が必要
申込書を記入する段階で肉親の同意が必要、さらに最終的に献体として提供する際にも肉親の同意が必要になります。 これは、献体を希望する人と、最終的に決定を下す人が異なるためです。
そのため、献体を希望するのであれば、生前から周囲の人たちに自分の考えを伝え、献体として遺体を提供することに十分理解を得ておく必要があります。
献体できないケースもある
ドナー登録をしている方の献体の登録を受け付けていない大学もあります。臓器提供をすると、献体を行うことができないからです。つまり両方に登録している場合、遺族がどちらかを選択することになります。意志を反映するためには、生前に遺族としっかり話し合っておくことが大切です。
また、事故などで遺体の損傷が激しい場合も断られてしまうことがあります。実習などに使うには、身体や臓器が完全な状態である方が望ましいのでしょう。ただし、病気や障害を持っているといった場合は、受け入れ先によって対応が変わってきます。他の遺体と比較するなど、役立てられる場合もあるからです。
いずれにしても大学によって受け入れの基準は異なりますので、事前に確認した方がよいでしょう。
献体登録の手続き
献体の登録方法について簡単にご紹介します。
(1)申込書の取り寄せ
献体篤志家(けんたいとくしか)の団体、あるいは医科・歯科大学に申込みをします。各都道府県の団体・大学に問い合わせれば、申込書を入手できます。手続きは各団体によって異なるため、申込む団体の様式に従ってください。
(2)申込書の記入
各団体へ、必要事項を記入した申込書を郵送します。この際、自分自身の捺印はもちろんのこと、肉親の同意の印が必要です。
(3)会員証の発行
申込書が受理されると、会員証(献体登録証)が発行されます。会員証は献体登録をしたという証明になるため、不慮の事故に備えて旅行先などにも持っていく必要があります。この会員証には登録先の団体名や死亡時の連絡方法などが書かれているため、失くさないようにしましょう。
<関連記事>
葬儀の湯灌にかかる費用は?手順やマナーも解説します
小さなお葬式で葬儀場をさがす
献体をする場合の葬儀について
献体をするのであれば、葬儀は献体前もしくは献体後に行います。
葬儀後に献体として提供する場合
通夜・告別式などの通常の葬儀儀式を行った後に、献体として遺体を提供することができます。一般的な葬儀では出棺のあと火葬場に運ばれますが、献体の場合は登録先の各団体に運ばれます。
火葬は各団体によって行われるため、火葬費用や搬送費用を遺族が支払う必要はありませんが、通夜式や葬儀を行う場合は遺族が負担しなければなりません。
葬儀前に献体として提供する場合
この場合、葬儀は遺体がない状態で行うことになります。遺体を解剖した後、遺骨が返還されてから、改めて葬儀を行うこともできます。ただし、遺骨が返還されるまでには1年~2年かかってしまいますので、献体前に葬儀を行うと良いでしょう。
火葬費用や搬送費用は、葬儀後に献体する場合と同じく、各団体が負担することになります。
献体した場合の香典マナー
献体をする場合、葬儀も通常とは少し異なることが多いようです。香典に関しては、渡す方もいただく方も、「勝手が変わってくるのでは……」と悩むことも多いでしょう。献体した場合の香典についてどのようにするのが良いのか、それぞれに見ていきましょう。
香典は受け取らないほうが良い?
献体の場合、葬儀が簡略化されることがほとんどですので、香典の受け取りを辞退する場合が多いようです。しかし、受け取るのはマナー違反ではありません。たとえこちらが辞退する旨を伝えていても、参列者によっては快く受け取ってほしいという思う方もいるでしょう。
香典はお悔やみの気持ちを表すものですので、どのような場合でもマナーは変わりません。基本的には一般的な葬儀と変わらないと考えて良いでしょう。
香典返しは用意すべき?
香典返しは、香典をいただいたことに対するお礼の気持ちの表れです。例え香典を辞退していたとしても、いただいたのなら香典返しを準備する方が良いでしょう。
香典返しは仏教でいうところの四十九日法要が済んだころ、つまり忌明けの時期に送るのが一般的です。献体をすると遺骨が戻ってくるまでに数年かかることになりますが、法要は故人が亡くなった日から日数を数えて行われるため、香典返しについても時期に変わりはありません。香典返しには、弔事を滞りなく終了したと報告する意味も含まれているのです。
また、いただいた額の半分ぐらいの金額の品を贈ること、不祝儀を残さないという意味を込めて、食べ物や日用品など、後に残らない消耗品を贈るのが一般的です。
<関連記事>
【香典まとめ】香典の金額相場・渡し方、香典袋の選び方・書き方などをすべて解説!
小さなお葬式で葬儀場をさがす
葬儀費用は大学側が負担してくれるの?
献体をすることによって、大学が葬儀費用を負担してくれると考えている人もいますが、これは間違いです。大学は大学への搬送費用、火葬費用は負担してくれますが、葬儀を行う場合は別途費用が必要になり、大学はこれらを負担することはありません。
そのため、火葬費用が必要なくなる分の金額は安くなりますが、葬儀が無料で行えると考えていると、想定外の出費が発生することになるので注意しましょう。
葬儀をしないケースもある
献体を行うことによって葬儀が無料になると考える人の背景には、少子高齢化の影響によって、身寄りのない高齢者が残された人の負担を少しでも軽くしようと葬儀をしないケースが増えていることも関係しています。
そのため、亡くなった後に献体をすることによって、火葬費用を大学が負担し、葬儀を行わずに、葬儀費用を抑えることもあります。
ただし最近は大きな葬儀ではなく、家族だけで催す小さなお葬式も可能になっているので、献体後に身内だけで静かにお葬式を行うこともできるようになっています。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
献体で葬儀をしない場合のメリット・デメリット
献体をする方の中には、葬儀をしない選択をする方もいますが、葬儀をしない場合には、どのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか。それぞれに見ていくことにしましょう。
葬儀をしないメリット
葬儀をしないメリットは、遺族が手を煩わされないことや費用を抑えられることでしょう。献体を選択する方で、火葬の費用を負担してもらえることを理由に挙げる方などは、それ以外の費用に関しても気にかけているものです。
また、献体の受け入れは死後48時間以内です。これに関しては通夜と告別式を同じ日に行う一日葬を行って時間に間に合わせる場合が多いのですが、葬儀をしないのなら余裕を持って搬送を行うことができるでしょう。
身寄りのないお年寄りなどは、葬儀をしてもらうつもりがないという理由で献体をする方もいるでしょう。その後の対応も大学側が行ってくれるのなら、このような方にとっては大きなメリットになります。
葬儀をしないデメリット
葬儀をしないデメリットは、遺族の気持ちのけじめが付きにくいことでしょう。遺族にできる限り負担をかけたくないという故人の思いがあっても、やはり遺族はきちんと葬儀を執り行って故人を見送りたいと思うものです。
葬儀やそれに伴う法要は、遺族が故人の死を徐々に受け入れていくための儀式という意味合いも込められています。献体するから葬儀はしなくて良いと短絡的に考えるのではなく、親族と相談するべき重要な問題と認識しておきましょう。葬儀をするかしないかは、献体とは別問題なのです。
実際に献体登録した方やご家族の声
ここでは、実際に献体の登録をされた方の声をご紹介します。
「まっすぐに生きていけそうな気がしました。
(献体が)私が生きていく目標、生きる力になっている。」
「そのまま火葬されるよりも、人のためになるんだったら、自分の体のいいところが少しでも役に立てば。」
引用元:http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3649/
やはり、献体を通して人の役に立てるという点に大きな意義を感じられているようです。そして、それは今を生きるための力にもなっているとのこと。
ここからは、献体登録者のご家族の声もご紹介します。
「ただ、遺体がいつ戻るかが分からないので、そのあとのいろいろ(お墓などの関係)が予定が立たないことに母や叔父たちは戸惑っていたようでしたが。3年を過ぎた今、献体してもしなくても、その後には変わりがないと感じています。」
引用元:http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0819/435928.htm
献体の登録をするときには、家族へ献体後の流れについて詳しく知っておいてもら必要がありそうです。
「父が亡くなった時、生前の父の希望『病院にお世話になったから少しでも恩返しがしたい。その時には反対しないでほしい。』という遺志により、入院していた大学病院(逝去した場所)に献体しました。結果的には、とてもよかったです。
父は亡くなった直後の顔は、娘の私でさえ見たことのない苦しそうな顔をしていました。けれど、献体を終えた後、綺麗に死化粧をされて、非常に穏やかないつもの父の表情に戻って帰ってきてくれました。」
引用元:http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0819/435928.htm
献体すると解剖されるとはいえ、とても大事に扱われ遺族への配慮がなされているようです。
「私が高校生の時に祖母が病院で亡くなり、家族が駆けつけるとほぼ同時に、すぐに献体の職員?の方が霊安室にいらして、祖母は車に乗せられ、運ばれて行きました。車は普通の黒いワゴン車でした。
とにかく遺体の搬送がスピーディーで、あれよあれよという間に祖母は目の前から居なくなって、不思議な気持ちがしたのを覚えています。」
引用元:http://www.jineko.net/forum/4709
なかには亡くなったことの実感をしっかりと得られぬまま、最期のお別れとなってしまった方もいらっしゃるようです。
あくまでごく一部の方の声ですが、献体へのイメージがより明確になったのではないでしょうか。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
献体として遺体を提供することは、医学の発展や優秀な医師を輩出するために重要なことです。人の役に立ちたいと考える方には検討の価値があるでしょう。
しかし、献体をするのであれば考慮しなければいけないこともありますので、ご家族に対してしっかりと説明しておきましょう。
葬儀に関するご準備は事前に行うことが大切です。いざという時困らないように、葬儀全般に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
献体とは?
献体する場合の注意点は?
献体登録の手続きはどうすればいい?
献体をする場合の葬儀や香典マナーは?
葬儀費用は誰が負担してくれるの?
葬儀をしない場合のメリット・デメリットは?

お彼岸の時期は年に2回で、春分の日、秋分の日の頃だと覚えておくとよいでしょう。ホゥ。