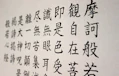ご遺体を安置するとき、僧侶に枕経(まくらきょう)をあげてもらいます。一昔前は自宅で葬儀を行うことが多く枕経に触れる機会もありましたが、現在は自宅以外で葬儀を行うことが主流になり枕経も省略されるようになりました。
この記事では、枕経を依頼する際の流れ、お布施について、僧侶への対応などをまとめています。
<この記事の要点>
・枕経は、故人を偲び、故人の冥福を祈るための重要な儀式です
・枕経は菩提寺の僧侶に依頼をする
・枕経の場合は単独でお布施を用意する必要はなく、通夜~葬儀までを含めたお布施を渡す
こんな人におすすめ
枕経の概要を知りたい方
枕経を依頼する際のお布施について知りたい方
枕経を依頼する際の流れを知りたい方
枕経とは…故人の成仏を願うお経
枕経は、「故人を仏弟子にして往生してもらうために行うお経」のことで、僧侶に来ていただき枕経をあげてもらうことを枕勤め(まくらづとめ)といいます。この時、遺族は僧侶の後ろで亡くなった方の冥福を祈ります。
以前は臨終(りんじゅう)を迎える人の枕元でお経をあげていましたが、現在は臨終後に行うのが一般的です。また、近年は病院で亡くなり、病院から斎場に搬送されることが増えています。その場合には枕経が省略されたり、通夜の前に行われたりということもあります。
枕経を依頼する際の流れ
ここでは、菩提寺(ぼだいじ)の僧侶に枕経を依頼する流れをご紹介します。
1. 遺体の安置場所を確保する
枕経をあげる場合、基本的には自宅に安置することになります。ご遺体を安置できる十分なスペースを確保し、布団を敷いておきます。枕飾りを置くスペースも考慮しましょう。
↓
2. ご遺体の受け入れを行う
病院からご遺体を搬送してもらいます。予め敷いておいた布団に寝かせ、枕飾りをします。葬儀社に依頼をしていた場合は、枕飾りは葬儀担当者が行ってくれます。
↓
3. 寺院に連絡する
寺院に連絡し、枕経を依頼します。日時も指定します。故人の名前、死亡時間、享年、生年月日などを伝えなければいけないため、把握しておきましょう。
↓
4. 枕経をあげてもらう
ご僧侶が到着したら枕経をあげてもらいます。このとき、親族も同席しますが、喪服を着る必要はなく、平服で構わないとされています。数珠は用意しておきましょう。
↓
5. 通夜や葬儀の日程、戒名などの相談をする
枕経が終わったら、通夜や葬儀でも同じご僧侶にお願いする場合は日程や戒名などの相談も行います。
僧侶への対応
枕経をお願いする僧侶へのお布施や挨拶についてご紹介します。
お布施はどうする?
ご僧侶への謝礼としてお布施を用意しますが、枕経の場合は単独でお布施を用意する必要はなく、通夜~葬儀までの全てを含めて包みます。そのため、ご僧侶に渡すのは葬儀の最後になります。
お布施の金額は、寺との関係や地域によって変わりますし、戒名料も含めてお布施を渡す場合は戒名のランクによっても変わります。
ご僧侶への挨拶は?
ご僧侶に一言挨拶をする機会があります。このとき、次のような挨拶の言葉をかけましょう。
■枕経をお願いするとき
お世話になっております。○○町の○○でございます。父が先ほど亡くなり、ただいま入院先より連れ戻りました。ご住職様に枕経をお願いしたいと思うのですが、ご都合はいかがでしょうか。
■ご僧侶をお迎えしたとき
お忙しい中、ご足労いただきありがとうございます。父もさぞ安心することと思います。何分不慣れなため、よろしくご指導ください。では、よろしくお願いします。
■お布施の費用を尋ねるとき(どうしても決められなかった場合)
私ども初めてのことで何もわかりません。誠に失礼とは存じますが、お布施はいかほど用意すればよろしいでしょうか。
■お布施を渡すとき
本日は大変丁寧なおつとめを賜り、ありがとうございました。おかげさまで、無事葬儀を終えることができました。些少ではございますが、どうぞお納めください。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
枕経は、故人がきちんとあの世へ渡れるようにという願いを込めた儀式です。
近年は、故人をあの世へ送り出すと共に、ご遺族がきちんとその死を受け止めるためにも大切なことなので、こういった儀式があるということは覚えておくと良いでしょう。
葬儀に関するご準備は事前に行うことが大切です。いざという時困らないように、葬儀全般に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



直葬とは、通夜式や告別式などの式をはぶき、火葬のみを行う葬儀のことです。ホゥ。