「檀家」や「檀那寺」という言葉を聞いたことがあっても、意味や関係性について深く理解している人は少ないのではないでしょうか。昨今では、檀家は減少しつつありますが、檀家と檀那寺の関係性はどういった時代背景で築かれたのでしょうか。
この記事では、檀家や檀那寺の意味と関係性、歴史的背景をわかりやすく紹介します。檀家の義務や役割についても解説していますので、参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・特定の寺院に所属して経済的に支援する家を「檀家」、自身が帰依している寺院を「檀那寺」という
・檀家にはお布施や寄付をする役割があり、寺院から供養や儀式の優先的な提供を受ける権利がある
・檀家は檀那寺の墓地にお墓を建てるのが一般的だが、墓地は借りて墓石を買うのが基本
こんな人におすすめ
檀家と壇那寺の意味を知りたい方
檀家の義務や役割を知りたい方
檀那寺の墓地を利用する際の規則・注意点を知りたい方
檀家と壇那寺の意味を簡単解説
核家族化の進行に伴い寺院離れも進み、檀家は減少傾向にあります。そのため、檀家や檀那寺とは何かについて知らない方も増えてきました。まずは、檀家と壇那寺の意味を簡単に解説していきます。
【簡単解説】檀家とは
檀家(だんか)とは、特定の寺院に所属し、お布施や寄付などで寺院を経済的に支援する家のことです。その見返りとして、寺院は檀家の葬儀や法要、お墓の管理などを手厚く行います。
「檀家」という呼び名は、古代インドで使われていたサンスクリット語の「ダーナ」という言葉が語源です。ダーナは、「施す・与える」といった意味を持ちます。
【簡単解説】壇那寺とは
檀那寺(だんなでら)とは、自身が帰依している特定の寺院を指します。つまり、自身が檀家となって経済的に支援している寺院のことです。檀那寺には、葬儀・法要やお墓の管理、先祖の供養をしてもらう代わりにお布施を納めます。
檀家と門徒は何が違う?
「檀家」と「門徒」の違いは宗派にあります。浄土真宗では門徒と呼ぶのに対し、その他の宗派では檀家と呼びます。呼び名は違えど、特定のお寺に所属し、お布施や寄付で経済的支援をしながら葬儀や法要などを行ってもらうという意味は同じです。
菩提寺と壇那寺は違うもの?
近年では「菩提寺」と「壇那寺」は同じような意味合いで使われますが、厳密には異なります。壇那寺は自分が帰依する寺院のことで、檀家となった寺院のことを壇那寺と呼びます。一方、菩提寺は檀家であるかどうかは関係なく、葬儀や法要を依頼する寺院を指します。
檀家を持たない寺院もある
ここまで檀家について説明してきましたが、檀家を持たない寺院もあります。檀家を持たない寺院には墓地もなく、お墓がありません。
「檀家からの支援なしでどのように成り立っているの?」と疑問を抱く方もいるかもしれませんが、檀家を持たない寺院は祈祷料や拝観料を経済的基盤としています。
そのため「祈祷寺」と呼ばれることがあります。菩提寺は先祖の供養をする寺院ですが、祈祷寺は今後の繁栄を祈るための寺院です。
檀家はどのように生まれた?檀家の歴史
檀家の意味を知るうえで、檀家の歴史を知っておくことも大切かもしれません。「檀家制度」の歴史は古く、江戸時代から設けられた制度と言われています。キリスト教を禁止し、寺院と檀家とのつながりを強固なものにするためにスタートしました。
檀家の由来をひも解く
「檀家」は「檀越(だんおつ)」とも呼ばれ、鎌倉時代から存在しています。「寺請制度」のように、檀家が強制され制度として確立したのは江戸時代以降ですが、室町時代には檀家と檀那寺による寺檀関係(じだんかんけい)ができていました。
江戸時代の寺請制度
寺請制度とは、江戸幕府がキリシタン弾圧や戸籍管理などのために設けた制度です。すべての人が檀家になることを強いられ、「寺請証文」で檀家であることを証明するよう義務付けられたのです。
檀家はお布施で寺院を支え、寺院は檀家の葬儀や法要など、仏事の一切を執り行います。さらに、寺院が檀家の動向チェックや戸籍管理までを請け負っていました。
檀家に課せられた義務
幕府や大名、武家にとって寺院の維持費用は大きな負担でした。そのため、幕府はすべての人を檀家にして、お布施や寄付で寺院の経済基盤を安定させたのです。
寺請制度により年忌法要や命日供養、墓参りなどの仏事が義務化され、檀家の人々はお布施を納めました。これにより武家の負担は軽減し、寺院の経営も安定的なものとなったのです。
寺請制度の終わり
江戸幕府により始まった寺請制度は、明治時代になり廃止されました。江戸幕府の倒幕が企てられるのと同時に近代化改革が推進されたのです。
これを明治維新と呼び、身分制や宗教、思想についての改革が行われます。明治維新の政策として神道と仏教を分離させる「神仏分離令」が発足され、寺院や僧侶たちは激しい弾圧を受けました。こうして寺請制度は終焉を迎えたのです。
檀家の義務と権利は何か?壇那寺との法的関係
檀家になろうとしている人の中には「檀家の役割は?」「檀那寺との法的な縛りはあるの?」と疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。
ここからは、檀家の役割と権利や、壇那寺との法的関係の有無について解説します。
寺檀関係において法的縛りはある?
過去には江戸幕府が定めた国の制度として「寺請制度」という縛りがありました。檀家になることが強制され、葬儀や法要を行い、お布施を納めることが義務化されたのです。
寺請制度が廃止された今も「檀家」という慣習は残っています。しかし、現在において檀家と壇那寺の間に法的な縛りはありません。お布施を納めることは義務ではなく、檀家と壇那寺の間には持ちつ持たれつの関係性が築かれています。
檀那寺との契約書とはどんなもの?
入檀する際は、「檀家契約書」「墓地申込書」といった契約書を取り交わします。檀家契約書には、会費や離檀料などの金銭的な規約や檀家心得、改葬に関する取り決めなど重要事項が記載されています。
特に、お金にまつわる部分はしっかりと読んでから契約締結することが大切です。捺印した契約書は家族間で共有し、保管しましょう。ただし、入檀契約書などがすべての寺院にあるというわけではありません。
お布施を納めないとどうなる?
「お布施や寄付金は必ず納めないといけないの?」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。お布施や寄付は義務ではないため、強制はされません。お布施の本来の意味は、いつもお墓を守ってもらっていること、先祖を供養してもらっていることへの感謝の気持ちです。
檀家の経済的支援により、寺院が支えられているのは事実です。とはいえ、寺院の修繕や改修の際は寄付を求められることもあり、経済的負担を感じてしまう場合もあるかもしれません。
金銭的事情や高額な寄付を要求された場合など、納めるのが難しい場合は「寺院に相談する」「離檀する」といった方法を検討しましょう。
慣習としての檀家の役割と権利
檀家になるとどのような役割と権利が与えられるのか見ていきましょう。
・役割
日頃の感謝の気持ちを込めたお布施を納めます。また、寺院の改修・修繕時など、必要に応じて寄進をします。
・権利
葬儀や供養、お墓の管理をしてもらえます。お盆などの繁忙期には、寺院にもよりますが優先して対応してもらえる場合もあります。
檀那寺の墓地に関する基礎知識と注意点
檀家は壇那寺の墓地にお墓を建てるのが一般的です。壇那寺と良好な関係を築くためにも、墓地を使用する際の規則や注意点については知っておくと安心でしょう。ここからは、壇那寺の墓地に関する基礎知識と注意点を紹介します。
墓地は借りて墓石は買うのが基本
「墓地を買う」と聞くと、土地を買う必要があるのか不安に思う人もいるかもしれませんが、墓地は借りて墓石を買うのが基本です。墓地を買うというのは、「土地を使用する権利を買う」という意味を持ちます。
墓地やお墓に関連する法律はある?
お墓参りが慣習化されている日本では、墓地、埋葬等に関する法律が整備されています。
埋葬に関する法律では「墓地外の埋葬等の禁止」が定められており、故人の遺骨を勝手に埋めたり、自分の土地にお墓を建てたりすることは禁止されています。遺骨を埋葬するときは、市町村長(特別区の区長も含む)の許可を受けなければなりません。
また、檀家に影響する法律は民法第897条です。
「系譜、祭具、墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰する人が承継する。 但し、被相続人が指定に従って、祖先の祭祀を主宰するべき人があるときは、その人が承継する。」とされており、お墓を継ぐ権利や承継する人について定められています。
墓地使用規則はしっかり確認を
寺院にもよりますが、たいていの墓地には墓地の利用に関する規則が定められています。宗派の規定や管理料の支払い、墓石建立に際する石材店の指定などは注意したいポイントです。
管理料は1年ごとに支払うのが一般的ですが、数年分を事前に納めるケースもあるようです。また、お供え物の制限がある寺院もあるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。
宗教を変えたらお墓はどうなるのか
宗教や宗派を変えた場合、壇那寺の墓地に眠る先祖代々の遺骨やお墓はどのような扱いになるのでしょうか。
宗派を変えたとしても寺院はお墓の撤去を強制することはできませんが、寺院のしきたりに則って埋葬しなければなりません。そのため、宗派の違いから埋葬や供養の方法に齟齬が生じたときには、他の場所に移転する必要があります。
墓じまいをするときの費用と注意点
他の場所にお墓を移動するときは、「墓じまい」をする必要があります。墓じまいとは、墓石を解体・撤去し墓地を更地に戻してから、寺院に返還することをいいます。
墓じまいする際は、閉眼供養を行ってから墓石を解体・撤去します。閉眼供養とは故人の魂を抜くための法要です。閉眼供養は3〜10万円、墓石の解体・撤去費用は10〜20万円が相場です。ただし、寺院が指定する石材店を利用しなければならないケースもあるため、事前に確認しましょう。
その後改葬するのか、散骨するのかなど、選択する方法によって費用が変わってきますので家族でよく話し合ってから決めましょう。
新しい時代の寺院との関わり方
核家族化やライフスタイルの変化により、昨今では寺院との関わり方も多様化してきました。
檀家であるかどうかを問わず、「新しい寺院との関わり方」が注目されつつあります。まずここでは、檀家の意味や檀家としての在り方を改めて考えるヒントとして、新しい寺院との関わり方をご紹介していきます。
オンラインでつながる関係
新型コロナウイルスの影響で、気軽に寺院を訪れる機会も減少してしまいました。そんな状況を打破しようと、多くの寺院が「オンライン」を活用した新しい取り組みを始めています。
・奈良の大仏さま24時間ライブ
定点カメラで奈良の大仏さまをライブ配信したり、東大寺の散策ガイドをライブ配信したりして、反響を集めました。
・オンライン法要
法事や法要で人が集まり密になるのを避けるため、「オンライン法要」が登場しました。オンライン法要では、Zoomなどの会議ツールを用いて法要を中継します。リモートで法要を営むため、遠方でも参加できることから人気が高まっています。
・座禅アプリ
座禅とは、あぐらの状態で精神統一する修行方法です。寺院で禅体験を受けるのが一般的でしたが、新型コロナウイルスの影響で気軽に座禅体験を受けられなくなりました。
そこでリリースされたのが「座禅アプリ」です。座禅アプリを使えば、音声ガイドを聴きながら、自宅で座禅を組むことができます。
葬儀や法要だけのお付き合い
檀家にならずとも葬儀や法要を執り行う選択肢はあります。それが「寺院手配サービス」です。寺院手配サービスとは、寺院とのお付き合いがない方向けに、僧侶の手配を行うサービスです。
小さなお葬式では、寺院手配サービスを承っており、僧侶を手配することができます。お寺院とのお付き合いがない方はお気軽にご相談ください。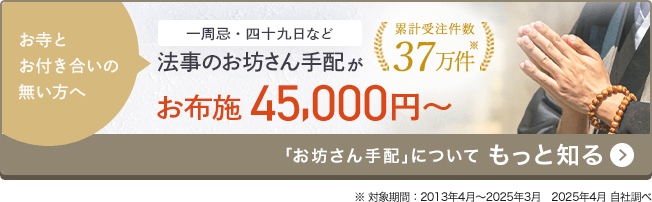
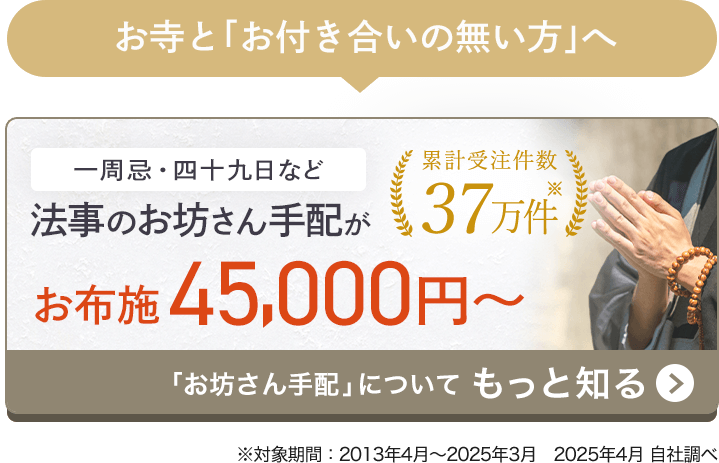
お寺の都合によっては希望日に添えない場合もあるため、1ヵ月~2週間前を目安に寺院手配の予約をすることをお勧めします。
仏様の教えを知る場所として
現代の日本では、ライフスタイルの変化により寺院離れが進んでいます。「葬式仏教」と呼ばれることもあるとおり、葬式や法事の際にしか「仏教」が必要とされていません。
そんななか、「さまざまな人が集い、相談できる場」に原点回帰しようと活動している寺院もあります。
そういった寺院の僧侶たちは、寺院の一角にカフェを設けたり自主制作映画をつくったりして、仏様の教えを広め、本来の寺院や僧侶の役割への原点回帰を目指しているのです。
「家」ではなく「個人」として
檀家と言うと、今までは「家」と「寺」との関係でした。しかし、承継者不在などの問題もあり、これからは「個人」と「寺」が繋がる時代になっていくでしょう。
寺と聞くと葬儀・法要のイメージが強く、寺院離れが叫ばれるなかで「個人へ寄り添う」ことを目指している寺院もあります。「幸せに生きるためにはどうしたらよいか」に焦点を当て、終活のサポートなどを行なっているのです。
家として強制的に参加するのではなく、自分にとって最適な寺院を選び参加することで得られるものもきっとあるはずです。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
檀家の歴史的背景や役割、檀那寺の墓地に関する基礎知識と注意点について紹介しました。
核家族化やライフスタイルの変化により寺院離れが進んでいますが、オンライン寺院や大仏さまのライブ配信などを通じ、寺院との新しい関わり方を試してみるのもひとつの選択肢です。寺院との繋がりを持つことが、日本の歴史や自身の人生について、深く考えるきっかけになるかもしれません。
寺院手配サービスや無宗教葬以外にも、葬儀全般に関する疑問がある場合には「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。


御霊前は「亡くなった方の霊魂の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。






























