浄土真宗は他の仏教宗派と異なる「往生即成仏」の考え方を持つ宗派ですが、死者の供養の儀式である四十九日法要は執り行います。考え方が異なる場合、四十九日の計算は異なるのか、どのようなことをするのか、分からない方も多いのではないでしょうか。
浄土真宗の四十九日についての確かな知識を持てば、四十九日法要を営む準備もしっかりと進められるでしょう。
そこでこの記事では、浄土真宗における四十九日の意味、四十九日の計算方法、法要の予備知識について詳しく説明します。四十九日法要の新型コロナウイルス感染対策も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・浄土真宗の四十九日は、亡くなった日を1日目として数え、49日目のことを指す
・浄土真宗の四十九日法要は、故人の供養ではなく遺族の心を癒すために行う
・命日の月の翌々月に四十九日法要を執り行う「三月またぎ」は避ける
こんな人におすすめ
浄土真宗の四十九日について知りたい方
四十九日法要に向けて準備することを知りたい方
浄土真宗の特徴を知りたい方
四十九日の計算方法と日程の決め方(浄土真宗)
葬儀の後に迎える四十九日法要は、仏教の教えに基づいて執り行われる大切な法要です。四十九日とは具体的にいつのことなのでしょうか。また、四十九日法要は四十九日当日に行わなければならないのでしょうか。
浄土真宗における、四十九日の計算方法、四十九日法要の日程を決める際に影響の大きいポイント、お付き合いのある寺院がない場合の寺院の手配方法について説明します。
亡くなった日を「1」としてカウント
四十九日の計算方法のポイントは、いつから数え始めるのかという点です。四十九は、亡くなった日を「1」としてカウントし始めて、「49」日目を数えた日を指します。
例えば、3月1日が命日の場合は、49日目となる4月18日が四十九日です。ただし、関西地方では、亡くなった日の前日を「1」としてカウントする地域もあります。
法要日程決めに影響大の4つのポイント
法要の日程を左右させる、注意しなければならないポイントは4つあります。故人の命日、家族や親族の希望、寺院の都合、会場の空き状況です。
故人が亡くなって49日目が四十九日になりますが、当日に法要を営まなければならないわけではありません。平日で参列者が集まりにくい場合などは、前倒しした土日など、人が集まりやすい日を法要の候補日とするのが一般的です。
さらに、僧侶に読経してもらうために寺院の都合も考慮しなければなりません。法要の会場は、自宅の他にも寺院であったり葬祭ホールであったりしますが、会場の空き状況も早めに確認しておきましょう。
| 影響の大きいポイント | 内容 |
| 故人の命日 | 明日から数えて49日目から前倒しした土日を法要の候補日とする |
| 家族や主たる親族の希望 | できるだけ関係者が集まりやすい日程 |
| 寺院の都合 | 僧侶に読経を依頼するため |
| 会場の空き状況 | 寺院・葬祭ホール(時間も確認) |
お付き合いのある寺院がない場合は?
菩提寺などのお付き合いのある寺院がない場合は、知人縁故からお寺を紹介してもらう方法や、葬儀の際にお世話になったお寺に相談する方法があります。
その他最近では、インターネット上でお坊さん手配サービスを利用される方も増えています。寺院手配サービスのメリットは以下の通りです。
・インターネットや電話で簡単に寺院手配の予約ができる
・料金が定額制となっている
・寺院からの電話で打ち合わせができる
・自宅はもちろん、手配したお坊さんのお寺での法要も行える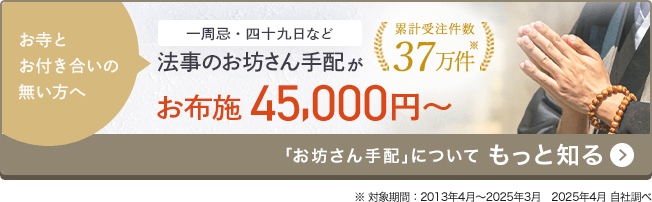
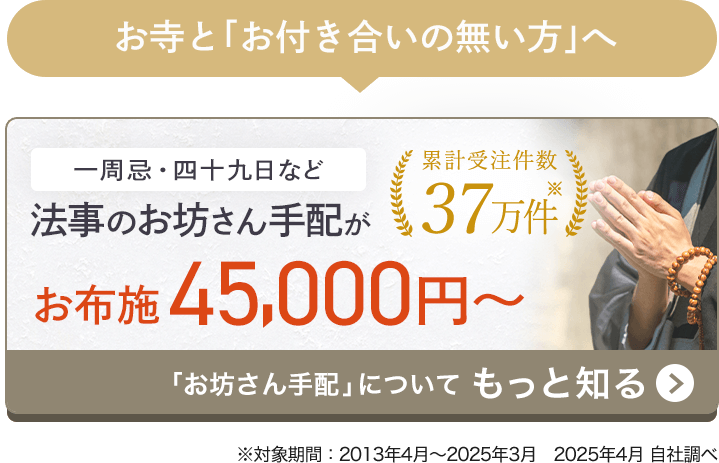
お寺の都合によっては希望日に添えない場合もあるため、1ヵ月~2週間前を目安に寺院手配の予約をすることをお勧めします。
浄土真宗で四十九日法要の日程を決める際に注意したいこと
四十九日法要の日程を決める際には、いくつか注意したいことがあります。いつから法要の準備に取り掛かったらよいのか、法要の開始時間はいつごろが良いのか、四十九日当日にできない場合は、前倒しと後ろ倒しのどちらにすべきか、友引や「三月またぎ」など、法要がタブーとなるケースの対処法について説明します。
葬儀後すぐに準備に入る
四十九日法要は、葬儀を終えてから1か月半ほどたった日程で組まれます。葬儀前後は弔問客の対応や手続きなどでとても忙しくなるので、すぐに時は経ってしまうものです。
日程決め、僧侶の手配、会場や食事の手配、関係者への案内、出欠席の確認などを考えると、葬儀後なるべく早い時点で準備に入ったほうがよいでしょう
午前と午後、開始時間
四十九日法要の開始時間については、こうしなければならないという明確な決まりはありません。ただし、会食をする場合は法要終了後に席を設けます。
そのため、会食の終了時間を考え、法要を午前から開始して昼前後に会食をするのが一般的です。会食をしない法要の場合には、午後からとしてもよいかもしれません。
日取りの前倒し後ろ倒し
四十九日法要を、四十九日当日に営むことが不都合な場合があります。その場合は、四十九日近くで日取りをずらさなければなりません。その場合、考え方のベースとなるのは「仏事は先送りせず」です。古くから伝わる慣例に従って本来の四十九日よりも前に法要を設けます。
この考えは地域での差異もあるものの、前倒しを良しとする地域が多いようです。ただし、一部の地域では、後ろ倒しを良しとする所もあります。また、前倒しでも後ろ倒しでも差し支えのない地域もあるので、周囲に対応を相談するのもよいでしょう。
友引など避けるべき日は?
友引に葬儀をしないほうがよいという考え方は、全国的に広まっています。しかし、故人が友をあの世に引っ張っていってしまうというのは迷信であり、仏教の教えとは関係がありません。法要を行う際にも友引を気にする必要はないと捉えておきましょう。ただし、迷信であっても気にされる方もいるため、説明や配慮が必要です。
「三月またぎ」はタブー?
命日が含まれる月の翌々月に四十九日法要を執り行うことを「三月またぎ(みつきまたぎ)」と言い、これを避けるべきだという考えもあります。例えば、3月15日が命日だとすると、四十九日は5月2日となり、当日に法要を営むとなると翌々月です。
なぜ、「三月またぎ」がタブーとされるかというと、「始終苦が身に付く」(しじゅう、くが、みにつく)という語呂合わせから来ていると言われています。つまり、仏教の教えとは関係なく、本来は気にする必要のないことです。ただし、こうした考えを気にされる方への配慮はするべきでしょう。
四十九日法要を迎える前に準備しておくこと
四十九日法要を迎える前に準備しておくことは、いくつかあります。案内状を送付したり、喪服の手入れをしたり、お布施やお車代を用意したり、供花、料理、返礼品を手配したりしておかなければなりません。それぞれについて、準備をするポイントを説明します。
案内状はメールでもOK?
四十九日法要の案内状は、郵送するのが正式ですが、近年では、近しい親族や家族のみであれば、メールやメッセージアプリでのやりとりで済ませてしまうことも多くなっています。
相手が失礼だと感じる可能性がない場合には、次のような文面のメールを送信して案内状としましょう。特に、日時と場所については正確に記載します。
いつもお世話になっております
このたび下記のとおり亡父○○○○の四十九日法要を執り行いますので お知らせいたします
日時 ○月○日(日) 11:00~
場所 ○○寺
(住所:東京都○○区○-○-○/電話番号:○○○-○○○-○○○○)
施主 ○○○○(長男)
*法要後に会食の席を用意しております
お手数ですが出席の有無を確認したいので○月○日までにご連絡をお願いいたします
(送信者の名前) ○○○○
喪服の手入れも忘れずに
四十九日法要を迎える準備として忘れがちなのが、喪服の手入れです。案内状の送付や会場や僧侶の手配が整っていても、自分自身の支度にまで気が回らない場合があります。
法要当日になって喪服を着用しようとした時に、かびが生えていたり、しわだらけだったりしたことが分かったのでは、身支度が間に合いません。事前に喪服の確認、手入れをしておきましょう。
お布施やお車代その他
お布施は対価ではないため、決まった額がありません。どのくらいにすればよいか分からない方は、葬儀で準備したお布施の金額を目安に決めましょう。葬儀で準備するお布施は、30万円~60万円程度といわれています。四十九日法要ですと、この10%~20%程度の金額を包むことが多く、3万円~5万円程度となるでしょう。
また、御膳料は5,000円~1万円、お車代1万円程度を用意します。ただし、地域や宗派、寺の各式、関係性、親族の考えによっても金額は大きく変わるので周囲に相談するのがおすすめです。
供花・料理・返礼品の手配
四十九日法要での供花は、白い花を中心に準備するのが一般的です。葬儀の際にお願いした葬儀社や仏事対応している生花店で手配します。当日早めに現地に届くよう依頼しましょう。
料理は、法要会場の近隣の料亭などに予約します。その際には、法事であることを申し添えておきましょう。また、寺院や葬祭ホールでも会食をできるところもあります。予約時に確認するのがおすすめです。
返礼品は不祝儀を残さないようにするという考え方があるため、食べてなくなるもの、使ってなくなる洗剤などの日用品を選ぶのが主流です。頂いた香典の半分から1/3程度の返礼品を目安としましょう。返礼品には、のしのない掛け紙をかけます。
知っておきたい浄土真宗の特徴や作法
浄土真宗で法要を営むとなった場合、浄土真宗の中心にある教義とはどのようなものなのかを把握しておくべきでしょう。浄土真宗の四十九日法要は供養とは異なるのか、四十九日法要当日の流れ、独特の焼香の仕方があることなど、浄土真宗の特徴や作法について説明します。
浄土真宗の中心にある教義とは
浄土真宗の中心にある教義として「他力本願」があります。自ら苦しい修行を重ねたり、お経を覚えたりして成仏しようとするのではなく、阿弥陀如来の本願に頼って成仏するという教義です。
浄土真宗は、阿弥陀如来のみを本尊とし、「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えることによって、人々は救われ成仏するという考えを持っています。また、亡くなったと同時に仏になる「往生即成仏」という教義が特徴的です。
浄土真宗の四十九日法要は供養ではない?
他宗派では、亡くなった人はすぐに仏とはならずに霊として7日ごとに生前の行いについての審判を下され、49日後に最終的な審判が下されて、あの世へ旅立つとされています。一方、浄土真宗では、亡くなったと同時に仏になるという考えです。そのため、四十九日法要は、故人の供養のためというよりも、遺族の心の癒しのために行うと考えられています。
法要当日の流れを見てみる
法要当日の流れは、一例として次のようになります。
1.法要:僧侶が入場後、喪主が挨拶で開始。僧侶による読経が行われる。施主から順番に参列者が焼香
2.法話:僧侶による法話が行われ、四十九日法要は終了
3.墓参り:多くのケースで納骨式へと進む。最後に施主による挨拶で終了
4.会食:お斎(おとき)と呼ばれる会食が献杯によって始まる。その後は自由解散
線香を立てずに寝かせる/焼香の仕方
仏教の宗派によって線香のあげ方や焼香の仕方は異なります。線香の場合、他宗派は1本~3本を立てますが、浄土真宗は1本の線香を香炉の大きさに合わせて2つか3つに折り、火が左にくるよう横に寝かせて置きます。線香が発明される以前の風習を受け継いでいるからとされています。焼香は本願寺派が1回、大谷派は2回、押しいただかずに行います。
四十九日法要の新型コロナウイルス感染対策
四十九日法要は人を集めて行うものですから、昨今の社会情勢を鑑みると、新型コロナウイルス感染対策をしないわけにはいきません。これまでとは異なった形式で執り行なったり、中止または延期したり、縮小化したりなどの対応が始まっています。現在進行中の、法要における新型コロナウイルス感染対策を紹介します。
料理業者とも充分な打ち合わせを
新型コロナウイルス感染対策について、料理業者との打ち合わせでは以下のポイントを確認しておきましょう。
・席と席の距離は十分にとってあるか
・衝立は設置しているか
・アルコールの設置をどうするか
・換気は十分に行われているか
加えて、滞在時間の制限なども確認しておくと安心です。注文する料理は、個々に供される御膳タイプにしましょう。
食事なしとした場合の対応方法は?
法要後に会食の席を設けるのは一般的なことでしたが、新型コロナウイルス感染対策として食事なしとすることも増えました。その場合は、参列者に事前に会食がないことを伝えておく必要があります。また、返礼品とは別に、持ち帰り用の弁当を注文しておき参列者に渡しましょう。
四十九日法要自体を中止するときは?
四十九日法要をやむを得ず中止や延期する場合、まずは、早急に参列予定者に電話やメールで連絡しましょう。その後に、中止や延期の案内状を送付します。案内状の文例は次のようなものです。
謹啓 皆様方におかれましてはご清祥のことと存じます
さて ○月○日に予定しておりました故○○○○の四十九日法要は、新型コロナウイルスの感染が拡大する状況を鑑みて実施を見送ることといたしました
法要が差し迫った時期となってのご連絡となり大変申し訳ございません
感染拡大の防止および感染リスク回避のためやむを得ず中止とさせていただきます 皆様のご理解をいただきたく何卒よろしくお願い申し上げます 謹白
法要の規模は縮小化の傾向にはある
新型コロナウイルス感染対策の観点から、多くの人を集める法要のあり方も変わってきています。法要の規模は縮小化の傾向にあるといえるでしょう。参加者を絞って、家族のみで法要を行うケースも増えています。ただし、その場合には、本来であれば四十九日法要の案内状を出すべき方に、法要の事後報告を送付しておきましょう。
オンライン法要という手段はどうか
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンライン法要を営むケースもあります。オンライン法要とは、お寺にいる僧侶と、おのおのの自宅にいる家族や親族をWeb会議システムでつないで執り行う新しい法要のスタイルです。通常の法要のように、読経、焼香、法話を行います。遠方で参列できない親戚も参加できるという点もメリットです。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
浄土真宗の四十九日の計算方法は他宗派と同じで、亡くなった日を1日と数え始めて49日目となります。しかし、四十九日法要など中陰や法要に関する考え方が異なることを留意しなくてはなりません。また、焼香の仕方が異なりますので注意しましょう。
四十九日法要の日程を決める際には、友引や「三月またぎ」など、法要の日取りとしてタブーとされる日を気にする必要はありません。ただし、気にされる方がいる場合もあるので、説明や配慮が必要です。
浄土真宗の四十九日法要以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問がある場合は、お気軽に小さなお葬式にご相談ください。24時間365日通話無料でコールスタッフがご連絡をお待ちしております。


御仏前は「仏となった故人の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。

































