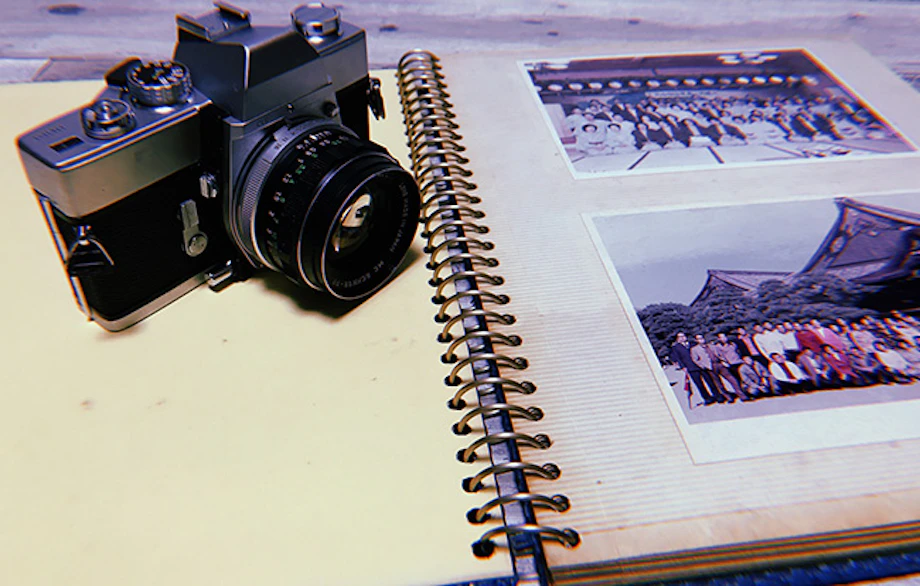葬儀の式場から火葬場へと向かう際、棺桶には故人の思い出深い品を入れます。中には、故人との思い出の写真を一緒に火葬したいという方もいるでしょう。
ただし、実は火葬の際に棺桶に入れてはいけないものも存在します。入れてもいいものといけないものの違いを知らなければ、困ってしまう方もいるのではないでしょうか。心からのお別れの時間を過ごすためにも、入れてもいいものについて知っておくことが大切です。
この記事は、棺桶に入れてもいいものやいけないもの、写真は入れてもいいのかなどを解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・棺桶に写真を入れることは問題ないが、参列者への確認が必要
・棺桶に入れるものとしては故人が好きだった食べ物や生前着ていた洋服などが一般的
・お酒が入った缶や瓶、メガネなどは棺桶に入れてはいけない
こんな人におすすめ
火葬について知りたい方
棺桶の中に写真を入れてもよいか知りたい方
棺桶に入れてよいもの・いけないものを知りたい方
火葬について
火葬とは、故人のご遺体を荼毘に付し、遺骨を葬ることです。日本では、火葬をして収骨し、納骨します。しかし、海外では火葬に参列せず、郵送で遺骨を送ってもらうことが一般的だとされています。他にも火葬について知っておくべきことがいくつかありますので、具体的に見ていきましょう。
六文銭とは
「六文銭」という言葉を耳にしたことがある方もいるのではないでしょうか。しかし、実際の意味まで知っている方は少ないかもしれません。
「文」とは、江戸時代のお金の単位です。六文銭は「三途の河の渡し金」と呼ばれています。江戸時代の旅人が旅に困らないように持ち歩いていた金額が六文であったことから、極楽浄土への道のりも安全に行けるようにという願いを込めてそう呼ばれるようになりました。
このような背景から、故人が安心して極楽浄土へ行けるようにと、1円~50円玉を火葬の前に棺桶に入れる風習がありました。現代ではお金を燃やすことは法律で禁止されているため、印刷したものを入れることが多いでしょう。
火葬許可証
火葬をする際には、「火葬許可証」という証明書が必要です。火葬許可証がないと火葬を行うことができません。火葬許可証は役所で発行してもらうことが可能ですが、死亡届を提出する際に、一緒に火葬許可証をもらう手続きをするのが一般的です。火葬場で必要となるので、忘れず持参しましょう。
火葬が終わると、火葬許可証は返却されます。返却された火葬許可証は納骨の際に必要となるので、紛失しないよう保管しましょう。紛失した場合、別途費用がかかるので注意が必要です。
分骨
分骨とは、故人の遺骨を分けて納骨することです。遺骨は先祖代々のお墓に埋葬するのが一般的ですが、お墓が遠方にありお墓参りに行きにくいケースや、宗派によっては分けて納めたいというケースもあるので、状況により分骨するという選択をすることもあるでしょう。
また、埋葬する際には「埋葬許可証」が必要です。埋葬許可証とは、火葬が終わった際に返却された火葬許可証のことなので、新しく用意する必要はありません。ただし、分骨するためには「分骨許可証」が必要です。葬儀会社に事前に連絡をしておくと用意してもらえます。
写真は棺桶に入れてもいいのか
棺桶には、故人に思いを馳せて、さまざまな品を入れていきます。では、故人が大切にしていた写真がある、あるいは故人との思い出の品が写真である場合は、棺桶に一緒に入れてもいいのでしょうか。
ここでは、写真を入れることや、棺桶にものを入れる際の注意点を説明していきます。
火葬に参加する人に確認を取る
結論からお伝えすると、火葬の際に棺桶に写真を入れることに問題はありません。ただし、写真を棺桶の中へ入れる際には、火葬に参加する他の方々に確認を取りましょう。棺桶に入れる写真に自分が写っている場合、火葬されることを不快に感じる人がいる可能性があるからです。
火葬には、煙が空へ上がることから、故人の死後の平安を祈るとともに、極楽浄土へと行けるよう願うという意味合いがあります。しかし、棺桶の中に入れて一緒に火葬する写真に、まだ存命中の人が写っていた場合、その人は自分も極楽浄土へと連れて行かれてしまう、と考える可能性があります。そうすると、思いもよらないトラブルに発展する恐れがあるのです。
もちろん、写真以外であっても、火葬に参加した人から不謹慎だと思われるケースもあるかもしれません。棺桶の中へ品を入れる際には、確認を取るのが賢明です。
写真の他に注意しておくべきもの
このように、写真は棺桶に入れる際に注意しなければなりませんが、写真の他にも注意しておくべきものがあります。
例えば、毛布や布団など、生地が厚すぎて燃やすのに時間を取られてしまうものです。火葬に時間を取られると遺骨が傷ついてしまうので、棺桶の中へ入れるのを断られる可能性がゼロではありません。
また、分厚い本も燃やすのに時間を取られることがあります。灰が多く残り、収骨する際に手間がかかることもあるので、棺桶へ入れる際には注意してください。
さらに、故人の心臓にペースメーカーが埋め込まれていた場合は注意が必要です。ペースメーカーは火葬している間に爆発してしまう恐れがあります。そうすると、参列者だけでなく火葬を行う人にも危険が及ぶでしょう。故人がペースメーカーを使用していた場合は、火葬を行う会社へ問い合わせ、対処方法を確認することが大切です。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
棺桶に入れてもいいもの
棺桶の中に品を入れる行為には、故人があの世へ行っても苦労しないように、という願いが込められています。そのため、棺桶の中に入れる品のことを「副葬品」と呼ぶのです。
では、副葬品にはどんなものを選べばよいのでしょうか。一般的には、故人が好きだった果物や、故人が生前大切に着ていた洋服などを副葬品として選ぶことが多いです。ここでは、副葬品として棺桶に入れてもいいものを紹介します。
お菓子・果物
お菓子や果物は入れても問題ありません。ただし、みかんや桃など水分の多い果物は、不完全燃焼になる恐れがあるため避けたほうが賢明です。また、お菓子を入れる際にも小分けにされた、なるべく燃えやすいものを選択することをおすすめします。
おもちゃ・ぬいぐるみ
おもちゃやぬいぐるみは入れてもいいとされています。ただし、注意が必要なのは、おもちゃやぬいぐるみの素材がプラスチックである場合です。プラスチック素材だと燃え切らないことがあるので、火葬をする前に入れてもいいか確認しておくと安心でしょう。
手紙
故人への思いや伝え残したことを文字にしたためた手紙は、棺桶に入れてもいいとされています。故人に対する気持ちを文字に表すことで、心残りなくおくってさしあげられるでしょう。
洋服
故人が生前よく着ていた衣類は入れてもいいとされています。ただし、注意が必要なのは、棺桶内に入れる衣類の量や枚数が制限されることが多い点です。あまりにも多い量は棺桶に入りませんし、たくさん入れると燃えにくくなるので、よく吟味する必要があります。
棺桶に入れてはいけないもの
棺桶に入れてもいいものについて紹介しましたが、棺桶に入れてはいけないとされるものにはどのようなものがあるのでしょうか。故人を大切に思って選んだ副葬品であっても、入れてはいけないものだと火葬場で指摘され、断られることがあります。中には炉が壊れて大問題になることもあるので、配慮が必要でしょう。ここでは、棺桶に入れてはいけないものを紹介します。
缶・瓶
故人がお酒を飲むのが好きだった場合、缶ビールや日本酒の一升瓶を副葬品として入れてあげたいと考えることもあるでしょう。故人を思う気持ちはとても大切ですが、缶や瓶は燃えないので、棺桶に入れてはいけません。
メガネ・アクセサリー
メガネやアクセサリーは、ガラスや金属で作られていることが多いです。そのため、燃えなかったり燃えたガラスが骨にこびり付いたりするリスクが少なからずあるので、入れてはいけません。燃え残ったガラスや金属を処理するのが困難になってしまいます。
硬貨や紙幣
硬貨や紙幣は棺桶の中に入れて一緒に燃やしてはいけません。紙幣は燃やすと法律違反になりますし、硬貨はそもそも燃えないからです。
入れてはいけないものをどうしても故人に贈りたい場合
棺桶には、燃焼しにくいものや、燃えた時に危険が発生する恐れのあるものは入れることができません。とはいえ、棺桶に入れてはいけないものだったとしても、故人との思い出のあるものはたくさんあるでしょう。
そういう場合は、仏壇やお墓にお供えすることをおすすめします。仏壇やお墓にお供えすることも、故人を思う大切な行いのひとつです。火葬をする際、棺桶に入れて一緒に火葬することができなかったものでも、お供えすることによって、故人に対しての思いを落ち着かせることができるでしょう。
<関連記事>
お供え物選びにもマナーがある!用意する方法・ふさわしい品物・渡し方を紹介
小さなお葬式で葬儀場をさがす
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
写真を棺桶の中に入れる際には、故人以外の、存命中の誰かが写っている写真はなるべく避けましょう。故人に対する思いから、たくさん副葬品を入れてお見送りをしたいという方もいるかもしれません。しかし、何を入れるにしても火葬に参加する方々に確認を取ることを忘れないでください。
滞りなくお見送りをするには、最低限のマナーを覚えておくと安心です。しかし、いざお見送りをする際に悩んでしまったり、専門的なことになると困ったりするかもしれません。その際には、ぜひ小さなお葬式にご相談ください。専門的な知識と豊富な経験を持ったスタッフが、丁寧に適切なアドバイスをさせていただきます。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



全ての箇所を自筆する普通方式の遺言書を「自筆証書遺言書」と呼びます。ホゥ。