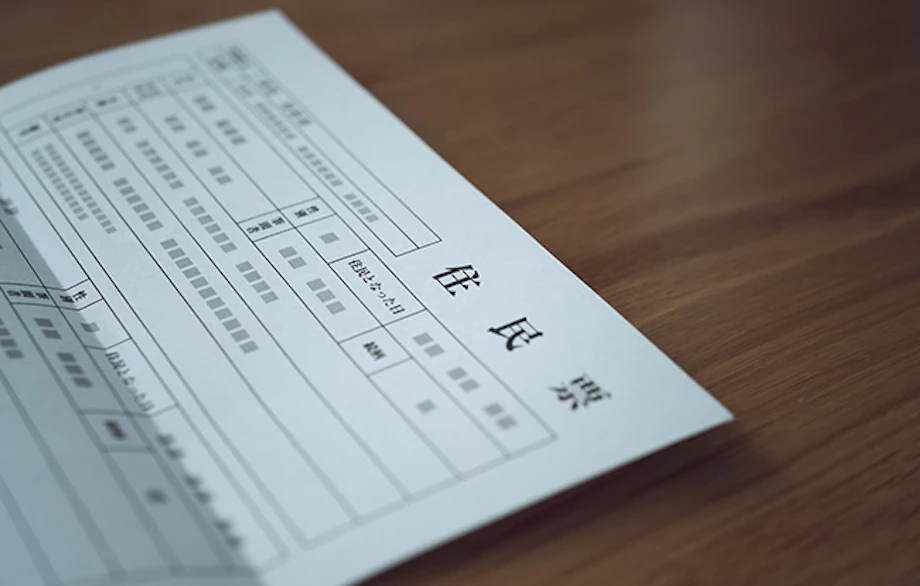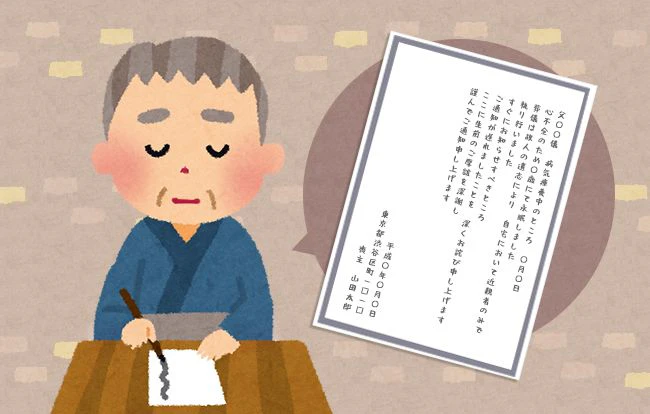公的な施設やサービスは、政府や地方自治体が管理・整備をしており、国民はそれに対して税金を納めます。この税金のことを地方税と呼び、「住民税」もその中の1つです。
しかし、税を納めている本人が死亡した場合、納めていた住民税はどうなるのでしょうか。誰かが納めないといけないのか、何か手続きが必要なのかなど疑問を持つ方もいるかもしれません。
この記事では、死亡した方の住民税はどうなるのか説明します。ぜひ参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・死亡した日が1月2日以降だった場合は課税の対象となり、相続人がその年に限り住民税を納める
・相続人は、身分証明書や故人との関係性がわかる書類、故人の所得がわかる書類を用意して税の申告を行う
・財産の相続はできないが、相続放棄をすることで納税義務を回避できる
こんな人におすすめ
死亡した方の住民税の課税はどうなるのか知りたい方
死亡した方の住民税の納税の方法を知りたい方
死亡した方の住民税の納税義務を回避できる方法を知りたい方
死亡した方の住民税の課税はどうなる?
住民税は、年の始まりである1月1日が課税の基準日となっています。死亡した方に住所があり所得があれば、納めることが必須です。したがって、死亡した日が1月2日以降だった場合は課税の対象となります。その場合、納税の責任は相続人へと引き継がれ、死亡した方に代わり相続人が納税しなければなりません。
納めるのは、その年だけの住民税となります。翌年1月からは課税されることはないため、納税の対象にはなりません。
住民税とは
住民税という言葉は、納める税金の呼称の中でも聞いたことのある方が多いのではないでしょうか。住民税とは、その地域で生活している方々が地域社会への費用として納める税金のことで、「個人住民税」と「法人住民税」の2種類があります。
市区町村に住所があり、個人が所得に応じて納める住民税が個人住民税です。事業所や事務所がある市区町村に、申告をして納める住民税のことを法人住民税と呼びます。
相続人とは
納税していた方が死亡した場合、納税の責任は相続人へと引き継がれます。「相続」と聞くと土地や財産を受け継ぐことができるイメージが多いですが、負債である納税の責任も引き継ぐことになるので、相続する際には注意が必要です。
また、相続人の対象になる人は決まっており、遺言書があればその内容が優先されるでしょう。遺言書が特になければ、民法によって定められた優先順位によって誰が相続できるのかが決まります。一般的に、配偶者や血族者が相続人になることが多いでしょう。
<関連記事>
親が亡くなったらするべき相続手続きまとめ!手続きの期限にも注意
死亡した方がどの方法で納税していたのかを知る
死亡した方の住民税を納める際には、生前どのような方法で納めていたかによって納税する方法が変わってくることがあります。ここでは、どのような種類があるのか紹介していきます。
普通徴収
普通徴収の場合、税を納めなければならない個人宛に役所から納付書が送られてきます。その納付書に従い住民税を納めます。
給与所得以外で収入のある個人事業主や、退職をしていて次の就職先がまだ決まっていない人、特別徴収から普通徴収に切り替わった人などは普通徴収者と呼ばれています。普通徴収では、年に4回住民税を納めているので一度にかかる税の金額が多いのが特徴の1つです。
特別徴収
給与の支払い者である会社が毎月の給与から住民税を差し引いて納めることを特別徴収と言います。会社に勤めている方のほとんどが、特別徴収に当てはまるでしょう。
住民税は所得によって金額が変わってくるので、勤めている会社が住民に代わって納めることでより確実に徴収できるようにする「特別徴収」というのが会社側の義務となりました。
また、仕事を退職して年金をもらっている方は支払われている年金から住民税を差し引いて納めています。これが「年金特別徴収」です。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
納税の方法はどうすればよいのか
では実際に、死亡した方の住民税を納めるにはどうすればよいのでしょうか。一般的には、死亡した方が生前納めていた方法に沿って納めていきます。
ここでは、用意しないといけないものや、やるべきことについて見ていきましょう。
申告をする
死亡した方の相続人は、代わりに納税を行うために税の申告を行います。その際に必要となる書類は、以下の通りです。
・申告する本人の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
・死亡した方との関係性がわかる書類(戸籍謄本など)
・死亡した方の所得がわかる書類(源泉徴収など)
以上の書類が申告の際に必要となるので、書類があるかどうか確認しておくと安心でしょう。
普通徴収の場合と特別徴収の場合
普通徴収の場合は、住民税を納めていた本人の住所に納付書が届くので、それに従い手続きを行えば納めることができます。また、死亡した方の住所がある管轄の役所に問い合わせるのもよいでしょう。
特別徴収の場合は、給与から住民税を差し引いて会社が代わりに納めていましたが、死亡した場合、給与から差し引いて納めることができなくなります。そのため、残りの住民税は個人で納税する普通徴収へと切り替わり、相続人の住所に納付書が送られてきます。
年金から住民税を差し引いて納めている年金特別徴収の場合でも、残りの住民税は普通徴収へと切り替わるため覚えておきましょう。
納めなかった場合はどうなる?
では、住民税を納めないとどうなるのでしょうか。死亡した方の住民税は、相続人が責任を持って納めます。住民税をそのまま放っておいてしまうと、延滞税が発生する可能性があるため注意が必要です。
納付書は、死亡確認後に届くため時間が空くことがあります。そのため忘れてしまいがちで、自分とは関係のないものだと放置してしまうこともあるかもしれません。延滞税が発生すると住民税と同時に余計なお金を失うことになるので、事前にしっかりと確認しておくとよいでしょう。
納付期間が過ぎていた場合は速やかに管轄の役所へと連絡をします。病気やその他の事情がある場合でも早期の相談が大切です。
相続放棄をすることで納税義務を回避できる
一般的に、死亡した方の住民税は相続人が納めますが、「相続放棄」をすれば納税が不要になります。財産の相続はできませんが、負債である税金の納税も不要になるということです。ではどのような時に相続放棄を選択した方がよいのでしょうか。
ここでは、相続放棄を選択する場合について詳しく説明していきます。
負債が明らかに多い
相続では、死亡した方の財産を引き継ぐことができますが、それと同時に負債も引き継ぐことになります。引き継いだ負債が財産よりも多かった場合、多額の損失を被ることになるかもしれません。
問題に巻き込まれたくない
財産が多い場合、相続人同士で揉めてしまうことがあります。お金に関する相続人同士の問題に巻き込まれたくない方は、相続の権利があっても相続放棄をすることもあります。
負担になってしまう
負債はないものの、今後のことを考えると負担になるような財産があります。例えば、田んぼや畑などの土地を相続した場合、その土地の管理が負担になってしまうでしょう。相続者が遠い場所に住んでいて、他の仕事をしていればなおさら大変です。
土地を売却するにしても、さまざまな手続きが必要になってきます。そのようなことを回避するために、相続放棄を選択する状況があるかもしれません。
限定承認
死亡した方の負債を、引き継いだ財産の範囲内で負担することにする「限定承認」という方法があります。相続放棄をしてしまうと手放したくない財産も手放さなければなりません。そのため一部の財産を相続し、引き継いだ財産で支払える程度の負債を引き継ぐ選択をすると安心できます。
また、限定承認をする場合も必要な書類や申告しないといけないことがあるので、事前に確認しておくとよいでしょう。
<関連記事>
相続放棄の手続きや必要書類を分かりやすく|ポイントを知って後悔しない選択をしよう
小さなお葬式で葬儀場をさがす
その他の住民税に関する豆知識
住民税について、他にもわからないことや詳しく知りたい方もいるのではないでしょうか。ここでは、住民税に関するその他のことを説明します。
住民税の減免
減免とは、支払う金額を減らすことです。豪雨や地震、土砂崩れなどの自然災害にあった時には住民税減免の対象になる場合があります。また、前年度の所得に応じて減免できることもあるので、不明な点は管轄の役所に問い合わせてみるとよいでしょう。
所得割と均等割
住民税は、所得割と均等割の2種類で構成されています。所得割は前年度の所得によって金額が定められ、均等割は住んでいる市区町村によって金額が定められています。
住民税の非課税枠
前年度の所得によって、非課税枠となり住民税は不要になることがあります。また、未成年や障がいのある方も非課税の対象となることが多いです。住んでいる市区町村によって異なってくるので、近くの役所へ相談してみるのもよいでしょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
死亡した方の住民税は、死亡したその年までは納めないといけません。納めるのは相続人となるので、手続きや確認をしておくことがあります。死亡した方の住民税を納めることは、葬儀が終わった際にすべきことの1つでしょう。
死亡した方の住民税の扱いについては、専門的な知識を必要とする時もあるかもしれません。わからないことが多く、不安があるという方もいらっしゃるでしょう。そんな時には、ぜひ小さなお葬式にご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



告別式とは、故人と最後のお別れをする社会的な式典のことです。ホゥ。