相続した遺産を分割するときは、相続人同士でいざこざが起きやすいため注意して話し合いや手続きを進める必要があります。慎重に進めなければ相続人との関係に大きな亀裂を生んでしまう可能性も否めません。滅多に会わないような人同士が相続人だった場合、意思疎通が取りにくく話がスムーズに進まないということもあるでしょう。
そこで、相続をどのように進めたらよいのか事前に把握しておくと安心です。今回は、相続分割において相続人同士でいざこざが起きる原因や、いざこざに発展させないための注意点、被相続人が生前にやっておくべきことを解説します。家族信託のサービスについても紹介しているので、参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・遺産分割の際にいざこざが起きる原因は、お金が絡んでいることである
・相続分割の際は遺産の総額を正しく把握する必要がある
・相続人同士で揉めないために遺言書は必ず遺しておく
こんな人におすすめ
相続分割の際に相続人同士でいざこざが起きる原因を知りたい方
相続分割の際にいざこざを起こさないための注意点を知りたい方
相続分割で揉めないために生前にしておきたいことを知りたい方
相続分割の際に相続人同士でいざこざが起きる原因
相続した遺産の分割の際は、相続人同士のいざこざが生じることも少なくありません。事前に原因を知っておき、気をつける必要があるでしょう。故人(被相続人)が遺してくれた遺産をめぐっていざこざに発展することを避けるため、正しく対応することが大切です。
まずは、相続分割の際にいざこざが起きる原因をご紹介します。原因を知ることで事前に対策が可能です。
お金が絡むため
いざこざが生じやすい一番の原因は、何よりもお金が絡んでいることです。相続が発生する以前は関係性が良好だった者同士でも、お金が絡んだ途端に仲が険悪になってしまう可能性があります。特に、遺産を誰か1人が多くもらっている、あるいはもらうべき人物の取り分が少ないといったことがあると、いざこざが生じやすくなります。
遺産が原因でいざこざが生じてしまうと、相続人も逝去した被相続人もよい気持ちはしないでしょう。お金が絡む問題はいざこざが生じやすいということを頭に入れて、慎重に相続分割を行わなければなりません。
法定相続人に連絡が取りづらいことがあるため
被相続人が亡くなったときは、相続の権利を持っている全員に連絡を入れ、状況を説明する必要があります。相続人全員で遺産分割協議書を作成しなければ、遺産分割の段取りは一切進みません。
ただし、普段から連絡を取っている方でなければ、親族であっても連絡先さえも知らないということもあるでしょう。その場合は、連絡先を集めるところから始めなければなりません。故人が持っていた連絡先が古く連絡先が変わってしまっている場合や、前の配偶者との間の子どもに連絡を取らなければならない場合などは、話し合いの場に呼び出すことが難しい可能性があります。
こうした事態を避けるためには、故人が元気なうちにあらかじめ連絡先を整理し、相続の権利があることを本人の口から伝えておかなくてはなりません。また、連絡が取りやすいよう新しい連絡先を遺しておく必要もあります。
連絡が取れないと、相続分割の段取りそのものが進まなくなり、実際に遺産を受け取るまで相当な時間がかかってしまいます。相続が発生したものの連絡先が見当たらない、連絡がつかない場合は専門家への依頼も検討しましょう。
相続分割の際に相続人同士でいざこざを起こさないための注意点
相続分割の際にいざこざが生じやすいとは言っても、できるだけ穏便に段取りを終えたいところです。普段あまり会うことのない人が相続人だった場合、意思疎通が取りにくいことも懸念されます。
しかし、工夫をすれば揉めることなく段取りを完了させられる可能性が高くなります。相続分割で揉めないための注意点をしっかり把握し、適切な対応を心がけましょう。
人の気持ちを思いやる
遺産関連の話し合いはどうしても感情的になり、自分の気持ちを相手に押し付けてしまうことも少なくありません。自分の権利を主張したいあまり、相手を傷つけてしまっては本末転倒です。
また、相続分割ではお金が絡むため、話し合いの内容が複雑になるだけでなく、故人との関わり方や親密度を持ち出した議論に発展する場合も多くあります。しかし、故人から見て立場は異なっていたとしても、相続人同士が冷静に話し合わなければ話は進みません。相手の気持ちを思いやりながら、冷静に話し合いを進めましょう。
金額を正しく把握する
相続分割では遺産の総額を正しく把握しなければなりません。遺産が全部でいくらあるのか正しく把握できていなければ、相続分割は完了しないでしょう。少しでも早く手続きを終えるために、まずは正確な遺産の金額を確認するよう心がけてください。
なお、遺産の金額が正しくなかったことが後からわかった場合、再度遺産分割協議が必要です。再び法定相続人全員を集めるにはかなりの労力と時間を要するでしょう。そのような事態を避けるためにも、遺産の金額を正確に把握しておくことが重要です。
専門家に依頼する
相続分割は難しい手続きが多く、専門知識のない方が調べながら進めるのは困難だと言えるでしょう。特に、遺産が預貯金だけでなく不動産や株式などを含んでいる場合、査定や現金化を行う必要が出てくることもあるので、計算方法はさらに複雑になります。
専門知識のない状態で複雑な計算を行うと、抜け漏れや計算ミスにつながりかねません。計算が間違ったまま申告してしまうと、書類に不備があるとして受理されない可能性が高くなります。そこで、専門家に依頼して手間や時間を減らし、正確な書類を作成してもらうのも一つの方法です。依頼には費用がかかりますが、相続に関する手続きを確実に、そして早く終えたいという方はぜひ検討してみましょう。
相続分割の際に相続人同士で揉めないために生前にできること
相続分割は大きなお金が絡む場合があり手続きが複雑になることから、親族間での揉めごとが起こりやすい傾向にあります。このような相続時の揉めごとを避けるため、遺産を持っている方(被相続人)が生前にできることはあるのでしょうか。ここからは、相続分割を円滑に進めるため、相続が発生する前、つまり生前にできることをご紹介します。
遺言書を遺しておく
遺言書は必ず遺しておきましょう。遺言書がなければ、法律にしたがって相続順位を確認し、順位通りの分割で遺産が相続されます。しかし、中にはその分割方法だと損をしてしまう相続人がいる場合もあります。例えば、故人が逝去する直前まで一緒に暮らして介護をしてもらっていた方に、遺産が一切渡らないといったことも考えられます。こうしたことを避けたい場合、理由を添えて遺言書に記しておきましょう。
遺言書は自筆で作成するのが基本です。パソコンなどで作成してもよいとされているものの、自筆で記載しなければならない箇所も複数あります。そのため、全文を自筆で作成するという認識でいると間違いないでしょう。
また、日付をしっかり記載し、署名して印鑑を押します。遺言書が複数枚あった場合は、日付が新しいものが正式な遺言書と認定されるので、日付は必ず入れなければなりません。そして、署名は自筆する必要があります。本人とわかるものであれば正式な氏名以外でもよいとされていますが、法定相続人全員に浸透している呼び名でなければトラブルに発展する可能性もあるため、基本的には正式な氏名を記載しましょう。
なお、印鑑に関しては実印でなくても問題はありませんが、インクが内蔵されているタイプの簡易なスタンプ式の印鑑は避けたほうが賢明です。
これらは全て、遺言書が偽造されたものではなく、被相続人本人が書いたものだと証明するための大事なポイントです。トラブル防止のために遺言書を作成するのであれば、しっかり守ることが大切です。
平等性を意識する
遺言書がある場合、相続発生時には遺言書の内容が最優先されます。法律で決められた順位を多少無視していても、故人の意思が通る可能性は高いです。
ただし、あまりにも偏りのある内容や理不尽な内容の遺言書作成はおすすめできません。逝去した後に大きないざこざに発展し、遺された相続人たちの関係に亀裂が入る可能性があるからです。
遺言書の内容はあくまでも平等に、相場を意識した内容にするのが基本です。どうしても法律で定められている内容と異なる内容で相続人に遺産を相続させたい場合は、その理由を明確に記し、生前に周囲に伝えておくとよいでしょう。
事前に相続人に話をしておく
事前に相続人と話をしておくのも重要なポイントです。相続分割の際に揉めごとが起こりやすい原因のひとつとして、故人から何も話がなかったという例は少なくありません。
逝去してから法定相続の分け方とは違う内容の遺言書が発見され、その内容に不満や疑問が生じたとしても、被相続人が理由を説明することはできません。そうなると、相続人たちの間で不満や怒りが爆発し、お互いの関係を悪化させてしまいます。
そのため、遺言書の内容は被相続人が元気なうちに自ら相続人に伝えておくことをおすすめします。
納得感を重視する
遺言書の内容は、相続人にとって納得感があるものにしなければなりません。例えば、正妻ではなく愛人に遺産を全て渡すという内容が記載されている場合、法定相続人である正妻は納得できないでしょう。このような理不尽な内容だった場合には、争いが生じる可能性が高いといえます。
遺言書の内容に不満があった場合、裁判で決着をつけることもあります。しかし、裁判に発展すると状況はどんどん悪化し、手続きを終えるまで相当な時間がかかってしまいかねません。遺産を遺したい人のためにも、こうした事態は避けたほうが賢明です。相続人が納得感を持てる内容の遺言書を作成することでトラブルを避けられるでしょう。
寄与分が適用される人物がいないか確認する
寄与分とは、被相続人に対し、介護や仕事などで貢献した人物が使用できる制度です。生活を共にして介護をしていた方や、実家の仕事を無償で手伝っていた方などが該当します。しかし、この寄与制度の判断は非常に難しい問題です。
一緒に住んでいたのであれば食費や家賃、光熱費などの自己負担は発生しません。そうすると、被相続人から補助を受けていたという認識になるので、寄与分を受け取れる条件には該当しない可能性があります。
相続人の中には、1人あたりの遺産の金額を減らしたくないと考える方もいるため、様々な理由をつけて寄与分を適用できない理由を探る可能性は否定できません。また、寄与分をめぐって裁判に発展してしまうことも珍しくありません。自分の世話をしてくれた方に遺産を遺したいと考えている場合は、必ず遺言書に記載しておきましょう。
家族信託という選択肢もある
相続した遺産の分割について詳しく知りたい際に、認知症による口座の凍結などについても気になるという方は多いのではないでしょうか。認知症になると、法的に意思能力がないものとされる可能性があり、本人名義の不動産の売却や、銀行口座からの出金が凍結によってできなくなることがあります。唯一の対処法である「成年後見制度」も、費用や財政管理の面で戸惑う方が多いようです。
そこで今注目されているのが、大切な財産を信頼できるご家族に託す「家族信託」です。認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することができます。
ファミトラの「家族信託」は家族信託に必要な手続きを、弁護士や司法書士など多様な専門家がサポートし、誰でも簡単に・早く・安く組成できるサービスです。資産管理にお困りの方は、お気軽にお問合せください。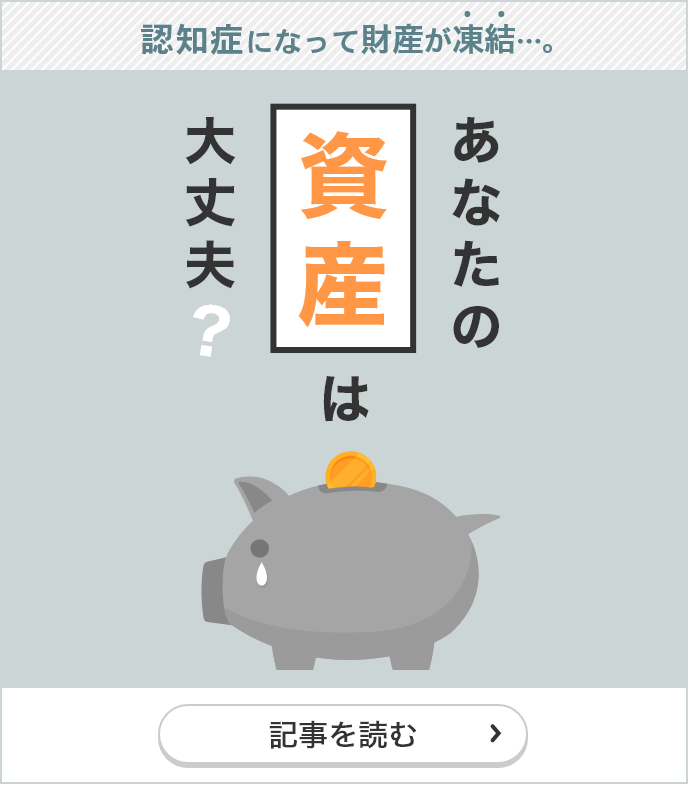
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
相続分割はトラブルに発展しやすく、親族関係に亀裂が入ってしまうこともあり得ます。遺産にまつわる問題についてはお金が絡むため、意見がぶつかりやすく話し合いが一筋縄ではいかないこともあるでしょう。
故人が遺してくれた遺産をめぐって関係が悪くなってしまうのは避けたいものです。そうならないためにも、まずは遺産を持っている方が、ご紹介した生前の準備をすることが大切です。そして、相続人にあたる方は早い段階で専門家への相談を検討することをおすすめします。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
相続分割の際にいざこざが起きる原因は?
相続分割で揉めないための注意点は?
相続分割の揉めないために生前にできることは?
相続分割で相続人全員に連絡を取らないといけない理由は?
葬儀の喪主を選ぶとき、もっとも影響力を持つのは故人の遺言です。ホゥ。
































