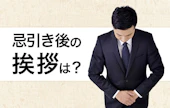身内が亡くなった際、多くの方が葬儀を執り行うでしょう。その際、身内や親戚にとどまらず、働いている会社や職場の方々から香典を渡される可能性も少なくありません。職場から香典をいただく場合、規定などによって香典返しの様相が変化することがあるので、注意事項を確認しておきましょう。
この記事では、職場に対する香典返しのマナーややり方について、複数のケースを例にしながら解説します。事前に知っておくことで、職場に対するマナーを遵守でき、今後の人付き合いに役立つでしょう。
冠婚葬祭に関しては、普段から常に行われる儀式ではないため、急なことだと疑問や不安に思うこともあるでしょう。しかし、少しでも基礎知識を身につけておくことで、突然の不幸にも対応できるようになります。また、香典をいただく遺族側の立場だけでなく、香典を渡す参列者側としてのマナーもあわせて確認しましょう。
<この記事の要点>
・会社規定がなく個人名で香典を渡された場合は、香典返しが必要
・職場への香典返しはいただいた金額の半分程度がマナー
・職場で香典返しを渡す際は、香典のお礼や忌引きのお詫びなどを伝える
こんな人におすすめ
職場に対する香典返しの方法・マナーを知りたい方
職場に適した香典返しとは何かを知りたい方
職場で香典返しを渡す場合のポイントを知りたい方
職場のきまりをよく確認する
突然の訃報があった場合、職場の関係者からも香典を受け取る場合があります。その場合は、まず以下を確認しておきましょう。
・誰からの香典であるか
・職場からひとくくりなのか
・名義は何と書かれているか
一般的に、職場からいただく香典には会社名と、社長などの代表取締役等の名前が記されていることが多く見られます。しかし、実際に手配しているのは、総務などの実務を行っている部署が用意していることがほとんどでしょう。また香典は、職場の直属の上司等から手渡されるパターンが多いでしょう。
「会社全体」として香典をいただいた場合は、社内規定に記されている冠婚葬祭の欄にその旨が記されていることが一般的です。多くの会社が、社員の身内や家族に不幸があった際は、社内規定に則って香典を出すきまりを設けています。
香典は、社員から徴収する場合もありますが、基本的に経費で賄われることが多いといわれています。そのため、香典返しを改めて用意する必要がない場合が多いでしょう。香典のほかにも、供花や弔電をいただいた場合も同様で、お返しの必要はありません。
社内規定がない場合は香典返しをする
会社によっては、社員規定に冠婚葬祭に関する情報が載せられていなかったり、規定そのものがなかったりする場合もあるでしょう。その場合は、社長などが個人の意思で、訃報を聞いて香典を包んでくれることがあります。
定められたきまりがない会社から、または有志から善意で香典をいただいた場合は、他の親族や遺族からいただいた香典と同じように香典返しをする必要があります。
香典返しを渡すときはお礼とセットで
香典返しを渡すときは、香典をいただいたお礼と、弔問に来ていただいたお礼をあわせて伝えるとよいでしょう。不幸があって休んだ場合は、その趣旨も忘れずに伝えるようにします。
不幸の休暇は関係性にもよりますが、会社によっては長い期間を設けるといった配慮があることも多いでしょう。忌引休暇で長期間休んだ場合は、迷惑をかけた趣旨のお礼をしっかりと香典返しに込めることが大切です。
上司や同僚からも香典をいただくことがある
通常、職場から香典をいただくときは、規定に沿ったものを会社や代表から渡されます。一方で、まれに会社関係でいつもお世話になっている上司や同僚、後輩、また取引先などから香典を受け取る可能性も視野に入れておきましょう。
場合によっては、香典だけでなく弔問に訪れてくれることもあります。個人名で渡された際には、親族と同様に香典返しの用意が必要です。職場関係であれば直接お礼と挨拶を添えて渡すことができるので、少し早い時間か、帰り際の人が少ない場所などでしっかりと渡すようにしましょう。
会社規定がない場合は、いただいた香典は個人の有志であるという認識を持っておきましょう。
香典返しを渡す時期
身内や親族に対する香典返しの一般的なマナーとしては、渡す時期や挨拶の時期は、一旦法要が落ち着く四十九日のあとが適切とされています。しかし、会社関係の場合は日程が少々ずれても問題ない傾向にあるようです。例えば、会社へは忌引きが明けた翌日にはもう出勤するため、お詫び等とあわせて忌引き明けにすぐ渡すのもよいでしょう。
香典返しのマナーは、基本的に手渡しとされています。そのため、忌引きが明けて出勤したタイミングは、朝や終業後など、皆が事務所に集まっているときに切り出すのがベターです。しかし、手配を一括にしている場合は、もちろん四十九日が終わったあとでも問題ありません。
郵送する場合は、職場だとしても挨拶状やお礼状を用意するのを忘れないようにするのがマナーです。香典返しの品物とは別に封筒を用意し、マナーに沿ってしっかりとお礼状を用意しておきましょう。
職場に適した香典返しとは何か
自分が勤めている会社関係からの香典を渡された場合、親族と異なる香典を用意した方がよいのではないかと悩む方も多いのではないでしょうか。例えば、会社からの香典は、会社名や社長名義で送られてくることも多いのですが、場合によっては連名で受け取るケースもあるためです。
会社が連名を使う理由
会社側は、社員の不幸があった場合は香典を渡すのがマナーだと考えていることが多いでしょう。社内規定などに即しながら総務に手配される反面、同じ部署や親交の深い場合は有志で人を募り、連名で送られることも考えられます。
連名にすることで、一人ひとりへの香典返しの手間を省略し、故人を悼む気持ちを伝えることができます。また、贈る側としても、一人あたりの金銭的な負担を軽減できるメリットがあります。
社員が香典を連名で渡すときの負担は、一人あたり数百円~数千円程度で収まることが多いでしょう。人数にもよるので一概にはいえませんが、合わせて三千円~五千円程度にまとめることで、故人への追悼の気持ちを伝えることができるでしょう。また、お返しの際も気負わせることが少なくなるので、お互いに楽な気持ちで最低限のやり取りが行えます。
菓子折りが一般的
社長名義といった会社代表ではなく、同部署の社員や上司が有志で集まり、連名での香典を渡された場合、適切だとされているお返しは菓子折りです。忌引き明けに一度に渡すことができ、お礼も全員に平等に伝えることができます。
基本的に、職場からの香典へのお返しはいただいた金額の半分程度がマナーとされています。高額過ぎてもいけないので、忌引き明けはもらった金額の半分程度の菓子折りを持って出勤しましょう。
また、香典返しの専門店や葬儀会社に依頼することで、半返し程度の菓子折りやお返しを用意してもらえるので、相談して選ぶこともおすすめです。
職場で香典返しを渡す場合のチェックポイント
香典返しを持って出勤する際、注意しておきたいことや、気を付けたいことをポイントごとにまとめました。まずは、以下の点に注意しましょう。
・香典のお礼
・忌引きのお詫び
・職場復帰の報告
・香典返しがある趣旨
これらをしっかりと上司や同僚に伝えることが、香典返しを持参した場合に必要なマナーです。
お礼状と異なり、口頭で伝えるのは難しいかもしれませんが、お礼を伝える程度であれば問題ありません。口頭でのお礼や挨拶が難しいと判断した場合は、事前にマナーサイトを見て文章を読んでみるのがおすすめです。
マナーが気になる場合は専門会社に依頼
香典返しの包み紙や、会社に渡すための菓子折りに添えるマナーなどが不安だという場合は、葬儀社に相談することで、香典返しのアドバイスを受けることができます。
参考になるWEBサイトや便利に利用できる情報を教えてもらえることもあるので、マナーが気になる場合は相談してみてもよいでしょう。
職場の香典返しを郵送で手配する場合
香典返しを郵送で手配することもあるでしょう。その際は、職場や上司、社長などにお返しが必要な場合でも同様に手配したものを贈っても問題ありません。その場合は、挨拶状やお礼状と呼ばれる封筒に入れた手紙を同封するのがマナーです。
郵送する場合は、葬儀社に相談することでお礼状の定型文のアドバイスを受けることができます。また、文房具店などで購入したお礼状の用紙には基本的なマナーについて添えられている場合があるので、安心できるでしょう。
香典返しだけではなく、感謝の気持ちや、元気にしている趣旨などを簡潔に文章にしたため添えることがマナーとして必要です。香典返しは、必ずしも直接菓子折りなどのお返しを持っていくスタイルでなくても問題ありません。しかし、郵送にした場合は口頭で行う予定だった挨拶を文章にするのを忘れないようにしましょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
香典返しは、親族に贈る場合にもマナーが重要視されますが、場合によっては会社関係のケースで悩むこともあるでしょう。その際は、社内規定に香典について記されているか確認してみましょう。
多くの会社では、会社が取り決めた規約に従って、経費を利用して香典を用意するので、その場合は会社に対して香典返しをする必要はありません。しかし一方で、有志で集まって連名で受け取った際や、規約が明確にされていない会社からのものには、通例通り半返しを行います。
郵送で香典返しをする場合は、お礼状を同封することが大切です。連名の香典へのお返しの場合は、半返しになるよう菓子折りなどを用意するのがおすすめです。
小さなお葬式では、葬儀手配のサポートはもちろん、四十九日後に必要な香典返しのアドバイスも行っています。職場関係に渡したい際には、四十九日前の用意が必要な場合もありますが、そういったケースにも対応しています。香典返しについての疑問がある際には、ぜひ一度小さなお葬式にお問い合わせください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



全ての箇所を自筆する普通方式の遺言書を「自筆証書遺言書」と呼びます。ホゥ。