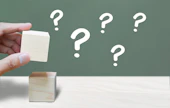親が亡くなると、その遺産は子どもや相続人へと引き継がれます。その際、一定の金額以上の遺産があると相続税が発生します。親が急に亡くなった場合など、相続税の問題に突然直面して戸惑う方もいるでしょう。
この記事では、相続税が発生する金額や相続税の特徴について解説します。相続税で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
<この記事の要点>
・相続税の基礎控除額は3,600万円で、法定相続人が1人増えるごとに基礎控除額は600万円ずつ増える
・相続税には、相次相続控除、小規模宅地の特例、暦年課税、相続時精算課税などがある
・相続税の申告は「相続の開始があったことを知った日から10か月以内」に行う必要がある
こんな人におすすめ
相続税はいくらからかかるのかを知りたい方
相続税額に影響する基礎控除以外の控除や特例を知りたい方
相続税の対象となる財産とならない財産を知りたい方
相続税はいくらからかかるのか
相続税の基礎控除額は3,600万円で、法定相続人が1人増えるごとに基礎控除額は600万円ずつ増えます。国税庁の調査によると、令和元年に相続税の納税対象者の割合は8.3%(12人に1人程度)でした。この結果から、多くの方は相続税を納めることなく遺産を相続していることがわかります。
土地を相続した場合でも、土地の相続税評価額が基礎控除額の3,600万円を超えない限り、相続税はかかりません。相続税がかかる場合でも、遺産全額に対してかかるわけではなく、3,600万円を超えた分に対してだけ課税されます。
参考:国税庁『令和元年分 相続税の申告事績の概要』
相続税額に影響する基礎控除以外の控除や特例
相続税は基礎控除以外にも、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、小規模宅地の特例、贈与税額控除(暦年課税)、贈与税額控除(相続時精算課税)などの控除があります。それぞれの内容について、わかりやすく解説しましょう。ここに挙げる控除や特例について知っていれば、相続税の負担を減らすことができます。
配偶者の相続税額軽減
配偶者の相続税額軽減とは、配偶者が相続した財産が1億6,000万円以下であれば、相続税は課税されない制度のことです。また、1億6,000万円を超えた金額を相続した場合でも、遺産相続の割合が「配偶者の法定相続分」の範囲内であれば課税されません。
配偶者の法定相続分は、ほかに誰が法定相続人になるかによって変わります。
未成年者控除
相続人の中に未成年者がいる場合は、未成年者が本来納めるべき相続税額から一定金額を控除できる「未成年者控除」という仕組みがあります。
控除される金額は次の計算式で算出できます。
(20歳-相続したときの年齢)×10万円
未成年者控除は、以下のすべてに当てはまる人が受けられます。
(1)①相続や遺贈で財産を取得したときに、日本国内に住所がある人、または②相続や遺贈により財産を取得したときに、日本国内に住所がない人でも次のいずれかに該当する人
イ 日本国籍を有しており、かつ、その人が相続開始前10年以内に、日本国内に住所を有していたことがある人
ロ 日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に、日本国内に住所を有していたことがない人(被相続人が、外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)
ハ 日本国籍を有していない人(被相続人が、外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人である場合を除きます)
(2)相続や遺贈で、財産を取得したときに20歳未満である人(令和4年4月1日以後は18歳)
(3)相続や遺贈で、財産を取得した人が法定相続人であること
未成年者控除の金額は、その未成年者が成年になるまで1年につき10万円で計算した金額です。
参考:国税庁『未成年者の税額控除』
障害者控除
障害者が財産を相続した場合に相続税が軽減される特例措置が「相続税の障害者控除」です。
障害者控除は、以下のすべてに当てはまる人が受けられます。
(1)相続や遺贈で財産を取得したときに、日本国内に住所がある人
(2)相続や遺贈で財産を取得したときに、障害者である人
(3)相続や遺贈で財産を取得した人が、法定相続人であること
障害者控除は、その相続人が満85歳になるまで、1年(1年未満は切り上げ)につき10万円が控除されます。特別障害者の場合は、1年につき20万円が控除されます。
参考:国税庁『障害者の税額控除』
相次相続控除
相次相続控除とは、相続が発生してから10年以内に次の相続が発生した場合に、相続税の金額から一定の金額を控除できる制度です。相続が立て続けに起こった場合に利用することで、税負担を軽減することができます。
相次相続控除は、以下のすべてに当てはまる人が受けられます。
(1)被相続人の相続人であること
(2)その相続の開始前10年以内に開始した相続により、被相続人が財産を取得していること
(3)その相続の開始前10年以内に開始した相続により、取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと
相次相続控除は、前回の相続から次の相続までの期間が短いほど控除額が大きくなります。
参考:国税庁『相次相続控除』
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たした場合に土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。この特例は、亡くなった後も故人の配偶者や家族が自宅に住み続けられるように制定されました。
小規模宅地等の特例の対象となる土地は以下の3種類です。
・実際に住んでいた土地(特定居住用宅地)
・事業を行っていた土地(特定事業用宅地)
・賃貸していた土地(賃貸事業用宅地)
贈与税額控除(暦年課税)
贈与税額控除とは、同じ財産に対して相続税と贈与税が二重課せられないように、贈与財産に課税された贈与税を相続税から控除できる仕組みです。
贈与税額控除の適用条件は以下の2点です。
・生前贈与加算されていること
・贈与税が課税されていること
贈与税額控除(相続時精算課税)
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から、成年以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。この制度を選択するには、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、一定の書類を添付した、贈与税の申告書を提出しなければなりません。父母または祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に、この制度を適用した贈与財産の価額を加算して、相続税額を計算します。
本来であれば贈与した時点で贈与税が発生しますが、その贈与税を死亡後に納めるよう調整できるのが「相続時精算課税」と呼ばれる制度です。贈与税の納税時期を生前から死亡後に先送りできる制度といえるでしょう。
相続税の対象となる財産とならない財産
相続税は、死亡した人の財産を、相続した場合に課税されます。しかし、相続した財産すべてにはかかりません。相続税の対象になる財産と、ならない財産をまとめてみましょう。相続税の対象になる財産は、かなりの数に上るので、一覧表にしてまとめておきました。
対象になる財産
相続税の対象になる財産には、以下のようなものがあります。
・現金、預貯金
・土地
・建物
・上場株式、非上場株式
・投資信託
・公社債
・生命保険
・死亡退職金
・事業用財産
・ゴルフ会員権
・貸付金
・未収金
・自動車
・金地金や貴金属
・書画骨董
・電話加入権
・家庭用財産(家具、家電等の家財)
・海外財産(コンドミニアム等の不動産や、海外の預金や株券等)
・被相続人の亡くなる前3年以内に被相続人から受けた贈与
・相続時精算課税による贈与
・名義財産(配偶者、子、孫などの名義であっても、亡くなった人が資金を拠出し、管理をしていた場合には相続税の対象)
対象にならない財産
亡くなった人に専属的に帰属していた財産や、相続税法で非課税と規定されている財産(非課税財産)には、以下のようなものがあります。
1. 墓地、仏壇、仏具、神棚、神具 など
2. 弁護士資格、医師免許等の一身専属権 など
3. 生命保険の非課税枠
法定相続人の数×500万円までは非課税です。
4. 死亡退職金の非課税枠
法定相続人の数×500万円までは非課税です。
相続税がいくらかかるのかを調べよう
相続税の計算は、実際に取得した財産に直接税率をかけて算出するのではありません。
ここからは、相続税額の計算方法について具体的な例とともに解説します。
速算表に基づいて計算する
遺産総額から基礎控除額を差し引いた残りの金額を、民法に定める相続分で按分した金額に、税率をかけたものが相続税額になります。法定相続分により按分した法定相続分に応ずる取得金額を、下表にあてはめて計算して算出された金額が相続税の総額です。
【相続税の速算表】
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 35% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この速算表で計算した、法定相続人ごとの税額を合計したものが、相続税の総額になります。
相続税の申告要否判定コーナーを利用する
国税庁のホームページにある、相続税の申告要否判定コーナーを利用して、相続税のシミュレーションをする方法をご紹介します。
1.「国税庁ホームページ」の「申告・申請・届出等、用紙(手続の案内・様式)」をクリックします。
2.「確定申告等情報」の「相続税」をクリックします。
3.「相続税の申告要否判定コーナー」をクリックします。
4. 画面の案内に従って法定相続人の数を入力すると、遺産に係る基礎控除額を自動で算出します。
5. 相続等により取得した財産や債務の価額等を個別に入力します。
6. 画面の案内に従って金額等を入力すると、相続財産等の評価額等を自動で計算します。
7. 上記の入力内容をもとに、相続税の申告要否のおおよその判定を行います。
8. 相続税の申告要否の判定後、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)、及び配偶者の税額軽減(配偶者控除)を適用した場合の、税額計算のシミュレーションを行うこともできます。
9. 税額計算のシミュレーションでは、相続税の申告要否の判定後、「小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)」、及び「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」を、適用した場合の税額計算を行います。
相続税がかからないなら申告は必要ない?
遺産を相続しても、相続税がかからないこともあるでしょう。相続税がなければ申告をする必要はないと思ってしまいがちですが、その場合でも申告が必要なケースがあるので詳しく見てみましょう。
相続税がなくても申告が必要な場合がある
遺産総額が基礎控除額以内であるかどうかはっきりとわからない場合は、相続税を申告したほうがよいでしょう。遺産総額を見直したら、想定以上に高額になるケースもあるからです。相続税がかからないと思う場合でも、念のために申告したほうが安心です。
基礎控除額を超えた場合でも、配偶者相続税額軽減や小規模宅地等の特例で、最終的に相続税がなくなる場合もあります。ただし、基礎控除額を超えた場合には、申告が必要になります。申告する窓口は被相続人の居住地を管轄する税務署です。自身の居住地を管轄する税務署ではないので、間違えないように注意しましょう。
相続税の申告は10ヶ月以内が期限となる
相続税の申告は、「相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内」に行う必要があります。期限を過ぎてから申告すると、加算税が課せられるので注意しましょう。10ヶ月という期間は余裕があるように想えますが、遺産分割などで揉めたりするとあっという間に時間が経ってしまいます。期限を過ぎた日数分だけ延滞税が課せられるので、申告や納税は早めに済ますことをおすすめします。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
家族が急に亡くなってしまうと、相続税の問題に頭を抱えてしまうこともあるでしょう。心の整理もつかず大変な時期ではありますが、相続税を申告には期限がきめられています。自分や家族だけでは判断できない場合は、税理士に依頼することもひとつの方法です。
小さなお葬式では葬儀に関するさまざまなお悩みやご相談をお受けしております。葬儀後の手続きなどについても、お気軽にご相談ください。専門知識が豊富なスタッフが、24時間365日通話料無料でご連絡をお待ちしております。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


葬儀の挨拶では、不幸を連想させてしまう忌み言葉と重ね言葉には気をつけましょう。ホゥ。