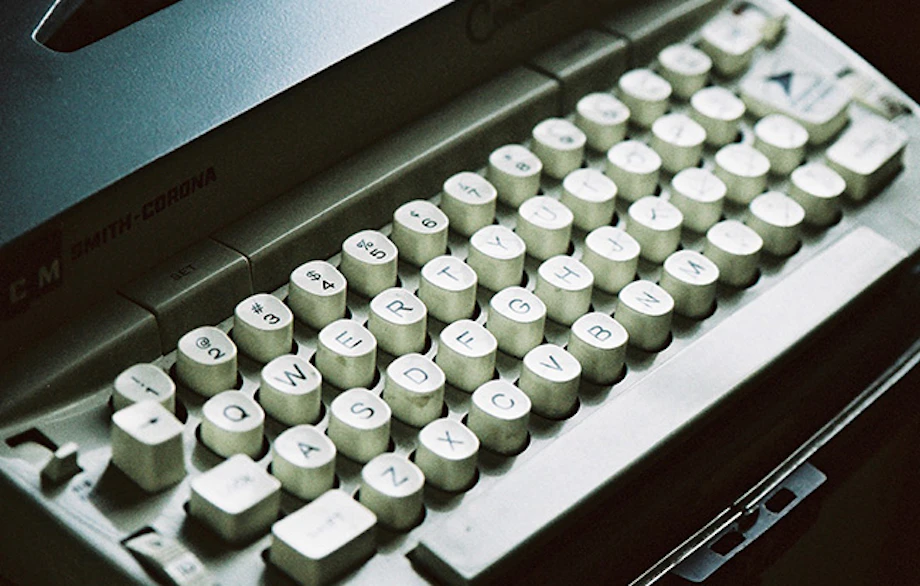親族や知人、会社の人などの訃報を受けたものの、通夜や葬儀に参列できない場合は弔電を送るのがマナーです。しかし、弔電は人生のなかでも書く機会は多くないため、書き方が分からない方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、弔電の書き方や送り方について解説します。
<この記事の要点>
・弔電を書く際は正しい敬称を使用し、忌み言葉は避ける
・弔電の受取人名は喪主の氏名にするのがマナー
・弔電は、通夜や葬儀の前日までに送るのがマナー
こんな人におすすめ
弔電の書き方にお困りの人
やむを得ず通夜や葬儀に参列できない人
故人や遺族にお悔やみの気持ちをしっかりと伝えたい人
弔電を書く前に!確認しておくべきことは?
弔電とは、故人や遺族にお悔やみの気持ちを伝える電報のことです。弔電を書く前に、確認すべき点が3つあります。弔電を書く際はここで紹介することを押さえておきましょう。
葬儀の詳細について
弔電は式場で読み上げられるため、式場へ直接送るようにしましょう。事前に通夜や葬儀、告別式の日時と場所をきちんと確認しておかなくてはいけません。くれぐれも亡くなった方の家に送らないように注意しましょう。
喪主の氏名と故人との続柄について
弔電の受取人は「喪主」です。喪主の氏名と故人との続柄についてきちんと確認しておかないと失礼にあたるため、気をつけなくてはいけません。
喪主の名前はフルネームでミスなく記載しましょう。故人との関係性によって、敬称が変わる可能性もあるため、続柄の確認は重要です。
宗教や宗派について
故人が信仰していた宗教や宗派によっては、使用を避けたほうがよい言葉があります。仏教なのか、キリスト教なのかなど、事前に確認しておきましょう。
仏教の場合、「迷う」「天国」といった言葉を使うと失礼にあたります。キリスト教の場合、「供養」「成仏」といった他宗教の言葉は避けましょう。
弔電の書き方!3つのポイント
弔電は人生のなかで何度も書くものではないため、書き方が分からない方も多いでしょう。ここでは弔電の書き方のポイントを3つ紹介します。
正しい敬称を使う
弔電を書く際は正しい敬称を使わないと失礼にあたります。以下のような敬称を参考にしてください。
・夫:御主人
・妻:御令室
・実父・義父:御尊父
・実母・義母:御母堂
・息子:御子息
・娘:御令嬢
・兄:御令兄
・姉:御令姉
・弟:御令弟
・妹:御令妹
なお、息子・娘・兄弟姉妹の場合は、血縁でなくても上記の敬称を用います。
故人との関係に合った文面にする
弔電は自分と故人との関係性に適した文面にするのがポイントです。故人が親族や友人の場合、過去の思い出やエピソードを盛り込んだ内容にするとよいでしょう。
故人が職場の上司である場合、個人的なエピソードや思いを伝えるのではなく、簡潔にお悔やみの言葉を伝えるようにすることが大切です。
忌み言葉は避ける
弔電では、忌み言葉に気をつけて文章を作成する必要があります。忌み言葉とは、冠婚葬祭で使用を控えたほうがよい言葉のことです。
例えば、「重ねる」「再び」「いよいよ」といった繰り返す言葉、数字の「9」「4」といった「苦しみ」「死ぬ」を連想させる言葉などがあります。
ケース別!弔電を送る際の文例
ここでは、ケースごとの弔電の文例を紹介します。故人との関係性によって使うべき言葉が異なるため、注意して弔電を作成しましょう。
一般的な弔電のケース
下記が一般的なシーンで使える弔電の文例です。
・ご逝去を悼み、心からお悔やみ申し上げます。
・突然の訃報に接し、心からお悔やみ申し上げます。
・〇〇様のご逝去を悼み、心からお悔やみ申し上げますとともに、ご冥福をお祈りいたします。
故人が先方の父母であるケース
父親や母親を失った人に対して向ける弔電は、以下のように遺族へ労いの言葉を盛り込むとよいでしょう。
・御尊父様のご逝去の報に接し、惜別の念でいっぱいです。ご遺族様のお悲しみは計り知れないものとお察しいたします。在りし日を偲び、安らかな旅立ちを心からお祈りいたします。
故人が先方の配偶者であるケース
夫や妻を失った人は、特に精神的につらい状況にあります。悲しみに寄り添い、ご遺族に配慮する気持ちを伝えるようにするとよいでしょう。
・〇〇様のご逝去の報に接し、茫然としております。奥様のご心痛はいかばかりかとお察しいたします。在りし日のお姿を偲び、安らかなご永眠をお祈り申し上げます。
故人が先方の子どもであるケース
子どもを失う悲しみはとても深いものです。ご遺族の悲しみに寄り添い、気遣うような文章を作成しましょう。ただし、長文な弔電にならぬよう、気をつけてください。
・御令嬢様の突然の悲報に愕然といたしております。ご両親様のご無念のお気持ちはいかばかりかとお察しいたします。ご生前のご厚情に感謝するとともに、安らかなご永眠を心よりお祈り申し上げます。
故人が社長や会長であるケース
会社関係の場合、部署や会社単位で送ることがほとんどであるため、内容は簡潔にしましょう。社長や会長の功績をたたえる気持ちを含めるのがポイントです。
・社長様のご訃報に接し、お悔やみ申し上げます。会長様には、弊社社員一同、言い尽くせない恩義を感じております。ご功績に敬意を表しつつ、心よりご冥福をお祈りいたします。
弔電を送る方法は?
弔電は電話注文や郵便局、インターネットで申し込む方法があります。電話注文の場合、局番なしのダイヤル115で受け付けてもらえます。弔電の受付時間は、午前8時から午後の10時です。インターネットの場合は、24時間受け付けています。
弔電を送る際のマナー
弔電にはマナーがあります。弔電を送るのに慣れていないとはいえ、マナーを守らないとご遺族を不快にさせてしまうため注意しましょう。ここでは、弔電を送る際のマナーを3つ紹介します。
受取人名は喪主の氏名にする
弔電の受取人名は故人ではなく、喪主の氏名にするのがマナーです。喪主の名前は必ずフルネームで記載しましょう。他の遺族に宛てた弔電であっても、表向きは喪主にします。社葬の場合は、喪主の名前ではなく、会社や葬儀委員長宛に送る場合もあります。
通夜や葬儀の前日までに送る
弔電は、通夜や葬儀の前日までに送るのがマナーです。訃報を聞いたらすぐに準備しましょう。送るタイミングを間違えると、ご遺族を不快にさせてしまう恐れがあります。遅くても、通夜や葬儀がはじまるまでに送るようにしましょう。
葬儀を営む場所に送る
弔電は通夜や葬儀で読み上げられます。葬儀が自宅で行われる場合は自宅に、斎場や葬儀場で行われる場合は、そちらの住所に送るようにしましょう。葬儀の開催場所や日時は事前にきちんと確認しておき、間違えないように気をつけてください。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
弔電を書く機会は人生のなかでもそう多くはないため、書き方に悩んでしまうものです。しかし、マナーを守って送らないと失礼にあたります。この記事で紹介したポイントや注意点を押さえ、お悔やみの気持ちが伝わるような弔電を送りましょう。
「小さなお葬式」では、葬儀や法要に関する相談を受け付けています。小さな疑問にもお答えいたしますので、お客様サポートのフリーダイヤルからお気軽にお問合せください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



全ての箇所を自筆する普通方式の遺言書を「自筆証書遺言書」と呼びます。ホゥ。