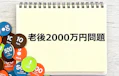「老後の資金作りとしてiDeCoが話題だけれど、不向きな方もいるのではないだろうか」このようにお考えの方も、いるのではないでしょうか。様々な事情でiDeCoを使えない、またはiDeCoよりも他の金融商品を使ったほうがよい方はいます。
重要なことは、それぞれの事情にあわせた方法で資金をつくることです。そこでこの記事では、iDeCoをおすすめしない9つのケースを取り上げ、どのような方法が向いているか考えます。あわせてiDeCoをおすすめする5つのケースについてもご紹介します。
<この記事の要点>
・iDeCoで運用する資金は、原則60歳にならないと引き出せない点に注意が必要
・マイホーム資金や教育費が今後必要な人はiDeCoへの加入は適していない
・収入が少なく国民年金の免除を受けている場合はiDeCoへの加入ができない
こんな人におすすめ
iDeCoについて知りたい人
iDeCoを検討している人
iDeCoはおすすめしないと聞いたことがある人
iDeCoとはなにか?
iDeCoとは、以下の特徴を持つ私的年金です。
・原則として60歳まで引き出せないため、老後の資金づくりに特化している
・月々の拠出額だけでなく、運用成績によって将来の年金額が変わる
・運用する金融機関や商品、拠出額は、自分の意思で決められる
・拠出時、運用時、受給時のそれぞれについて、非課税などの優遇措置がある
このため、「自分の年金は自分でつくる」という意識を持っている方に向いています。
以降の見出しでは、iDeCoのデメリットやおすすめしない9つのケース、またiDeCoをおすすめする5つのケースを紹介していきます。
(参考:『iDeCo(イデコ)の特徴』 国民年金基金連合会)
iDeCoを利用する際の7つの注意点
「iDeCoを利用し、老後の資金を準備したい」とお考えの方に、ぜひ知っておきたい注意点が7つあります。詳しく確認していきましょう。
60歳になるまで原則引き出せない
iDeCoで運用する資金はご自身のものですが、原則として60歳にならないと引き出せない点に注意が必要です。たとえ自己破産をしなければならない状況になったとしても、「まとまったお金が必要」という理由で引き出すことはできません。しかし強制的に解約されないため、老後の資金が守られるメリットはあります。
とはいえ、まとまった資金が必要なときに対応できないと困る場合も多いでしょう。iDeCoを選ぶと、このような事態に対応できないことが難点です。
元本割れのリスクがある
iDeCoで資産を増やすためには、「投資信託」の活用が欠かせません。一方で投資信託は日々価値が変動する金融商品なので、元本割れのリスクがあります。預貯金のように元本保証でないため、運用成績によっては払い込んだ額よりも受け取る額のほうが少なくなる可能性があることに注意が必要です。
途中でやめられない
iDeCoによる運用は、長い期間におよびます。ときには、iDeCoをやめたいと思う場合もあるかもしれません。しかしiDeCoをやめられるケースは、以下の条件を満たした場合に限られます。
1.国民年金保険料の納付を免除されていること
2.確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
3.通算拠出期間が5年以下、又は個人別管理資産が25万円以下であること
4.最後に企業型確定拠出年金(企業型年金)又は個人型年金の資格を喪失した日から2年以内であること
5.企業型年金の加入者資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと
iDeCoをやめられるケースは拠出期間が短く運用中の資産も少額な方で、国民年金の免除を受けた方に限られます。ハードルは高いといえるでしょう。
一方でiDeCoでは運用商品を変更する、掛金の拠出を停止するといった方法を選べます。途中でやめたいと思った方は、リスクの少ない商品に変更して運用する、掛金の支払を止めるといった方法をご検討ください。
投資の勉強が必要
iDeCoで資産を増やすことは、投資信託の上手な活用方法とほぼ同じです。このため投資に関する基本的な勉強は必要ですが、デイトレードに代表される短期投資に関する知識は必要ありません。
またiDeCoでは、複数の投資信託から選べます。投資先は自分自身で決める必要があるため、投資信託の商品を適切に選ぶ知識も身につけておきましょう。
手数料や維持費がかかる
iDeCoでの資産運用には、以下の費用がかかります。
・加入時や受け取る際には手数料が必要
・毎月数十円~数百円の口座管理料がかかる
・投資信託の場合は、信託報酬が日々差し引かれる
口座管理料は金融機関ごと、信託報酬は商品により大きく異なります。また定期預金で運用する場合は金利が非常に低いため、受け取る利息よりも口座管理料のほうが上回り、元本割れとなるリスクもあることに注意が必要です。
参考:確定拠出年金教育協会「手数料(口座管理料)で比較」
加入年齢に上限がある
2022年5月以降は、会社員・公務員などで60歳以上65歳未満の方、国民年金に任意加入している60歳以上65歳御南の方も加入できるようになりました。「60歳以上になっても、働いて老後資金を増やしたい」という方には、朗報といえるでしょう。
(参考:『iDeCoに加入できる年齢の要件などが拡大されます』厚生労働省)
企業型確定拠出年金と併用できない場合がある
企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入する企業にお勤めの場合、iDeCoへの加入は企業が認めていることが条件です。実際には多くの企業が両方への加入を認めていません。このため「もっと老後の資金を増やしたい」と思っても、iDeCoを使えない制約があります。
ただし2022年12月以降は、企業型DCとiDeCo両方の上限額の範囲内で、iDeCoへの投資が可能です。企業型DCに加入しているものの、掛金が少ない方には朗報といえるでしょう。
(参考:『企業型DC加入者が iDeCo を利用しやすくなります』厚生労働省)
iDeCoをおすすめしない方:9つのケースを紹介
iDeCoで老後の資金をつくることは、すべての方に適した方法ではありません。ここからはおすすめしないケースを9つに分け、理由も含めて解説していきます。
安全・確実がモットーの方
「絶対に損したくない」など、安全・確実がモットーの方もいるのではないでしょうか。このような方に、iDeCoはあまりおすすめできません。iDeCoの主な運用商品となっている投資信託は、運用成績により受け取れる金額が変動するためです。
もっともiDeCoには、定期預金や保険といったメニューもあります。しかし定期預金で運用しても、ほとんど増えません。また保険で運用するならば、iDeCoを使わないほうが60歳を待たずに解約できるため使いやすいと思う方も多いでしょう。このため加入時に将来受け取れる金額がわかる年金を希望の方は、個人年金保険も検討ください。
加えて自営業の方は、国民年金基金も選べます。国民年金基金は、加入した際に将来受け取れる年金額が決まることがメリットに挙げられます。
投資を面倒と感じる方
投資信託はリスクのある商品のため、ある程度の勉強が必要です。そのため投資を面倒と感じる方には、iDeCoをおすすめできません。
世の中には、「投資を勉強するくらいならば自分自身に投資したい」という方もいるでしょう。自らのスキルアップに集中投資して年収を増やすことも、老後に備える1つの方法です。
手数料を取られたくない方
さきに解説したとおり、iDeCoは口座管理料や信託報酬など、様々な手数料が差し引かれます。このうち口座管理料はiDeCoならではの手数料であり、年額に換算すると7,000円前後におよぶ金融機関もあるため無視できません。
なるべく手数料を払いたくない方にとっては、ストレスに感じることもあるでしょう。このような方はNISAや一般の投資信託など、他の方法も検討ください。
様々なライフイベントを控えている方
人生にはお金が必要なライフイベントがあります。なかには急にお金が必要となるケースもあることに留意が必要です。以下に該当する方はiDeCoへの加入が必要かどうか、慎重に考えることをおすすめします。
20代・30代の方
20代や30代はこれから結婚やマイホームの取得など、数百万円~数千万円を要するライフイベントを迎える時期です。このため老後資金を蓄える場合は、いざというときに迅速に取り崩せる金融商品を選ぶ必要があります。
教育費の増加が予想される方
今後大学や専門学校への進学を控える子供がいる方は、入学後に教育費の飛躍的な増加が予測されます。
・専門学校の場合、2年間の学費は200万円~300万円
・大学の場合、4年間の学費は250万円~500万円
また私立大学で医学部や薬学部など6年制の学部を選んだ場合は、学費の合計が1,000万円を超えるケースも珍しくありません。少々年収が高い方でも簡単に払える金額ではないため、いざというときにすぐ現金化できる金融商品で運用することがおすすめです。
収入が少ない方
会社員以外で収入が少ない方のなかには、国民年金の免除を受けている方もいます。たとえ一部免除であっても、国民年金の免除を受けている方はiDeCoへの加入ができません。
免除の基準は、扶養する家族の人数や社会保険料控除額により異なります。日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」のページでご確認ください。
(参考:『国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度』日本年金機構)
貯蓄が少ない方
貯蓄の少ない方が老後資金を作る際には、いざというときに引き出せることが重要です。iDeCoは60歳にならないと引き出しができないため、貯蓄が少ない方には向いていません。このため、他の商品を検討することをおすすめします。
NISA(ニーサ)は以下の点で、老後やいざというときに備える資金づくりに有効です。
・いつでも売却し、引き出し可能
・値上がり益や配当金・分配金は5年間(つみたてNISAは20年間)非課税
・NISAでは5年を経過する年末までに翌年の非課税投資枠へ移す手続き(ロールオーバー)をおこなうことで、引き続き非課税のメリットを受けることが可能
NISAとつみたてNISAは、どちらか一方を選ぶことになります。「老後の資金作りならiDeCo」という固定観念を持たず、幅広い金融商品から選ぶことが重要です。
(参考:『NISAを知る』金融庁)
終身年金が欲しい方
iDeCoの主な受け取り方法は、2つあります。
・5年以上20年の期間を決め、分割で受給する
・一時金としてまとめて受け取る
生きている限りずっと年金が支払われる「終身年金」を選べるとよいですが、対応する保険会社は明治安田生命など、一部に限られることに注意が必要です。また終身年金を選ぶ場合は資産をいったん売却して、終身年金を購入する必要があります。このため終身年金が欲しい方にとって、iDeCoはあまりおすすめできません。
結果に一喜一憂する方
損すると運用成績のよい商品にすぐ乗り換えたいと思う方もいるのではないでしょうか。しかしiDeCoでこのような投資をすることはおすすめできません。運用成績は過去のものであり、今後得するかどうかは保証しないためです。このため頻繁に商品を乗り換えると、かえって損するかもしれません。
多くの金融商品は上下を繰り返すことが特徴です。iDeCoでは「ドル・コスト平均法」により、平均した購入金額を下げられるメリットがあります。「ドル・コスト平均法」は高値の時期は少なめに、安値の時期は多めに購入する方法です。このメリットを十分に活用するためにも、投資は長い目で見ることが欠かせません。
必要なチェックをしない方
損失に一喜一憂し頻繁に運用商品を乗り換えることと同様に、運用状況をチェックしないこともおすすめできません。投資信託は運用成績により、資産の残高が大きく変わる可能性があります。このため定期的に運用状況をチェックしていないと、大きな損失を出していることに気づかないかもしれません。
加えて指定された振替日に確実に掛金が引き落とされるよう、振替日直前の平日に残高を確認することも重要です。万が一振替日に残高が不足していた場合、iDeCoでは再振替がされず、振込による入金もできません。その結果、受け取れる年金額が下がるおそれもあります。
少しの手間をかけることで、上記に挙げた事態を防げます。毎日のようにチェックする必要はありませんが、月1回など定期的にチェックしておきましょう。
iDeCoが適する方:5つのケースを紹介
ここまでiDeCoをおすすめしないケースを取り上げましたが、もちろんiDeCoの利用が適している方もいます。どのような方におすすめか、5つのケースに分けて紹介していきましょう。
リスクや手数料負担を許容できる方
iDeCoは自分自身の創意工夫によって、預貯金よりも老後の資金を大きく育てることが可能な年金です。そのため、以下の事項を許容できる方が向いています。
・資産額が変動するリスク
・手数料の負担
iDeCoは「より大きなリターンを得るためには、少々のリスクや手数料負担はかまわない」という方におすすめです。
投資に興味がある方
投資に興味がある方は、iDeCoで増やすために必要な投資信託も抵抗なく使いこなせるでしょう。投資の経験があれば、なおよいといえます。また非課税であることは、資産が増えやすくなる大きな要因です。
収入や貯蓄がある方
ある程度の収入や貯蓄があれば、いざというときにもお金を準備できることでしょう。このような方には、iDeCoへ資金を振り向ける余裕が生まれます。iDeCoの活用により非課税のメリットを受けつつ、より豊かな老後を過ごす資金づくりをおこなえます。
公的年金までのつなぎが欲しい方
iDeCoは60歳以降、5年~20年の間で期間を決め、定期年金として受け取ることが可能です。このため公的年金までのつなぎとなる、有効な手段に挙げられます。たとえば69歳までは働きながらiDeCoの年金を受給し、国民年金や厚生年金は70歳から繰り下げ受給して年金額を増やすことは、豊かな老後を過ごす有効な手段の1つです。
長い目で運用できる方
iDeCoは60歳以降に受け取る際に、目標とする利益を出していればよいわけです。このため値下がりしたからといって、あわてて運用商品を変えることはおすすめできません。目先の損益に一喜一憂せず、適切に運用商品を変えながら長い目で運用できる方が適しています。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
iDeCoは老後に向けた資金作りに有効な手段ですが、万能ではありません。ときには希望するライフプランを実現する妨げとなる場合もあります。このためお金のかかるライフイベントが予測されている方は、加入にあたり慎重な判断が必要です。
老後資金をつくる方法には、NISAなどほかの方法も使えます。様々な手段を検討した上で、ご自身に合った資金作りの方法を選びましょう。ファイナンシャルプランナーをはじめとした、専門家への相談もおすすめです。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


全ての箇所を自筆する普通方式の遺言書を「自筆証書遺言書」と呼びます。ホゥ。