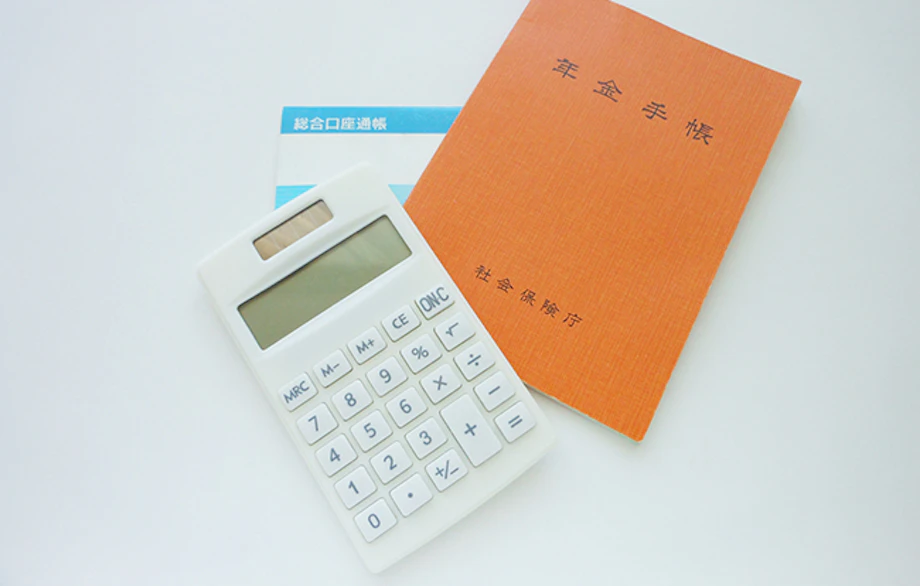身近な人が亡くなると、「遺族年金って誰がもらえるの?」「実際にどれくらいもらえるの?」というようなことも気になるでしょう。特に、亡くなった方の収入で生活していた同居の家族の場合、悲しみのなか収入不足も不安になるかもしれません。
そこで、遺族年金を受給できる条件や受給額について解説します。年金にはいくつか種類があり、給付加算も存在するため、該当するかどうか確認してみましょう。
<この記事の要点>
・遺族基礎年金は国民年金の被保険者が死亡したときに、子のある配偶者が受給できる
・遺族厚生年金は、条件によって子のある配偶者や父母、孫などが受給できる
・遺族基礎年金の受給額は「81万6,000円+子の加算額」で計算する
こんな人におすすめ
遺族年金について知りたい人
遺族年金の受給条件が気になる人
遺族年金の種類を知りたい人
遺族年金の種類と対象者を確認しよう
遺族年金の条件を確認する前に、基本から押さえておきましょう。ここでは主に「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」、そして受給の対象者について解説しています。子の有無や年齢によっても受給できる年金が異なるので、注意が必要です。
遺族年金の種類は2つ
年金制度では、自営業の方は国民年金、会社員・公務員は厚生年金に加入します。国民年金加入者の遺族は「遺族基礎年金」、厚生年金加入者の遺族は「遺族厚生年金」を受給できます。また旧制度の共済年金に加入していた方は、制度改正により「遺族厚生年金」を受け取ると覚えておきましょう。
遺族年金は誰がもらえる?遺族年金の種類は?
死亡者が「国民年金」に加入していたケースと、「厚生年金」に加入していたケース、それぞれ受給可能な遺族についてまとめました。
【死亡者が国民年金に加入していた(自営業)】
・子のある配偶者、または子(※)/遺族基礎年金
・子のない妻/死亡一時金、寡婦年金
※子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。
【死亡者が厚生年金に加入していた(会社員または公務員)】
・子のある配偶者、または子/遺族基礎年金、遺族厚生年金
・子のない妻(※)/遺族厚生年金、中高年齢寡婦加算(40~65歳)
※子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給。
ただしすべての遺族が受給できるとは限りません。受給の条件を満たした場合に、請求書を提出すると受け取れます。
遺族(基礎・厚生)年金の条件と受給額
遺族年金を受け取るうえで、条件に該当するか確認しなければなりません。納付期間や年齢、子の年齢、障害の有無といった条件があります。ここでは、遺族(基礎・厚生)年金それぞれの条件についてまとめました。
遺族基礎年金の条件
遺族基礎年金を受給するには、死亡者・遺族がそれぞれ条件を満たしていなければなりません。下記では、それぞれの条件をまとめました。
| 【死亡者の条件】 |
・死亡日の2か月前まで保険料の3分の2以上納付していた ・死亡日の2か月前までの1年間に保険料の未納期間がない 下記のうちどちらかが当てはまる方 ・国民年金の加入者で60~64歳 ・老齢基礎年金を受給中 ・日本国内に住所を有する ※受給資格期間の合計が25年間以上ある (※保険料を支払ったとカウントされる期間) |
| 【遺族の条件】 |
・死亡者によって生計が維持されていた子ありの妻、または子 ・遺族の前年の収入が850万円未満、または所得が665万5千円未満 |
| 【遺族の子の条件】 |
婚姻していない子で、下記のどちらかを満たしている必要がある ・18歳になった年度の3月31日を経過していない子 ・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子 |
(参考:『遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)』日本年金機構)
遺族厚生年金の条件
遺族厚生年金を受給するには、死亡者・遺族がそれぞれ条件を満たしていなければなりません。下記では、それぞれの条件をまとめました。
| 【死亡者の条件】 |
・死亡日の2か月前まで保険料の3分の2以上納付していた ・死亡日の2か月前までの1年間に保険料の未納期間がない 下記のうちどちらかが当てはまる方 ・厚生年金に加入していた ・老齢厚生年金を受給していた ・障害厚生年金1級もしくは2級を受給していた ・受給資格期間の合計が25年間以上ある ・厚生年金の加入中に傷病が原因で初診日から5年以内に死亡した (上記は被保険者期間に初診日があること) |
| 【遺族の条件】 |
・配偶者(子なしの妻で30歳未満の場合、5年間限定で受給できる) ・子、孫(18歳になった年度の3月31日を経過していない子、もしくは20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子) ・父母、祖父母(死亡当時55歳以上の方で、受給できるのは60歳から) |
(参考:『遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)日本年金機構』)
遺族基礎年金の受給額
受給額は、子の人数によって異なります。令和6年4月から受給額は「81万6,000円+子の加算額」で計算します。子の加算額は1~2人目まで23万4,800円で、3人目以降が7万8,300円です。
・子のいない配偶者/なし
・配偶者+子1人/105万800円
・配偶者+子2人/128万5,600円
・配偶者+子3人/136万3,900円
給付加算の該当者は、上記に加算分が上乗せされます。
(参考:『遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)』日本年金機構)
遺族厚生年金の受給額
受給額は、基本的に老齢年金の4分の3の割合になります。ただし複雑な計算式を用いるため、ここでは目安の受給額を紹介します。
平均標準報酬額/受給額の目安(年単位)
・20万円/25万円前後
・30万円/37万円前後
・40万円/49万円前後
・50万円/61万円前後
・60万円/74万円前後
※「平均標準報酬額」とは、標準報酬月額と標準賞与額の総額を月数で割った数
※「標準報酬月額」とは、従業員の収入を一定の幅で32等級までに分けた数字
※「標準賞与額」とは、税引前の賞与総額から千円未満を切り捨てた数
遺族年金はほかにもある!状況に応じて支給される
遺族(基礎・厚生)年金のほかに、死亡者の受け取るはずだった年金を受給する方法として「寡婦年金」「死亡一時金」があります。ここでは、それぞれの条件・受給額についてまとめました。両方を受け取ることはできないため、内容を比較してひとつを選択しましょう。
寡婦年金の条件と受給額
自営業をしていた夫の妻には、本人が受け取るはずだった年金の一部が「寡婦年金」として支払われます。詳しくは、下記の表にまとめました。
| 【条件】 |
・夫の受給資格期間が10年以上ある ・婚姻関係が10年以上 |
| 【受給額】 |
夫の老齢基礎年金の4分の3相当 (満額で受け取る予定だった場合は45万円ほどになる) |
| 【支払われる期間】 | 妻の年齢が60~65歳になるまで |
| 【条件】 |
・配偶者と※2親等までの親族 (子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹) ・36か月以上の納付期間がある |
| 【受給額】 |
・納付期間に応じて12万~32万円 ・付加保険料(定額保険料に上乗せして納めること)を36か月以上納めている方は、8,500円が加算される |
(参考:『死亡一時金』日本年金機構)
労災による「遺族補償年金」の条件と受給額
通勤中の交通事故や業務中に起こった不慮の事故による傷病が原因で亡くなった場合、労災保険の遺族補償年金が発生します。対象者は、死亡者の収入により生計を維持していた親族です。
| 【条件】 |
・配偶者 ・父母、祖父母、兄弟姉妹(55歳以上) ・子、孫、兄弟姉妹(18歳になった年度の3月31日を経過していない子) |
| 【支給額】 |
・遺族(補償)年金 1人:給付基礎日額の153日分 2人:給付基礎日額の201日分 3人:給付基礎日額の223日分 4人:給付基礎日額の245日分 ・遺族特別支給金(一時金) 300万円 ・遺族特別年金 1人:算定基礎日額の153日分 2人:算定基礎日額の201日分 3人:算定基礎日額の223日分 4人:算定基礎日額の245日分 |
(参考:『遺族(補償)等給付 葬祭料等(葬祭給付)の請求手続』厚生労働省)
中高年齢寡婦加算の条件と受給額
中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金の加算給付の一つです。夫と死別した妻に対して、40歳~65歳になるまでの期間に加算されます。
| 【条件】 |
・妻:40歳以上65歳未満 ・子のない妻 ・子がいる場合は、遺族(基礎・厚生)年金の子の年齢要件から外れた方(子が18歳になった年度の3月31日を経過したまたは障害のある子は20歳に達した) |
| 【加算額】 | 61万2,000円(2024年4月時点) |
(参考:『た行 中高齢寡婦加算』日本年金機構)
経過的寡婦加算の条件と受給額
経過的寡婦加算は、上記の中高年齢寡婦加算の対象者が65歳に達したときに支給されます。65歳になると自分の老歴基礎年金を受給しますが、中高年齢寡婦加算より低い金額になることもあるでしょう。年金額の低下防止を図るのが、経過的寡婦加算です。
| 【条件】 |
昭和31年4月1日以前生まれの妻 下記のいずれかを満たす者 ・65歳になり遺族厚生年金の受給権が発生した ・中高齢寡婦加算を受けていた妻が65歳になった |
| 【加算額】 | 生年月日によって加算額が異なり、年齢が高い人ほど金額は多くなる |
(参考:『か行 経過的寡婦加算』日本年金機構)
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
遺族年金は、死亡者の加入していた年金制度の種類と納付期間、遺族の年齢や障害の有無によって受給の可不可と受給額が決まります。受給の条件を確認して、該当する場合は申請書を提出しましょう。
配偶者や身内が亡くなった場合、通夜や葬儀の手配をしなければなりません。「小さなお葬式」では、火葬のみのプラン、告別式から火葬までのプラン、家族葬といった小規模のプランをご用意しています。プラン内容の問い合わせや葬儀に関するご質問など、どうぞお気軽にお問い合わせください。24時間365日、お客さまサポートダイヤルより対応いたします。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


一日葬とは、通夜をはぶいた葬儀形式のことです。ホゥ。