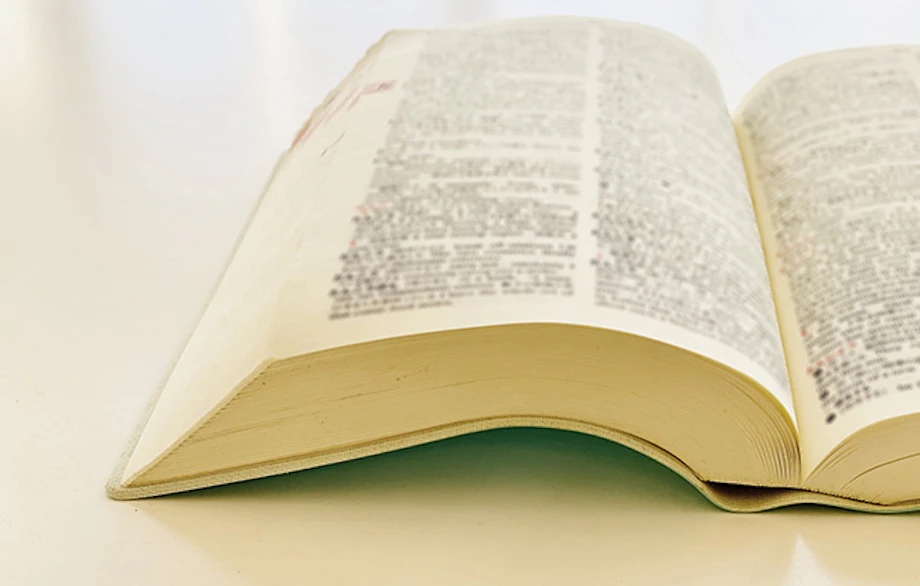人が亡くなったときに「ご逝去されました」といいますが、誰に対しても使ってよい言葉ではないため、使用する際には注意が必要です。
この記事では、「逝去」の意味や使い方、類語について解説します。また、身内が亡くなった場合に周りに伝えるポイントや、すぐにすべきことについても説明します。
<この記事の要点>
・身内以外の方が亡くなった場合は「逝去」、身内が亡くなった際は「死去」を使う
・「ご逝去されました」は二重敬語で文法的には正しくないが、一般的に使われている
・「逝去」の類語には「永眠」「他界」「急逝」がある
こんな人におすすめ
「逝去」の言葉の意味が知りたい人
「逝去」と「死去」の違いについて知りたい人
身内が亡くなった際の対応が知りたい人
「ご逝去されました」の意味や死去との違い
まずは、「ご逝去されました」という言葉の意味を正確に理解しておきましょう。また、「逝去」とよく似た言葉として「死去」がありますが、どのような違いがあるのかも押さえておきたい部分でしょう。逝去の意味と、死去との違いについて解説します。
逝去の意味
逝去とは「死ぬ」の尊敬語です。そのため、身内以外の方が亡くなった場合に、相手に対する敬意を込めて使う言葉です。
会社の社長や上司、その家族など、自分の身内ではない方が亡くなったことを伝える際に使います。会社の部下、年下の友人や後輩など、普段であれば敬語を使わない相手に対しても、死を悼み敬意を込めて「逝去」という言葉使います。
逝去と死去の違い
死去とは「人が死ぬこと」です。死についての通常の表現であり、身内が亡くなった際に使う言葉です。家族など自分の身内だけでなく、自分が勤めている会社の社長、上司、部下などが亡くなった際にも他者に対しては身内扱いとなるため、訃報を伝える言葉として「死去」という言葉を使います。
身内以外の方が亡くなった場合には「逝去」を使い、身内が亡くなった場合には「死去」を使うと覚えておくとよいでしょう。
「ご逝去されました」を使用する例
「逝去」という言葉は、それ自体が尊敬語です。そのため本来であれば「ご」を付けて「ご逝去されました」と表現すると二重敬語になってしまい、文法的には正しくありません。しかし、人が亡くなった際に敬意を表すのに適した表現として広く使われているため、間違った使い方ではありません。
例えば、次のように使用します。
・「◯◯様がご逝去されました」
・「ご逝去されました◯◯様のご冥福をお祈りいたします」
小さなお葬式で葬儀場をさがす
逝去や死去の類語と意味
逝去や死去には、似た意味の言葉がいくつかあります。4つの類語の意味と、それぞれの言葉がどのようなシーンで使われるのかについて解説します。
「亡くなりました」
「亡くなる」は「死ぬ」の尊敬語で、「死ぬ」という言葉を使わずに、遠回しな表現で伝えたい場合に使用します。
もともとは身内の死を表現する言葉でしたが、身内以外の死に対しても使われるようになりました。そのため尊敬語ですが、身内の死に対しても使うことができます。
「永眠いたしました」
「永眠」の意味は「長い眠りにつくこと」であり、つまり「死ぬこと」です。死を遠回しに表現できるため、亡くなったことを伝える喪中はがきなどの文面に、「◯◯が◯月◯日永眠いたしました」というように使われます。また、キリスト教においては、人が死ぬことを「永眠」と表現します。
「他界しました」
「他界」は、「人間界から他の世界へ行く」という意味から「死ぬこと」を指す言葉として使われます。特に、輪廻転生を繰り返し別の世界へと生まれ変わるという、仏教の教えから来ている言葉だと考えられています。死を遠回しに表現する際に使用され、身内の死に対して使うこともできます。
「急逝いたしました」
「急逝」という言葉の意味は、「急な死」です。普通に生活していた方が、ある日突然亡くなったときに使われます。病気の容体が急変して亡くなったり、事故で突然亡くなったり、予測ができなかった死に対する表現です。一般的には高齢の方よりも、若い方に対して使われます。
<関連記事>
【急逝とは】読み方や身内が亡くなった場合の対応方法を解説
身内が亡くなった場合に伝えるポイント
身内が亡くなったら、すぐに関係者に訃報の連絡をしなければなりません。葬儀を執り行う前に、確実に知らせたい相手に伝える必要があります。
身内が亡くなったときに伝えるポイントとして、訃報を知らせる範囲を確認することや、電話での連絡を優先することについて解説します。
訃報を知らせる範囲を確認する
まずは、訃報を知らせる範囲を確認して、漏れのないようにしましょう。第1に家族や親族です。3親等までが目安になりますが、故人と関わりの深かった方には必ず連絡しましょう。第2に葬儀社です。第3に故人と親しくしていた友人に知らせます。
葬儀の日程が決まり次第、会社や学校の関係者、知人、遺族と関係する方、町内会など、必要な方々にも知らせましょう。
電話での連絡を優先する
訃報の連絡方法については特別なきまりはありません。ただし、迅速かつ正確に伝えなければならないので、電話での連絡が確実です。高齢者に伝える際にも、基本的には電話が適しています。
ただし、全ての相手に対して電話をかけるのは大変ですので、メールなども活用できます。家族や親族、故人と親しかった友人などには電話をかけ、会社や学校の関係者、知人などにはメールで伝えることもあるでしょう。
訃報の報せ以外にもある!身内が亡くなった際にすべきことは?
身内が亡くなったときには、訃報の報せ以外にも、すぐにしなければならないことがあります。葬儀を執り行うための準備として必要なことについて解説します。
依頼する葬儀社の決定
身内が亡くなったときに、すでに葬儀社が決まっている場合はすぐに連絡しましょう。この段階で葬儀社がまだ決まっていない場合には、決めなければなりません。
病院と提携している葬儀社に依頼してもよいのですが、割高になるケースがあるかもしれません。病院が提携している葬儀社を断わり、希望の葬儀社を選んでも失礼にはあたらないため、できる限り落ち着いて決定しましょう。
安置する場所の決定
葬儀までの間、遺体を安置しておく場所を決めなければなりません。自宅を希望する場合には、葬儀社にその旨を伝えて搬送してもらいましょう。
自宅ではなく斎場の安置施設を選ぶこともできます。その際には葬儀社に葬儀を執り行う斎場に搬送してもらい、葬儀の準備を進めてもらうことになります。
遺体を搬送する手配
病院で亡くなった場合、病院の霊安室には遺体を長く安置できない場合が多いため、自宅や斎場などに搬送して安置する必要があります。遺体を搬送する手配をしましょう。
葬儀社に身内が亡くなったことを伝えると、すみやかに遺体を搬送し、希望の場所に安置してもらうことができます。
<関連記事>
ご遺体の安置とは?場所や特徴・費用・注意点などを解説!
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
この記事では、「ご逝去されました」の意味や使い方、類語、訃報の伝え方、身内が亡くなった際にすべきことなどについて説明しました。死を表現する言葉を使用するときは、相手に失礼にならないように配慮が必要です。言葉の意味や使い方を正確に理解しておきましょう。
小さなお葬式では、葬儀に精通したコールスタッフが、24時間365日、通話料無料でご連絡をお待ちしております。「逝去」など言葉の使い方や、葬儀についてお悩みの方はぜひ小さなお葬式にご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



故人が年金受給者の場合は、すぐに年金受給停止の手続きが必要になります。ホゥ。