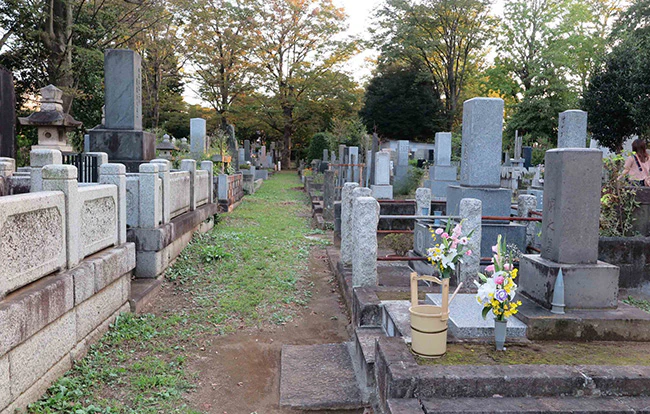改葬とはお墓に納められている遺骨を取り出し、別のお墓や納骨堂へ移し替えることです。また、遺骨を取り出した後のお墓を更地にして、使用していた土地を返還することを墓じまいと呼びます。これらを行う際に「お布施は必要なのか」「どのような書類や手続きが必要になるのか」など疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、改葬にお布施が必要な理由、お布施を渡す際のマナーについて解説します。また、改葬全体の流れを必要書類や手続きなどの面から、1つずつみていきましょう。改葬をする予定のある方はぜひ参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・一般的に改葬をする際は位牌の閉眼供養を行うため、お布施は必要
・お布施の金額は閉眼供養と開眼供養に各30,000円~50,000円、離檀料30,000円~300,000円が目安
・お布施は切手盆や袱紗の上に乗せて渡すのがマナー
こんな人におすすめ
改葬のお布施が気になる人
改葬する際のお布施の金額の目安を知りたい人
改葬でお布施を渡す際のマナーや対応が知りたい人
改葬にお布施は必要なの?お布施の種類は?
改葬・墓じまいを行う際には、お世話になった菩提寺に改葬したい意思を伝え、閉眼供養を行います。ここからは、改葬に必要なお布施とその種類について紹介します。
僧侶への謝礼金として必要
一般的に、改葬をする際は位牌の閉眼供養(魂抜き)を執り行います。僧侶を招いて位牌を焚き上げることで、ご先祖さまを合祀、もしくは新しい場所で供養できるでしょう。
閉眼供養は法事の一つなので、その他の法事と同じように、僧侶へのお礼としてお布施を準備しておきましょう。
改葬で渡すお布施の種類
改葬で僧侶や菩提寺に渡すお布施の種類は、閉眼供養のお布施・離檀料・開眼供養のお布施の3つです。
閉眼供養は改葬を行う際にお墓から故人の魂を抜きとるための儀式です。離檀料はお墓を管理してきた菩提寺に対して、お墓を守っていただいたことや、お世話になったことへの感謝の気持ちとしてお渡しするお布施です。
お墓を新しい場所に移す場合は、お墓に故人の魂を吹き込む開眼供養を行う必要があります。そのため、ここでもお布施を渡すのが慣習だといえるでしょう。
改葬する際のお布施の金額の目安
改葬に必要となるお布施の金額の目安は、それぞれ異なります。閉眼供養のお布施の目安は、30,000円~50,000円程度です。
離檀料の金額の目安は、30,000円~300,000円程度です。お墓を建てるときに署名した契約書などに、明記されている金額をお布施として渡すこともあるでしょう。
新しくお墓を建てる際の開眼供養のお布施の目安は、30,000円~50,000円程度と考えておきましょう。
改葬でお布施を渡す際のマナー
改葬でお布施を渡す際には、気をつけるべきマナーが2つあります。ここからは、お布施を渡す際の包み方や渡し方に関するマナーについて紹介します。
お布施の包み方
お布施を包む袋はお布施袋や不祝儀袋を選びましょう。表書きには「お布施」や「御布施」など、お布施を渡す目的を書きましょう。下部に自身の氏名を記載します。裏面には包んだ金額とともに実際にお布施を包んだ方の名前と住所を記載します。書き方としては、裏面の右側に「金○○圓」と包んだ金額を書きましょう。数字ではなく、漢数字の旧字体を使用するのがマナーです。
基本的にお布施に水引は不要ですが、地域によっては水引を使用することもあります。その際は地域のルールに従いましょう。
お布施の渡し方
お布施を渡す際は、閉眼供養や開眼供養などの法事が終わったタイミングに切手盆や祝儀盆などの小さなお盆に乗せて渡しましょう。また、お布施を乗せる小さなお盆が用意できない場合には、袱紗で包み、渡す際には袱紗の上に乗せて渡します。お布施の入った封筒が見えるように袱紗を開き、相手からみて文字が上下反対にならないように向きを変えたら、感謝の言葉を述べながら、お布施を渡しましょう。
改葬全体の流れは?
改葬を行うために、実際の流れについて知りたいという方もいるのではないでしょうか。改葬には事前にいくつかの手続きが必要となります。ここからは、改葬当日の実際の流れについて解説します。
1.関係者への説明
改葬をする場合、まずは関係者への説明を忘れないようにしましょう。ここでいう関係者とは、親族だけでなく、お墓を管理している霊園や菩提寺の関係者も含みます。
関係者への相談をせずに改葬した場合、それに伴う費用や離檀する際の手続きにおいて、トラブルが発生するリスクも考えられるでしょう。
2.新しい供養先の確保
改葬のために、お墓の移転先について事前に決めておく必要があります。遺骨をどこに移せばよいのかわからない状態で時間が過ぎる恐れがあるためです。改葬を決める際は焦らずに、納骨先についてしっかりと検討してから決断するとよいでしょう。
3.改葬の手続き
改葬して納骨先を具体的に決めるためには、お墓のある菩提寺や霊園から「埋葬証明書」と新しい納骨先の管理者に、「受入証明書(墓所使用承諾証)」を発行してもらう必要があります。
場所によっては、「永代使用許可証」をもらえる場合もあるでしょう。
「埋葬証明書」と「受入証明書(墓所使用承諾証)」を各自治体に提出し、「改葬許可書」が発行される流れです。この段階になると新しい土地で改葬できます。
4.遺骨の取り出し
お墓のある自治体の役所から「改葬許可証」を受け取ったら、いよいよ改葬に向けて動き出しましょう。霊園を管理する寺院、もしくはお付き合いのある菩提寺にお願いをして閉眼法要を行います。お墓から遺骨を取り出して、新しい墓地への移動に備えます。
5.新しい埋葬先への納骨
基本的に、遺骨をお墓から取り出したあとは墓石を解体し、土地を更地にしてから返還します。墓石の解体は石材店などに依頼しましょう。場合によっては、遺骨とともに墓石を移動することもあります。取り出した遺骨を新しい供養先に納骨し、お墓に魂を入れる開眼法要を行います。
改葬はOHAKO-おはこ-の「お墓お引っ越し」プランで!
「小さなお葬式」では、専門知識豊富なスタッフが葬儀に関する疑問や質問にお答えします。改葬についてのご相談は、お気軽にご利用・ご相談ください。
小さなお葬式の「OHAKO-おはこ-」には、「お墓お引っ越し」プランもあります。業者を活用することで効率的に改葬を実施でき、さらにトラブルも回避できるので、「改葬に踏み切れない」という方におすすめのプランだといえるでしょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
改葬の際には、閉眼供養のお布施や離檀料、開眼供養のお布施の3つを用意しましょう。また、僧侶や菩提寺にお布施を渡すタイミングや渡す際のマナーは、注意点をおさえておくことが大切です。
改葬を行う前には、関係者への連絡や、新しい供養先の準備も事前に決めておく必要があります。その際には、必要書類の準備をすることも重要です。改葬のお布施や書類、手続きについて事前に知っていると、スムーズに改葬を行うことができるでしょう。
「小さなお葬式」では、改葬についてだけでなく、葬儀の知識やマナーに精通したコールスタッフが、24時間365日、通話料無料でご連絡をお待ちしております。葬儀についてさまざまな疑問をお持ちの方は、ぜひ小さなお葬式へお気軽にご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


遺産相続が発生した場合、いかなる場合でも配偶者は相続人になります。ホゥ。