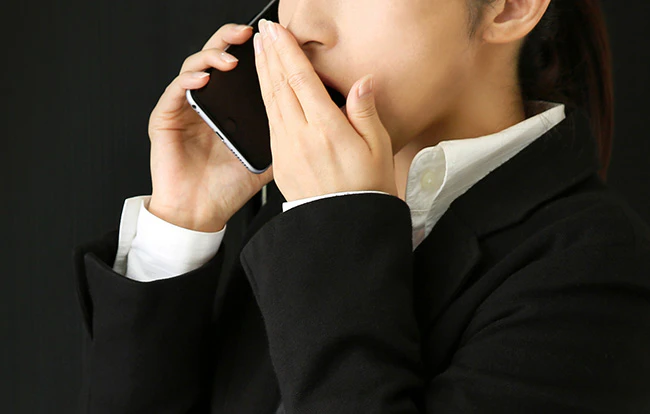突然危篤の知らせを受けると、誰でも慌ててしまいます。危篤の連絡を受けて駆けつける際は、どのような服装で行けばよいのでしょうか。いざというときに備えて、服装やマナーについて知っておきたいものです。この記事では、危篤の知らせを受けて駆けつける際の服装やマナーなどを解説します。
<この記事の要点>
・危篤の連絡を受けた場合は、できるだけ早く駆けつけることが重要
・急な知らせの場合は、普段着や仕事帰りの服装でも失礼にはあたらない
・危篤状態でも、亡くなることを前提とした言葉は控える
こんな人におすすめ
危篤者のお見舞い方法のマナーを知りたい方
危篤者の家族にかける言葉を知りたい方
危篤の連絡を受けた後の対応を知りたい方
【危篤】連絡を受けた際の対応方法と服装
危篤の連絡を受けて駆けつける際は、相手の家族に失礼のないように服装やマナーに気をつける必要があります。ここからは、危篤の連絡を受けた際の対応方法や服装について紹介します。
連絡を受けたときの対応は?
危篤の連絡を受けたら、できるだけ早く駆けつけたほうがよいでしょう。生きている間にその方と会える最後の機会になるかもしれないからです。親しい間柄であれば、危篤になった方も会いたがっていることでしょう。危篤の知らせは、親族だけでなく友人知人にも届くことがあります。
駆けつける際の服装は?
急な知らせで駆けつける場合には、普段着や仕事帰りの服装でも失礼にはなりません。着替える余裕があれば、黒やグレーの色味の落ち着いた装いがおすすめです。ただし、喪服を着ていくのは縁起が悪く失礼にあたるため注意しましょう。
しかし、遠方から駆けつける場合は、念のために喪服も用意しておきましょう。その際は、相手の家族の目につかないように配慮することが大切です。
危篤の連絡を受けた際のマナー
危篤になると、危篤者本人はもちろん家族も切羽詰まった状態に陥っています。そのため、マナーを守った対応と細かい配慮が必要です。ここからは、危篤者本人にかける言葉や家族にかける言葉、手土産の必要性について解説します。
危篤者や家族にかける言葉は?
危篤者や家族は精神的にとても不安定な状態にあります。そのため、言葉遣いには細心の注意を払いましょう。たとえ危篤状態でも、亡くなることを前提とした言葉は控えるように気をつけましょう。
たとえば、「また飲みに行きたかったな」と言うのは「もう二度と飲みに行けない」という意味に聞こえてしまう可能性があります。同じ意味の言葉でも「元気になったらまた飲みに行こう」と言えば問題ありません。家族に対しても、安心感を与えるような言葉遣いを心がけましょう。
<関連記事>
危篤状態の本人にかける言葉とは?家族にかける言葉も紹介
手土産を持っていく必要は?
危篤の知らせを聞いて駆けつけるのは、普通のお見舞いとは違うので手土産は必要ありません。手土産を選んでいる時間があるならば、一刻も早く駆けつけましょう。危篤になると家族も大変なので、手土産はかえって気を遣わせることになります。また、手土産を持参しても危篤者は食べられる状態ではなく、家族も喉を通らないでしょう。相手に対して余計な気を遣わせない思いやりの気持ちを忘れないようにしましょう。
お見舞金は必要?
危篤で病院に駆けつけるのは、通常のお見舞いとは異なるのでお見舞金は必要ありません。また、袋に入ったお金は香典を連想させるため、危篤の際はタブーとされています。危篤になると、家族は不安定な精神状態に陥ります。マナー違反をして家族の心を傷つけないようにしましょう。
<関連記事>
危篤状態の方へのお見舞いに行く際守るべきマナー
小さなお葬式で葬儀場をさがす
【臨終】連絡を受けた際の対応方法や服装
臨終の知らせを受けた場合の対応は、故人との関係性によって異なります。ここからは、臨終の連絡を受けた際の対応方法や弔問時の服装について紹介します。
臨終の連絡を受けたときの対応は?
親族の臨終の知らせを受けた場合は、すぐに駆けつけて手伝いを申し出るようにしましょう。多くの方が弔問に訪れるので、人手はいくらあっても足りません。友人や知人の場合も、すぐに弔問に駆けつけましょう。
故人と親しい関係性であれば、遺族を励ます言葉や寄り添う言葉をかけるとよいでしょう。故人とそれほど親しくない場合は、長居するとかえって失礼になります。お線香をあげたらすぐに帰るようにしましょう。
弔問する際の服装は?
臨終の知らせを聞いて弔問に駆けつける場合は、喪服ではなく平服でもよいとされています。着替える場合は、黒やグレーなど落ち着いた色合いの服装にしましょう。ただし、華美なアクセサリーや派手な化粧は控えます。
お悔やみの言葉のかけ方は?
臨終の知らせを受けて駆けつけたら、まず遺族にお悔やみの言葉をかけましょう。代表的なお悔やみの言葉の文例は以下のとおりです。
「このたびはご愁傷さまでございます。心よりお悔やみ申し上げます。」
不慮の死の場合は「なんと申し上げていいのか、言葉が見つかりません」など心情を添えても問題はありません。手伝いを申し出る場合は「何かお手伝いできることがあればお申し付けください」と伝えましょう。
<関連記事>
お悔やみの挨拶とは?伝え方のマナーと文例を状況・関係性別にご紹介
故人と対面する際のマナーは?
故人と対面する際は、以下の手順が一般的なマナーとされています。対面する方が多い場合は、手短かに済ませます。
1. 故人の枕元に正座し、両手をついて一礼する
2. 遺族が白布をとったら、そのままの姿勢で対面する
故人・遺族とも親しい間柄であれば、ここで言葉を交わしてもよい
3. 故人に再び一礼して、合掌する
4. 遺族に一礼してから下がる 
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
危篤や臨終の知らせを受けたら、いち早く駆けつけることが重要です。服装は落ち着いた色合いに統一して、アクセサリーを身に着けたり派手な化粧をしたりするのは控えましょう。なお、危篤時に喪服を着用して行くのはマナー違反です。
家族に対してかける言葉には、十分に注意を払う必要があります。服装や対応のマナーをあらかじめ把握して、いざというときに備えましょう。
葬儀に関するご準備は事前に行うことが大切です。いざという時困らないように、葬儀全般に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



「お悔やみ申し上げます」は通夜や葬儀の定型句なので、宗派を気にせず使えます。ホゥ。