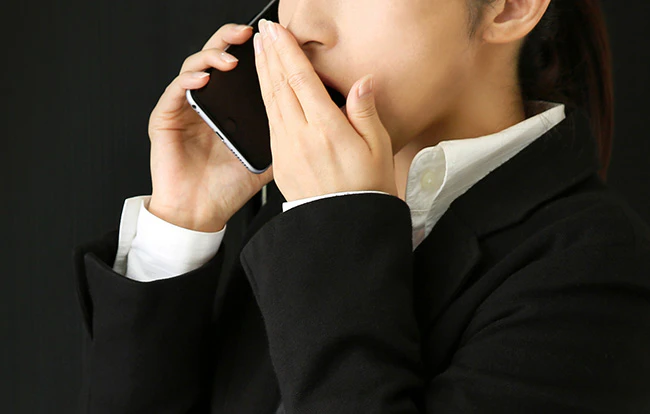身近な方の臨終が近いとき、慌てず落ち着いて対応するためには、知識を身に付けておくことが重要です。この記事では、臨終が近いことを知らせる身体症状と心の状態、前後に家族が行うことを詳しく解説します。
<この記事の要点>
・臨終が近づくとバイタルサインの変化や飲食・排泄の困難、呼吸音の変化、錯乱などの身体症状が現れる
・臨終直前には親族や友人に連絡を取り、本人に感謝の言葉を伝えるなど話しかけるとよい
・家族が亡くなった後は葬儀社への連絡や死亡届の提出などの手続きを行う
こんな人におすすめ
ご臨終間近の症状について知りたい人
ご臨終が近づいたとき、家族がやるべきことを知っておきたい人
臨終とは何か
臨終とは死を迎える直前の時期のことで、死にぎわ、いつ亡くなっても不思議ではない状態のことをいいます。「臨命終時(りんみょうじゅうじ)」という仏教の言葉を略した言葉です。
臨終の際の人相によって、極楽浄土へ往生できるかどうかが決まると考えられ、心穏やかに死を迎えることが大切だと考えられてきました。
臨終が近いことを知らせる身体症状
臨終が近いかどうかを把握するためにはどうすればよいのでしょうか。臨終が近いことを知らせる代表的な身体症状を4つ紹介します。あらかじめ知識を持っておくことで、安心して家族や知人の臨終を迎えることができるでしょう。
バイタルサインが変化する
バイタルサインとは「生命兆候」と訳され、生きていることを示す「脈拍」「血圧」「呼吸」「体温」などの指標のことです。
臨終が近くなると、これらのバイタルサインが不安定になります。健康な体は恒常性を保とうとする働きがあるので、一時的に変化があっても時間とともに安定しますが、臨終が近い方にはそのような力がないためです。
飲食・排泄の変化
意識レベルが低下してくることによって、飲み込む力が弱くなり、飲食ができなくなってきます。唇も乾燥してくるでしょう。
また、心臓や腎臓の機能が低下してきて、排尿が少なくなったり出なくなったりしてきます。このような状態で点滴を行うと体内に溜まってしまい、苦痛を引き起こす可能性があることは認識しておきましょう。
呼吸音が大きくなる
気管に分泌物が溜まったり、喉の筋肉が緩んだりすることによって、呼吸するときにゴロゴロという音が発生し呼吸音が大きくなります。これは、死前喘鳴(しぜんぜんめい)と呼ばれる現象です。
付き添っている家族は、苦しいのではないかと心配しますが、本人は昏睡状態で苦しみを感じていないと考えられています。
錯乱して会話が成り立たない
臨終が近づいた方は注意力や思考力が低下しており、眠気や錯乱が生じ、会話が成り立たないことが多くなります。
呼びかけても答えのない場合もありますが、本人は話の内容を理解していることが多いといわれています。優しく話しかけるようにしましょう。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
臨終が近いことを知らせる心の状態
臨終が近付くとどのような心の状態になるのでしょうか。そばにいる家族が感じることのできる、心の状態の変化について解説します。
意識が薄れる
意識については個人差があり、亡くなるまで意識がはっきりしている方もいますが、時間や場所の感覚がなくなってきて意識が薄れる方もいます。
何かをつぶやいたり、何もないところを見つめていたりすることもあるかもしれません。昏睡状態になり、数時間~数週間後に亡くなる場合もあります。
落ち着きがなくなる
普段は静かな方であっても、臨終が近づくと落ち着きがなくなる場合があります。シーツを引っ張ったり、点滴を外そうとしたりという行動は、苦痛や薬の副作用など、さまざまな理由によって生じます。
静かに話しかけてマッサージをしたりして、気持ちを落ち着かせてあげましょう。また、家族も慌てることなく、ゆったりと構えていることが大切です。
お迎え現象
お迎え現象とは「孫が迎えに来た」「亡くなった母が迎えにきた」などと、その場にいない人や、すでに亡くなった人に会ったという話をしはじめることです。
このように臨終間近の方が幻覚を見るのは、医学的には脳が酸欠になり、正常に機能していないためであると考えられています。
臨終直前に家族が行うこと
臨終が近いことを知らせる症状が見られた場合に、家族は臨終直前に何ができるのでしょうか。親族・友人に連絡をすること、話しかけることという2つについて説明します。
親族・友人に連絡をする
臨終が近いことを知らせる症状が見られたり、医師から危篤であるといわれたりした場合には、できるだけ早く親族に連絡をしましょう。連絡する範囲は一般的には3親等までとされています。
特に本人が会いたいだろうと思われる方がいる場合には、3親等を超えた親族や、友人にも伝えましょう。
話しかける
意識を失ったとしても、耳は最後まで聞こえているといわれています。たとえ反応がなくても、ゆっくりと穏やかに話しかけましょう。
「もっと話しかければよかった」などと、後悔をすることのないように、あきらめずに感謝の言葉を伝えます。家族にできる最後のことは、本人を安らかな気持ちにさせてあげることではないでしょうか。
<関連記事>
臨終に立ち会うときの心構えとその後の準備
小さなお葬式で葬儀場をさがす
亡くなった後にやるべきこと
家族が亡くなった後には、やるべきことがいくつもあります。悲しみに暮れる中でも進めていかなければならないので、あらかじめ手順を理解しておきましょう。亡くなった後にやるべき5つのことについて解説します。
医師による死亡確認
病院で亡くなると、まず医師が死亡確認を行います。医師は死亡診断書を作成し、遺族に渡します。遺族の感情としては、悲しみのあまりそれどころではないかもしれませんが、この診断書は死亡後の手続きに必要となる大切なものです。なくさないように気をつけましょう。
末期の水・エンゼルケア
末期の水は、故人の口に水を含ませる儀式です。安らかにあの世に旅立ってほしいという願いを込めて、脱脂綿に水を浸して故人の口元にあてます。
次に、看護師や葬儀社のスタッフが、エンゼルケアを行います。エンゼルケアとは、遺体に施す処置のことであり、具体的にはアルコールで拭く「清拭(せいしき)」、死化粧、死装束への着替えなどを指します。
遺体を安置する
エンゼルケアが終わると、遺体は病院の霊安室へ運ばれます。ただし、あくまでも一時的に安置する場所であるため、すみやかに自宅あるいは葬儀社の遺体安置所などに移動しなければなりません。遺体の搬送を依頼するときには、死亡診断書が必要になります。
葬儀社に連絡する
葬儀社を決めて連絡し、遺体の搬送を依頼します。病院から紹介された葬儀社に頼んでもよいですし、自分の決めた葬儀社でもかまいません。
その後、葬儀社と葬儀の日程、会場、内容などについて打ち合わせをします。
死亡届の提出などの手続き
死亡後にすぐにしなければならない手続きは、「死亡届」と「火葬許可申請書」を市町村役場に提出することです。
葬儀社が代行してくれる場合が多いですが、亡くなってから7日以内に提出しなければなりません。死亡届が役場に受理されると、火葬許可証が発行されます。
<関連記事>
臨終直後に行う儀式「末期の水」とは
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
臨終が近いことを知らせる代表的な身体症状は4つあるといわれています。「バイタルサインが不安定になる」「飲食・排泄の変化」「呼吸音が大きくなる」「会話が成り立たない」などです。また、意識が薄れたり、落ち着きがなくなるなど、心の状態も変化します。
臨終直前に家族が行うことは、親族や友人に連絡をする、本人に話しかけるなどです。本人を安らかな気持ちにさせてあげるように心がけます。臨終についてよく理解し、いざというときに慌てないようにしましょう。
小さなお葬式では、葬儀に精通したコールスタッフが、24時間365日、通話無料でご連絡をお待ちしております。葬儀についての疑問をお持ちの方は、ぜひ小さなお葬式へご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



初盆(はつぼん)とは、亡くなった方の忌明け後、最初に迎えるお盆のことです。ホゥ。