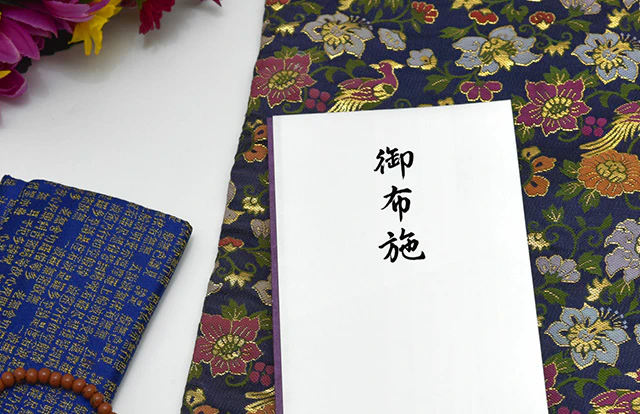葬儀や法要では僧侶への感謝の気持ちとしてお布施を渡します。しかし、お布施を渡す機会は人生のなかでもそれほど多くないため、「どのくらいの金額が正しいのか」「ダメな金額はあるのか」と気になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、お布施の一般的な金額の目安を紹介します。お布施袋の書き方やお布施の渡し方、マナーについても解説しているため、ぜひ参考にしてください。
<この記事の要点>
・お布施の金額は通夜や葬儀で20万円~30万円、法要で3万円~5万円が相場
・お布施袋の表書きには「お布施」や「御布施」と記載し、下部には自分の名前を記載する
・お布施は葬儀や法要の前の挨拶の際に渡すとよい
こんな人におすすめ
一般的なお布施の金額目安を知りたい人
お布施袋の書き方や包み方を知りたい人
お布施を渡すタイミングやマナーを知りたい人
お布施でダメな金額は?
葬儀や法要では、僧侶にお礼として「お布施」を渡します。お布施は「読経や戒名に対する対価」ではなく、「ご本尊に捧げる感謝の気持ち」であり、明確な金額は決まっていません。
そのため「ダメな金額」というのはありませんが、常識的な金額よりも少なすぎると失礼にあたる場合があります。また「4」や「9」といった数字も「死」「苦」を連想させるため、避けたほうがよいでしょう。
【状況別】一般的なお布施の金額目安
お布施の金額は葬儀や法要ごとに異なります。ここでは状況別のお布施の金額の目安を解説します。ただし、ここで紹介するのは一般的な金額の目安であり、地域や宗派によっても異なりますので確認しておきましょう。
通夜・葬儀
お布施の費用の目安はおよそ20万円~30万円です。通夜や葬儀は僧侶の役割が大きいため、法要や納骨時よりも高い金額となります。一般的にお布施には読経料も含まれていますが、お布施とは別に御車料や御膳料を渡す場合もあります。
法要
法要とは故人の命日に死者の魂を供養する行事のことです。葬儀が終わると、四十九日法要や一周忌法要などを執り行います。お布施の金額の目安は以下のとおりです。
| 【法要の種類】 | 【金額の目安】 |
| 初七日 | 3万〜5万円 |
| 四十九日 | 3万円~5万円 |
| 一周忌 | 3万円~5万円 |
| 三回忌 | 1万円~5万円 |
| 四十九日 | 3万円~5万円 |
納骨
納骨とは、骨壷に入れた遺骨をお墓へ納めることです。一般的には四十九日や一周忌の法要に合わせて行います。四十九日で納骨する場合は5万円~10万円が目安とされています。
<関連記事>
納骨式のお布施の金額相場|【相場一覧】葬儀・法事・納骨などお布施相場をチェック
新盆・初盆法要
新盆(あらぼん)・初盆(はつぼん)とは、四十九日の忌明けを過ぎてから初めて迎えるお盆を指します。新盆で渡すお布施は3万円~5万円、新盆以外のお盆で渡すお布施は5千円~2万円が目安とされています。
お布施袋の書き方
お布施袋の書き方が分からないという方もいるのではないでしょうか。お布施の書き方にはマナーがあるため注意が必要です。ここでは、封筒の表書きや中袋、裏面の書き方について解説します。
表書きの書き方
お布施袋の表書きは、中央よりやや上の部分に「お布施」「御布施」と記載し、下部には苗字またはフルネームで自身の名前を記載するのが一般的です。
中袋の表面の書き方
包むタイプの不祝儀袋は中袋がセットになっているのが一般的です。中袋の表面には包んだ金額を縦書きで記載します。金額の前には「金」という文字を入れ、最後は金額の書き足し防止として「也」を入れます。
金額は「30,000円」「3万円」と数字で記載せず、「参萬圓」と旧字体で記載しましょう。以下が書き方の例となります。
| 3万円を包んだ場合 | 金参萬圓也 |
| 5万円を包んだ場合 | 金伍萬圓也 |
| 10万円を包んだ場合 | 金壱拾萬圓也 |
中袋の裏面の書き方
裏面には自分の「住所」「氏名」「電話番号」を書きます。なお、裏面の住所は数字を用いて構いません。
お布施の包み方
お布施の包み方にもマナーがあります。お布施を直接封筒に入れて渡してしまうと失礼にあたるため注意が必要です。ここでは、「奉書紙」「白封筒」を使った場合のそれぞれの包み方について解説します。
奉書紙
お布施は「奉書紙(ほうしょがみ)」に包んで渡すのが一般的です。奉書紙は和紙の一種で、表面はつるつるとしていて裏面はざらざらとしています。
包む際はまず紙幣の肖像画を上向きにし、半紙で包んでから奉書紙で包みます。奉書紙はつるつるとした面が表になるように包みましょう。
白封筒
奉書紙が用意できない場合は白い封筒でも構いません。ただし、郵便番号が記載されていないタイプを選びましょう。
また封筒には中袋があるタイプ(封筒が二重になっているタイプ)もありますが、「不幸が重なる」といったマイナスなイメージを持たれる可能性があるため、使わないようにしましょう。
お布施を渡すタイミングと渡し方
葬儀や法要中は準備などでなにかと慌ただしいものです。お布施を渡すタイミングが遅いと、僧侶に対して失礼にあたるのではないかと心配されるかたもいるかもしれません。ここではお布施を渡すタイミングと渡し方について解説します。
葬儀の場合
葬儀でお布施を渡す場合、葬儀が始まる前の挨拶の時にお布施を渡すのが一般的です。渡すタイミングを逃した場合は、葬儀のあとでも問題ありません。
法事・法要の場合
法事・法要の場合も同様に、基本的には法要前の挨拶時にお布施を渡しましょう。ただし、複数の故人に対して合同で行う場合は、直接僧侶へ挨拶できない場合もあるでしょう。
その場合は、受付が用意されていれば、受付係のかたに渡しましょう。渡すタイミングを逃したら法要後の落ち着いた段階で渡すとよいでしょう。
袱紗(ふくさ)に包んで渡す
お布施はお布施袋のまま渡すのはマナー違反です。袱紗(ふくさ)と呼ばれる布に包んで持参し、渡す際に僧侶の目の前で袱紗から取り出して渡しましょう。
お布施を切手盆に乗せて渡すとなおよいでしょう。切手盆は葬儀社で貸し出している場合もあるため、確認してみましょう。切手盆がない場合は袱紗の上に乗せて渡します。
<関連記事>
葬式で使用する袱紗(ふくさ)とは?袱紗の包み方と渡し方
お布施以外にかかるものは?
僧侶に渡すのはお布施だけだと思われるかもしれませんが、交通費やお食事代が必要な場合もあります。ここでは、お布施以外に必要となるお金と金額の目安について解説します。なお、地域や宗派によって金額が異なる場合があるため事前の確認が必要です。
御車料
御車料は、僧侶が自宅や葬儀会場に足を運んでくれたことに対する感謝の気持ちとして渡すお金です。金額の目安はおよそ5千円~1万円ですが、遠方から足を運んでもらった際には距離に見合った金額を渡しましょう。
表書きは「御車料」か「御車代」と記載し、お布施とは別の封筒に入れて渡します。お布施を渡すタイミングでお布施の下に重ねて渡しましょう。
御膳料
御膳料は僧侶が会食の席に参加しない場合に、おもてなしの代わりとして渡すお金です。僧侶が参加する場合は渡しません。御膳料は5千円~1万円が目安とされています。僧侶が複数人の場合は人数分の金額をひとつの封筒にて入れて渡します。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
お布施は「ご本尊に捧げる感謝の気持ち」であり、ダメな金額はありません。ただし、あまりにも金額が少ないと失礼にあたる場合があります。また「4」や「9」は「死」「苦」を連想させるため避けたほうがよいでしょう。
お布施の金額で悩む場合は、ぜひ「小さなお葬式」へご相談ください。小さなお葬式は通話料無料で24時間365日、専門スタッフが対応いたします。
またお布施に関するご質問以外にも、お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
お布施に入れるお札の向きはどちらが上?
お布施の金額はどこに書く?
お布施の金額は奇数?
お布施の金額が少ないとマナー違反?
湯灌は故人の体を洗って清める儀式のことです。ホゥ。